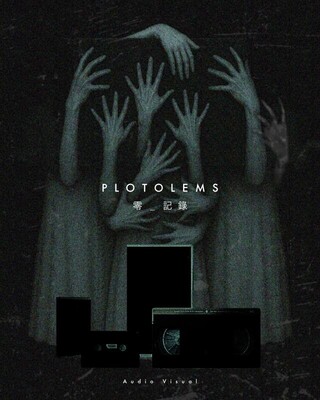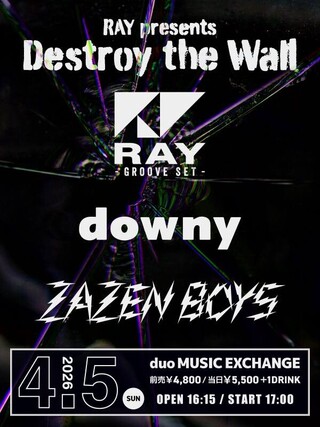何にもない状況だけど“今”を撮ってくれ
──ブッチャーズの歩みとバンドの特性を、中込さんを始めとする縁の深い方々の証言によって補完している手法も功を奏していますね。
川口:札幌在住のReguReguの小磯(卓也)さんはドキュメンタリーの流れで不可欠だなと思って、“ライジングサン”へ行った時に会えて話ができたんです。それとは別に、映画的にインタビューを撮らなくちゃいけないと考えた時に、フラットに話せる人がいいなと思って。それで最初に中込さんに電話して、「すいません、助けて欲しいんですけど…」ってお願いしたんですよ(笑)。ブッチャーズの歴史を捉えるには中込さんの力が必要だったんです。
中込:私は大したことはやってませんよ。時系列的なことや交友関係とかを説明したくらいなので。
──でも、結成直後からブッチャーズのメディア露出を積極的に図った中込さんの功績はとてつもなく大きいですし、ブッチャーズを語る上で絶対に欠かすことのできないキーマンの1人ですよね。
川口:そうなんですよ。僕自身、中込さんの文章でブッチャーズに入っていきましたから。
中込:今にして思えば、逆に私のほうが有り難かったんですよね。『STRAIGHT AHEAD II』とかのアルバムを作ったりライブを企画したりもしましたけど、それは本来ライターがやらなくてもいいことじゃないですか。ブッチャーズに出会わなければそんな企画もやらなかったと思うし、ブッチャーズを何とか世に知らしめたいと思って動いたことが結果的に今の自分の財産になっているんですよ。だから、私としては「やってやったぞ」という気持ちは微塵もなくて、むしろいろんな企画をやらせてもらえたことにただただ感謝しているんです。
──映画を観て、「よくぞここまで成長して…」みたいな親心に近い感慨が中込さんのなかにはあったんじゃないかと思うのですが。
中込:それはあまりなかったですね。“ねぇちゃん”って呼んではくれてるけど、基本的に友達みたいな感覚ですし。それに、私はやっぱりようちゃんのことを尊敬してるんですよ。自分が追い求めても出せないものとか理由のつかない何かを音で表現してくれるわけじゃないですか。だから友達でもあり、尊敬する存在でもあるんです。歳はあまり関係ないんですよ。
吉村:そうは言っても、俺も明日(1月20日)で44になるしね。“死んでしまえ”のナンバーになっちゃうよ(笑)。
中込:いいじゃない、厄は明けたんだし(笑)。
──『NO ALBUM 無題』制作中の尋常ならざる悶絶ぶりは、多分に厄年も関係していたんでしょうか?(笑)
吉村:精神的には「抜け出してやる!」って思ってたよ。あまりにも地団駄を踏んでたからね。「上手く行かねぇなぁ…」の連続で、その状況から何とか抜け出したいと思いながら作ってたのは確かなんだよ。
──8カ月間付きっきりなわけですから、撮り溜めた映像は膨大な量だったんでしょうね。
川口:もう考えられないくらいの量でしたね。ライブはほとんど撮っていたし、行けなかったのは確か2回くらいだったと思います。
──そこから116分の作品として仕上げるのは至難の業ですよね。
川口:想像を絶する作業でしたよ。残したいシーンはたくさんありましたからね。
吉村:歴史的なものを追うのか、証言を追うのかで照準も変わってくるしね。俺は川口君に「今を撮ってくれ」って最初に言ったんだよ。「何にもない状況だけど今を撮ってくれ」って(笑)。
──でも、バンドの歴史と関係者による証言はとても理想的なバランスで構成されていると思いましたけど。
川口:中込さんに時系列的なことをお願いした時点で、「この辺の出来事は必要だろう」っていうチョイスはある程度固まっていたんですよね。あと、結果的にはほとんど使わなかったんですけど、僕がブッチャーズと知り合ってから撮っていた素材も一応全部チェックしておいたんです。でも、吉村さんが言うようにブッチャーズの今の姿に重きを置いたんですよ。ただ、ある程度歴史的な素材がないと「だから今の姿はこうなんだ」という説明がつかないので、アーカイブ映像は必要最小限で入れたんです。
吉村:ドーンと人気のあるバンドでも何でもないし、雑多なバンドだしね(笑)。
川口:でもたとえば、ザック(・デ・ラ・ロッチャ)とメンバーが楽屋で話し込んでいたのも事実なわけだし、本人のOKも取れたので、そういう素材は入れておきたかったんですよ。
吉村:誇大なイメージが出るのは俺もイヤだったし、川口君はそういう部分もよく分かった上で昔の映像を取り入れてるんだよね。