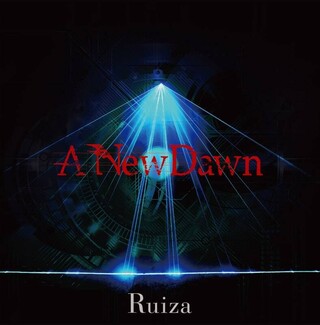日本のロック史における生ける伝説、頭脳警察が最新ライブ・アルバム『会心の背信』を発表した。2020年9月、オリジナル・メンバーであるPANTAとTOSHI(石塚俊明)、サポート・ギタリストの澤竜次が長野市のライブハウスで行なったシークレット配信ライブから全13曲が収録された本作は、革命三部作から近年の「絶景かな」に至るまで53年に及ぶ頭脳警察の歴史とエッセンスが凝縮した、文字通りの"会心"作だ。ここでの彼らはまるで昨年デビューしたばかりのニューカマーのように実に生き生きとしている...いや、そんな生半可な表現では到底済まされない。荒削りで猛々しく、鬼気迫る歌とアンサンブルは、円熟という言葉とは程遠いソリッドで鋭角的な鳴りに終始している。体良くデザインされたパンク・バンドなどは到底足元にも及ばないパンクのアティテュードが全編に漲っており、永遠の叛逆児であり無冠の帝王である頭脳警察の凄みを久々に実感した。配信ライブというライブに対する背信行為を真空パッケージした『会心の背信』がなぜこれほどまでに頭脳警察らしい作品になり得たのか。なぜ頭脳警察だけが半世紀以上にわたり日本のロックの最前線を疾走できているのか。肺疾患による長期療養が必要と診断されたために昨秋よりライブ活動を休止しているPANTAの自宅を訪ね、止まることを知らない創作意欲と飽くことのないオリジナリティの追求を続ける彼の根源にあるものを掬い取るべく話を聞いた。(interview:椎名宗之)
これまで生きてきた証、爪跡を残しておきたい
──ここがPANTAさんの生家なんですね。
PANTA:こっちは離れで、向こうの純和風の母家で暮らしてた。父親が米軍基地に勤めていたわりに純和風の家なんだけど(笑)。まあ、当時は西洋風の家を建てる発想なんて全然なかった頃だからね。俺が小学1年生くらいのとき、親父がすでに買ってあった土地に家を建ててさ。それも大工に手伝ってもらいながら仲間たちと一緒にほぼ自力で建てたらしい。ここから歩いて5分くらいで基地に着くんだけど、子どもの頃に親父に弁当を届けに行ったのを覚えてる。ゲートで白いヘルメットの衛兵に「中村ですけど、弁当を持ってきました」って言うと「ちょっと待ってね」と言われて、親父が部下にジープを運転させてやってくるわけ。「ご苦労」とか言って敬礼してさ。それが子どもながらに格好いいなと思った。
──この辺りは米軍のジープがよく往来していたんでしょうし、PANTAさんは幼児期からアメリカの存在を殊のほか身近に感じていたんでしょうね。
PANTA:家の近くに大きな木があって、そこにパラシュートが引っかかったりね。あと、誰も信じてくれないんだけどP-38が編隊飛行しているのを子どもの頃に見たり。俺が生まれたのは昭和25年、1950年だから朝鮮戦争が始まった年で、P-38が飛んでるのを見たのはおそらく6、7歳。ということは朝鮮戦争はもう終わってる。実際、朝鮮戦争でP-38が使われたとは思えないんだけどさ。
──病気療養中の時間を使ってWEB Rooftopに寄稿していただいている『乱破者控「青春無頼帖」』も気づけば50回を超えまして、いつも洒脱な原稿を仕上げてくださってありがとうございます。
PANTA:こちらこそ掲載できる場を作ってもらえて有難いよ。自分の原稿を発表できる場所なんてなかなかないからさ。
──ウチの連載以外にも『夕刊フジ』では毎週金曜日にミッキー吉野さんとの対談連載『JAPANESE ROCK ANATOMY 解剖学』があったり、杉作J太郎さん責任編集の『現代芸術マガジン』では『PANTA 琴心剣胆』を連載していたり、療養中とはいえだいぶ精力的に活動されている印象を受けますが。
PANTA:自分のSNSであれこれ書いても広がりがないからね。面白いのは、『琴心剣胆』に1969年のシャロン・テート殺害事件がテーマの一つだった『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』を取り上げて「1969年は終息の年だった」と書いたら、図らずも『夕刊フジ』のほうで日本では1969年に渋谷東横劇場で上演された『ヘアー』のことがテーマになってシンクロしたんだよね。これまで何度も話してきたけど、俺は1969年を変革の年だとずっと思っていたわけ。ところが実は終息の年だった。1969年は〈愛と平和と音楽の祭典〉と呼ばれた『ウッドストック』が開催された年だけど、1月に安田講堂陥落、8月にマンソン・ファミリーによるシャロン・テート殺害事件、12月にオルタモントの悲劇が起こっているし、この年に公開された『イージー・ライダー』でも主人公が最後に殺されてしまう。いわゆる“サマー・オブ・ラブ”、愛と平和とロックの時代は1967年の『モントレー・ポップ・フェスティバル』辺りがピークで、1969年はあらゆる意味で終息の年だったと思えてならない。
──目下、数々のコラムを並走させているのは、そうした自身の体験した時代のうねり、当時見聞きしたことを伝え残しておきたい思いからですか。
PANTA:それもある。俺よりちょっと下の世代…60代の連中もそんなことをやり始めてるのが多いよね。たとえば自分の洋楽体験や知識をSNSに書き記したりとか。俺は別に残しておきたいわけでもないんだけど、自分の生きた証というか、爪跡を多少なりとも残しておきたいのかな。
──思っていたよりお元気そうに見えますが、体調はいかがですか。
PANTA:これから新しい治療が始まって、まだ具体的な対策法は聞いていないけど、今後は好転していくんじゃないかな。自分では笑いを絶やさずにこの状況を楽しんでいるけど、病院にはいつもイジメられてるよ(笑)。食事は不味いし、食事制限はないのに薬の副作用で食欲不振になっちゃってるし。
──そのせいか、だいぶお痩せになりましたね。
PANTA:ここ1週間ほど食欲がなくて、チョコレートをつまむ程度だったからね。医者には「まず25kg痩せましょう。そしたらすべて良くなりますよ」なんて言われたんだけど、薬のせいで強制的にそれくらいになってしまった。今は69kgかな。あと1kg減ったら18歳のときの体重と一緒になっちゃう。だけど筋力が落ちてるだけだから、これで体調が戻れば今度はリハビリをしなきゃいけない。車椅子を利用して両腕を鍛えないとね。まあでも、悪いことばかりでもないよ。今日みたいに2、3時間の点滴があるという日は読書に限るということで、今はベストセラーの『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬・著)を読んでいる。これが最高に面白いんだ。モスクワ近郊の農村に暮らす女性スナイパーの物語なんだけど、これはぜひ読んだほうがいいよ。
自分の音楽スタイルが改めて鮮明になった
──『乱破者控「青春無頼帖」』でも村上春樹の短編を映画化した『ドライブ・マイ・カー』のことを書かれていましたが、休養中でも最先端のカルチャーを貪欲に吸収されているのが窺えますね。
PANTA:『ドライブ・マイ・カー』は、カメラマンのシギー吉田が見ろってDVDを強制的に送ってきたから(笑)。ただ原稿にも書いたけど、肝心のクルマが原作では黄色のサーブ900カブリオレなのに、映画では赤いサンルーフ仕様のサーブ900ターボだったでしょう? それじゃちょっとニュアンスが違うのに…とは思った。映画自体が面白かっただけに、そういう細かい部分は残念だったね。その『ドライブ・マイ・カー』の原作だった村上春樹もそうだし、日本人初のノーベル文学賞を受賞した川端康成もそうだけど、文学の世界では日本語で作品を発表してもちゃんと世界に通じるものなんだよね。もちろん有能な翻訳者の存在ありきなんだけど、最初から日本語を英語に直した小説が海外に広まるわけじゃない。もっと時代を遡れば、日本には世界に誇る短歌という文化が『万葉集』の時代から存在していたんだから、もっと日本語で発信することにこだわるべきだと俺は思う。
──それゆえにPANTAさんも音楽の世界において日本語で唄うロックを10代の頃から頑なに志向されたわけですよね。
PANTA:日本語で唄うことで何が大きく変わるのか? と訊かれれば、日本語で何を唄うかが問題になってくるんだよ。唄いたいことがあるから自分の言葉で唄うんでしょ? そのときに日本人であるわれわれが英語で唄うのはおかしいよね。
──それは18歳のときにそれまで大好きだったブラック・ミュージックを捨て、借り物でない自分の言葉で唄うことを選択したPANTAさんならではの発言ですね。
PANTA:当時は稚拙な頭なりに悩んだよ。米軍キャンプで活動していたサミー&チャイルドみたいにブルースを唄わせると上手い連中もいたし、ジャニス・ジョプリンのブルース・フィーリングも素晴らしくて大好きだった。だけどロバート・ジョンソンすらろくに知らない俺がブルースを唄ってどうする? と。当時はローリング・ストーンズ経由でやっとマディ・ウォーターズの音楽に触れられた頃だったからね。アメリカの黒人たちの暗黒の歴史を知りもしない極東のクソガキがブルースを唄ったところで所詮猿真似なわけで、それなら稚拙でもいいから自分なりの言葉で、日本語で唄うべきだと決意した。こんなことを言うと語弊があるかもしれないけど、エレキギターを掻き鳴らして夢中になるようなミュージシャンは歌詞なんてまるで分かってないよね。PANTA & HALのメンバーですらそうだったよ。「マーラーズ・パーラー」の歌詞を理解してくれとは言わないけど、せめて「マラッカ」でどんなことを唄っているのかくらいは分かって演奏してほしかったよね。そうやって日本のアーティストは歌詞を軽んじてきたから海外で99%つまはじきにされてしまう。シュープリームスは「LOVE CHILD」=“私生児”なんてタイトルの曲をヒットチャートに載せちゃうんだから凄いよ。いつだったか、エミネムがゲイのことをボロカスに言ったことで「あんな奴をグラミー賞に出すな」とゲイの権利団体から抗議の声が上がった。そこでグラミーがどう対応したかと言うと、エミネムにエルトン・ジョンとデュエットさせたわけ。そのオファーを受けたエルトン・ジョンとエミネムも凄いし、企画したグラミーも凄い。そういうセンスを目の当たりにすると日本のエンターテイメントが海外の足元にも及ばないことを痛感するね。紅白やレコード大賞でそんな企画が生まれることはまずないだろうから。
──今年のアカデミー賞授賞式で起きたウィル・スミスの平手打ち事件は海外と日本で捉え方が大きく違いましたが、PANTAさんは『乱破者控「青春無頼帖」』の中でウィル・スミスを擁護していましたね。
PANTA:ウィル・スミスの気持ちになれば、あれはあれで正解だったと思う。ゲンコツじゃなく張り手だったわけだし。スパイク・リーが黒人差別を語る1万字インタビューよりも、あの一発の平手打ちのほうが“Do the right thing”の意味を伝える効果があったんじゃないかな。まあそれはともかく、音楽をやる以上はグラミーの凄さくらい分かれよと思うし、俺だってあらゆるジャンルに精通しているわけじゃないけど、自分なりのやり方でグラミーに比肩し得ることをやりたいと今でもずっと思ってる。ここ数カ月、療養しながらミッキーと対談して歴史を遡ったり、今回のライブ・アルバム用の音源を聴き返したことで頭脳警察や自分の音楽スタイルが改めて鮮明になってきたところもあるね。日本のポピュラー・ミュージックはいわゆるシティ・ポップが主流で、世の中はシティ・ポップも踏まえてロックと捉える節があるけど、俺は別にシティ・ポップをやってきたわけじゃないからさ。70年代のポップ・カルチャーは絵画も写真もロックを中心に回っていたけど、ヴィヴィアン・ウエストウッドがロックをアクセサリーにしてしまった。それ以降、ロックは最先端の音楽ではなくなったのかもしれない。そんな昨今に『会心の背信』なんてライブ・アルバムを出して世の中にどう受け止められるんだろう? と思うけど(笑)。