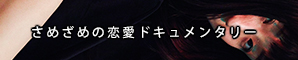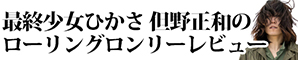「映画には時効はない。俺が死んでも作品は50年〜100年は残っている」(若松孝二)
「塩見塾が提出する、<実録・連合赤軍>を受けた、白熱の連合赤軍総括論争の現在」(2008.02.06@阿佐谷ロフトA)。右から若松孝二、塩見孝也(元赤軍派議長)、鈴木邦男(一水会顧問)、足立正生(映画監督)
「鈴木清順問題共闘会議」デモ
私が初めて若松孝二監督の作品に触れたのは、新宿のポルノ劇場で観た『犯された白衣』だった。もう40年以上前の話だ。この時代、世界は激動していた。アメリカのベトナム戦争を契機に、抑圧された第三世界の人民や先進国の学生達は、街頭に出て「反戦平和! 反帝国主義!」を叫んだ。かのチェ・ゲバラが「第二の、第三のベトナムを世界に!」とアジり、アンデスの山奥で壮烈な死を遂げた。
日本の60年代後半は、1970年の日米安保決戦前夜。反権力的な文化表現がめざましかった。私も20代だった。当時の若者は、大学のバリケードの中からヤクザ映画──鈴木清順、山下耕作、加藤泰、深作欣二監督なんかが人気だった──や、唐十郎、寺山修司の前衛劇を観に行った。各大学の学館では学生運営の「映画論」自主講座もあり、映画評論家の松田政男氏は、そのレギュラー講師だった。
ちょうどその頃、日活が鈴木清順監督の作品を「難解過ぎる」とし、全作品お蔵入り(公開も貸出もしない)という暴挙を行った。しかも、鈴木清順は日活から解雇されてしまった。たちまち、松田政男氏の呼びかけで「鈴木清順問題共闘会議」が結成され、日比谷公園から日活本社まで抗議デモを行った。大島渚、大和屋竺ら新進気鋭の映画人達も参加した。そのデモを指揮していたのは、実は私だった。その日、銀座の日活本社は誕生以来初めて、全館がロックアウトされた。
あの頃、毎日が青春していた。楽しかった。今と違い、日本は高度経済成長のまっただ中だった。だから多少跳ね上がっていても、少しだけ頑張れば若者には就職も、明るい未来も目の前にあった。今のような、「絶望がデリヘルみたいに玄関先まで来ている」(by サンボマスター・山口隆氏)悲しい時代ではなかったような気がする。
『11・25自決の日 三島由紀夫と若者たち』完成記念、若松プロ忘年会(2011.12.15 @新宿ロフト・バーラウンジ)。右から、若松孝二、鈴木邦男、平野悠
追悼・我が親愛なる若松孝二監督
当時、最も過激な映画を撮っていたのが若松孝二だった。若松さんは元々、左翼ではなかった。1936年、宮城県涌谷町出身。地元の農業高校を二年で中退。家出し上京してからは、職人見習いや新聞配達、ヤクザの下働きなどを転々とした。
1957年、チンピラ同士のいざこざから逮捕され、ひどい取り調べを受けた。そして、反権力的な映画を通じて警察への怒りを表現しようと考え、映画の世界へ踏み込んだ。監督デビュー作の『甘い罠』は、まさに警官殺しの映画になっている。
監督として有名になってからも、自ら交通整理をしたり小道具の料理を作ったり、手と身体を動かさずにはいられない人だった。脚本や企画書を数本、いつもカバンに入れて持ち歩き、最後まで、新作を撮ることに意欲的だった。
若松さんは、ロフトプラスワン開店初期から何度も出演してくれた。「こんな俺みたいな男を、みんなが『監督、監督』と言って慕ってくれる。この言葉がうれしいんだ」と、何度も何度もステージから言っていた。新宿で撮影した映画も多数ある。そんな若松さんが、新宿区内藤町の路上で交通事故に遭い、命を落とした。謹んで冥福を祈りたい。
ついこの間まで半袖だったのに、季節は一挙に冬だ。私の長年のテーマである世界の旅。目標であった100カ国制覇は完遂した。しかしまだまだ旅は続く。
12月から3月までの南極まわりのピースボートに、キャンセル待ちでやっと乗れることになった。長いこと行ってみたかったパタゴニアとマダガスカルにも、別料金だがオーバーランドツアーに参加すれば行ける。個人ではもうしんどすぎて行けそうもないと諦めていたので、これはうれしい。もちろん、若くて体力がある人は、こんな楽な方法ではなく、秘境の地までの道を自ら切り開く旅をして欲しい。