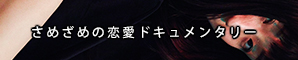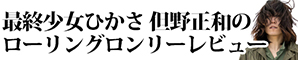【ホントシオリ】vol.19
『しおりは要らない。可愛げもないし…。うちで引き取るなら、修だけで。賢い顔してるし、長男だし、ね。○○家の跡取りとして……』
テーブルに母親と母方の祖母、対面に父親と父方の祖母が向かい合って座り、わたし達姉弟をどちらが引き取るか。当時三歳だったわたしは1歳まもない弟・修の面倒を見ながら、そんな大人同士の会話を聞いていた。わたしは要らない子なんだ、と三歳ながらにして、ちゃんと思えたし、この話が終わったら、このまま修とは離れて暮らすことになるんだ、と察することもできた。弟と離れるのが嫌で。初めての両親への抵抗。無言で弟の手を引き、家から出て歩きはじめ、そんなわたしを母方の祖母が走って追いかけてきて、わたしと弟を抱きしめてくれたことまでを覚えている。
人はいつだって、幾つになっても不安定で、危うい。
高校生のぼくらとそれぞれの家族。あなたはどんな思いを重ねる?
鳥がぼくらは祈り、 / 島口大樹
講談社 / ¥1,400+tax
わたしが最後に父親に会ったのは小学二年生の夏休み。池袋で待ち合わせをし、水族館やアトラクション施設で遊ぶ、という傍から見たら“ごく普通の家族”に見えたかもしれない。父親の隣はいつだって弟で、名前を呼ばれるのも弟で、父親の背中からわたしの存在は“要らない”を感じとった。
「大人になる前に、」
今ある自分と現状を認めないと。そしてそうなったのは
「俺らのせいじゃないって」
認めてあげないと。過去の自分を解放してげないと。ぬるい場所から抜け出さないと。被害者で居続ける自分から抜け出さないといけないんだよきっと。
幼い頃は周りの大人たち、学生の頃は周りの友人、先輩、先生。職場では上司たちの顔色ばかりを気にして、捨てられるかもしれない、と察したら必死に捨てられないようにと藻掻いて。離れた途端、大きな孤独がそこにはあって。決して、相手の機嫌を損ねないように、マイナスな言葉を言わないように、重荷にならないように、自分という存在が誰の記憶からも、いつ消えてもどうでも良いように。そんな風にずっと心の中で祈り続けていた。そうに生きてきてしまった。携帯に入っている連絡先は最小限。いつ自分がこの世界から消えても良いように、誰にも迷惑が掛からないように、返信後メールもLINEも電話の履歴もすべて削除して何も残らないようにしている。自分の言葉で、誰かを傷つけるのではないか、本意ではないことが伝わってしまうのではないか、文字だけの情報は小説のように頭の中でその情景を思い浮かべて、想像をすることができる。色を付けることだってできる。SNSも同じ。読み手の心情でどうとでも変換されてしまう。メールも、LINEも、自分の思いは極力伝えずに、愛想だけ振りまいとけば何とかなることも学んだし、勝手に期待され、勝手に裏切られたと嘆かれるのであれば、自ら近づかない。ちゃんと距離を取る。物理的にも精神的にも。いい子にしていたら好かれる、自然と幸せになれると思っていた。大人になったら勝手に誰かに愛されると、愛してくれるだろうと、そう思い、信じ、願っていたのに。もちろん、現実は違った。そんなことがある訳がない。
「自分を可哀想だと考えることに救いはない」
むしろ、それは人を中心とする世界を憎むことになる。そこからは何も生まれない。
本作品では、“ぼく”と三人の高校生がそれぞれに抱える絶望、傷つき躊躇いながらも自分の未来を、自らの意思で、未来へと手を差し出していく。わたしはそれぞれに少し気持ちを重ねてしまい、何度もそれぞれの視点から、過去を、人生の物語を読み込んでしまった。故に自分自身の過去が鮮明に甦り、どうに伝えていくか、誰に伝えたいのか、何を書きたいのか、可哀そうな自分を?不幸だと勝手に思い、被害者ズラしていた人生を?と、考え込んでしまった。
本連載を描くにあたり、第一回でも伝えてはいるけれど、あくまでも自分自身の経験・感性が軸なので、こんな人いるのねだったり、似た経験・体験をしている人や周りにいたら、ぎゅっと結ばってしまった心の紐が少しだけでも緩くなれば、書く意味もあるかな、と思う。(上手くそれを伝えられているのかはわからないんだけど)
※あくまでも本連載は私情をごりごりにのっけている。純粋に本作品の魅力を知りたい場合には書籍レビューを読んで頂きたい。
作中に登場する“ぼくら”と同じ年齢で出会えていたら、まだ明るい光が差し込む方へ進めたかもしれない。「大人になる前に、」今からでも遅くはない、はず。長く縛り付けてしまったせいで。どうかわたし、わたしとして生きることを諦めないで。
今年10月下旬。映画監督・今泉力哉さんと初めてお話をする機会があった。
一方的な出会いは2014年9月4日。阿佐ヶ谷ロフトAにて開催されたたまたまアルバイトスタッフとして出勤をしていた。以降、今泉監督がどんな作品を撮っていたのか、その後公開された作品は映画館で鑑賞をするようになった。(愛がなんだ は自分自身と重ね合わせてしまい本連載でも過去に紹介をしている)一方的な出会いが、7年の時を経て会話をし、一緒にお仕事が出来るようになり、内心激しく感動をしている。
11月29日(月)、30日(日)に当店LOFT9 Shibuyaにて開催をする「今泉力哉トークライブ2DAYS」。
2日目。今泉力哉さんと登壇をする島口大樹さん。今泉さんから島口さんとお話をしたい!とご希望を頂き、島口さんの作品をまだ読んだことのないわたしへ、僕は普段あまり小説は読まないんですが、詩的というか、文章が独特です、と。島口さんからもご連絡をさせて頂く中で「それこそ普通の書き方ではないので読みづらいかもしれません。ただ、根拠というか、その時の僕なりの最大限の表現方法ではあったので、お読みいただけると本当に嬉しいです。」と。どれだけ読みにくいのか、本を開き、わたしは冒頭から驚いてしまった。こんな表現に出会ったことがなくて。普段、本を読みながら一気に感情をのせたり、その世界を想像してしまうわたしにとって「。」は息継ぎのタイミングだったからこそ、「。」の少ない文章。“ぼく”がいるのにも関わらず、それぞれの視点からの会話は今までになく。「鳥がぼくらは祈り、」をまだ読んだことのない方は、一度手に取って欲しい。創作をする人たちは特に。“今まで”から解放され、新しい兆しが差し込むかもしれない。少なからず、わたしは絶望をしていた毎日に少しだけ光が差し込んだ。
創作と小説の夜。そして、この一年間、今泉力哉さん、島口大樹さんがどんな日々を過ごしてきたのか。是非、目の前にいる二人の言葉を真っ直ぐに感じてください。
文章:おくはらしおり(LOFT9 Shibuya)