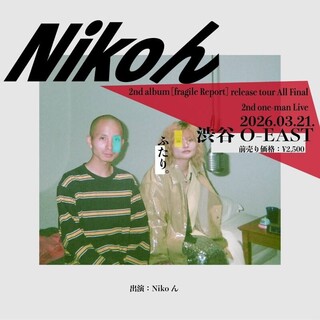今年7月にグランドオープンするライヴハウスLast Waltz in LOFT。オープンに先駆けて4月に開催されるイベント"LAST WALTZ Restarting prologue to new loft「RESPECT!!」"では、音速ラインとSPARKS GO GOのやくましんいちという異色の組み合わせが実現する。一見、世代もジャンルも異なる2組であるが、今回のイベントは、音速ラインの大久保が胸に秘める、やくまに対する熱烈なリスペクトにより実現したものであった。最後に大久保が告白するというまさかの展開となった(笑)、ベーシスト対談をお届けしよう! [Interview:近藤隆久(ベース・マガジン編集長)]
『六根』の1音目からヤラれちゃって。あの鬼気迫る感じが衝撃的でした。
──今回、大久保さんは八熊さんと初体面ということで、かなり緊張した面持ちですが……。
八熊:なんで!?
大久保:自分、ベースをやらせていただいているんですけど、八熊さんは本当に始めるきっかけになった方なので……。
八熊:あ、そうなの? それが不幸な始まりだった、と(笑)。いやもう、すいません! って感じだよ。音速ラインでは、自分が歌う曲はないの?
大久保:ないですね。
八熊:あ、そこは憧れなかったんだ(笑)?
大久保:いやいや! スパゴー(SPARKS GO GO)の曲は歌いながらコピーしていたんですけど、とにかく歌がヘタで。
八熊:何をおっしゃいますやら。俺もダメでしたから……いや、今でもダメですけどね。ここ最近、ひとりで曲作りしているんだけど、オケまでは“よしっ!完璧だぜ!”って思っていても、歌を入れたらガックリする。今日も朝から歌入していて、“ダメだ、なんでこんな歌しか歌えないんだ!”ってヘコみながらここまで来たんだもん。
大久保:最近だと、SHINKIBA JUNCTION 2009 “また倶知安じゃないジャン!”で拝見して。
八熊:えっ観てたの? ワンフーじゃないっすか(笑)!
大久保:その時、ベースのサウンドが断トツに良かったんですよ。
八熊:若い頃、海外でレコーディングをするとき、有名なプロデューサーに会うと“ドラムとは絶対に点で合わせろ”って必ず言われたんだよね。つまり、スピーカーから音が出るとき、音がズレてたらドドッて2回スピーカーを震わせることになる。それよりも、1回でドン! って鳴らしたほうが圧が出るし、いいわけじゃん。だから、特にドラムとは絶対に縦の線を合わせる。あとは、俺らって小学校からの同級生でしょ? テッチ(たちばな哲也/d)は小学5年生の頃から“叩けない〜!”ってドラムやりながら泣いてたのを知ってたぐらいだから。で、高校生からずっと一緒にやってたら、そりゃあ合うよね。ギターはその兄貴だし(橘あつや)、もはや3人兄弟みたいなもので。
大久保:あとは『六根』(94年6月リリース)の1音目からヤラれちゃって。あの鬼気迫る感じが衝撃的でした。
八熊:『六根』のレコーディングでは、ジョー・ブレイニーっていうプロデューサーがとにかくうるさくて(笑)。“ウッセーな、このオヤジ!”って思ってたら、キース・リチャーズがやってきて、“ハイ、ジョー!”とか目の前で会話していて。その流れで“ヘイ、ヤック!”ってキースに声をかけられたんだよね。で、“この人、すごいんだ……この人の言うことは聞こう”って思ったの(笑)。
大久保:うはは。
八熊:でも『六根』って不思議なサウンドなんだよ。激しい音ではないんだけど、なんか不思議なロック感がある。そして勉強になったレコーディングで……簡単に言うと、その前にやることがなくなっちゃったのね。もともとは“俺、歌えるのかな……”っていうところからこのバンドが始まって。で、歌えなければ、1年くらいで辞めようぐらいの気持ちだったんだけど、周りが盛り上がってきて動員も増えてきて、やべえ、これは辞められないぞっていう。そうしているうちに大阪城ホールでやったりして、さあ、次の作品を出そうってなった時、スタッフからカバー・アルバムっていうアイディアが出てきて。それが、『EASY』(93年10月)っていう作品。で、それは面白いと思ってニューヨークでレコーディングしたら、もう音楽家として満たされちゃったんだよね。で、辞めようかなって思った。
大久保:えっ!!
八熊:俺の中で欲求も何もなくなって。ライヴもやりたくなかったし、どこにいてもつまらなかった。そのときにジョーと出会ったんだけど、自分自身がゼロだからこそ、すごく染みたというか、勉強にもなったし、やる気にもなったんだよね。それが『六根』っていうアルバムで。
──そうだったんですね……。
八熊:でも、辞めようって考え出したら、あ、こんな良いこともあるんだって、周りで起こる良いことに目が行くようになって。意外と橘兄弟って良いヤツじゃんとか(笑)。だから、やっぱり最後は人間かな。意外と気を遣ってくれてるんだなってメンバーからも感じたし。
少しでも嘘をついてあげなきゃいけない。それがこの商売の辛いところでさ。
──大久保さんにとっての転機は?
大久保:ヴォーカルの藤井(敬之/vo,g)は、今、福島に住んでいるんですけど、2011年の震災の日は名古屋にいて。奥さんは自宅にいて、その瞬間に奥さんと一緒にいることができなかったっていう思いがずっとあったんです。それ以来、書く曲の質が変わったというか。翌年に出したアルバム『Alternative』(12年2月)で気持ち的なところで爆発して。やっぱり、福島に住んでいて感じるストレスを抱えたまま曲を作っていたんですよね。ここ最近、曲を書くことに関してはそのストレスが晴れてきて、EP盤『チルは散る』を出した時に、ファンの方から“おかえり”って言ってもらえて。
八熊:見えないストレスがあったんだろうね。
大久保:当時はアーティストの方々も福島まで来て活動してくれるんですけど、現地に住んでいる人とはベクトルが違うというか。“来てる”から“帰る”わけで。
八熊:そうね。そりゃそうだ。
大久保:来てくれるのはもちろん嬉しい反面、忘れたい事実なのにっていう。だから、自分たちは違うベクトルで動くというか。
八熊:忘れたいことなんだ?
大久保:毎日のしかかってくるものなので。そうなってくると、忘れたふりをしないと壊れちゃう。
八熊:そのストレスを抱えたまま作った曲はどうなの?
大久保:自分としては“正直によく言った!”って思うんですけど、やっぱりそれを投げて返ってきた反響が、“聴いていて辛い”とかだったんで。今となっては出して良かったと思うし、吐き出していかないと本人が潰れてしまいますから。
八熊:世間ってさ、辛ければ辛いほど、辛い音楽は聴きたくないんだよね。だから、少しでも嘘をついてあげなきゃいけないんだよ。それがこの商売の辛いところでさ、嘘ついてやらないと人は耳を傾けない。ま、嘘じゃなくていいんだけどね。今は良い方向に向かっているっていうことでしょ?
大久保:そうですね。6、7年経ってやっとっていう。
八熊:でもその6〜7年っていう時間が必要だったのかもしれないし、それがあったからこれから何かあるのかもしれないよね。俺らの場合、40代後半を超えてくると、昔から一緒にいる3人っていうシンプルな編成のなかで、得手不得手がわかっていて。もちろん、好奇心はあるけど、180度変えてみようっていうよりも、今持っている武器を磨いていくしかない。“包丁研いで何十年”っていう世界だよね。特に橘兄弟は完全に職人気質で、俺はその中では遊び人役なんだけど、3人でやっているんだから、その武器が錆びないように常に磨いていかないといけない。切れ味を保つのも大変だからね。
──というわけで、LAST WALTZ Restarting prologue to new loft「RESPECT!!」ではこのふたりの組み合わせが実現します。
八熊:今回はバンドじゃなくて、弾き語りだけどね。これがね、悲しきかな、ベースを弾くと、“やっぱり違いますね〜”って盛り上がる。こんなに“ギター練習したのに〜”って(笑)。
──やはり生粋のベーシストなのでは?
八熊:まぁね。だから当日は、ベースも弾きます!
──では大久保さん、最後に聞きたいことは?
大久保:とにかく今日は、“好き”っていう気持ちを伝えられたのでよかったです。
八熊:女子高生か(笑)!
大久保:すいません!