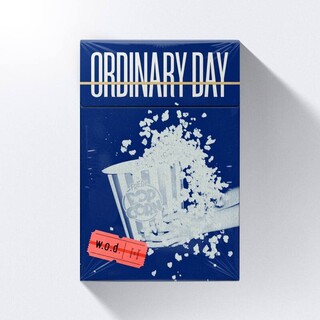ブラッドサースティ・ブッチャーズが往くケモノ道は決して平坦ではない。まずもって避け方を知らないから、魑魅魍魎に何度でもぶつかる。ぶつかって、ズッコケまくり、たちまち傷だらけになる。傷だらけになってもなお、彼らは砂を掴んで立ち上がる。進軍ラッパを勇壮に吹き鳴らしながら満身創痍で疾走を続ける。漆黒の闇の中で七転八倒しながらも足掻くだけ足掻く。ロバート・ジョンソンが四辻で悪魔に魂を売り渡した引き換えにブルースを身に宿したのとは異なり、ブッチャーズは悪魔に"クソッタレ!"と唾棄し、それでも敢えて荒野を突き進む。それがブッチャーズにとってのブルースという表現であり流儀でもあり、『NO ALBUM 無題』と題された作品には彼ら一流のブルースが重厚かつ繊細に、はたまたサイケデリックに轟いている。油絵のような激しい凹凸もあれば、水彩画のような瑞々しい透明感もある。豪胆でいてたおやかなその音塊と歌は、音楽のミューズの寵愛をも拒絶せんとばかりに孤塁を守る極北の佇まい。この真に迫る凄味、やはり只者ではない。疾走に継ぐ疾走を絶えず続けるさなかで握り締めた暗夜の一灯、そこから紡ぎ出された至高の歌の数々について、メンバー全員に話を訊いた。(interview:椎名宗之)
“その先にあるもの”に手を伸ばす
──『フランジングサン』をライヴで初披露したのが2007年11月14日に札幌ベッシーホールで行なわれた“official bootleg vol.14〜20th Anniversary / 僕達の疾走〜”でしたから、今回発表となる『NO ALBUM 無題』はほぼ2年を費やして完成に漕ぎ着けたことになります。この2年、吉村さんが公私共にひたすら悶々としていた印象が強いんですが。
吉村秀樹(vo, g):悶々としてたよ、歌詞を見れば判る通り。でも、その悶々が最後は表現になっていくからね。
──ここ数年では最大級だったんじゃないかと思えるあの七転八倒ぶりは一体何だったんでしょう? 思うような表現がなかなかできなかったとかですか。
吉村:それも一因としてあるし、思いと形が噛み合わないこともあるし、思いを掴みきれないこともある。最終的に仕上げるのに“これだ!”って判るまで凄く時間が掛かったんだよ。
田渕ひさ子(g, vo):もの凄く長い時間を掛けて作ったアルバムだから、これを人が聴いてどう思うんだろう? っていう感じなんですよね。僕としては達成感があるけど、人がどう感じるのかはよく判らないんです。
射守矢 雄(b):自分達でも一体どうなるんだろう? って感じだったからね。何とか完成に漕ぎ着けて、これでやっと気持ちがリセットできるんじゃないかな。そのリセットが前向きなのか後ろ向きなのかは判らないけどさ(笑)。
小松正宏(ds):メンバーそれぞれがやれることはやり切ったと思うよ。ただ単にやれることをやるだけじゃなく、いろんな思いも含めて投げ出さずにやり切った。多分、この4人じゃなければバンドを抜けてる人もいただろうし、4人全員がアルバムに対する責任をちゃんと果たしたと思う。
──昨年末の“SPACE bootleg X'MAS TOUR 2009”で『ocean』を初披露した時、吉村さんがMCで「この曲を作るための2年間だった」みたいなことを仰っていましたよね。『ocean』は強い確信に満ちた重厚なサウンドなれど、終盤に“生きている 生きて行こう”という一節もあるし、唄われている内容はかなりヘヴィですよね。
吉村:『ocean』は最後の大きな課題としてあって、『ocean』を『ocean』っぽくするには一歩踏み込まなきゃダメなわけよ。そこになかなか行けなかった。『ocean』の世界観みたいなものは『black out』にも凝縮してるんだけど、“生きている 生きて行こう”っていう答えは俺の中に最初はなかったんだよ。でも、曲を作ってるとやっぱり生きていたいし…っていう。もういいや、残された気持ちは握り潰しちまえ! って言うか…。そこで多少なりともポジティヴになれたんだよね。
──前作『ギタリストを殺さないで』で言えば、『イッポ』を完成させる時に「この曲が出来なかったらもうバンドをやめるぞ!」と吉村さんが3人に発破を掛けたことがあったじゃないですか。『ocean』もそんな領域にまで踏み込まなければ完成できなかった曲じゃないかと思うんですよね。
田渕:確かに、『ocean』は『イッポ』の時に近いことを言われたような気がしますね。
吉村:レコーディングはもっと楽しげなはずだったんだけどね。きっかけは曲でも何でもいいのよ。でも、“その先にあるもの”を作らないと同じことになっちゃうんだよね。今回は音的に『ギタリスト〜』の延長線上にはあるんだろうけど、もっとシンプルなものになるはずだったんだよ。それがフタを開けてみると全然そうじゃなかったっていう。
──作っては壊すの繰り返しだったんですか。
吉村:いや、そうでもないよ。音録りは最短時間で入れてるし。ただ、歌入れと歌詞を作るのがとてもとても苦労した。その先に何かが見えればいいわけ。『ocean』なら海が見えればいいし、『curve』なら宇宙が見えればいいわけよ。頭の前頭葉に余計なもんがあると、それが見えないんだよ。踏み外すと当たり前に時間が掛かる。
射守矢:“その先にあるもの”っていう答えは吉村しか判らないわけで、言い方は悪いけど、俺達は傍観してるしかないわけ。こっちは何がどうなっていくのか判らない状態で録るから、とても冷静じゃいられないんだよ。吉村が苦悩してる時に俺達ができるのは、ただひたすら待つこと(笑)。決して急かさず、けしかけず。そんなことくらいしかできなかったよね。
小松:順序立てると言うよりも、ブッチャーズは気分で作業を進めていくんだよ。“ポン”とひらめきが生まれればそこからダーッと進むんだろうけど、その“ポン”がなかったから『フランジングサン』から次の曲へ行くまでに凄く時間が掛かったんじゃないかな。ただ、そこで急かしても仕方ないし、俺達3人はその“ポン”をひたすら待つ。前はライヴを止めてスタジオに籠もることもあったけど、2、3ヶ月ライヴを止めたところで“ポン”が出てくるとは限らないし、それは20年以上バンドをやっていれば充分判ってることだから。
誰一人として抜けたらオシマイ
──そうした制作背景を含めて、アルバム全体に通底する色調は“ブルース”という言葉に集約されている気がしますね。図らずも『散文とブルース』という楽曲も収められていますし。
吉村:“ブルース”がないと何も始まらないからね。俺の中で“ブルース”っていうのは“エレジー”なんだよ。英語の“BLUES”じゃなくカタカナの“ブルース”って言うか、青江三奈とか藤 圭子みたいな歌謡曲に近いニュアンス。俺が最初に描いてたのは、演奏もプロデュースもメンバー全員でやってるようなイメージだった。『ギタリスト〜』はそれとは違う一面を出したかったのが本音なんだけど、なかなかそれが上手く行かないのよ。時間も熱量も掛かってるし、俺が最後の答えを見つけるのが凄く難しかった。単に4人の音を集約して作るだけなら前作でもいいわけだしね。ひとつの結果として作品の出来には凄く満足してるんだけど、最初に思い描いてた構想と違うってところで、家に帰って何度も壁を蹴りたい衝動に駆られたね。“何なんだ、俺は!?”みたいな感じでさ。その流れを断ち切って、“ああ、これだ!”ってカギを掴めたのは歌だったんだよね。サウンドがカギじゃなかったんだよ。
──『ギタリスト〜』で吉村さんの歌はかなり理想的な境地にまで達した感がありましたけどね。
吉村:そこもさらに違うところへ行きたかったわけ。自分で歌詞を作って歌を唄って、さらにそれを自分でプロデュースしなくちゃいけないから、ジャッジが凄く難しいんだよ。でも、歌に関しては今までとは違った表情が出せたと思う。
──前作は弾むような明るさと小気味良い軽やかさを基調とした作品でしたけど、本作は全体的にシリアスかつ内省的なトーンで、それでもなお砂を掴んで立ち上がろうとする強靱な意志みたいなものを感じますね。
吉村:ヘヴィ感はあるね。ただ、俺はそのヘヴィをサイケにしたいわけよ。サイケにできる要素が歌を重ねていく過程の中で見つかった。何もハッパを吸ってりゃサイケになるってわけじゃなくて、サウンド自体がサイケって言うかさ。4人とも“これしかできない”ってところで新しい何かを生み出すのが毎回の課題なんだけど、誰一人として抜けたらブッチャーズはオシマイなんだよ。代わりはいない。まぁ、その部分での甘えもあるんだけどね。俺はこのアルバムを作り終えた時にみんなに言ったんだよ、「もうこんなに辛い作業はしたくない!」って(笑)。違う方向性を探すことはもちろんしたいけど、今回みたいな突き進み方をしていたら、多分、次で死ぬね。それくらいの勢いが最後の作業であったから。まぁ、それを楽しんではいるんだけどさ。答えが見つかった瞬間は楽しいんだよ。サイケな瞬間がね。
──そのサイケな瞬間は雲のように掴み取るのが難しいんでしょうね。
吉村:どこにポイントがあるか判らないからね。それを探して提示しなくちゃいけないしさ。
──ひさ子さんはなかなか良いフレーズが浮かばずに不甲斐なさを感じているとレコーディング中のブログに書いていらっしゃいましたよね。
田渕:万年そんな思考なんですよ(笑)。
吉村:俺が良くないのは、褒めて伸ばすタイプじゃないってことなんだよね。
小松:ああ、それはあるね(笑)。
吉村:「もっと来いよ!」って言ってるんだけど、それが逆に作用しちゃうんだよ。いつも改善したいとは思ってるんだけどさ。
小松:ちゃこちゃんは特に最後に入ったメンバーだから、スタジオで何か言われたら萎縮しちゃうところもあると思うんだよね。ガーッと言われると、本来なら出せる力が出せなくなっちゃう。それは俺もよく判るしね。
──ただ、ブッチャーズはその緊張感がアンサンブルの妙味に繋がっている部分も大きいのでは?
吉村:いや、それをやりすぎると死んじゃうよ。
小松:若い頃はこっちも“何クソ!”って気持ちがあったから、功を奏した部分もあったかもしれないけどね。
吉村:そんな中でこれだけ長い間続いてるのは奇跡だと思うし、何かひとつカギを見つけていくことのプレッシャーは常にあるよね。オリジナルの3人は特にそうだろうし、ブッチャーズがなくなったら自分じゃないって気持ちもそれぞれにあると思う。その上でひさ子が入ってブッチャーズを動かしていく部分で、自分達が理解してる以上のプレッシャーがあるだろうしね。その厳しい状況の中で超えるべき作業が絶えずあるわけ。