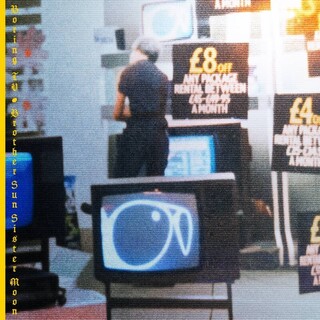『魔女の宅急便』の作者と知られ、89歳の今も現役で執筆をつづける作家・角野栄子。作品とともに本人も魅力的な彼女に迫ったドキュメンタリー映画『カラフルな魔女~角野栄子の物語が生まれる暮らし~』。時代を超えて愛されるチャーミングな世界はどのように生まれるのか、間近でその姿を観て本作を監督した宮川麻里奈に話を聞いた。
[interview:柏木 聡(LOFT/PLUS ONE)]
一目ぼれしました
宮川麻里奈:なぜ、この映画に興味を持っていただけたのですか。
――私がインタビューされる感じですか(笑)。
宮川:すみません、逆質問をしてしまって(笑)。
――いえ、大丈夫です。角野栄子先生の作品は国内外を問わずファンが多いと感じています。劇中でも子供たちの前に現れたときの歓声が凄く、世代を超えて愛されているんだなと改めて感じました。
宮川:アイドルみたいでしたよね。
――私も小学1年生の時にスタジオジブリで映画化された『魔女の宅急便』を劇場で観て本も買ってもらい読んでいたのです。
宮川:まさにど真ん中の世代なんですね。
――はい。意識はしていなかったですが他にも『ちいさなおばけアッチ・コッチ・ソッチ』シリーズなど角野栄子作品には多く触れていて、改めてどんな方なんだろうと気になったんです。
宮川:そうなんですね。
――インタビューされるのはこんな気持ちなんですね。このままだと記事にならないので、すみません(笑)。
宮川:はい、よろしくお願いします(笑)。
――宮川さんはなぜ、角野さんのドキュメンタリーを撮ろうと思ったのですか。
宮川:“あさイチ”や“スイッチインタビュー”“所さん事件ですよ”など情報番組を中心に制作して、怒涛のような30~40代を過ごしてきたんですけど、50歳を目前に、ふと地に足のついた暮らしを見つめるような番組をやりたいなと考えるようになりました。誰を取材したいかなと思いをめぐらせていた時、角野さんをインタビューしたいなと考えていたことを思い出したんです。
――温めていたアイデアが蘇ってきたんですね。実際に取材をされていかがでしたか。
宮川:角野さんのファッションやご自宅が全てを物語っていますが、自分のスタイルをお持ちの方です。豪邸という訳ではないし、ぜいたくをされているわけでもないですが、自分にとって心地のよいもの、好きなものだけに囲まれて暮らしている感じ、ご自宅の居心地の良さや角野さんご自身のかっこよさに一目ぼれしました。何だか一緒に遊んでいるような気持ちで取材を続けるうちに、あっという間に4年が経っていた、という感じです。
――分かります。
宮川:ドキュメンタリーは撮っていると1度はお互いを嫌いになる瞬間があると言われているんです。でも角野さんに対して嫌な気持ちになったことは一度もありませんでした。いつ行っても力のある言葉をもらえて、心豊かな気持ちで帰路に着いていたなと思います。
――スクリーンで観ていてもわかりました。少女のような、妖精のような雰囲気もあり、とても可愛らしい方ですね。
宮川:いつお会いしても愉快でお茶目でユーモアにあふれていて、佇まいも画になるとしか言いようがない。とても楽しい取材でした。
――映画の中でもずっと笑っていらっしゃる方だなという印象でした。あと、よく食べるなと。
宮川:重要なポイントですよね(笑)。
――EDで食事シーンがずっと流れていますが、分かっているなと。
宮川:見事な食べっぷりを見ていただきたくて、エンディングは食いしん坊シリーズにしようと思いついたんです(笑)。
「好きなことだからできるのよ。」とおっしゃって
――角野さんは人が好きな方なんだなとも思いました。
宮川:どこにでも「ヤアヤア」と胸襟を開いて飛び込んでいくタイプの方ではありませんが、いつも無理せず自然体で、誰に対しても分け隔てのない、器の大きな方だと思います。
――劇中の雰囲気は宮川さんやスタッフのみなさんが作り上げられた信頼関係から撮れた部分なんですね。
宮川:先ほど少女のよう、妖精のようとおっしゃいましたが、もちろんそういう側面もありますが、ご本人は成熟した大人の女性です。その一方で、意外と照れ屋な一面もあるんですよ。
――プライベートな時は朗らかですが、作家としてお仕事をされる時はプロフェッショナルな顔になるのも印象的でかっこよかったです。
宮川:私たちも固定カメラで撮らせてもらった映像を見て、びっくりしました。あの姿は編集者のみなさんも観たことがないわけです。
――現役の作家なんだなと感じました。
宮川:朝から夕方まで、執筆中はトイレとお茶を入れに行くくらいで、あとはほぼずっと机に向かっているんです。書いて・音読して・推敲して。毎日休まず書いている、とは角野さんから伺っていましたが、想像していた以上でした。驚異的な仕事量ですが、角野さんは「好きなことだからできるのよ。」と。
――好きなことでも嫌になってしまうこともあるじゃないですか。苦労がなかったわけではないでしょうが、「楽しかった。」と言えるのはそれだけ全力を注ぎこまれていたからだろうなと思います。
宮川:そうですよね。書けば書くほど、新たな楽しみを発見してこられたんだと思います。
――親子関係が仲良く素敵でした。あれだけ仲がいい親子はなかなかいないと思います。
宮川:母娘で撮ったインタビューは、実は意外な内容でした。娘のくぼしまりおさんが子供の頃に「普通のお母さんになってよ。」と言ったそうなんですが、それを角野さんは自身が幼い頃にお母さまを亡くされたこともあり、りおさんに過干渉になりがちだったから、と思っていたというんです。実際は、角野さんが執筆に夢中で“あっちの世界”に行ってしまっていて、どこか上の空というか、心ここにあらずだったので、りおさんからすると「お母さん、私の話聞いてる?」という感じだった、と分かりました。
――寂しかったということなんですね?
宮川:うーん、必ずしも寂しかったわけでもないと思いますが・・・。もうひとつ驚いたのは、りおさんが角野さんの作品を読んだことがない、ということ。それは全く予想もしない答えでした。
と言いながらも、りおさんは誰よりも角野栄子の世界観の理解者なんですよね。昨年11月にオープンした江戸川区角野栄子児童文学館(魔法の文学館)も、最初に角野さんが内装について「ピンク色のコリコの町にしたい。」と言ったら、みんな「?」となってしまったと。それを横で聞いていたりおさんが絵にして、「母が言いたいのはこういうことだと思います」と伝え、角野さんも「そう、それそれ。」となり、その絵がすべての出発点になった、と。その通じ合い方は凄いですよね。
――もしかすると距離が空く時期もあったかもしれませんが、根っこの部分ではずっと繋がっていたんでしょうね。
宮川:その絆は想像がつかない部分があります。りおさんも児童文学作家であり、児童文学館のアートディレクターでもありますから、クリエイター同士で通じ合うものがあるんだと思いますね。