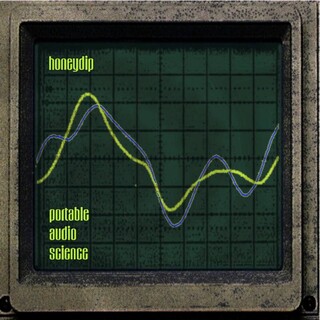時代との共時性がないところで存在していた楽曲群
──そもそもfOULが2005年の春に活動休止した背景には、バンドよりも家庭を優先させたいというメンバーの意向があったからなんですよね?
大地:俺は完全にそうでした。結婚して子どもが生まれたことで、バンドで食べていくという生活の在り方が現実的ではなくなったんです。ちゃんとした定職に就かないといけなかったし、大学に入り直して教員免許を取って、教員になって。しかも学校が青森だったので、青森と東京を行き来する生活になって。最初はfOULの活動を止めずに、たとえば練習で録った音をデータでやり取りしてドラムの音を足そうなんて話もあったんですけど、当時の自分は音楽をやる余裕がまるでなかったんです。
谷口:fOULの活動末期から大介はそんな感じで、それが結果的にfOULの活動における不具合やメンバー間の釣り合いが取れなくなったことに繋がっていったんです。実は新曲もあったんですよ。学がアクセントを入れつつ繰り返しベースを弾き続ける曲で、不甲斐なくギターが決まらないまま未完成になった曲なんですけど。あと、日の目を見ないまま歌詞を全部完成させた曲もありましたね。自分としてはニュー・ウェイヴっぽいアプローチができた曲で、歌詞もタイトルも気に入っていたんですよ。だから未発表曲が2つあったのかな。
大地:まあだから、活動休止に至ったのは俺個人の事情でしたよね。
谷口:いや、みんな仕事や家庭でいろんな事情があったんだよ。
平松:俺も結婚して、仕事をしながら『砂上の楼閣』をやっていた頃に「仕事を休んでんじゃねぇよ!」みたいなことを上の人に言われましたからね。昔ながらの職人が多い職場だったので。
──健さんはfOUL休止後、2005年12月にBEYONDSを復活。大地さんはfOUL休止後にTABLEに参加、2011年8月にはBEYONDSへ合流しますが、BEYONDSの健さんとfOULの健さんの一番の違いはどんなところだと大地さんは感じていますか。
大地:fOULを一緒にやってると、彼はやっぱり狂気の人なんだなと改めて感じますね。さっき彼も話していた通り、ギターを弾くことで狂った部分が増幅されるのを肌で感じます。歌詞で同じことを唄ってたとしても、BEYONDSとfOULでは全然違うので。
──確かに。「FEDDISH THINGS」が良い例ですね。
谷口:僕から見た大地大介もBEYONDSとfOULでは全然違います。BEYONDSでの僕はボーカルだけなので、ドラムとの呼応や絡むことによる込み上げてくるものがfOULほどはなかったんです。だから大介と楽器同士で繋がれていた暁生くんやテッキンが羨ましかったし、彼のドラムは特に他の楽器と呼応するドラムなんですよ。もちろんボーカルとも呼応するんだけど、fOULではギターでも呼応できる部分が多いのでBEYONDSとは強烈な違いがありますね。緩急の付け方、静と動のバランスが楽器同士だと如実に伝わりますし。
──時空を超えた楽曲の普遍性や鮮度の高さもfOULの大いなる魅力の一つだと思いますが、ご当人たちとしては17年ぶりに封印を解いてみてどう感じましたか。
大地:手前味噌ですけど、全然古びてないですね。ちょっとこれは古くさいからやるのはやめようかって曲がまるでないので。自分たちでも不思議です。
谷口:それは見方を変えると、1994年の結成当時からやっていた曲が古いも新しいもないってことなんでしょうね。おこがましい表現をするなら隔世の感と言うか、時代との共時性がないところで存在していた曲なのかなと思います。
大地:そう、その時代を切り取った音楽じゃないよね。
谷口:でもおかげさまでこうしてまたfOULをやれて気づくこともあるんです。たとえば「Smart Boy Meets Fat Girl」に「oh I'm a just poor boy just 29」という歌詞があって、ああ、これは自分が29歳のときの曲なのか、今の自分ならこういう歌詞は出てこないかもなと感じたりもして。「fOULの休憩」や「そして浸透」のようにふわっと出てくる気持ちを描いたような曲も、今ならああいう歌詞は出てこないかもしれないとか、いろいろ感じたりもします。今なら従来とは違う、未来を担う子どもたちや社会の現実に向けた歌詞を書けるんじゃないかと今は今で逆に楽しみですね。
大地:今思うと、fOULを始めたのは健ちゃんと俺が25、6で、学が22とかでしょ? それであんな曲をやってたのが凄いよね?
──そうですよね。歌詞の世界が妙に達観していると言うか、やけに諦観していると言うか。
谷口:そうそう。学なんて22歳であんなに平然と構えて流麗なベースを弾くんだから恐ろしいね(笑)。
平松:そういうベースのフレーズが生まれたのは大地さんと健ちゃんのおかげですよ。もともとSocial Distortionとか大好きだったのもあるけど。
大地:3人ともそれぞれfOULをやることによって違う回路が開いたんだよ。「こんな引き出しがあったんだ!?」っていうのをお互い感じてびっくりしたんだと思う。
──学さんのバッキバキで図太い鋭角ベース、大地さんの重すぎず軽すぎない安定と信頼のリズム&ビート、健さんのギターを弾けないのに弾こうとする精神性と実験性と狂気を孕んだ代替不可の歌声、三角形の辺の引っ張り合いで生じる3ピース特有のヒリヒリ感がfOULをfOULたらしめる要素だと思うのですが、古今東西どこを探しても見つからない、類型皆無の不世出バンドとしか言いようがないんですよね。
大地:学のベースはバッキバキでテンポ・キープがばっちりで粒揃い、コード弾きもするという何でも来いスタイルだったんです。だからこっちもやりやすかったし、いろんな曲を試せたんですよ。いろんなリズムやアプローチを試せたのは学のベースありきと思うし、その相乗効果としてギターのとんでもないフレーズが出てくるわけですよ(笑)。
谷口:その相乗効果でね(笑)。
──年齢を重ねてきたことで、fOULのようにパーソナルな部分をより出せるバンドが自身の拠り所としてあるのがいいなと感じたところはありますか。
大地:映画の中で学が「fOULは自分のすべて」と話しているんですけど、俺にとってもまさにそうなんです。人生、山あり谷ありの中でfOULはちょっとのあいだ止まっていただけで、今またこうして動かし始めてfOULが自分の人生の一部になっているのが凄く心地いいんですよね。これでまたfOULをやれないことになったら、俺自身のバンド人生がついに終わるかもしれない。だから絶対にやめたくないし、それくらい本気なんですよ。
平松:今はこの状況を噛み締めながらやらせてもらっていると言うか。「齟齬」や「大人になる予感」、「煉獄のなかで」や「fOULの皮算用」といったちょっと地味だけど8ビートのいい曲がfOULにはあって、その良さを弾きながら再確認してるんです。ああいう曲ってなかなかできないと思うし、今になってその良さを再確認できる喜びもあるし、その上でこれからまた新しい曲を作れるのは最強じゃないかと思って。