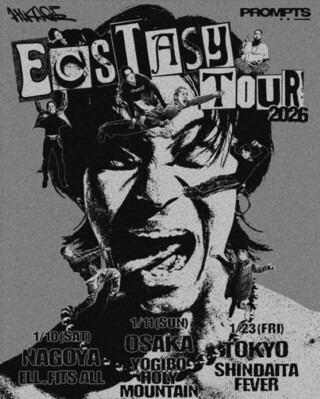運命を変えたコステロの前座経験、高橋幸宏との再会
──1979年に入ってからのロケッツは月一ペースで新宿ロフトに出演していますね。
鮎川:ライブをやりたくて上京しとるし、1日でも時間が惜しくてね。双子の娘たちは実家に預けてきとるし、有難いことにシーナの親父が「子どもたちはわしらが見とっちゃるけ、今のうち思いきりやってきない!」ちゅう感じで背中を押してくれたので、東京に来とるちゅうことは今思いきって音楽をやらんと悔いが残るっちゅう切羽詰まった感じでずっとおったね。そやけん、東京におるあいだに僕とシーナはライブがなくても新宿と下北のロフトや屋根裏まで友達のライブを観に行ったりしてた。
──新宿に比べて下北沢のロフトへ出演した回数は少ないですよね。
鮎川:1979年の最初のほうに出たね(2月2日、3月2日)。前の年の12月にレコーディングを完了して、そのちょっと前にコステロの初来日ツアーで僕らがオープニングアクトに抜擢されてね。ツアー初日の1978年11月23日、シーナの誕生日がシーナ&ロケッツを名乗った初めてのライブやったけど、その6カ所のツアーが当時の僕らにはでかかった。柏木とトムス・キャビンちゅうプロモーターの麻田浩さんが僕らを起用してくれて、それはもうカルチャーショックもいいとこでね。当時のコステロは怒れる若者の旗手、まさにパンクロックスターの象徴みたいな感じで、僕より6つくらい歳下やったけど凄い認めとった。サンハウスの終わり頃にはジョナサン・リッチマンやコステロ、ミンク・デヴィルといったニューヨークのCBGB常連バンドに凄い影響を受けてたしね。
──コステロの来日公演は、ロケッツがYMO人脈と邂逅する契機でもありましたね。
鮎川:(高橋)幸宏が一ツ橋の日本教育会館のライブを観に来て、3列目くらいにおるのをステージから見つけてね。久保田麻琴とサンディーが一緒にいて、ライブ中にこっちに聞こえるくらい大きい声で「あ、鮎川君だ!」って指差されてやりにくいなあと思った(笑)。でも終わってから幸宏が楽屋に訪ねてきて、凄く激励してくれてね。「細野(晴臣)さんもきっと君たちのことを気に入ってくれるはずだからぜひ紹介したい」って言われて、後日すぐに連絡が来た。YMOがその年の暮れに六本木のピット・インでいわゆる業界お披露目ライブをやるというので、ゲストで出てくれないかと呼ばれて。確か12月20日と22日、2回あったのかな。サディスティック・ミカ・バンドのミカさんと、ビートルズの『ホワイト・アルバム』でアシスタント・プロデューサーを務めたクリス・トーマスさんが狭いピット・インのフロアにいたりして。あの日、幸宏がコステロのライブを観に来てなかったら僕らがアルファレコードに移籍することもなかっただろうし、その意味でも幸宏はキューピッドやった。幸宏とはサンハウスのときにミカ・バンドと九州で2、3回共演して知りおうとったけれども、向こうはすでに大物やったからね。そんな幸宏が気さくにコステロの来日ツアーの楽屋へ顔を出してくれたことで、僕らの運命が大きく変わった。あの出会いがなかったら僕らは柏木と一緒に迷路にハマって終わっとったと思うよ(笑)。
──エイプリル・フール〜はっぴいえんど〜キャラメル・ママ/ティン・パン・アレーと渡り歩いてきた細野さんがアルファ在籍時代のロケッツの作品をプロデュースするという、畑違いの両者ががっぷり四つに組むのが面白かったですね。
鮎川:確かに畑は違ったけど、始まりはビーチ・ボーイズやったりストーンズやったりビートルズやったり、昭和20年代生まれのもんたちは1964年のブリティッシュ・インヴェイジョンにみんな頭をやられとるからね。幸宏やらも唄えばジョージ・ハリスンみたいな節回しやし。細野さんとはリハーサルの前に紀伊國屋ホールで会ったのかな。行ったときにはもうYMOのコンサートは終わっとったけど楽屋で初めてご挨拶して、「おお、細い!」とか言われて(笑)。少しは僕のことを知っててくれたのが嬉しかった。細野さんは日本のフォーク/ロックの重鎮で凄く尊敬しとる人やったし、「サンハウス、知ってます」と言われて、わあ嬉しかねえ…と思いよったら「ピット・インのゲストでどうでしょう?」ちゅう話になって。その話を引き受けて、赤坂のスタジオへリハーサルに行ったんよ。買い物袋にフェンダーのテレキャスターを突っ込んで(笑)。そこでYMOのメンバーとも打ち解けて、ライブでは途中に入って3曲くらいカバーを一緒にやるのはどうかって話になって。僕が提案したのはチャック・ベリーの「COME ON」とストーンズの「(I CAN'T GET NO)SATISFACTION」の2曲で、YMOからはビートルズの「DAY TRIPPER」ならやれるっちゅうことになった。「SATISFACTION」はコステロの前座のときにディーヴォのスタイルを意識して演奏してたのを幸宏が覚えててくれて、YMOのアレンジにはもってこいやけっちゅうことで。「COME ON」は細野さんのシンセベースが入った感じでね。「DAY TRIPPER」は後に『SOLID STATE SURVIVOR』に収録されるけど、実はその「DAY TRIPPER」こそ僕がギターを持って初めてステージに立って演奏した曲で。
──中洲のダンスホールでハコバンする以前に組んでいたバンドがあったんですね。
鮎川:うん。ビートルズが日本に来た1966年、武道館でライブをやったときはチャック・ベリーの「ROCK AND ROLL MUSIC」から始まって、「SHE'S A WOMAN」や「BABY'S IN BLACK」なんかが披露されて、いい所で「DAY TRIPPER」をやる。あれに頭をやられてしもうとったから、久留米の石橋文化センターちゅう所でやる夏祭りのために初めて誘われて組んだバンドで「DAY TRIPPER」をやれるっちボーカルの名前も知らん奴から言われて、ギターは上手く弾けんけど曲はもう完璧に知っとるからっちゅうんで半ば自分を売り込んだ感じで一緒に演奏して、そのまま自然にメンバーになったのが一番最初のバンド体験やった。それがザ・スランパーズっちゅうバンドで、『サマービート66』っちゅう夏祭りで。それも去年、久留米の若いロックバンドの仲間とそのバンドを54年振りに復活させたの。今年も二度目の復活ライブをやる予定やったけど、コロナの影響でできなくてね。でもまた復活しようと策略しとるけど。
新宿ロフトで共演したRCサクセション、プラスチックスらとの交流
──ぜひまた復活させていただきたいですね。ロフトの話に戻りますが、1979年2月25日にはプラスチックスと、同年7月5日にはショットガン、7月19日にはRCサクセションとそれぞれ対バンしています。いずれも覚えていらっしゃいますか。
鮎川:ショットガンはサンハウスのドラムだった浦田(賢一)のバンドやしね。RCはね、坂田(喜策)君ちゅうマネージャーがもともと久留米出身のイベンターで、サンハウス時代からよく知ってた。チェリーボーイズっちゅうバンドをマネジメントしてて、サンハウスが京都の円山公園音楽堂でダウン・タウン・ブギウギ・バンドとかと一緒のイベントに出たときにばったり会ったり。その後、僕らが上京した年の夏頃に渋谷のジァン・ジァンへRCを観に行ったときに坂田君と再会して、そこで「今はRCをやってます」とバンドを紹介してもらったんやけど、チャボ(仲井戸麗市)はまだいない過渡期だった。ちょうど(忌野)清志郎がフォークからロックに変わっていくような時期で。それと同じ頃にRCが下北ロフトでやってたから観に行って、そのときの清志郎が奇をてらう感じで、頭にゴムバンドを100個くらい巻いて奈良の大仏様みたいに摘んだヘアにしてて。それを見たシーナが「それはやめといたほうがいいよ」って言っとったね(笑)。そんときにはもうチャボも入って、バンドとしてスタートラインに立ってたけどね。ちょうどその日だったか別の日だったか、ブリンズリー・シュワルツっちゅうイギリスのザ・バンドみたいな名門バンドのメンバーが、グラハム・パーカー&ザ・ルーモアというバンドで来日してて、中野サンプラザへ僕らが観に行ってて。グラハム・パーカーはスターっぽくちょっと威張っとったけど(笑)、ルーモアのメンバーはパブロックの人やけ凄い気さくでフレンドリーで、彼らが東京のロックシーンのことを気にかけよったけ、それで確か僕が誘ったのかな。下北のロフトでRCが今日ライブをやってるち小耳に挟んどったからみんなで行こう行こうちなってね、確かグラハム・パーカーも来て。そいで来ただけじゃなく、ちょうどRCもステージが全部終わって、なんか1曲やりたいねっちゅう話になってみんなステージに上がって、RCの楽器を借りて一緒に演奏したんよ。そのときにやった「STICK TO ME」っちゅう当時一押しの曲の格好良さと言ったらもう、鳥肌もんやったね。適当にやるじゃなくてアレンジも完璧に為された状態で、それを他人の楽器でいきなりリハもなくバチッとキメるわけ。あれは凄いもんやった。僕が混ざって入る余地なんてなかったし、これがプロかと思ったね。店に合わせず、自分らのバンドサイズでバチン!とやる感じがあって。
──そんな歴史的セッションが下北沢ロフトで繰り広げられていたとは…。
鮎川:あと、ルーモアのメンバーに「僕らは『COME ON』をレコーディングのレパートリーにしとる」ちゅうたら凄い気に入ってくれて、その流れで福岡へ一緒に行ってね。サンハウスが拠点にしとった“ぱわあはうす”ちゅうロック喫茶でジャムセッションをしたりして、それがコステロの前座をやる1カ月前だったのかな。ちょうど僕らが『涙のハイウェイ』でデビューする頃やったと思う。1978年の10月25日。そやけその前後に僕たちは東京にもいるし、福岡にもいる感じでね。当時はエルボンレコードとフォノグラムのプロモーション・チームが動いてて、有線放送の拠点を挨拶して回った。1回でも余計にかかりますようにちゅうて、「『涙のハイウェイ』よろしくお願いします!」とシングル盤を置いて。その福岡の有線放送を回る予定とグラハム・パーカー&ルーモアの福岡でのライブの予定がたまたま重なったんだね。そういうロックの夢みたいな出来事がデビュー前後にぼんぼん起こり出してた。
──ロケッツが終演後のロフトで他のバンドとセッションすることはなかったんですか。
鮎川:ほとんどなかったね。一緒にセッションできるほど音楽の共通項がなかったし、そもそもおこがましいし。僕らはローリング・ストーンズが好きやから言われれば何でも弾けるけど、こっちから「ストーンズのあの曲やろうぜ」とかはあの時代は言えんかった。それぞれのフィールドもあったし、音楽的に好き嫌いもいろいろあったしね。
──『#1』のレコ発が『LP発表会 大セッションパーティー』と題されたライブでしたが(1979年2月25日、新宿ロフト)、山本翔さん、プラスチックスというゲストの顔ぶれに当時の交友関係が窺えますね。プラスチックスとは、ロケッツとRCサクセションの3組で『POP'N ROLL 300%』という武道館公演を翌年成功させていますし(1980年8月23日)。
鮎川:プラスチックスとはすぐに友達になったね。(佐藤)チカがスタイリストやったり、トシ(中西俊夫)は元祖DJの一人やったし、佐久間(正英)君は四人囃子をやっててプラスチックスで唯一のミュージシャンやったり、彼が四人囃子の頃からサンハウスはすれ違ったり会ったりしてたしね。それですぐ仲良くなれた。当時、表参道に原宿セントラルアパートっちゅうのがあって、その1階にあったレオンちゅう喫茶店へ行けばカメラマンの鋤田(正義)さんやら糸井重里、佐久間君たちの仲間…立花ハジメとかもよくいた。細野さんやらも来たりするし、いろんな人たちとそこで会うことが多かった。レオンにちょっと寄ってコーヒーを飲んで帰ろうちゅうてシーナと行くと誰がいる彼がいる、こんにちはちゅう感じでね。僕たちはたまたまバンドをやりよったけれども、レオンに集まる人たちはみんな広い意味で音楽仲間みたいな感じやったね、業種やアプローチは違えども。僕らは人前で演奏してわくわくしとるけど、みんな元はラジオからロックンロールを聴いて興奮した同じ音楽ファンだった。僕らはレコードを聴くより自分たちでバンドをやったほうが楽しいことに気づいてバンドを始めただけで、音楽が好きでロックが好きでっちゅうのはみんな同じやった。