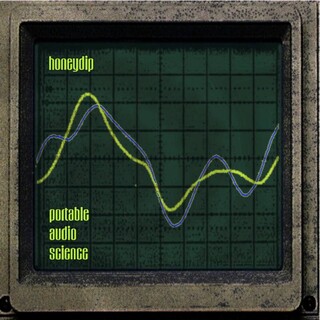バンドには奇跡を起こす力がある
──どんなセットリストでも臨機応変にプレイする奈良さんと川嶋さんの力量も凄いですよね。
鮎川:うん、もの凄い。何でもできるメンバーと今もこうしてずっと一緒にやれてるし、こんなに幸せなことはない。川嶋はほとんどのレコードでドラムを叩いてるし、奈良は途中10年ほどEXとか松田優作のバンドでも活躍してたけど、サンハウス時代からずっと一緒だから。今も川嶋と奈良とやれてるのはバンドの誇りだね。そして今はルーシーがシーナの歌をあんなに唄える驚きと喜びがある。シーナのお腹の中でずっとシーナの歌を聴いてたのは伊達じゃないし、「こんなにステキな歌をもっとたくさんの人に聴いてほしい」っちルーシーが心から言うんがとても嬉しい。たとえば「『HELP ME』やろう」とかね。あれはシーナのソロ・アルバム(『いつだってビューティフル』)に入ってる立花ハジメが作曲した歌で、サックスが入っとるし、細野さんプロデュースだからテクノサウンドやし、ルーシーはそういう曲をいきなり唄うてみたいと言い出して僕らは驚くけど、それが新鮮だったりもする。彼女はDARKSIDE MIRRORSちゅうバンドをずっとやってたから、バンドのこともよく分かってるしね。とにかくまたロフトでワンマンをやれるのは楽しみだし、夢のようだね。
──こちらこそです。日本で40年以上ノンストップで活動を続けるバンドもそうはいませんし、ロケッツにはまだまだ現役でいていただきたいものですね。
鮎川:ありがとう。バンドが仲良くずっと一緒にやるのは大変やけんね。音楽の好き嫌いも人間の好き嫌いもあるし、酒が入って人格が変わったりとかいろいろあるし(笑)。それも自分らの好きなことで稼がないかんし。それがギリギリやれてるっちゅうのは有難いことだね。
──今もこうしてバンドを続けている原動力は何なのでしょう?
鮎川:他に何やるの? ちう感じ。こんなに楽しいことは他にないし、そこにずっとしがみついとる感じだね。自分がもういいやと手を離せばいつでも簡単に吹き飛ばされてしまうし、そもそも誰に頼まれてやってるわけでもないし、誰かと契約したり約束してやってるわけでもない。ただ自分らがやりたいっち意志だけでここまで来て、次のライブがなければ自然消滅するだけ。でも自分がやるっち言えばまだやれるけんね、有難いことに。
──ロケッツがバンドをやり続けてくれることが僕らにとって勇気になるというか、われわれライブハウスも去年からのコロナ禍で思うようにライブがやれず、悔しい気持ちを何度もしてきました。そこで歩みを止めるのは簡単なことで、何かを続けることの大事さや尊さを身に染みて実感したんです。それはバンドマンでもライブハウスに携わる人間でも同じことだと思うのですが。
鮎川:長く続けてきたからこそ出せる音があるし、今もとにかく僕らが思う最高の音を出したいし、その音を聴いてもらいたい。それに尽きるし、それは僕が『サマービート66』に出たときからずっと変わらない。あの夏祭りに出たときのドキドキと、1人じゃ大したことはできなくても4人が集まってガーン!ちなったときにホントに凄いもんが生まれるあの感覚は絶対に忘れられない。バンドにはそういう奇跡を起こす力があるからね。それをロックの神様がステージの片隅から見ててくれる。そこで大事なんはどれだけ音で勝負できるかで、バンドはそりゃ格好もようないといかんし、頭の中も冴えとかないかんし、仲良しで売ったりお洒落で売ったりいろんな売り方もあろうけど、ロックバンドはいかに音でノックアウトさせるかが大事なんよ。僕らはゾンビーズを聴いてあの独特の音やムードにやられたし、ロキシー・ミュージックもそうやったし、いろんなロックを聴いて素晴らしい音と出会ってきた。デヴィッド・ボウイもいい男やけ惹かれたけど、やっぱりあのボウイのサウンドが素晴らしいからなお格好良く見えたわけで。ストーンズがいまだに魅力的なのは決断力の音をしとるから。ちゃんと弾けるのか? っちハラハラするくらい心配しても、ライブが始まるともうさらわれてしまうもんね。そういう音を僕らもまだこれから出していきたいし、バンドは奇跡を起こす力があるのを今も信じてる。奇跡なんて言うと柏木が付けた“ミラクルメン”ちゅうバンド名を肯定するみたいであれやけどね(笑)。