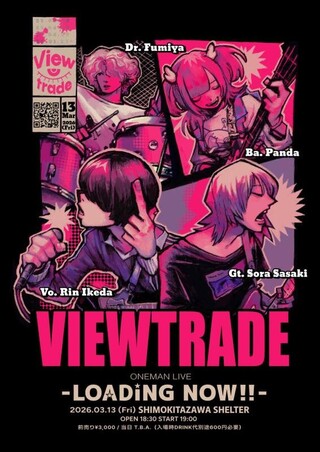ひとりにひとつずつ〈パペトピア〉がある
──『ずっとさがしてる』は中盤にあやつり人形の歌で物語を進めていく手法が取られていて、最後も「♪どこいったの?」という歌で締められます。これまでの作品はカヨさんの弾くピアノが劇伴の主体でしたが、『人造生物ホーンファミリー主題歌』や『パペトピアの歌』然り、〈歌〉を物語の中で効果的に使う作風が近年顕著になったように感じますが、それは意識してのことですか。
カヨ:人形に台詞を与えるということに違和感があって、言葉がないことでかえって語れること、にこだわってきたように思いますが、『人造生物ホーンファミリー主題歌』で歌詞を書いたときに、言葉があることで短くスッキリ伝えられること、歌は歌であって台詞ではないので違和感がない、ということに気づきまして。今さらなのですが。そういえば小磯さんはもともとボーカリストじゃないか、ということも思い出したりして、唄ってもらうのが面白くなってしまい、『すっとさがしてる』『パペトピアの歌』と続けて歌をつくりました。歌と物語との組み合わせは今後もやっていきたいと思っています。
──実際に『人造生物ホーンファミリー』という番組自体をつくってしまおうとは考えませんでしたか。
小磯:つくりたいという気持ちはあります。つくりたい、というより自分たちで観てみたい。でも一体どんな番組だったんだろう、というのはまだ想像の段階なので、いつか、まるでその番組の秘蔵映像が発掘されたかのようにはっきりと、二人の頭の中に浮かんでくるまでは待とうと思っているんです。
 ──『パペトピアの歌』では「みんなと一緒にいるときにふとひとりぼっちみたいな寂しい気持ちになる、そんなときは心の中でこの歌を唄う」と歌唱パートに導かれて、「ひとりで遊ぼう」と唄われます。また、「ひとりにひとつずつ〈パペトピア〉がある。そう思えばいい」という博士の台詞も強く印象に残ります。〈パペトピア〉=パペット(あやつり人形)+ユートピア(理想郷)の造語だと思いますが、この言葉にはどんな思いを込めたのですか。どれだけ失意の淵に沈んでも心の安寧さえ守れば良いというメッセージでしょうか。
──『パペトピアの歌』では「みんなと一緒にいるときにふとひとりぼっちみたいな寂しい気持ちになる、そんなときは心の中でこの歌を唄う」と歌唱パートに導かれて、「ひとりで遊ぼう」と唄われます。また、「ひとりにひとつずつ〈パペトピア〉がある。そう思えばいい」という博士の台詞も強く印象に残ります。〈パペトピア〉=パペット(あやつり人形)+ユートピア(理想郷)の造語だと思いますが、この言葉にはどんな思いを込めたのですか。どれだけ失意の淵に沈んでも心の安寧さえ守れば良いというメッセージでしょうか。
小磯:そうですね、〈パペトピア〉は心の中にある、ひとりで逃げ込む場所なんです。そこには悲しいことも何もわからないで、ただ遊んでいる小さな自分がいる。そんな自分と無心になって遊ぶことができたら、寂しさも辛さも消えちゃうよ、という思いを込めました。
カヨ:「ひとりにひとつずつ〈パペトピア〉がある。そう思えばいい」という博士の台詞が印象に残る、と言っていただけて嬉しいです。最初のバージョンでは博士に「〈パペトピア〉は誰にでもある、みんなだって同じだ」と言わせて、同じ舞台でみんなが踊っているような描写をしていたのですが、そこには矛盾があるのでは、というご指摘をいただき、なるほど、と考え直しました。〈パペトピア〉はひとりになる場所であるはずなのに、まるで他のみんなもそこにいるみたいなのは確かにおかしい。そこで「ひとりにひとつずつ〈パペトピア〉がある、そう思えばいい」というふうに書き換え、同じように見えてもちょっとずつ違う、といってもカーテンの色が違うだけなのですが、とにかくちょっとずつ違う、それぞれの〈パペトピア〉に変更しました。別に他のみんなにも〈パペトピア〉がある必要なんかないし、そんなことは気にせずにひとりで遊べばいいんだとは思います。でも「そんなふうに逃げているのは君だけじゃないはずだ」ということを博士に言ってもらわないと、思いきりひとりになって遊ぶことすらできない、そんな弱虫の自分のためにこの台詞を入れることにしました。情けないことに、ひとりになりたい、という気持ちと、ひとりになりたくない、という気持ちがいつもせめぎ合っているんですよね。そういう気持ちも隠さずに表現することにしたんです。
カヨの〈ひとり遊び〉を作品にするための行為=ReguReguかもしれない
──先日、美術家・作家の伴田良輔さんと話をした際、少女とはひとり遊びが上手な存在であるという興味深い持論を伺いました。「少女はおはじきをしたり絵本を読んだり、常にひとり遊びをしている。自分の世界を自分で築いて、その主人公になっている。少年にもそういう要素はあるけど、少女ほど空想力は豊かじゃない」と。『パペトピアの歌』の「ひとりで遊ぼう」という歌を聴いて、その伴田さんの話を思い出したのですが、〈少女性〉はReguReguの作品づくりにおいて不可欠な要素だと思います。小磯さんは自身の〈少女性〉をどう捉えて作品づくりに活かしていますか。また、カヨさんは小磯さんの〈少女性〉をどう見ていますか。
カヨ:「少女とはひとり遊びが上手な存在である」とは確かにそうかもしれません。そういう意味では、小磯さんは〈少女性〉が強いほうですよね。一緒になって空想の中で遊んでいるようなところがあるので。しかしビジュアルがあまりにも〈少女〉じゃないので、その質問には戸惑ってしまいました(笑)。
小磯:小さな頃はスポーツ全般が大嫌いだったので、野球やサッカーに夢中な同性よりも、部屋で女の子と一緒に本を眺めたり、話を聞くほうが断然楽しくて…。でも、決して女性になりたかったわけではなく、男の子の〈そうでなければいけない〉に抵抗を感じていて、そこに友達というより、社会とは別世界にいる〈仲間〉を感じていたんだろうなと思います。だんだん成長して、非常識を美徳とする、ロックに夢中になり、男同士で遊ぶことが増え、それがそのままバンドになって、その頃のことは忘れていくのですが、カヨさんと一緒に何かをつくるようになって、蘇った感覚が確かにあるのです。毎日、彼女と一緒に本を眺めたり、次の作品を考えたりしている今は、〈そうでなければいけない〉世界から外れても幸せだった、本当の仲間のいる自分に戻ったような気がするのです。私の〈少女性〉というのは多分、自分にとっての〈パペトピア〉で、小さな私は楽しく少女と遊んでいるのです。結局、彼女の〈ひとり遊び〉を作品にするための行為がReguReguなのかもしれません。だから才能のある方に手伝ってもらえば、もっと完成度を上げることはできますが、不器用ながらも2人だけで全部やっているのだと思います。
 ──本作の収録作品の中では最古の『触覚』は、むかしは仲の良かった夫婦の物語で、ある日突然、夫の頭に触覚が生えるところから話が転がりだします。『ずっとさがしてる』に出てくるツノの生えた4体の人形もそうだし、『捕食』に登場する触覚のある人形然り、『いちばんのり』のツノの生えた鳥然り、ツノや触覚は近年のReguReguの作品において一貫して重要なオブジェクトとなっています。それらは人間ならざるモノが放つ〈気〉の象徴のように思えますが、どんな意図があるのでしょうか。
──本作の収録作品の中では最古の『触覚』は、むかしは仲の良かった夫婦の物語で、ある日突然、夫の頭に触覚が生えるところから話が転がりだします。『ずっとさがしてる』に出てくるツノの生えた4体の人形もそうだし、『捕食』に登場する触覚のある人形然り、『いちばんのり』のツノの生えた鳥然り、ツノや触覚は近年のReguReguの作品において一貫して重要なオブジェクトとなっています。それらは人間ならざるモノが放つ〈気〉の象徴のように思えますが、どんな意図があるのでしょうか。
小磯:ReguReguの作品に出てくるツノや触角は、他者との明らかな違いを示す、〈しるし〉のようなものだと考えています。それは罰を与えられているようにも見えるし、特別な存在であることを示しているようでもある。そのどちらであるかは、見る立場や考え方によって変わってくるものなんだと思います。
 ──『触覚』は、互いに触覚のある夫婦の仲睦まじいスナップで終わります。これはマイノリティに対する共感というか、ReguReguなりの問いかけなのでしょうか。
──『触覚』は、互いに触覚のある夫婦の仲睦まじいスナップで終わります。これはマイノリティに対する共感というか、ReguReguなりの問いかけなのでしょうか。
小磯:そうですね。小さなことでも深刻なことでも、何かを抱えている人みんなに、隠さなくてもいい相手がいて、隠さなくてもいい場所があればいいのにな、と思います。そんな単純なことではない、と怒られてしまいそうですが、本当にそう思います。