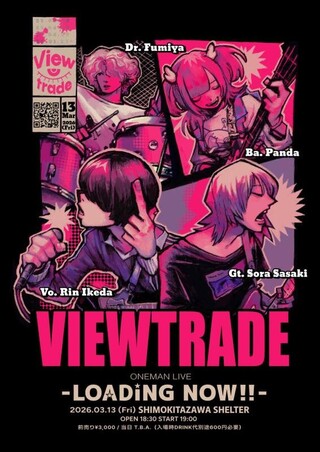かつてアイゴンこと會田茂一が、「そこらへんにあるようなパーツを工場で組み合わせただけみたいな音楽が多いけど、ブッチャーズはネジ一本から自分たちでつくってるっていう感じ」とブラッドサースティ・ブッチャーズの音楽を評したことがあるが、札幌在住のアートユニット・ReguRegu〈レグレグ〉は自身のあらゆる表現をネジ一本からつくりあげようとする稀代の魔術師だ。毛皮や骨で出来たパペットの制作、物語の原作、撮影、編集、サウンドトラックの作曲、演奏と歌、録音と、すべての作業を小磯卓也とカヨの二人だけで無から生成して現実化するという純度の高い表現を徹底している。
彼らの分身であるパペットたちは皆あいくるしく愛嬌たっぷりで、ストップモーションによって祈祷を捧げるように命を吹き込まれた様は現実に存在しているようにしか思えぬほど。まさに異聞奇譚としか言いようのないビターな物語は、透徹な世界観と緻密な舞台設定も相俟って、虚構と現実の境界線をひどく曖昧にする。彼らが魔術師たる所以である。
ReguReguの5年ぶり3作目となるショートフィルム作品集『パペトピア』は、この10年のあいだにネジ一本から生みだしてきた呪術の集大成であり、今の彼らが次のフェーズへと向かう過渡期にあることを感じさせる会心作だ。ストップモーションの技法も細密につくり込まれた奇怪な物語も一段と深みを増し、着実な進化が窺える。その進化が決してとどまりそうにもないことは、本作に収録された8篇の優れた短編と2篇の良質なミュージックビデオが雄弁に物語っている。と同時に、この『パペトピア』はひとりぼっちの世界に生きるすべての人々へ捧げるReguReguなりのエールでもある。〈パペトピア〉という心の拠り所でひとり遊びに興じる人たちに向けた、ささやかだけどありったけの、全力のエールだ。
〈パペトピア〉への扉はいつでも誰にでも全方位に開かれているし、〈どうしてもこんなことがあるやうでしかたないといふこと〉で満ちた異界迷宮に身を委ねるのも悪くない。おとぎの国と現実世界の結界をたゆたうReguReguの真骨頂、とくとご覧あれ。(interview:椎名宗之)
この5年のあいだの環境の変化、影響を受けたモノたち
──前作の発表から5年のあいだに作品づくりに影響を与えた出来事、あるいは映画や小説などの作品はありましたか。
小磯:前に住んでいた、元は下宿屋だった古い家から、やっぱり古いのですが、小さな森のような庭のある家に引っ越したことで、以前なら難しかったことができるようになりました。たとえば『捕食』に出てくるダンボールハウスを実際につくっちゃうとか、『ふとどきな果実』での、生えているヒメリンゴの木と、家のセットを組み合わせたりとかです。アトリエ以外に、誰にも気兼ねなく作業のできる野外を得たことにより、表現できることの幅が広がりました。
カヨ:札幌の美術家、斎藤幹男くんから、エンドロールで「え〜っ…」と言ってしまうような映画をいろいろ観せてもらった時期があったんです。「え〜っ…」という感じというのは説明が難しいのですが…。具体的には『トスカーナの贋作』(アッバス・キアロスタミ監督)、『太陽はひとりぼっち』(ミケランジェロ・アントニオーニ監督)、『永遠の語らい』(マノエル・ド・オリヴェイラ監督)などで、こうだと思って観ていると、いつの間にか違うところに連れていかれていて、結果的には感動しているというような、固くなった脳をぐにゃぐにゃにされる感じです。ちょうどその時期、個人的にカフカに浸っていたので、カフカの世界にも通じるその表現にすごく影響を受けました。ジャンプしたところとまったく違うところに着地するような作品をつくりたい、と。この影響は作品集『パペトピア』の中では『ずっとさがしてる』に色濃く出ていると思うのですが、まだまだうまくできていません。最近では、映画プロデューサーの福間恵子さんのエッセイ(ドキュメンタリーマガジンneoneoのWEB版に掲載の『ポルトガル、食と映画の旅』)で紹介されていて、アントニオ・タブッキという作家を知り、『インド夜想曲』という小説で同様の衝撃を覚えました。この感覚をもっと突き詰めたい、とますます思っているところです。
──去年の8月に高円寺のアンノウンシアターで『ReguRegu Film of 2014-2017』という上映会が開催されましたが、観客に生でショートフィルムを観てもらう経験がその後の作品づくりに活かされたところはありますか。
小磯:札幌でもやったことがなかった単独の上映会はいろいろと嬉しくて、ついつい舞い上がってしまい、冷静な自分を取り戻すのに数日かかったほどでした。たくさんの人に観てもらえたことはもちろん、『私たちの夏』『秋の理由』など、私たちが影響を受けた作品を撮った福間健二監督夫妻、そして、ヤン・シュヴァンクマイエルやチェコアート研究の第一人者の赤塚若樹さんに会場で褒めていただいたことは、大きな自信になりました。
──3作目となる作品集をつくるにあたり、気に留めたのはどんなことですか。
小磯:前の2作は、ミュージックビデオ以外の短編作品を時系列で並べていたのですが、今回は時系列ではなく全体の流れを考えた順番にしました。ひとつずつ好きなように選んで観ていただいても良いのですが、「ALL PLAY」で一気に観ていただくと、よりReguReguのやりたいことが伝わるんじゃないかな、と思います。
「本当にこんなことがあった」と思えるくらいまで思いつめる
──『人造生物ホーンファミリー主題歌』、『ずっとさがしてる』、『パペトピアの歌』の3作はいずれも額の真ん中にツノの生えた4体の人形と博士が登場するので関連作と言えますが、ReguReguの作風には〈設定のつくり込みの面白さ〉があると思います。ある孤島で博士がツノの生えた人造生物をつくっていて、それらを主人公にした子ども向けの番組が制作されて日本と旧ソ連で放送されたものの、あまりの内容にスポンサーが1話限りで下りてしまい、フィルムも火災で焼けて残っていない…。虚構でありながらいかにも実際にあったような話に思えるし、昨年、札幌のギャラリー犬養で開かれた個展では実際に『人造生物ホーンファミリー主題歌』のシングル盤のジャケットまで展示されていました。まず、『人造生物ホーンファミリー』という番組はどんなものにインスパイアされて着想に至ったのですか。不穏なピアノと歌が主体の主題歌は『妖怪人間ベム』を連想させますが。
小磯:主題歌はおっしゃる通り『妖怪人間ベム』のような雰囲気にしたくてつくったのですが、そもそもの始まりは何かのインスパイアではなくて、知人からエゾシカのツノを大量にいただいたことが発端でした。このツノで何かつくろう、と考えたことから始まったんです。こんなツノが額に生えている人がいたら、どんなことが起きるだろう。その人はきっとみんなから気味悪がられて、ひとりぼっちになるんじゃないか。それで自分と同じツノを持つ仲間をつくろうとするんじゃないか…。そんな物語を二人の頭の中でどんどん膨らませていきました。
カヨ:私たちは宮沢賢治の『注文の多い料理店』の序文がすごく好きなのですが、その中にこうあります。
「ほんたうにもう、どうしてもこんなことがあるやうでしかたないといふことを、わたくしはそのとほり書いたまでです」
この一文はいつも意識していて、「本当にこんなことがあった」と思えるくらいまで思いつめる、といった感じで物語をつくっています。要するに妄想ですね。だからヘンテコなほどのつくり込みになってしまう。でも「本当にこんなことがあった」と思うのだから仕方がないんです。
 ──『ずっとさがしてる』ではストップモーション・アニメーション以外にモノクロとカラーの実写がふんだんに盛り込まれています。『捕食』や『ReguReguマッチCM』以降、実写を多用することが増えたように感じますが、あえてストップモーション・アニメーションに特化しないのは、来たるべき長編映画の製作を見据えてのことですか。
──『ずっとさがしてる』ではストップモーション・アニメーション以外にモノクロとカラーの実写がふんだんに盛り込まれています。『捕食』や『ReguReguマッチCM』以降、実写を多用することが増えたように感じますが、あえてストップモーション・アニメーションに特化しないのは、来たるべき長編映画の製作を見据えてのことですか。
小磯:長編映画の構想はまだまだ全然できていなくて…。実写を多用しているのは、ただ単に思いついたからなんですよね。もともとアニメーションにこだわりがあるわけではないので、そのときに思いついたアイディアをどんどん取り入れるようにしているんです。これまでにも、『魔女の卵』の鎌田理恵ちゃん、『空の切符』の永田塁くん、といった、身近な人がイメージに浮かんできて、お願いして出てもらう、ということがありましたが、今回も『ずっとさがしてる』で男性と子どもが出てくるシーンを思いついて、友達の木村理臣くん(札幌のデザインユニットAmejikaの一人)と彼の息子さんに出演をお願いしました。さらにダメもとで現場に付き添いで来ていた奥様の安田香澄さん(同じくAmejikaのもう一人)にも出演を依頼、急な申し出にも関わらず快諾していただけて、本当に思った通りの画面ができたのでありがたかったです。
カヨ:『捕食』は段ボールハウスに住んでいながら気持ちは紳士、そしてとても食いしん坊、というキャラクターをまず思いついて、これは小磯さんしかいないと(笑)。基本的には二人だけでつくりたい、という思いはあるのですが、ときどきどうしても思い浮かんでしまうシーンがあって。そんなときには、思い浮かんでしまった人に出演をお願いして、つくるしかない。役者さんではない、雰囲気のある人に、その人のイメージのままで出てもらいたいんです。人形に出演してもらうのと、気持ちは同じですね。