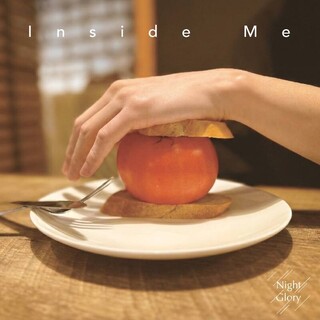「STANDING STANDING」で現在のスタンスの一歩目を成立させた
──『NAKED HEART』でデビューして以降は、矢継ぎ早にアルバムをリリースしましたよね。
OKI:『NAKED HEART』(1988年11月)、『VOICE』(1989年7月)、『MANIFESTO』(1990年3月)と、1年半の間に3枚のフル・アルバムを出してますからね。一気にホール・クラスのライブもやるようになったし、まぁバブルの頃だしそういう時代だったんですね。ところがそこで最初の事務所が飛んで、体制が一度ポシャるわけですよ。マネージメントにいろんな不具合があったり、急成長していく状況に追いついてないような感じで、いろいろと不本意なこともストレスも多かった。一度まる裸になって、そこから状況を立て直していくなかで、広島時代のメンバーである市川にもう一度声をかけてレコーディングしたのが2枚目のシングル「BARRIER CRASH」(1990年11月)でした。
 ──ということは、ターニング・ポイントになった2曲目の歌は、その「BARRIER CRASH」ですか?
──ということは、ターニング・ポイントになった2曲目の歌は、その「BARRIER CRASH」ですか?
OKI:そこからの、次の「STANDING STANDING」(1991年3月)にかけてですね。曲そのものというよりアルバムとしての『STANDING STANDING』。それを含めた、その時期が間違いなくターニング・ポイントでした。デビューからアルバムを2、3枚出してポシャるとそこでバンドは終了、っていうケースが当時は多かったし、そこで潰れるか、それともそこから新たな状況を切り開いて前進してゆくかの選択を迫られるバンドは当時俺たちに限らず多かったと思うんですよ。たとえばデビュー時に比べて宣伝の予算が大幅に減るとか、メディアへの露出もぐっと減るとか、条件もいろいろ厳しさを増してくる。でもそういうなかでもビーツの場合はもちろん前進していくことを選んだ。ここでもう一度しっかりと地に足を着けて、自分の足で立ち上がらなければダメだなと。だからこその重要なキーワードとしての「STANDING STANDING」、浮かれずに自分の足で立つべきだと。その意志表示のアルバムを作れたのは、ビーツの歴史のなかではすごく大きなことでした。いまに至る活動のスタンスの土台にもなっていると思いますしね。このアルバムの時期から男の客が格段に増えたというのもある。その意味でも現在に至るまでのスタンスの一歩目をここで成立させたと言えますね。
ワイルドサイドを生きる信条を唄った「I WANNA CHANGE」
──1991年1月に市川さん、同年10月に昌司さんが正式加入して、広島時代の布陣に戻ったビーツのリベンジが始まったわけですね。
OKI:現場的には市川は1990年の6月から、昌司は1991年の年明けから復帰していて、1991年は3月から年末まで1年かけて『STANDING STANDING』のツアーを100本近くやれたんですよ。これでやっとビーツの核的な部分でやりたいように活動ができるということで、めちゃくちゃアクティブにライブをやり続けた年でしたね。俺とSEIZIに市川と昌司というビーツの原点的なところと言うべき面子でね。この1991年はすごく充実していた。ところがその年の暮れに、今度は二度目の事務所が飛んだんですよ。しかも借金を残したまま逃げられたというね。おかげで全国のイベンターも引くし、翌1992年は全国ツアーすらまともに組めないような状況になってしまった。それでさすがに三度目の事務所を探すのもしんどいし、もう自分たちでマネージメントをやるように模索し始めて。だから1992年は年間で20本くらいしかライブをやれなくて。それも直接のやり取りに応じてくれた関東近郊のライブハウスくらいしか日程を組めなくて、地方ではライブができなかった。次のリリースの目処も立たなくて、かといってリリースが滞るのもイヤだったので、先行シングルみたいな形で新曲を3曲、ライブ音源を2曲入れたミニ・アルバム『風の街の天使』を年末に出すことにしたんです。
──『STANDING STANDING』で立て直せたと思ったら、またもやトラブルに見舞われてしまったと。
OKI:当時、1992年から翌1993年を含めてライブのタイトルは、だからずっと一貫して「LIVE ON THE WILD SIDE」と名づけているんですよね。ワイルドサイドを生きる、つまり、楽じゃない道だけどタフに生きていかざるを得ない。事務所もなくて誰がどうやって給料を出すんだというところで市川と昌司はまだ若かったし、不安も大きかったと思うんですよ。そこを俺が何とか体制を立て直しながら、並行して曲づくりも進めていったんだけど、そこでまた俺が次へ次へもっと音楽性を広げていきたいという感じの新曲ばかりを持ってくるものだから、市川と昌司はいよいよしんどくなってしまったんですね。いま思えば無理もないなと思うし、昌司には音楽とはまた別の海外移住というもうひとつの将来の夢もあったりしたし。まぁ結局そんなこんなでビーツはまた俺とSEIZIの2人だけに戻ってしまった(笑)。それを受けて『ワイルドサイドの友へ』(1994年2月)から、『SPIRITUAL LIFE』(1995年4月)、『LOVE, LIFE, ALIVE』(1996年3月)への流れというアルバム三部作の時代につながっていくわけです。「ワイルドサイド」という概念が自分のなかで重要な意味を持っていた時期。それもまたビーツ史のなかで大きなターニング・ポイントのひとつなので、3曲目は「I WANNA CHANGE」を挙げたいですね。
 ──「ワイルドサイドの友達に 伝えておきたい事がある」と唄われる代表曲中の代表曲ですね。自分らしく生きるために自分の殻を壊し続けていく。トラブルに見舞われたときは「BARRIER CRASH」、壁を壊していく。ビーツの30年に及ぶ歩みはその繰り返しですよね。
──「ワイルドサイドの友達に 伝えておきたい事がある」と唄われる代表曲中の代表曲ですね。自分らしく生きるために自分の殻を壊し続けていく。トラブルに見舞われたときは「BARRIER CRASH」、壁を壊していく。ビーツの30年に及ぶ歩みはその繰り返しですよね。
OKI:そもそもロックで食っていくという選択をした時点で楽じゃない道を自ら選んでるわけですから。自分で選んだ道なんだから弱音は吐かないし、タフに生きていくしかない。
──「I WANNA CHANGE」は後年、映画『クローズZERO』シリーズの主題歌に起用されて脚光を浴びましたね。
OKI:逆に驚きましたよね、十何年も経ってからヒットすることになるなんて思ってもいなかったですから(笑)。『ワイルドサイドの友へ』からの三部作はファンの人たちからすればある意味で衝撃作というか問題作という面もあったわけだし。これは余談だけど、いまのベースの山根とは1991年頃にはすでに知り合っていたし、ドラムの牟田くんはカメラマンの菊っちゃん(菊池茂夫)に紹介されて1993年の秋口には出会っていて。牟田くんには1993年の年末のライブからレコーディングも含めてその後1997年まで5年間サポート・ドラマーとして参加してもらったし、いまにつながる縁はすでに始まっていたんですよね。牟田くんと同じタイミングでベースに上田ケンジ(現・健司)、その後にエンリケに入ってもらって、音楽的な土台は一貫してバンド形態というのが基本にありましたね。その上で詞の世界観や音楽性の幅や柔軟性を広げて、音楽の本質的な部分で勝負したいと思っていました。『ワイルドサイドの友へ』からの三部作はそうした創作意欲の表れだと思うし、いつの時点でもそのときどきのいまある状況をすべてプラスに変えていくというのが、ずっと変わらないビーツの基本姿勢だと思いますね。
背水の陣で書き上げた「十代の衝動」
──では、4曲目を挙げるとすると?
OKI:「十代の衝動」ですね。『LOVE, LIFE, ALIVE』を出した1996年は景気の落ち込みも顕著になってきたり、音楽業界全体としてもそれまでより特にロックのCDが売れない時代に入ってきていて、外資との資本統合だったりとかビクターもいろいろ大リストラをやらなきゃいけないという時代の流れになってきていて。そのなかでビーツも、担当ディレクターだった村木さんもビクターを辞めることになってしまった。ビーツとしては、マネージメントもなければレコード会社もなくなるという崖っぷちみたいな状況に追い込まれて(笑)。そこで勝負の1曲を書き上げたかった。向こう10年持つような強力な歌。そうして生まれたのが「十代の衝動」で、『BEST MINDS』という1996年の暮れに出したその当時の直近5年間のベスト・セレクションに新曲として収録しました。バンドの今後のためにとにかくリリースが必要だったし、そこでほっぽり出されても周りにも説明のしようがない。とにかく鬼のように良い曲を書き上げますからとビクターを説得してなんとかリリースに漕ぎ着けた作品でしたね。
──「十代の衝動」の他にも「RESCUE RESCUE」、「TWO BLACK GUITARS」、「いのちの音」と、本当にクオリティの高い名曲だけで固められた新曲群でしたね。
OKI:向こう10年持つような説得力のある曲をここでつくれなきゃ今度こそ本当にポシャるぞというくらいギリギリの状況でしたからね。そこで「十代の衝動」が書けて、向こう10年どころか結果的にはいまに至る20年以上何とかなっているわけなので、ビーツのターニング・ポイントとしてすごく大きな曲になりましたね。贅肉をそぎ落として、ざっくり切ったら真っ赤な血がほとばしるような、ザラザラな感じの、むしろそのザラザラな質感だけでいい。色で言えばモノクロ。無駄なものは何も要らなくて本質だけを言う。「生き急いでもいいだろ、壊れたってかまわない」。そんな気持ちだけを全力で突っ込んで書き上げた曲ですね。
──原点回帰みたいな部分もあったんですか。
OKI:本質のさらに本質というところだったでしょうね。
 ──逆境に晒されるたびに強度と輝きを増した名曲が生まれるという、不思議な因果を感じますね。ビーツの底力が生半可なものではない証左といいますか。
──逆境に晒されるたびに強度と輝きを増した名曲が生まれるという、不思議な因果を感じますね。ビーツの底力が生半可なものではない証左といいますか。
OKI:もしどこかの時点で逆境に押し流されていたとすれば、俺はいまここにいないわけですからね。時代や状況に対する反骨心や抗う気持ちというのは基本ですね。
──ファンの存在も大きな支えになるのでは?
OKI:もちろんです。ファンの人たちがいなければ始まらない。需要がなければ成立しない。ビーツは大手芸能事務所やスポンサー的なものが後ろ盾としてあったことは一度もないし、支えてくれているのはむかしもいまもファンの人たちです。そしてメンバー、スタッフという「人の縁に恵まれた」こと。すべてにおいて本当に感謝しかないですね。
──「十代の衝動」と並んで「TWO BLACK GUITARS」が今回のベスト・アルバムに収録されたのは個人的にも嬉しいです。
OKI:「TWO BLACK GUITARS」も「十代の衝動」と同じくビーツというものの原点たるところがテーマですね。ビーツの根幹の大元を成す部分を唄っている。作詞・OKI、作曲・SEIZIというのもいい。ベスト・アルバムに入れられて良かったです。ちなみに「十代の衝動」も「TWO BLACK GUITARS」もこの時点ですでに牟田くんがレコーディングでもライブでもプレイしてるんですよね。それが巡り巡っていまに至るという縁の不思議さ、面白さがあるし、ビーツは本当に人の縁に恵まれてここまでやってこれたバンドだなぁというありがたさを実感しますね。