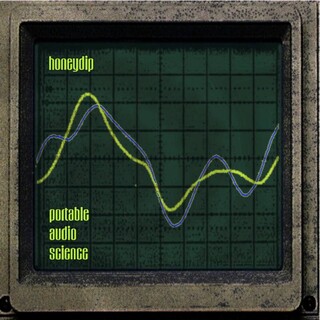映画はあくまで素材で、自分の作品ではない
──でも、その辺のシーンがあるからこそ終盤のチーターズマニアのライブ・シーンが活きるっていうのもありますよね。ところで、谷ぐちさんが「共鳴にサラブレッドみたいな才能があったら映画として成立してなかった」と話していたのですが、YUKARIさんも同感ですか。
共鳴:サラブレッド? なにそれ?
大石:すごく優秀な人ってこと。
YUKARI:共鳴はどう思う? 生まれつき優秀だと思う?
共鳴:思わない。
──思わないんだ(笑)。
YUKARI:わたしもタニの言ってることに同感ですけど、でもなんでかな? とは思いますね。タニもわたしも「自分が、自分が」って感じなのに、共鳴がこんな控えめな性格になるなんて。
大石:よくよく考えてみると、レスザン周りのバンドマンって引っ込み思案な人が多くないですか?
YUKARI:そうかもね。クラスの中では自分を上手く表現できずにいたタイプって言うか。
──確かにシャイな人は多いかもしれませんね。
大石:シャイだけどすごく優しい人が多いから、共鳴くんはその代表なんじゃない?
共鳴:そうかなぁ?
──シャイで引っ込み思案な共鳴くんが、高円寺ドムスタジオへの道すがら「間違えてもいいから、やるしかない」って自分に言い聞かせるように力強く話すのがグッとくるんですよね。
YUKARI:あのシーンは「そんなことを思ってたんだ?」ってびっくりしましたね。
大石:(共鳴に)格好良かったよ。あの後、結局カットしちゃったけど、「格好いいと思うよ、今の共鳴くん」ってわたし言ったもん。

 ──撮る前と撮り終えた今とでは、谷ぐち家に対する印象は変わりましたか。
──撮る前と撮り終えた今とでは、谷ぐち家に対する印象は変わりましたか。
大石:いろんなものがわたしの想像以上でしたね。自分が想像していた家族以上に楽しい家族の姿があって、タニさんもYUKARIさんも共鳴くんもわたしが考えてた以上の個性がありました。
──もっともっと谷ぐち家を密着していたかった?
大石:もっともっとこの家族のことを知りたくなりましたけど、これ以上撮ってるとどこで区切りをつければいいのか分かりませんよね(笑)。リミエキのライブを撮りに行くとすごく元気をもらえるから、ライブを撮りに行く名目で関わりを持ち続けたいとは思ってますけど。
YUKARI:いろんな人がわたしたちのライブを撮ってくれるけど、くらのすけに撮られてるのを意識したことがないんだよね。くらのすけがその場にいると思ったことはあまりないかも。
大石:気づかれないようにしてるし、プレーヤーとお客さんの邪魔をしたくないですからね。だからわたしは目線を低くするんですよ。
YUKARI:カメラも大きいしね。
大石:それもあるし、純粋にライブが格好いいから下から見上げる格好で撮ることが多いんです。自然とそうなっちゃう。お客さんの目線を遮りたくないのもありますしね。川口さんがそういう撮りかたをしていたので影響を受けてるんです。
 ──YUKARIさんの中では、この映画もまたCDと並ぶ自分の作品という意識がありますか。
──YUKARIさんの中では、この映画もまたCDと並ぶ自分の作品という意識がありますか。
YUKARI:自分の作品ではないですね。わたしたちはあくまで素材だと思ってます。映画のパンフレットを作ってると、「あ、そうか。これ自分たちの映画なんだ」とか思ったりはするけど、「自分の作品です」って感じではない。自分から何かをしたわけじゃないし、ただ当たり前の生活を送ってるところをくらのすけがカメラを回してただけだから。
大石:この家族にとっては、この映画もただの通過点ですからね。この間、谷ぐち家の3人で対談する企画があって、その日程を決めてる時にYUKARIさんが「映画を撮ってた去年のことなんてもう忘れちゃったよ」って言ってたんですよ(笑)。それがすごく谷ぐち家っぽいなと思って。
YUKARI:ホントに覚えてないんだもん。映画を何回か観てるから思い出せることもあるけど、それは親から「あんた、3歳の頃にこんなことがあったんだよ」って言われて記憶を後づけするみたいな感じだから。
大石:それくらい1日のうちに起こることが谷ぐち家にはいっぱいあるってことですよね。とにかく異常なスピード感ですから。でもそのスピード感が気持ちよくて、わたしは撮ってて楽しかったんです。