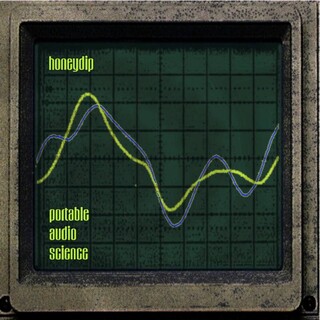映画になることを聞いていなかった共鳴
──レスザンTV周りのバンドを撮る、谷ぐち家の日常にも密着するという話を聞いた時、YUKARIさんは率直なところどう感じたんですか。
YUKARI:格好いいバンドをいっぱい見せたいっていう意図はよく理解できたけど、ウチの家までカメラが入るっていうのはどこまで撮るんだろう? と思って。ちゃんとした部屋着を買わなくちゃいけないのかな? とか思ったり(笑)。
大石:共鳴くんの誕生日プレゼントで鬼怒川温泉に行ったじゃないですか。さすがにそれは家族水入らずで過ごしてほしかったのでわたしは同行しなかったけど、そこで3人が露天風呂でモッシュする映像をタニさんが撮ってきてくれましたよね。それを今回の映画にも使いましたけど、お風呂の中でカメラを回すのってどう思いました?
YUKARI:わたしは全然良かったけどね。
大石:そうなんですか!? お風呂はそれぞれゆっくり入ればいいのに、3人同じ湯船でモッシュしてるっておかしくないですか?(笑)
共鳴:なんでそのシーンが必要だと思ったの?
大石:それはみんなが楽しそうで微笑ましかったから。でもわたしは「入浴シーンを撮ってきてください」なんてパパにお願いしなかったんだよ?(笑)
YUKARI:わたしは入浴シーンが映るの、全然良かったけどな。ただ、風呂場でタニがカメラのアングルを何度も直しに行ってたから、後でくらのすけに局部を見られるんじゃないかと心配したけど(笑)。でも、そういう入浴シーンよりも普通に家の中を撮られるのがイヤだったな。とっ散らかってるし、それがでっかいスクリーンに映るわけだから。後ろの背景をトリミングしてほしかったくらい(笑)。

 ──自分たちの日常生活を撮影して何が面白いんだろう? みたいな気持ちはありました?
──自分たちの日常生活を撮影して何が面白いんだろう? みたいな気持ちはありました?
YUKARI:ありましたね。タニが餃子を頬張りながらわたしと言い合ってるシーンが試写会であんなに面白がられるとは思わなかったし。
共鳴:おれ、知らなかったんだからね。何も言われてなかったんだから。
YUKARI:そうそう、共鳴には映画を撮ってることをけっこうな段階まで言わなかったんですよ。
大石:第一稿のプレビューに共鳴くんが訳も分からず連れてこられて、その時に初めて伝えたんですよね。「実はさ、共鳴くんの映画を撮ってたんだよね」って。
──共鳴くんは自分が映画に出るのを知って、どう思ったんですか。
共鳴:イヤだった。
YUKARI:今は?
共鳴:もう別に…大丈夫。
大石:でも、全部はちゃんと観てないよね?
YUKARI:そうだ。共鳴は自分が出てくると観るのをやめちゃうんですよ。
大石:自分が怒られるシーンになると、試写会の部屋から出て行っちゃって(笑)。もったいないよね、チーターズマニアのライブ・シーンはみんな格好いいって言ってるのに。
 ──YUKARIさんは完成した作品をご覧になって、どう感じました?
──YUKARIさんは完成した作品をご覧になって、どう感じました?
YUKARI:人が映ってるところ、喋ってるところは純粋にいいなと思ったし、いっぱい観てもらいたいなと思ったけど、インフルエンザ事件のところからわたしが一人でベラベラ喋ってる部分はなんだかエラそうだなぁ…って思いましたね。ただ、すごく個人的なことを言えば、たとえばチーターズマニアのライブを終えた共鳴に「よく頑張ったね」って言ってあげるシーンを観ると、自分もこんなふうに親から愛情を注いでもらって育ったんだなと思ったりしたんですよ。いつか共鳴がこのシーンを観てくれたらいいなっていう、そういう個人的な思いはありますね。でも、そういうシーンも含めて映画にして皆さんに観ていただくのはどうなんだろう? っていう気持ちはいまだに拭えない(笑)。
バンドの在りかたをめぐる夫婦の考えの相違
──チーターズマニアが初めてのライブをやるまでのYUKARIさんの共鳴くんに対する親心、同じ板の上に立つ人間としての思いが複雑に絡み合うのが本作の見所のひとつだと思うのですが、あの時期はやはり冷静ではいられませんでしたか。
YUKARI:いや、逆に冷静だったからこそ「このままじゃヤバイぞ」と感じて、練習を怠る共鳴を叱ったと思うんですよね。
大石:YUKARIさんには同じバンドマンとしての意識と親としての意識、その両方があったからあの時は混乱してたのかなと思ったんですけど。
YUKARI:共鳴に対して「ここまで言う必要があるのかな?」とは思ったよね。その辺がタニとわたしの考えかたが違うところで、タニは「バンドっていうのは楽しくやるものだ」っていうのが基本なんです。もちろんわたしもそうなんだけど、人前で表現したり何かを生み出す上でストイックさも大事だとわたしは思ってる。多少イヤなことでも無理して頑張らなきゃいけないとかね。そう思う部分がタニよりも強いんですよ。共鳴にそういうわたしの考えを伝えていいのか、それともタニみたいにもっと楽しくやりなよと伝えればいいのか、そこはちょっと迷いましたね。
大石:でも、YUKARIさんのあの叱咤がなければ共鳴くんはライブをやり遂げられなかったと思いますよ。
YUKARI:それは思う。ただ、辛い練習をやる必要があるのか? っていうのは命題としてあるよね。バンドは楽しいからやるものだと思うし。

 ──チーターズマニアが初ライブをやるまでの過程を映画のハイライトに据えるのは、最初から構想としてあったんですか。
──チーターズマニアが初ライブをやるまでの過程を映画のハイライトに据えるのは、最初から構想としてあったんですか。
大石:撮り始めた段階からチーターズマニアの初ライブが撮りの最終日くらいに考えていました。パンクな家族を中心とした日本のアンダーグラウンドの音楽を描く映画だけど、同時進行で共鳴くんの成長と言うか、チーターズマニアの初ライブまでのプロセスも追いたかったんです。子どもの奮闘をドキュメンタリーで追うと、どうしても『はじめてのおつかい』みたいな感じになっちゃうと思うんですけど、この映画に関してはそうじゃない感じに仕上がったと自分では思ってるんです。ただのサクセス・ストーリーにはなってないと思うし。
──『はじめてのおつかい』は親の目線で子どものハプニングを温かく見守るけど、チーターズマニアのメンバーは共鳴くんを決して子ども扱いせず、同じバンド仲間として対等な立場で共鳴くんと接しているから、『はじめてのおつかい』みたいではないですよね。
YUKARI:チーターズマニアのメンバーは共鳴の友達だし、わたしたち以上に共鳴と親しいですからね。
──レスザンTV主催のライブに集まるお客さん、バンドマンも共鳴くんのことをかわいがるけど、必要以上に子ども扱いをしていないと思うんですよ。あれはなぜなんでしょう?
YUKARI:なんなんですかね。そうあるべきみたいな感じで接してくれるし、それはとてもありがたいことなんですけど。
大石:確かに、当たり前のことすぎて考えたことがなかったですね。他の子どもへの接しかたはもっと違うだろうし。
YUKARI:共鳴は生まれた頃からライブハウスにいたから、彼自身がその環境に慣れてるっていうのもありますよね。
大石:なるほど。ライブハウスでPhewさんと2人でお絵描きして、Phewさんに「ジバニャン描いて」って言えるのは共鳴くんくらいだよね(笑)。
共鳴:ひゅーさん?
YUKARI:会ったら分かるよ(笑)。