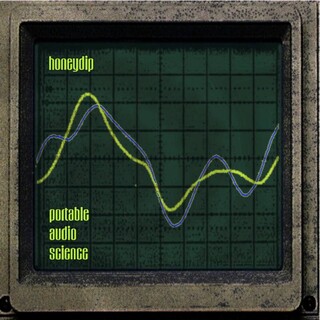共鳴のインフルエンザ事件で深まった仲
──谷ぐち家の3人はカメラを向けられてもごく自然で、身構えたところが全く感じられませんが、それはやはり勝手知ったる大石監督が撮影していたことが大きいんですよね?
YUKARI:だけど、撮り始めの頃はそれほど親しくなかったんだよね。
大石:そうなんです。YUKARIさんはバンドの人、わたしは撮る人で、一線を引いていたんですよ。現場にいてもそこまで深く話したこともなかったですし。ステージでバッチバチにライブをやるYUKARIさんしか観てなかったから、ちょっと怖くて尻込みしてたところもあったと思うんです(笑)。でも話してみたら、こんなに話しやすい人なんだなと思って。
YUKARI:FOLK SHOCK FUCKERSの「イン マイ ライフル」のMVを撮ってもらった時に初めてちゃんと接したんだよね。今回の映画の撮影が始まって、だんだんと距離が縮まっていった感じ。
大石:インフルエンザ事件でYUKARIさんと深く話し込むことがなければ、ここまで親しくなることはなかった気もするんですよ。あの時の新幹線移動でYUKARIさんがいろんな話をしてくれて、こんなに喋ってくれるんだと思ってすごく嬉しかったんです。
YUKARI:あのインフルエンザ事件は自分の中でもすごく大きな出来事で、あの時、タニは車で先に行ってわたし一人だったから、自分の気持ちをくらのすけに吐き出したかったんだと思う。それまでもライブの前後に共鳴が熱を出すことは何度かあったけど、ギリギリ何とかなったんですよ。でも、インフルエンザとなると事は重大じゃないですか。面倒を見てもらう友人にうつしてしまうかもしれないし、重症化して取り返しのつかないことになってしまうかもしれないし。そもそも病気の息子を置いてまでライブをやっていいのか? っていう葛藤がすごくあった。その気持ちを誰かに話すことで自分の中で整理したくて、そのいいタイミングでくらのすけがカメラを回してくれたんですよ。
大石:インフルエンザ事件は撮影の序盤で、それもヘンな話、タイミングが良かったんですよね。そこでYUKARIさんの考えかたを聞いて引き込まれて、その後の方向性を見定めたところもあったので。
YUKARI:自分がどういうふうに共鳴を育てながらバンドをやっているのかを、それまでくらのすけに話したことがなかったから良かったよね。

 ──たとえば監督がよく仕事をご一緒される映像作家の川口潤さん(代表作:『77 BOADRUM』、『kocorono』、『山口冨士夫 皆殺しのバラード』など)の場合、撮影対象との距離を一定に保って必要以上に深入りしない作風だと思うのですが、大石監督は距離感を大事にしつつも対象と寄り添うと言うか、一歩踏み込んで包み込むような眼差しを送っているように思えるんですよね。
──たとえば監督がよく仕事をご一緒される映像作家の川口潤さん(代表作:『77 BOADRUM』、『kocorono』、『山口冨士夫 皆殺しのバラード』など)の場合、撮影対象との距離を一定に保って必要以上に深入りしない作風だと思うのですが、大石監督は距離感を大事にしつつも対象と寄り添うと言うか、一歩踏み込んで包み込むような眼差しを送っているように思えるんですよね。
大石:対象との距離感というものを、わたしはよく理解していないと思うんです。距離感の取りかたがよく分からないからつい近づきすぎちゃうし、川口さんはいつも冷静に距離を一定に保ってるからすごいですね。
YUKARI:まぁ、今回はわたしもタニも「(こっちへ)来い! 来い!」ってやっちゃったからね(笑)。
大石:その「来い! 来い!」がまたすごく楽しそうだったんですよ。今までも仕事でドキュメンタリーはいろいろ撮ってきましたけど、谷ぐち家ほど深く立ち入ることはなかなかできなかったんです。自分からは輪の中へ入っていきづらいところもあったし。でもYUKARIさんもタニさんも最初から「おいでー!」ってわたしを受け入れてくれたんですよね。
YUKARI:確かに「来い! 来い!」言いすぎたところもあって、「今日のくらのすけ、楽しくなりすぎちゃってたんじゃない?」みたいな話をタニともしてたんだよね。仕事じゃなくて、普通に遊んじゃったみたいな。
──YUKARIさんの言う「来い! 来い!」がレスザンTVの本質、真髄なのかもしれませんね。誰とでも分け隔てなくシェイクハンドできる開かれた場だし、新参者でも輪の中へ自由に入っていける風通しの良さもあるし。
大石:そうですね。YUKARIさんもタニさんも常に楽しいことと本気で向き合ってるのを撮影しながら直に感じたので、わたしも映像を撮る人間として楽しみながらもガチで作品づくりに臨まなくちゃいけないと思ってたんです。ふざけることも真剣にやるのがレスザンの流儀ですからね。だからホントは第一稿でOKをもらうくらいの勝負をしなくちゃいけなかったんだけど、完成に至るまでは紆余曲折ありましたね。
谷ぐち家とレスザンTVの良さを出しきれなかった第一稿
──ちなみに、第一稿はどんな感じだったんですか。
大石:わたしがエモくなりすぎてしまって、この家族やレスザンの面白さを出しきれなかったんですよ。なんて言うか、感動で終わらないのがレスザンじゃないですか。この間の『METEO NIGHT』もSTRUGGLE FOR PRIDEで終わっておけばいいのに、締めはタニさんとトクさん(プンクボイ)の相撲ですからね(笑)。結局、2日にわたって何を観ていたんだろう!? っていう気持ちにさせられるレスザンらしさみたいなものを第一稿では完全に見失っていたんです。
YUKARI:いろんな要素を詰め込みすぎて、取捨選択できていない感じはあったかもね。
大石:そう、それも感動モノをいろいろ入れすぎちゃった感じだったんですよ。
YUKARI:わたしから直接くらのすけに「もっとこうしてほしい」とか話したことはなかったけど、第一稿を観た後に家でタニと話していたのは、「何を見せなきゃいけないのかをくらのすけと話したほうがいいよね」ってことで。限られた上映時間の中であれもこれも詰め込むのは無理だから、焦点をギュッと絞らないとね、っていう。
大石:わたしは結婚もしてないし、子どももいないから、今回のように家族や子どもと対峙するのが初めてで、共鳴くんの一喜一憂にだいぶ感化されちゃってたんですよ。
共鳴:カンカってなに?
YUKARI:すごいなぁって感じたり、ジーンとすること。
大石:最初は共鳴くんの細かいネタを随所に入れすぎたところがあって、自分の映画だから別にいいかなとか思ったんですけど、それじゃ全体像が伝わらないなと思い直したんです。
──木を見て森を見ず、だったと言うか。
YUKARI:まぁでも、撮ってる人はあのシーンもこのシーンも思い入れがあるんだろうし、そう簡単には選びきれないんだろうなとは思った。
大石:今回ばかりは「カットするのが辛い…」って本気で悩みましたね。あと、見えかたの問題っていうのがあるんです。YUKARIさんが共鳴くんを叱咤するシーンで、ちょっとキツく言いすぎてるように見えるところがあって。
YUKARI:虐待っぽく見えるやつでしょ?(笑)
大石:そこまでじゃないんですけど、そんなふうに見えてしまう可能性もあるから気をつけたほうがいいよとプロデューサーの近藤さん(近藤順也)から言われて、なるほどなと思って。
YUKARI:確かにそういうのはあるよね。わたしがタニに怒ってるのは全然いいけど、共鳴を叱りつけるのも、彼がインフルエンザになって置いていくのも、観る人によっては誤解を招きかねない。わたしにはわたしなりの考えがあって生活とバンドを両立させようとしているけど、「子どもをないがしろにしてまでバンドをやるなんてどうなんだ?」っていう見かたをする人もいると思うんですよ。だけど、何を言われてもいいんだ、わたしはわたしのやりたいことをやるんだ、って思えるようになったのは、今回の映画を観たからなんです。誰に何と言われようとも自分のやってることは間違ってないと思えたのは、この映画のおかげ。
大石:ホントですか? すごく嬉しいです。

 ──ミュージシャンの中でも、インタビューで新作について話すことによって初めて作品を対象化できたという人がいますよね。
──ミュージシャンの中でも、インタビューで新作について話すことによって初めて作品を対象化できたという人がいますよね。
YUKARI:それに似てますね。この映画が公開されて、わたしたちの家庭環境のことを悪く言う人が出てくるかもしれない。でもわたしたちにはわたしたちなりの信念があるし、胸を張っていられる。特にウチの母はこの映画を観たら絶対に怒ると思うんですけど。
大石:映画が公開されることをまだお母さんには言えてないんでしたっけ?
YUKARI:うん。
共鳴:なんで言えないの?
YUKARI:怒られそうだから(笑)。大阪で上映されるギリギリのところで言おうとは決めてるんだけどね。わたしのことは置いといても、共鳴がスクリーンに映るのは嬉しいはずなので。だから大阪で上映するやつだけ、インフルエンザ事件と共鳴を叱りつけてるシーンをカットしてもらっていいかな?(笑)