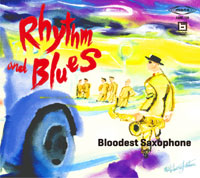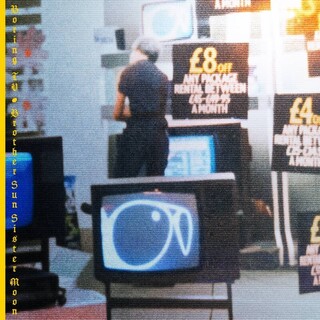日本屈指のヒップなジャズ&ジャンプ・ブルースの雄、Bloodest Saxophone(通称:ブラサキ)の通算8作目となるオリジナル・アルバム『Rhythm and Blues』は、15年に及ぶバンド史上最も高い頂にまで登り詰めた作品であることをここに断言したい。
アナログ一発録音による驚異のヴィンテージ・ハイファイ・サウンドはまさに完全無欠、昨年共演を果たした伝説のホンカー、ビッグ・ジェイ・マクニーリーの代表曲を始めとするセンスの良いカバー曲と秀逸なオリジナル曲のバランスも実に申し分なし。しかもその音楽性に観念的かつ学究的要素は皆無で、誰しもが踊れて泣けてグッとくるという至って大衆性に富んだスタンスが貫かれている。おいおい、ここまで完膚無きまでの傑作を作ったらこの先どうなるんだよと思わずツッコミを入れたくなるほどの逸品なのだ。
ここはひとつ、ブラサキの顔役である甲田"ヤングコーン"伸太郎にご登場願ってこの最新作について尋ねてみよう。これ、日本はおろか、ぶっちぎりで世界レベルの大傑作じゃないですか? と。(interview:椎名宗之)
一番好きで聴いているレコードの音が録れた
──ブラサキのヴィンテージ機材を使ったアナログ一発録音も今作でいよいよ極まれりという印象を受けましたが、ご自身の手応えは如何ですか。
甲田:8作目にして一番いいアルバムを作れましたね。途中、4作目だけはプロトゥールスを使った現代的なレコーディングをしてみたんですけど、それ以外はずっとアナログの一発録音にこだわってやってきたんです。僕らはインスト・バンドなので、自分たちの楽器の出音を一番素直に録れるやり方を第一に考えていて、リズム&ブルースやジャズ、ジャンプ・ブルースといったジャンルの都合上、音と音が被さり合わないとちょっと不自然なんですよ。となると、ブースなしの一発録りしかないということになって。
──ファースト・アルバムからそのスタイルは不変なんですね。
甲田:最初は大田区のホールを借りて録ったんですよ。僕らのやり方だと後でトラックダウンができないので、そこそこの響きがあって広めの所で録るしかなくて、予算もそれほどかけずに借りるには公共の施設しかなかったんですよね。そこにエンジニアのシュガー・スペクターに機材を全部入れてもらって、彼のマイクと卓で録ってもらうというスタイルで。セカンドも同じ場所で録って、サードで同じ大田区内の別の公民館に移って録りました。
──大田区内引っ越しをしたと(笑)。4作目でプロトゥールスを試したものの、やはり性に合わなかったんですか。
甲田:僕らには合いませんでしたね。後で直しの利かない緊張感や重圧はもちろんないんですけど、その代わり時間と予算がかかるなっていう(笑)。出来上がった音もどこか他人行儀で、これは自分たちの音じゃないなと思いました。エンジニアも変わらずシュガー・スペクターで僕らの音に理解はあるはずなんだけど、やっぱりちょっと違うなと。
──アナログで録るとは言え、最終的にはデジタルに変換しなくちゃいけませんよね。そこでヴィンテージの機材を当時の基準で使うと、現代の制作スタイルでは完全なアナログ仕様を遂行するのが難しい側面もあるんじゃないですか。
甲田:デジタルに落とした段階で音がグッと痩せるのは確かですね。それはもうしょうがないとして、僕らは作業工程が少ないぶん変換作業は2回だけなので、痩せ細り方が少ないとは思いますけどね。
──今作はオリジナルとカバーのクオリティと配分も良し、有機的に絡み合うアンサンブルも良し、真に迫る音も良しと、ホントに理想的な作品に仕上がりましたよね。
甲田:ありがとうございます。一番好きで聴いているレコードの音が録れているなという自負はあります。今回、アンプを通さないでベースを録ることに初めて挑戦したんですけど、それも上手くやれた手応えがあるんですよ。
──じゃあ、「Baron」みたいな曲は現場で異常なデカさのベースが鳴り響いていたということですね(笑)。
甲田:演奏が終わるたびに、ベースのTHE TAKEOが冷却スプレーを両腕にシューッと延々かけてましたからね。
──スタジオの環境も良かったそうですね。
甲田:前回から使わせてもらっている山中湖のSTUDIO GALAXYという所で、響きが凄く理想的なんです。ベースを生で録るということで、特にドラムのKiminoriにベースの音が聴こえないかもしれないという不安もあったんですけど、全パートの音がはっきり聴こえたのは奇跡的でしたね。
──真ん中にマイクを1本置いて、円陣を組んで演奏するんですか。
甲田:マイクは全部で3本使ったのかな。ど真ん中にメインのマイクを1本立てて、僕のテナー・サックスを中心にトロンボーンとバリトン・サックスがその前に並んで、ギターとそのアンプが僕らの左隣、ベースが右隣、つい立てをしたドラムが一番後ろという配置なので、半円くらいでマイクを囲む感じですね。歌が入る場合は僕らと向き合うように、つい立てなしの一発録りなんですよ。僕らはこのやり方を始めて長いから慣れたものなんですが、今回ボーカルでゲスト参加してくれたBan Ban Bazarの福島康之さんもピアノで参加してくれた伊東ミキオさんも一発でその場の勘をつかんで、演奏にノッてくれたので有り難かったですね。
生音のダイレクトさを受け止めてくれるヴィンテージ機材
──リハも一応やるんですか。
甲田:いや、時間がもったいないので最初から録っちゃいますね(笑)。1曲につき3テイクがギリギリなんですよ。それ以上やっても良くならないので。多少間違っても最後まで演奏を止めずにやります。歌も含めて全員がヘッドフォンをつけずに演奏するから、曲によってタイムラグが生じるんですよね。なるべく各自がタイムラグを感じないような位置を確保するんですけど、曲によって多少マイクに近づかなくちゃいけないことがあると、余計にタイムラグが生じたりもするんです。
──タイムラグの計算までしているとは(笑)。レコーディングのメンバーの配置は奇跡のレイアウトでもあるわけですね。
甲田:録る音も演奏のしやすさも含めてベストの位置ですね。こういう録り方がやっている側のエゴなのか、リスナーにいい音を届けたいのかは自分でもよく分からないんですけど、作り手として一番好きでベストと思える音を生み出すのに妥協をしたくないんですよ。その一念だけですね。
──その甲斐あって、今作の音の鳴りと響きは絶品だと思うんですよ。途中でボリュームを上げても音の輪郭が際立っているし、逆に下げても音の抜けの良さがよく分かるし。
甲田:頑なに時代錯誤なやり方をした上でいいものを作れたので、自信を持って「これ聴いてみて下さい」と言えますね。自分たちにはやっぱりこのやり方しかないんですよ。一度プロトゥールスを試した時は確かに便利だと思ったし、効率のいいところもあったけど、僕らはそのやり方のほうが煮詰まるんですよね。トラックダウンに頼りすぎるレコーディングはどうもウソくさい感じがするし、いつもライブでやっているのと同じ環境で録ったほうが作業も早いんです。全員で合奏すれば、多少のミスも上手いことライブ感に繋がりますからね。エンジニアの仕事もその場で決めたフェーダーのみなので、一緒にライブをやっている感覚があるんです。
──シュガー・スペクターさんはもはやブラサキの7人目のメンバーと呼んでも過言じゃありませんよね。
甲田:完全にメンバーですね。彼自身ミュージシャンで、リボン・マイクや真空管アンプといったヴィンテージ機材をメンテナンス込みでできる専門家なんです。日本に出回っているその手の機材は彼がどっかしらで携わっているものが多いんですよ。ニートビーツの真鍋(崇)君やマックショウの機材は完全に彼が関わっていますね。シュガー・スペクターが真鍋君に譲ったテープ・レコーダーを始めとする機材は僕らがファースト・アルバムで使ったものなんですけど、今回はモノラル録音だったからそれを真鍋君からお借りしたんですよ。
──ヴィンテージの機材を一度使うと、とてもじゃないけどもう普通の機材は使えないみたいな感じになるものなんですか。
甲田:やっぱり素直な録れ音になるし、僕らみたいなバンドにはベストですね。たとえばリボン・マイクは繊細で温かみのある音で録れるし、前はライブにもリボン・マイクを持ち込んでいたんですけど、破損が怖くてやめたんです。たまに他のバンドのレコーディングで普通のマイクを使って録音することがあって、プレイバックを聴いているとどっかで諦めちゃうんですよね。これはもう別に誰がどうのってわけじゃないし、最初から入口も出口も全部違うわけだから。
──言うなれば、ヴィンテージ機材は熟成したワインみたいな感じなんでしょうか。
甲田:まさにそんな感じです。今風な録音機材はボジョレー・ヌーヴォーみたいなものですね(笑)。何と言うか、昔の機材には生音のダイレクトさを余すところなく受け止めてくれる懐の深さがあるんですよ。
──シュガー・スペクターさんは機材面ばかりでなく、今作では“Announcement”として曲の橋渡しをするDJで参加もされていますね。
甲田:全曲を録り終えて、みんなで聴き直してみたら「ちょっと曲が多いね」って話になったんです。レコードなら裏返す行為があるからいいけど、CDはそういうわけにもいかないしねって。で、ふと真夜中にひらめいたのがカバー曲の前にだけ“Announcement”を入れようというアイディアだったんですよね。それなら箸休めのタイミングができていいんじゃないかってことで。シュガー・スペクターは練馬生まれのベルギー育ちなんですけど(笑)、フランス語は一度日本語に変換しなくても出てくるんです。英語も喋れるんですけど、それは一度フランス語か日本語に置き換えるらしいんですよ。そんな彼いわく、今回のDJのコンセプトは「フランス訛りのイギリス英語」らしいんですけど(笑)。ノリノリのDJではなく、淡々と曲を紹介する感じがちょっと本物っぽいかなっていう。単なる思いつきだったけど録ってみて良かったし、一度バラした機材をまたセッティングするのはエンジニアが嫌がるはずなんだけど、本人が喋るってことでノリノリだったんですよね(笑)。