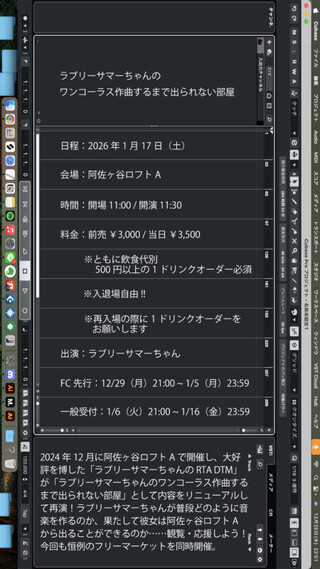2014年にアメリカ黒人女性ボーカルの最高峰である実力派シンガー、ジュウェル・ブラウンとの共演盤『Roller Coaster Boogie』で大きな反響を巻き起こしたブラサキことブラッデスト・サキソフォン。彼らの最新作は、「Deacon's Hop」などのヒット曲で知られる伝説のテナー・サックス奏者でありリズム&ブルース界の巨人、ビッグ・ジェイ・マクニーリー(御年90歳!)とタッグを組んだ最強のスタジオ録音盤『Blow Blow All Night Long』だ。国境もキャリアも世代も飛び越え、ブロウ・テナーのレジェンドとの純粋な音の交歓を経て生まれた本作、その完成に至る背景にはどんなドラマがあったのか。ブラサキの顔役、テナー・サックスの甲田"ヤングコーン"伸太郎を直撃した。(interview:椎名宗之)
ライブ中に水を飲むヒマがどこにあるんだ!?
──本作の甲田さんのライナーノーツを読んで意外だったんですけど、一連のビッグ・ジェイ・マクニーリーとの共演はビッグ・ジェイ側から「俺を日本に呼べ」と連絡が来たのがきっかけだったそうですね。
甲田:一番最初はそうでしたね。ビッグ・ジェイがどうやってブラサキのことを知ったのか分からないんですよ。おそらくYouTubeで見てくれたか、ロス在住の日本人に教えてもらったかだと思うんですけど。2012年11月にビッグ・ジェイが来日した時にその辺のことを聞こうと思ってたんですけど、結局、聞けずじまいで。
──21歳の時にビッグ・ジェイから絶大な影響を受けた甲田さんからすれば、まるで神の啓示のような出会いですね。
甲田:ビッグ・ジェイからのオファーを受けた時よりも今のほうが運命みたいなものを感じますね。ビッグ・ジェイのオファーがなければ今のブラサキはないと思っているので。実を言うと、ビッグ・ジェイとはちょっとしたニアミスをしてるんですよ。1996年に彼が来日した時、客としてライブを見に行ったんですけど、その店の従業員が僕の頭の上に降ってきたんです。
──降ってきた!?
甲田:アンコールでカウンターの上に立って盛り上げていた従業員が、僕の頭上に落ちてきたんですよ。それが凄く痛かったので、そいつの首を絞めながらフロアを右往左往していたら、そのどんつきに今まさにステージに上がろうとしていたビッグ・ジェイがいたんです。彼と目が合っちゃって、僕のところへ来てこう言うわけですよ。「やめろ! お前のためにもう1曲やるから、ケンカをやめるんだ!」って。そのままステージに上げられそうになったんですけど、それはちょっと恥ずかしいから勘弁してくれって言ったんです。その出来事を覚えているか聞いてみたいのもあって、2012年のビッグ・ジェイからのオファーを受けた部分がなきにしもあらずなんですよ(笑)。
──ビッグ・ジェイはそのことを覚えていたんですか?
甲田:覚えてませんでした(笑)。まぁ、その時点で16年も前の話ですからね。そんなビッグ・ジェイからオファーをもらうなんてびっくりしたし、まだ音楽をやってたんだ!? っていうのも驚きだったんです。やってたとしてもホントにできるのか? っていうのもあったんですけど、いろいろと調べたらロスで毎日のようにライブをやってたんですよね。だから最初は驚きの連続でした。
 ──2012年に自力でビッグ・ジェイを招聘して、どんなことを学べましたか。
──2012年に自力でビッグ・ジェイを招聘して、どんなことを学べましたか。
甲田:ライブをやる時は常にお客さん目線であることの大切さ、ですかね。自分がやりたい曲だからこれを聴け! っていうのもあるけど、それよりも今お客さんが何を欲しがっているか、何をやれば喜ばれるのかをビッグ・ジェイは常に考えているんです。初来日の時は最初の公演が大阪のクラブクアトロだったんですけど、ビッグ・ジェイの横に水を置いておくのを忘れてしまったんです。歌もがなるからヤバいなと思ったんですが、結局、最後まで一滴も水を飲まずにステージをこなしたんですよ。終わった後に「なんで水を飲まなかったんだ?」と聞いたら、「水を飲むヒマがどこにあるんだ!?」と言われて。僕もライブでは水をほとんど飲まないんですけど、それは後で映像を見た時に水を飲む姿が画としてうるさく感じるからなんですよ。ライブに必要のない画だし、汗を拭くのもうるさく感じてしまう。だけどビッグ・ジェイのポリシーはもっと上を行っていて、ステージで真剣勝負をしている時は水なんて飲む時間がないと。喉が渇いてると感じているようじゃダメだと。あの一言には心を射抜かれましたね。同じステージに立つ人間として襟を正されたと言うか。
──板の上に立つ人ならではの矜恃なんでしょうね。
甲田:いま自分が何をやるべきかを必死に考えて、全神経をフル稼働させて行動に移しているってことですよね。それに、当時85歳という高齢で足も弱っているにも関わらず、ライブ会場の一番後ろからフロアを練り歩いてステージに上がるんですよ。演奏の前にフロアを充分に温めるのを必ずやるんです。あの年齢でそこまで徹底してこだわるのは純粋に凄いなと思って。その後にステージを3時間ぶっ通しでやりますしね。
ビッグ・ジェイと対等な形で闘いたかった
──まさに怪物ですね。
甲田:ロス在住のビッグ・ジェイの知人から事前に注意されていたのは、「ライブを途中で止めてくれ」ってことだったんです。「誰かが止めないといつまでもライブをやるから」って。老人だから途中で倒れる可能性もあるし、3時間ぶっ通しのライブはお客さんもキツいですしね。
──座りの席じゃないとキツいでしょうね。
甲田:ビッグ・ジェイ本人はずっと椅子に座ってるんですけどね(笑)。それにビッグ・ジェイは、疲れた時は吹かないのが必殺技なんですよ。僕に「お前、吹いとけ」って合図が来るんです(笑)。で、ライブが終わると物販でサイン会をして、記念撮影にもニコニコ応じる。それを毎日やりますからね。リハーサルも全曲やらないと気が済まない人だし。
──セットリストは用意してあるんですか?
甲田:全くないですね。それも含めて真剣勝負なんです。リズム&ブルースの全盛期を生きたサックス・プレイヤーでヤバい音を出す人はたくさんいるけど、ビッグ・ジェイはそこに留まってないんですよ。バンド全体でのキメみたいなものがあったり、仕掛けや工夫をステージに持ち込む人なんですよね。
──決してスタンド・プレイではないと。
甲田:そうですね。同じことをバンドのメンバーにも求めるし、「勝手についてこい!」ってことに留まらずにバンド・サウンドを理想としている。自分が目立つのが第一じゃないんですよ。
──ステージ上でどれだけ白熱しても、ビッグ・ジェイにはちゃんと冷静な視点があるんですね。
甲田:それはあるでしょうね。だからこそ休んで吹かないこともできるんじゃないかな(笑)。
 ──それから3年後、2015年11月のビッグ・ジェイ再来日の時は、逆にブラサキからオファーをしたんですよね。
──それから3年後、2015年11月のビッグ・ジェイ再来日の時は、逆にブラサキからオファーをしたんですよね。
甲田:2015年はレコーディングが主な目的だったんです。どうせ呼ぶならライブもやろうってことになったんですけど。
──2013年に『Rhythm And Blues』という素晴らしいオリジナル・アルバムを、2014年には『Roller Coaster Boogie』というジュウェル・ブラウンとの共作をリリースして自信を持ったことも関係していますか。
甲田:それもあるし、2012年にビッグ・ジェイが来日した時は「Big Jay McNeely & Bloodest Saxophone」みたいな感じで、要はビッグ・ジェイのバック・バンド的な扱いでツアーをやったんですよ。でも僕らはそこで終わりたくなかったし、対等な形でビッグ・ジェイと闘いたかった。それでレコーディングのオファーをビッグ・ジェイにしたところ、快諾してくれたんです。バンドの名義も「Bloodest Saxophone feat. Big Jay McNeely」にしたいと事前に伝えて。
──2015年の再来日の時はビッグ・ジェイの対応に変化があったんですか。
甲田:僕らのことを凄く信頼してくれるようになりましたね。ライブ前のリハーサルも全曲やらなくなったし。レコーディングでも、ここは絶対ビッグ・ジェイが吹くだろうってところを僕にどんどん譲ってくれて。それは信頼の表れなので、凄く嬉しかったですね。
──やはり2012年の来日時にブラサキのことをちゃんと認めたということなんでしょうね。
甲田:初来日公演が終わって成田へ見送りに行った時、「お前たちのCDとプロフィールを送れ。俺の署名付きでアメリカのプロモーターにばら撒いてやるから」って言われたんですよ。そのことに別に期待はしなかったんですけど、あのビッグ・ジェイに認められた嬉しさはありましたね。基本的に褒め言葉を一切言わない人ですから。
──再来日してブラサキとのレコーディングとライブにOKしたのが何よりの褒め言葉みたいなものですよね。
甲田:最初はビッグ・ジェイもびっくりしたと思うんですよ。自分がキャリアをスタートさせたリズム&ブルース全盛期のサウンドを日本人の僕らがやってるわけですから。なんで今どきそんな音楽をやってるのか? なんでコール&レスポンスやソロの回し方を分かってるんだ? っていう驚きがビッグ・ジェイには最初あったと思うんです。レコーディングもそうですよね。オープンリールで録るスタイルはビッグ・ジェイが喜んでくれるんじゃないかと思ったんですけど、逆に凄くびっくりされましたからね。「お前ら、一体何をやってるんだ!? おいおい、今は何年だと思ってるんだ?」って(笑)。ビッグ・ジェイですらプロトゥールスが当たり前と思ってる時代ですからね。僕らがそこまで徹底して昔ながらの手法でレコーディングに取り組むことに対してビッグ・ジェイがどう感じたのかは分かりませんけど、ビッグ・ジェイが一番得意とするやり口にブラサキは付き合えるよ、ってところは見せられたと思います。