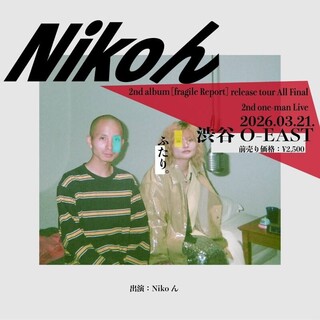日活映画『野良猫ロック』シリーズ、東映映画『女囚さそり』シリーズ、東宝映画『修羅雪姫』シリーズといった人気作で70年代に一世を風靡し、80年代にはテレビドラマ『鬼平犯科帳』や数々の大映ドラマ等でその比類なき存在感を放ち続け、64歳を迎えた今なお第一線をひた走る大女優、梶 芽衣子。クエンティン・タランティーノ監督の『キル・ビル』の中で自身の唄う『修羅の花』と『怨み節』が挿入歌として起用されたことで歌手=梶 芽衣子に対する再評価の気運が近年高まっていたが、2009年に発表した25年振りの新曲『女をやめたい』で歌手活動を解禁した彼女が31年振りとなる待望のオリジナル・アルバム『あいつの好きそなブルース』を先月末に発表した。シングル『残り火』以来実に33年振りに宇崎竜童・阿木燿子という日本屈指の名ソングライター・コンビとがっぷり四つに組んで完成させた本作は、30年以上歌を封印してきたとはとても思えぬほどに円熟した梶 芽衣子の唄い手としての魅力が凝縮している。と同時に、まるで昨年デビューしたばかりのような瑞々しさがあるのも素晴らしい。宇崎竜童の全面プロデュースの下、ロック、ジャズ、ポップス、ブルース、ボサノヴァといった音楽的要素を貪欲に採り入れた新機軸の楽曲が数多く収録されているものの、描写されているのはいずれも紛うことなき梶 芽衣子の深淵なる歌の世界。女性の視点ながら義侠心に満ち、こんな時代だからこそしなやかにしたたかに生き抜こうと聴き手に投げ掛ける大いなる人間讃歌なのである。今再び唄うことを選んだ理由、長年にわたる戦友とも言うべき宇崎とのやり取り、アルバムの制作に懸けた思いに至るまでを梶本人がざっくばらんに語り尽くしたロング・インタビューをここにお届けしよう。(interview:椎名宗之)
怒髪天を聴いてロックに対する概念が変わった
──去年の10月に東京キネマ倶楽部で行なわれた怒髪天のライヴに梶さんがゲスト参加して『唐獅子牡丹』を熱唱した時のオーラがとにかく神々しくて、その存在感にただただ圧倒されたんですよね。
梶:あら、恥ずかしい…急に意識しちゃったわ(笑)。私、怒髪天のライヴには2回お邪魔したんですよ。[註:2009年10月にSHIBUYA-AXで行なわれた怒髪天の結成25周年記念イヴェント『オールスター男呼唄 秋の大感謝祭〜愛されたくて…四半世紀〜』で『うたのうた』を披露]もう迷惑してると思うのよ、怒髪天の皆さんは(笑)。私はそれまで怒髪天のことは存じ上げなかったんですけど、ある日テイチクの営業部の方から「怒髪天というグループの増子(直純)さんというヴォーカルの方が梶さんの大ファンで、対談したいという話が来ているんですが…」と打診されて、「いいわよ」とOKしたの。それで増子さんにお会いしたら、「僕は今までに8回対談したいと言いました。8回目にしてやっと叶いました」って言われたんです。で、「増子さん、私はそのことを今初めて聞きましたよ」って答えたんですね。「私は1回でOKしますよ」っていう意味で。だって、何もお断りする理由がないじゃないですか。
──対談前に怒髪天のCDをしっかりと聴き込まれたそうですね。
梶:私は怒髪天のロックンロールを聴いて、ロックに対する概念が変わったんですよ。それまでは何を唄っているのか判らない、ただうるさいだけっていうイメージだった。ビートルズやエルヴィス・プレスリーは好きだったけど、ミック・ジャガーの何がいいのかさっぱり判らなかったし。それが怒髪天を聴いて、演歌もロックにするとこうなるんだなと思って。つまり、日本人が日本の言語で唄って表現する怒髪天の歌には日本男児の精神が息づいている。それに、実際に彼らと会ってみると、メンバー個々に何をやっても生きていける強さを持った人たちじゃないですか。何をやっても生きていけるんだけど、敢えてロックという表現を選んで4人でタッグを組んでずっと活動を続けている。私は彼らのロックに対する純粋さが大好きなんです。
──怒髪天の歌は聴き手に対して何を伝えたいかが明瞭ですしね。
梶:明瞭だし、ちゃんと訴えていますよ。歌の中に芯の通ったメッセージがあるじゃない? それに、彼らならではの社会に対する目があって、それが的確に表現されている。尚かつ、媚びない、めげない、挫けない。あの精神が私と合うの。大好きなのよ、私。あっぱれだと思っているの。バンドを維持していくのって大変じゃないですか。この間も宇崎さんと会って話したんだけど、宇崎さんはダウン・タウン・ブギウギ・バンドを10年近くやっていらして、その間ずっと赤字だったそうなんです。あんなに大ヒットを飛ばして、あんなにメジャーなバンドで、あれだけテレビに出て、あれだけ営業をこなしていたにも関わらずですよ? それで赤字だったなんて、私はもうびっくりしちゃって。バンドってやっぱり甘くないんだなと。その話を聞いて、怒髪天のことが頭に浮かんだんですよ。彼らはやっぱり凄いヤツらだなと思いましたね。
──今の梶さんのお言葉をメンバーが聞いたら、さぞかし感無量でしょうね(笑)。
梶:そうですか? 私はずっとそう思っているし、怒髪天に出会えて本当に良かったですよ。
──対談なりライヴでの共演というのは、怒髪天のファンに対して梶さんの存在をアピールできるという良い相乗効果もありましたよね。
梶:そう、それは彼らのお陰。彼らが応援して下さっているからこそです。去年、東京キネマ倶楽部で共演した時に、私は本当は『フーテン悪ツ』を唄いたかったんですよ。それを増子さんに言ったら、「いや、ここは是非『唐獅子牡丹』を唄って下さい」と言われたの。おっ、そう来たか、考えてもみなかったリクエストが来たなと思って(笑)、それからが大変でしたよ。一生懸命聴いて、勉強して。
──『フーテン悪ツ』とは、また通好みな選曲でしたね。
梶:あの曲、大好きなんですよ。あのタイトルの付け方も好き。“ワルツ”が“悪ツ”ですからね(笑)。ああいうセンスが凄く増子さんらしい。それに、今までいろんな世界を這い上がって生きてきた彼らの逞しさがあの歌ほど出ているものはないですよ。世の中のことをちゃんと判っていなければあんな詞は書けない。
──決して順風満帆な活動ではなかったですし、煮え湯を飲まされるような苦労も散々ありましたしね。
梶:あの人たちはそういう苦労を見せないのがいい。あのあっぱれな潔さが私は惚れ惚れする。
──辛いことをただ辛いとは絶対に表現しないし、ちゃんとユーモアのオブラートに包んで歌にしているのが粋ですよね。
梶:そこが凄いんですよ。だからああいう人たちがメジャーにならないのが私は癪に障ってしょうがないの。
──まぁ、今や怒髪天もライヴの動員が年々増加の一途で上り調子ですからね。
梶:そうなって当たり前よね。増子さんが言わんとしていることとメンバー全員が伝えようとしている音に若い子たちがやっと目覚めたんでしょう。私に言わせれば、ようやく今目覚めたか、もっと早く目覚めなさいよ! ってところだけど(笑)。ああいう人たちがメジャーにいれば、もっとこの業界が良くなるんじゃないかっていうくらいのメッセージが彼らの音楽にはあるんですよ。
──確かに。そして音作りやライヴ、リハーサルに際しては完膚無きまでにプロフェッショナルですしね。
梶:東京キネマ倶楽部の時も音合わせを1回したんですけど、その時に私、とんでもなく高い声が出ちゃったんです。でも、それで唄い切ってしまった。それで増子さんが呆れて、「出ちゃいますね、上の音も」って言われて。でも、バンドの演奏には合ってないのよ。だから増子さんも心配になっちゃって、本番当日も舞台の袖で執拗に言われたの。「いいですか梶さん、どんなに声が低く出ても低く出すぎるってことはないから、あくまでも声は低く、低くですよ!」って(笑)。それをずーっと言われてた。増子さんが私をエスコートして舞台まで連れていって下さりましたけど、連れていって私にマイクを渡すまで「いいですか、低くですよ! 低く! 低く出るぶんにはいくらでもいいんだから低くですよ! 梶さん!」って(笑)。あれだけ言われればさすがにちゃんとやるわ、私も(笑)。
──往年の大女優に対しても物怖じせずにキッチリと意見を言う増子さんであると(笑)。
梶:いや、増子さんは優しいんですよ。それにシャイだから突っぱねるような態度を取るけど、とても心根の優しい人なんです。怒髪天はメンバー全員がそう。凄く優しいし、人柄がいい。だから、きっと今まで揉めたことがないと思うよ。何と言うか、出会うべくして出会ったんだと思う。本当にあの北海道の4人衆は男前で惚れ惚れするね。