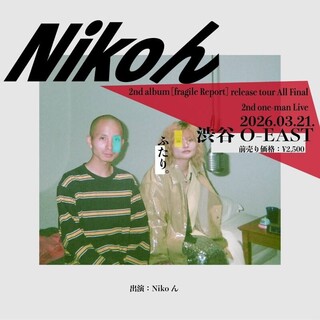再び歌を唄ってみたいと思った理由
──このまま怒髪天の話ばかり伺っていると『あいつの好きそなブルース』の話ができなくなってしまうので(笑)、本編に移りましょう。まず、2009年に25年振りとなるシングル『女をやめたい』を発表されていますが、再び歌を唄おうと思ったきっかけは何だったんですか。
梶:歌に関しては、まず私が漠然と唄いたいと思ったんです。その6年くらい前にクエンティン・タランティーノ監督の『キル・ビル』の中で私の『修羅の花』と『怨み節』が使われましたよね。その余波で『修羅雪姫』がDVD化されて、それが世界的に売れちゃった。オーバーではなくね。そんなこともあって、若い人たちが私の存在に気づいてくれるようになったんです。その時にテイチクさんが20曲入りの『全曲集』を出したんですね。当時、私の歌できちんとCD化されているものはなかったんですよ。だって昭和の女ですから。それに、『女をやめたい』は確かに25年振りのシングルでしたけど、ちゃんとした歌の活動は30年以上全くやってこなかったんです。ホリプロ制作のコマーシャル・ソングをすぎもとまさとさんと唄ったのが最後で、それ以来レコードを出していなかったんですね。
──それが、いつからか唄いたいと思うようになった。
梶:『鬼平犯科帳』という時代劇をかれこれ22年間もやらせて頂いているんですが、そこに甘んじて安住しているのもどうかと思うようになったんですよ。このまんまじゃ歳を取るだけで元気がないんじゃない? って。自分を元気づけられるようなことを何かやらないといけないんじゃないか? と考えていた時に、漠然とまた歌を唄ってみたいと思ったんですよ。
──ある種の突破口を見出そうとしていたと。
梶:そうです。それに、『団塊の世代』で知られる堺屋太一さんがある日の新聞で団塊世代に向けて書かれていたことも発奮材料になったんですね。つまり、「団塊世代はそろそろ定年退職の時期に差し掛かっているけれど、高度成長期からずっと大変な時代を生きてきた団塊世代がそのまま何もやらずに終わっていいのか?」と。確かにそうだなと実感したんですよ。だからと言って別に大したことをやるわけでもないんだけど、できるとしたら歌しかないんじゃないかと思って。と言うのも、役者としては梶 芽衣子の従来のイメージや“らしさ”、今の年齢でしか役柄のオファーが来ない部分もあるんですよ。それに対して凄く抵抗があったんです。『鬼平犯科帳』の密偵おまさは36歳の設定で、役は歳を取らないから、22年経ってもずっと36歳のまま演じているわけですよ。そこに凄く救いはあったんだけれど、それにしても何か新しいチャレンジがしたかったんです。
──『怨み節』や『女の呪文』といった往年のヒット曲のイメージを覆したいとは思いませんでした
梶:覆したいとか何とかと言うよりも、純粋に新しいものをやりたいと思いましたね。実を言うと、テイチクさんが出した『全曲集』に私は何も関与しなかったんですよ。唄いたくなかった33年間がずっと続いていた頃だったし、『キル・ビル』の世界的なヒットに合わせて出したものでしたから。でも、それも1万枚近く売れたんです。私は何もしなかったのに(笑)。と言うことは、私の歌を未だに求めて下さる人たちがいらっしゃるということですよね。そんなことも唄うことの後押しをしてくれました。
──そんな折、とある雑誌の対談で宇崎竜童さんと再会を果たすわけですね。
梶:そうなんです。心中して以来31年振りの再会(笑)。
──増村保造監督の『曽根崎心中』ですね(笑)。梶さんと宇崎さんは主人公のお初と徳兵衛を演じられて。
梶:普通は撮影所やテレビ局で偶然会うとか、新幹線とか飛行機で偶然乗り合わせるとかあるじゃないですか。不思議なことに、宇崎さんとは『曽根崎心中』で共演して以来一度も会ったことがなかったんです。それは阿木燿子さんも同じ。
──何ででしょう。心中したからでしょうか?(笑)
梶:そうかもしれない(笑)。とにかくその対談の話が来るまで全然会わなかったんですよ。宇崎さんとは『曽根崎心中』で共演する前に『欲しいものは』、『袋小路三番町』というシングルを2枚作って頂いてたの。当時はまだ歌の活動をしていましたからね。ホリプロの鈴木正勝さんという方が宇崎さんに曲作りを依頼して、宇崎さんは快く引き受けて下さったんです。その時に映画の話になって、宇崎さんも「いいですよ」ってことになって映画が出来たんですよ。だから『曽根崎心中』の前に歌があったんですね。
今までに唄ったことのない歌を唄いたい
──31年振りにお会いした宇崎さんの印象は?
梶:何もお変わりなく若々しくて、お化けかと思いましたね(笑)。すぐに意気投合しちゃって、31年のブランクも何もなかったです。
──その対談に合わせて、宇崎さんが事前に『女をやめたい』を聴いて下さっていたそうですね。
梶:私が25年振りにシングルを出したのをご存知で、私と会うというので対談の前日にわざわざCDショップに行って買って下さったそうなんです。「ちゃんと聴いたよ」って言うから、「どうも恐れ入りました」ってお礼を言って。その対談の時に宇崎さんから「梶さんさ、唄う使命感を持ったほうがいいよ」っていきなり言われたんですよ。あと、「自分が作って唄って頂いた頃よりも遙かに成長してるね」って言って下さったんです。「それ、お世辞?」って訊いたら「お世辞じゃない」と。それが素直に嬉しかったんですよ。しかも、「オファーがあればいつでも曲を書くよ」って言って下さったんですね。そのことをテイチクさんに話したら話が即決まっちゃって、まさにトントン拍子だったんです。
──31年ものブランクを微塵も感じずに肚と肚で共鳴し合うのだから面白いものですよね。
梶:やっぱり、伊達に心中しなかったね(笑)。何て言うか、戦友と再び巡り会ったような気持ちでしたよ。テイチクさんからGOサインが出てから宇崎さんに正式にお願いしたんですけど、その時に私が呆れるくらいにいろんなお願いをしたんです。『女をやめたい』を出した時は25年振りだったから、「また歌を始めましたのでよろしくお願いします」って全国のCDショップを100店くらい巡ったんですよ。
──CDショップお百度参りですね(笑)。
梶:その時に、大人の場所があまりないんだなと気づいたんですね。テイチクの営業部の方が本当によく頑張ってくれて、少しでもコーナーを確保して私のCDを置いてくれたんですよ。DVDのコーナーには特にお願いしなくても私の出演作を置いてくれていて、そこに並べてくれればいいのに、わざわざCDのコーナーを作ってくれたんです。それと、CDショップによっては私が行くと曲を店内で掛けてくれるんですよ。でも、私が店を出るか出ないかのタイミングで曲を止めちゃうんですね。これはマズイだろうというのがまずあった。DVDは別として、大人の場所として確保されているのは落語しかないし、演歌は肩身の狭い所にあるんですよ。後は全部若者文化で、そのほとんどが字余り的なロックとか延々と喋り続けているような感じ。そういうのを凄く感じて、CD業界の現実を見た思いがしたんです。それで、私はまず宇崎さんに自分の気持ちを伝えたんですよ。CDショップを100店巡りした時に感じたことをありのままに。それでこう話したんです。「私は今まで作家の方にこんなことを申し上げたことはないし、宇崎さんが今回快く引き受けて下さったので、せっかくやるのならばちゃんとやりたいんです」と。「梶さんはどんなことがやりたいの?」って訊かれたので、やりたいことを全部言いました。「私が今までにやったことのないもの」って。
──それは音楽のジャンル的なことですか。
梶:ジャンルもそうだし、一番言ったのは『怨み節』をそこに入れたくないということですよ。宇崎さんは「エッ、『怨み節』を入れなくていいの?」って驚いてましたけど、いいんですと。要するにそういう音にしたいということね。「だからどういうこと?」って訊かれて、「ロック、ジャズ、ポップス、ブルース、ボサノヴァ…そういうのを全部やりたい」って答えたの。それで「ああ、そういうのをやりたいのね」ってことになったんです。宇崎さんは最初、シングルを作るつもりでいたと思うんです。でも、テイチクのディレクターさんがこれは絶対にアルバムだと考えていて、私もいろんなことがやりたいからアルバムがいいと思っていた。それでいて、CDショップで私がいなくても曲を掛けてもらえるようじゃなきゃイヤだって言ったの。それと、タワーレコードとかああいう場所に似合う曲、抵抗なく店で掛けてくれるような曲じゃなきゃイヤだと。私が行ったからしょうがなく『女をやめたい』を掛けるんじゃなくね(笑)。って言うのは、タワーレコードさんもそうだし、TSUTAYAさんもそうだし、新星堂さんもそうだし、若いスタッフの方は私のことなんて知らないはずなんですよ。ところが、『キル・ビル』があったから若い子でも私のことを知っているんです。それで喜んで頂けたりして、それが私は凄く嬉しかった。それに『全曲集』もあるし、全部で82曲入っている『梶芽衣子ベスト・コレクション』っていうBOXセットもあるし、だからこそ『怨み節』は要らなかったんです。もっと言えば、宇崎さんには従来の梶 芽衣子だと思わないで曲作りをして頂きたかったんですね。今回、完成したものを聴いてしみじみと思いましたよ。宇崎さんはプロ中のプロだってことを。だって、それでも私っぽく作られているんですから。