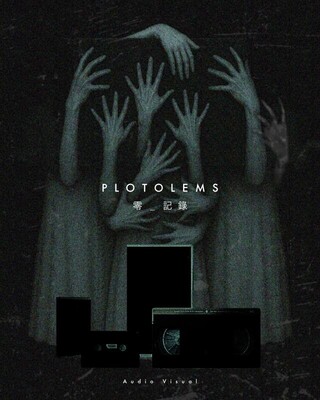一人で山をアタックするようなもの
OHNO:今世の中エコロジーだとかいろいろあるけど、時代がどうのこうのっていうよりかは、俺たちなりに時期が来たんだよね。別に俺たちが年老いたからやるとか全然なくて。普通にバンドも以前と同様にやってる。ただ、アコースティックの音色って基本だと思うし、そこにまたみんなが気付き始めてるというか。俺たちもそうだし。
岩田:時代がどんどんデジタルになって、簡単に言ったらデジタルの技術でサウンドはどうにでもなるところがある。そうなってくると究極的にはRAWの部分って人の声かもしれない。歌うヤツは面白いところに来てるんじゃないかな。そんな時代への反動もあるかもしれない。それもきっかけのひとつだね。でもまぁなんだかんだ言ってもそれはバンドがあったうえの話だから俺もしょっぱいマネしたら突き上げ喰らうでしょ(笑)。バンドなくて、やりたいワケじゃないから。
OHNO:そこは必須条件だよね。自分の逃げ道になっちゃったらダメなんで。バンドをちゃんとしっかりやった上じゃないと絶対できない。
──あくまでバンドがあった上でのプラスαっていうスタンスなんですね。
岩田:何よりバンドが好きだしね。そこはもう当然の話。
OHNO:俺の場合、バンド以上に影の部分が相当出るかもね。暗闇の部分がいっぱいあるだろうし、それは出すの覚悟でやってるんで。
岩田:資質が出るよね。俺たちに限らず出たヤツの資質が暴かれるというかそれは匂うだろうね。
OHNO:完全に露呈されるよね。
岩田:そこが面白さだから。
OHNO:楽しさをね、バンドとして乗り越える楽しさとちがって過酷だよ。一人で山登って行くようなものだし。みんなでパーティ組んで登るんじゃなくて一人でアタックしなきゃならない。自分の力のみで登るみたいな。そこはね、楽しさも意味が違うことになるかも。次やるときにすごい緊張感に潰されてやっぱやりたくないなって思うかもだけど、経験をとにかく積んでみて、そのあとで答えだせばいいかなって。
岩田:バンドやってる人間ってメンバーに頼ってるところあるからね。
OHNO:バンドのメンバーがいるって、保護者付きみたいな感じの安心感かな、ボーカリスト的には。
岩田:そう、支えられてるよね、メンバーには。そこは大感謝だね。
OHNO:でも、そういうのも一切ないわけでしょ。他の人の力もなければ、他の人に怒ることもないわけだし。全部自分の力だからね。
岩田:人のせいにできないねえ。
OHNO:自分が問われてるところだよ。
岩田:俺、個人的な話なんだけど、ずっとバンド・シンガーとしてやってきて、最近歌うことが改めて好きだなと思ったんだよね、今更ながら(笑)。なんだろう...、ずっと叫ぶ、吠えるってところでただ闇雲に必死だったという。歌うっていうよりも衝動的にジャンプしたり、ステージで覚醒するっていうかそういう感じでやってきた。でも俺単純に歌を歌うことが好きだなって、最近それをすごく思うね。それは数多くの経験もあるからかもしれないし、回りを見渡す余裕が少し出来たのかもしれない。自分の器量というのも理解するようになった。だからなんか、そういう意味で今の自分の芸風を自分で自分をコントロールできるというか、楽しめるんだよね。そういうところでいい機会かなっていう気はあるね。

チャレンジ精神があるから
OHNO:ウマくないとミュージシャンになれないっていうのと違うところにいるから。例えばロカビリーとかメタルとか見ると、こんな難しいの俺たちにはできないよって思う。ロックンロール!とか言っても技術的に、みんなすごいウマいんだよね。パンクロッカーって言うと、いつの時代も技術より気迫、コード弾き最高みたいな(笑)。シロウトでも、明日から俺バンド組んでやるぜ!って言ってやれる希望があるジャンルだと思ってるし。テクニックの部分がなくても成立できるっていうか、俺はそれは逃げ道じゃなくていつまでもメッセージとして伝える方が重要であって、無骨さがあっていいじゃないかっていう基本があるジャンルだと思ってやってる。そこの部分をアコースティックギター持ったときに、ヘタでもいいから唄ってみて何か出せればいいじゃんっていうね。技術重視なら違う音楽やればいいじゃん、ソロ弾けないからパンクやってるんだよって。そういう意味じゃ、音楽人で言えばたぶん一番下層階級に君臨するパンクロッカーな人間が、アコースティックギター持って音楽として成立するのかみたいな(笑)。自分もその場所で、自分試しをするんだよ。
──今後はどういった展開を考えていますか。
OHNO:ドラムが入る形態の人がいてもいいと思うし、普段からアコースティックやってる人が参加してくれてもいいし。俺たちからすると、本体のバンドがあって、それでもアコースティックをやるっていうチャレンジ精神みたいなのがあるからね。今現時点で最初の取っかかりとしたら、普段やってる本体と違うことをやるチャレンジ精神があるかなってことだよ。
岩田:ある意味攻撃的なモノでないとね。そこがないと、バンドの方がいいって話で終わっちゃうから。
OHNO:やる側も気構えとして通常のバンドとは違うところですごいプレッシャーかかってる。本当に真剣にやってるっていうのは出るんで。それは見てる側も必死さゆえのぎこちなさ(笑)も面白いかなと思うんだけど。
岩田:新しいムラをそこで作りたいワケじゃなくて、ただ単純に世間的なイメージだったりをブッ壊してもいいんじゃないの。パンクの姿勢って本来そういうものだと思うし。それのひとつのやり方がこのACO MANIAって、俺はそう思って参加してる。
OHNO:個人個人多面的であったり趣味もいろいろあったりするワケだけど、バンドっていう集団だと個性が見えなかったりするよね。ベールに包まれているというか。アコースティックだと個人の趣味をどんどん出してもいいんだよ。アイテムも面白いよね。そういうところもかなり見所だったりするし。普段着で出ちゃったりとかして意外とそっちの方がカッコいいって逆転したり。酔っぱらっててもかっこいいというか。
岩田:俺は、これをきっかけに新しいファン層を拡げたいとか、別の一面を売りたいとかそういうのはないんだよね。自分たちのいちばんベーシックになってるもの、積み重ねてきたもの、俺たち自身も単なる音楽のフリークだし、そういうところをリアルに出せればいいんじゃないのかなって、それがACO MANIAの中で出てくるだろうし、そういうのを楽しめるヤツはいるだろうしね。普段はダイブという楽しみ方もあるだろうけど(笑)。もちろんアコースティックだからといって、おとなしくご静聴っていうワケじゃなくてもいいと思う。これもパンクですよって言い切りたいね。あと、近年パンクっていう言葉が安っぽい市民権を得た風潮がかゆい。そこに当事者としても疑問もあったりする。
──昔みたいにバイオレンスなイメージが真っ先に挙がるのとは変わりましたね。
岩田:世間的に認知されたパンクロックのジャンルって、それって業界っていう ものが作った仕切りだと思うのね。いっぺんそのレッテルやカテゴリーを外してやるっていうところはあるよね。重たいことじゃなくて、そういうところを自ら壊しちゃった方が楽しいよって。在り方として俺はどうあろうとパンクシンガーでしかないから、アコギ一本の横でやろうと俺の歌を歌うだけ。まあとにかくビール飲みながら自由に楽しんでくれっていう。
OHNO:実際に俺的には、そんな酒飲んで歌うっていうのはないだろうけど(笑)。今後どういう風な図式になるかわからないけど、今までバンドでやってきた原曲はこういう感じで歌いながら、作ってきたんだよとか、そういうのも含めていろんな打ち出し方はあると思うし。聴く方としても楽しんでもらえるかなと。ウラネタ的なお楽しみパッケージかなと思うしね。今回集まった連中がたまたまパンク・バンドやってるヤツらばっかりだったけど、今後はいろんな人たちとコラボしていきたいっていうのはあるね。パンク・ロッカーが集まってっていうのに限定せず、いろんな人たちとやっていって、そういうところで、俺たちはパンク・ロッカーとしてアコギを持った時に堂々と歯向かえるものをやっていきたいっていうのがあるよ。
岩田:やりたいヤツはどんどん参加すればいいと思うしね。それだけ窓口自由だと思うし。俺もそういうつもりでやってる。でも気分屋だから、飽きたらやらなくなるかもだな(笑)。
──え、こんなに語ってくれたのに(笑)。この先対バンが一緒だったからよくやってるっていう人たちだけでなくて、意外なつながりも見せてもらえそうですね。
OHNO:結局パンク・ロックって言ったって友達はいろんなジャンルにいるワケで。俺なんか友達すごい少ないけど(笑)、岩田君なんか顔広いし。やりたいって人が出てきたら参加して欲しいよね。
──音源のウワサもありますが。
OHNO:やってる以上、俺は自分的なこと言うとアコースティック用の曲も出していこうかなっと思ってるし。RYDERSでずっとプレイしてない過去の曲とか敢えて自分が責任を持ってやってみようかと思ってるし。
岩田:それ単純に聴いてみたいじゃん(笑)。
OHNO:あとは、みんなのパフォーマンス見たから、これはちゃんとカタチにして残したいなっていうのはあるんで、きっちりレコーディングやっていってみんなで録音はしていこうかなって。そしてそれは誰か協力者がいてくれたらどこかのレーベルで音源出してもらおうぜって(笑)。
岩田:俺的にはMike Nessばりの『J. OHNOアコースティック・アルバム』がまず聴きたいけどね(笑)。
OHNO:できれば俺個人も出したいしね。後々になっちゃうかとは思うけど。あとはこの間のライブ映像とかもあるから、みんなのパフォーマンスを順々に紹介していければとも考えてる。いつもとは違う見慣れない俺たちの本質的な部分を、様々な人たちに観てもらえたらと思うよ。