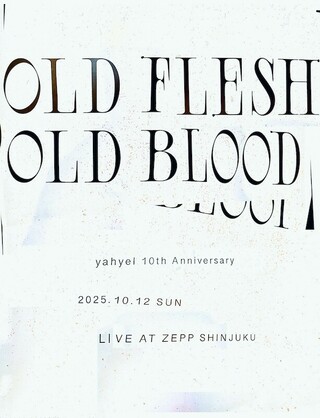破格のスケール感を持ったユニークなルーキーが"MySpace世代"から登場した。ジョンズ・ゲリラを名乗るこの平均年齢22歳の4人組、あの輝かしい60年代後半のサイケデリック・カルチャーを分母に置きつつ、今日性に富んだハイブリッド感覚を加味した極めて知的刺激性の高い独自の音楽を志向/試行している。その音楽は人間の内に秘めた無限の可能性を揺さぶり起こし、聴く者に意識の覚醒を促すという意味において確信的な心のゲリラと呼ぶべきものである。そのスタイリッシュなルックスも相俟って一見クールな印象を与えるが、愛と平和が盛んに唱えられたあの時代の熱やギラギラした武骨さがファースト・シングル『Shoot the radio / Shadow disco』からは確かに窺える。また、その歌にはバンドとオーディエンスが魂のハグをするべく巧妙にブラック・ボックスが組み込まれてもいる。そして、その知的遊戯が普遍的な愛に貫かれたものであることを聴き手は如実に知ることだろう。さあ、知覚の扉を全開にして、水晶の舟を漕ぎ出そう。(interview:椎名宗之)
精神に潜り込むきっかけとしての音楽
──ジョンズ・ゲリラの音楽的志向を語る上でのキーワードである"我流のNEW PSYCHEDELIC"とは、どんな定義なんでしょうか。
Ryoji(g):自分たちが影響を受けているのが、60年代後半の実験性に富んだサイケデリック・ミュージックなんですよ。端的に言えば、あの時代の音楽の斬新さや遊び心を今風にデフォルメしたものという感じですね。
Leo(vo, g):サイケデリックって知覚的なものとかいろんな意味合いがあるけど、俺の中で一番重要なのは"精神に潜り込むきっかけ"みたいなものなんです。歌詞で言えば英詞の奥に在るもの、言葉を超えた言語と言うか、サイケデリックとは知覚や聴覚を超えたところで結び合わせる扉だと捉えているんですよ。
──"もし知覚の扉が浄化されるならば、全ての物は人間にとってありのままに現れ、無限に見える"。まさにドアーズの世界ですね。
Leo:そう、ウィリアム・ブレイク。俺たちの音楽を聴いて、知覚の扉を開けた向こうで会おうぜ、って言うか。約束の場所に行くための扉を開くものがサイケデリックなんです。
──やはりドアーズやジミヘンといったあの時代の音楽が前提としてあるわけですね。
Leo:ビートルズの『サージェント・ペパーズ〜』やドアーズのファーストとセカンド、ジェファーソン・エアプレインの『シュールリアリスティック・ピロー』といったロック史に残る名作が立て続けに発表された1967年のすべてが好きなんですよ。
──全世界が"サマー・オブ・ラヴ"というヒッピー・ムーヴメントに沸いた1年ですね。
Leo:うん。あれから40年以上経ってもなお残っている愛と意志の力に強いシンパシーを感じるんです。きっと100年後も残り続けている音楽だと思うし。当時の音楽や思想は凄く純粋だし、そういった人間の根源的なものと自分たちの音楽が俺の中で同じベクトルで実存していないとダメなんです。音楽とそれをやる人間にズレがあるのは唄っていてもイヤだし、生きていく上でもイヤですね。自分たちの奏でる音楽通りに生きたいんですよ。
──英詞で唄うのは、Leoさんのネイティヴ感覚に基づいているからですか。
Leo:聴いてきた音楽は英詞だったし、バンドを始めたきっかけはビートルズだったし、英詞で唄うことが自然なんです。むしろ日本語で唄うほうが俺には媚びている感覚があるんですよ。
──今回発表されるファースト・シングル『Shoot the radio / Shadow disco』は、バンドにとってクラシックの部類に入る楽曲なんですか。
Leo:いや、それほど古くもないです。「Shoot the radio」をシングルに選んだのは、この曲が意志について唄ったものだからなんですよ。人を突き動かしていく意志と湧き起こる歓びを主題にしているし、リズムもドンドンドン...と歩いていく感じで、朝陽が昇るニュアンスもある。バンドの始まりとして旗を掲げるにはぴったりの曲だと思ったんですよね。
──でも、「Shoot the radio」とは随分と不吉なタイトルですよね(笑)。
Leo:まさにゲリラですよ(笑)。ラジオというのはカルチャーにおける偶像のひとつとして挙げているだけで、別にテレビでもパソコンでも構わないんです。要するに、何か大事なものを得る時は何かを捨てなければならないということを唄っているんですよ。何かを捨てて捨てて吐き出しまくった末に自分の中に残るもの、そこに個性や自我、果ては人生が問われると思うんです。
──ラジオに代表される、権威の象徴としてのメディアをブチ壊せといった意味合いは?
Leo:そんな強い嫌悪感はないです。普段からお世話になっていますからね。(取材用のICレコーダーを指さしながら)これもそうでしょ? 大事なものを捕まえる時は破壊と再生を繰り返さなければならないということですよ。
目に見えない音に色や形がある
──そういった普遍的なテーマは、「Shadow disco」でも通底していますよね。
Leo:「Shadow disco」は美のひとつの観念について唄っているんです。「Shoot the radio」が太陽だとしたら、「Shadow disco」は夜から始まる人間の姿を描いているんですよ。一人は太陽と共に歩くけど、もう一人は漆黒の闇の中に迷い込んで観念に埋もれていく。そして美に灼かれたいと望むわけです。
──この1枚のシングルにおいて、人間の光と影を等比に唄っているということですか。
Leo:地球というひとつの惑星の何処かで朝の訪れがあれば、それと同時に何処かで夜も存在しますよね。朝と夜は分かれているようで実はひとつなんですよ。朝と夜、光と影、動と静といった誰しもが抱えている相反するものを普遍的なテーマとしているんです。
──曲作りはどういった感じで進められていくんですか。メイン・コンポーザーはLeoさんとRyojiさんなんですよね?
Ryoji:元になる曲をLeoが歌メロとコードで最初に持ってくるんですよ。それをバンドでジャムりながらアレンジを固めていく。ただ、そればかりだと不純物を含みがちなので、"これは本当に必要な音なのか?"を最初に頭の中で想像して見極めるんです。そうやってイメージを先に描いてから音を固めたほうがアレンジも映えるんですよね。「Shoot the radio」は特にそうでした。
──「Shadow disco」はいわゆる4つ打ちをベースにした文字通りディスコティックな曲調ですが、決して一筋縄では行かない粘着質な部分がありますよね。
Leo:多分、歌詞とリンクしているからでしょうね。詞の毒々しさがサウンドにもにじみ出ているんですよ。
──Leoさんはギターを弾きながら唄っているんですか。
Leo:うん。最近、詩の朗読をしたりする時にはギターを置きますけどね。
Ryoji:基本的にはLeoがコードを鳴らして、それに僕がリフを足していく感じですね。音作りの面でも、Leoがローミッドで僕がハイミッドで振り分けてます。2本のギターは、これからもっと駆け引きをしていきたいんですよね。シンプルさの中でエグく絡み合っていくと言うか。よりエグく、ダーティーにするのがポイントなのかなと。
──サウンド作りにおいて気を留めている点というのは?
Ryoji:ギターは上から乗せるパートだから、パンチのあるLeoの歌声に余り被せたくないんですよ。だから歌がなくなった時に前に出ていくように心懸けていますね。歌がない時でも聴き手を退屈させないと言うか、歌とサウンドが常に主張し合ってる感じにしたい。
Leo:レコーディングに入ると、俺はすぐにぶっ飛んだ方向に行きたがるんです。つい実験っぽいことをしてみたくなる。でも、Ryojiにはポップな資質があるし、彼の意見をちゃんと聞いたほうがポップ性が出ていいんですよね。それは判っているんだけど、つい...ね。
Ryoji:Leoの実験的な面も凄く好きなんですけど、彼が行きすぎた方向になると「この部分は敢えて主張しないで、この後に取っておいたほうがスリリングだし仕掛けになるよ」って僕が説得してみるんですよ(笑)。
Leo:でも、大抵は聞き入れない。「ここでタコの音が必要なんだよ!」って主張するんです。
──タコの音?(笑)
Leo:音にはそれぞれ色やイメージがあるでしょう? 感覚的なものですよ。「あの色、うざいね」みたいな。
Ryoji:音は目に見えないものじゃないですか? でも、特にライヴの時はそれが見えるんですよ。色や形が見えたりする。
Leo:曲作りをする人なら必ず判る感覚だと思いますよ、その音の色とかイメージみたいなものは。
──では、「Shoot the radio」と「Shadow disco」はそれぞれどんな色をしているんでしょう。
Leo:聴き手のイメージを限定させたくないので、そこは余り言わないほうがいいかな。でも、どちらもちゃんと色を感じてもらえると思いますよ。
いいメロディを探すことは愛に向かうこと
──シングルには「Shoot the radio」のPVも収録されているんですよね。
Leo:自分たちなりのモダンさを出せたと思いますね。これは是非、iPodで見て欲しい。そのほうが伝わると思うから。大画面のテレビで見るとニュアンスが変わってダメなんです。テレビよりもネットで見たほうが映えるPVだと思うんですよ。
──感性は60年代のサイケデリックを基軸としているのに、そういった部分は極めて今日的なんですね。
Leo:アンチにせよ肯定にせよ、そこは逃げちゃいけない。僕らは2008年という現代に生きているわけだから。
──今回のシングルにはもう1曲、「Jewel」という曲がライヴ・ヴァージョンで収録されていますが、これは掛け値なしの名曲ですね。
Leo:お披露目的なシングルだし、自分たちのライヴはこういった感じですっていうのを出そうと思って。俺たちの場合、ライヴは4人それぞれ志向が異なるんですよ。4人の子供が集まって初めて1人の人間になるみたいなところがある。4人の資質やライヴに対する心構えもまるで違うんです。たとえばRyojiが戦いの狼煙を上げる役割だとしたら、俺はただ祈りを捧げる感じなんですよ。そうでもしなければ、何で俺はステージに立ってこんなに辛いことをやってるんだ? と思ってしまう。だから祈るんです。
──己の心身を犠牲にして表現と対峙する、それを公衆の面前に晒すから辛いということですか?
Leo:そうですね。よく「お客様は神様です」という言い方がありますよね。ただ、俺が聞いたある噺家の話によると、お客さんの頭上に神様という純粋な力があって、そこに向けて話をするそうなんです。そういう考え方に似ていて、ステージの上に立つと生と死が対話するようになるんですよ。ただ、今までは観念を捨てて自分の存在を無にすることで何かを受け取ろうとしていたのが、最近は能動的に愛することで何かを受け取ろうとするようになってきた。愛すれば必ず大事なものが自分の中に残るし、与えたほうが受け取りやすいんですよね。
──それこそビートルズが唄う「The End」の歌詞の通りですよね。"And in the end, the love you take is equal to the love you make."、最終的にあなたが受け取る愛の量はあなたが生み出した愛の量と等比であるという。
Leo:そういうことですね。唄うことが心から楽しいという感覚が今まで余り理解できなかったんですけど、ここのところ視界がちょっと開けてきた気はするんですよ。徐々にですけどね。ライヴは魂が直接触れ合う場だから、どうしても真摯にならざるを得ないんです。
Ryoji:僕たちのライヴは最高か最悪かの二つに一つなんですよ。真ん中がないし、浮き沈みが激しいんです。最高のライヴをやるに越したことはないけど、仮に最悪なライヴをやってオチても、次は必ず見返してやろうと思うから無駄なことは何もないんですよね。
──ちなみに、ジョンズ・ゲリラというユニークなネーミングはどんな経緯で付けられたんですか。
Ryoji:最初はフィジカル・マターっていう名前だったんですよ。言葉も音と同様に色を持っていると思っていて、フィジカル・マターは青白いイメージだった。青白さだけじゃ音楽的に矛盾があったり、レンジの狭さを感じたんですね。僕たちはもっと赤くて土臭いサウンドを鳴らしたいと思ったので、去年からジョンズ・ゲリラと名乗るようになったんです。
Leo:"ジョン"はジョン・レノンの"ジョン"なんですよ。ジョン・レノンの「マインド・ゲームス」に"心のゲリラになって、平和のマントラを唱えるのさ"という一節があるのを偶然見付けて。あと、"ジョン"には"ヨハネ"という聖書っぽい意味合いもある。その二重の意味があって面白いなと思って名付けたんです。そういうミックス的な感覚が好きなんですね。音楽的にもそう在りたい。実験性の中にも愛に向かっていくのが俺たちにとってのポップだし、いいメロディを探すことと愛に向かうことは同義なんですよ。俺たちの生み出す音楽は愛そのものですから。