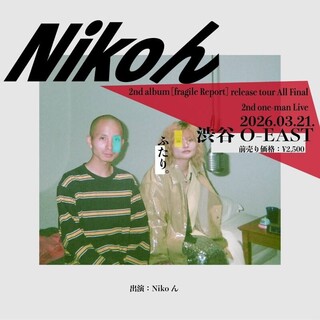常にギリギリのところで喘いでやっている感じ
──こうしてあの当時の福岡シーンを振り返ってみて思うところは?
中尾:シーンと言われても、当事者として渦中にいたから対象化するのは難しいですよね。シアトルやサンディエゴ、ワシントンD.C.のシーンには憧れましたけど、そういうのが当時の福岡にあったのかと思うと、どうなのかな? って。単純に懐かしいとは思いますけど。10代の終わりに福岡に出てきて、20代の前半までの感受性豊かな時期で、いろんなものを吸収できたのは良かったですね。70'sパンク一辺倒だったのを、保田さんの影響ですっかりグランジ色に染められて(笑)。
吉田:女の子からキャーキャー言われないとロックじゃないのか? という疑問が当時主流と呼ばれていたロックに対してずっとあって、地味でも自分達にしか出せない音楽をやっているバンドが自由に演奏できる場所を作れたら楽しいのになぁといつも考えていましたし、それが『CHELSEA-Q』へと発展していって…。状況がないから自分達で作るしかなかったんですよ。それが今思えばシーンと言えばシーンだったのかな、と。『CHELSEA-Q』に影響を受けて、今福岡で独自のシリーズ・イヴェントを行なっている人達がいると聞くと素直に嬉しいですし、何かのきっかけは作れたのかなと思いますね。
三栖:PANICSMILEに関して言うと、精神的にも肉体的にもギリギリのところで喘いでやってる感じが良かったですね。今振り返ってもそういうバンドだったなと思える。その常にギリのところでやってるからこそ、ちょくちょく摩擦が起きたりもしたんだろうし。それは人間関係だけじゃなくて、音作りにおいてもそうだったと思うんですよ。今は吉田さん達も歳を取ったけど(笑)、今の年齢なりのギリのところでPANICSMILEは続いているし、ずっとそのままでいて欲しい。自分も怠けてないで、常にギリのところでデザインに打ち込みたいと今も思っています。当時からそう思ってたしね。PANICSMILEやNUMBER GIRLのライヴを観て、凄まじいキワキワ感を全身に突き付けられて、“ああ、もう俺はダメやぁ…”ってよく思ってましたからね。
中尾:“ダメや”じゃダメじゃん(笑)。
──聞くところによると、目下制作中のPANICSMILEの新作は随分と趣が異なるそうですけど…。
吉田:そうですね。かなり歌モノのテイストが強い、アダルトな感じになると思いますよ(笑)。
──『E.F.Y.L.』をPANICSMILEの後期と呼ぶ憲太郎さんからすると、今のPANICSMILEは一体何期になるんでしょうね?(笑)
吉田:東京に出てきてからのPANICSMILEは、憲太郎にとっては別物でしょ?
中尾:そうですね。メンバーも違いますからね。
吉田:東京に来てから対バンもしたし、ライヴも観に来てもらったりもしましたけど、憲太郎が「いい」って言ったことは一度もないですからね(笑)。
──では逆に、吉田さんから見たSLOTH LOVE CHUNKSは?
中尾:勘弁して下さいよ(笑)。
吉田:僕は好きですね。特に憲太郎がリード・ヴォーカルを取ってる曲がいいですよ。憲太郎の声は、僕の中ではシド・バレットに近いですから。「自分がリーダーをやるバンドなんだから唄いなよ」って、stink bombをやってた時もずっと言ってたんですよ。だから憲太郎にはもっと唄って欲しいですね。どんどん唄って、とにかくバンドを続けて欲しいです。福岡にいた頃は、こんな未来が来るとは思ってもみなかったですからね。みんな三々五々に散らばってもう二度と会わなくなるのかなと思っていたのに、東京に出てきても??みんなそれぞれ好きなことをやって、苦境に臆することなく音楽を楽しんでやっている。その図太さ、強さは信頼できると思うんですよ。だから憲太郎や一明君を始め、同郷の仲間達に対しては「これからも末永くよろしく」と言いたいですね。