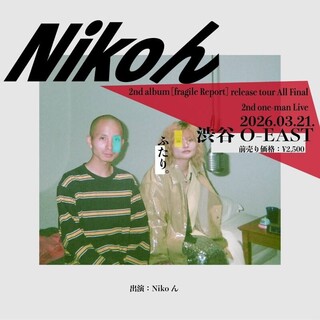福岡出身バンド独特の匂い
──『CHELSEA-Q』の1回目は、イヴェントとしては成功だったんですか?
中尾:天神のハートビートっていう200人入るところでやって、もうパンパンでしたからね。
吉田:300人キャパのビブレホールにお客さんが10人くらいっていうイヴェントを僕はずっと見てきたから、1回目は状況として凄く広がったなと思いましたね。出演したのもヴェルヴェッツチルドレン的な割と淡々とした音楽をやっていたバンドばかりだったから、“こういうイヴェントでもちゃんと成立するんだ!”ってショックだったのを覚えていますね。自分達で企画しておきながら何ですけど(笑)。
──『CHELSEA-Q』は、椎名林檎さんも常連のお客さんだったそうですね。
中尾:だいぶ後期でしたけどね。ハートビートでやるのをやめて、ビーベンとかでやってた頃かな。デラシネのメンバーとかも観に来てましたね。
──豊嶋さんがライナーに書いていましたけど、『CHELSEA-Q』の中心スタッフに誰も福岡出身の人間がいなかったというのが面白いですよね。
吉田:そうですね、生粋の福岡市内の人間は誰一人としていなかったですね(笑)。向井君と一明君は佐賀県、憲太郎は北九州市だったし。僕は実家が福岡市内ではあるんですけど、高校時代は広島にいたんですよ。広島から福岡市の大学を受験したんです。だから、純然たる福岡市民は誰もいなかったんですよね。
──当時のロレッタセコハンはどういった存在だったんですか?
中尾:ひとつのライヴハウスを基軸に独自の企画を展開していくというよりは、イヴェント用のバンドみたいなところがありましたね。
吉田:メンバーも公言しているのでこの場で話しても差し支えないと思いますけど、前進して突破していこうみたいな意識が元々ないバンドだったんです。東京に出てメジャー契約して成功しようとか、そういう上昇志向は端からなくて、常に自分達のやりたいことをやり続けようとしていた傍観者的な立場だったんで??すよ。ロレッタセコハンとの出会いは『E.F.Y.L.+1/72』のライナーに豊嶋君も書いていますけど、このCDにも入っている「メリーゴーランド」という曲がFM福岡で掛かった時に、たまたまロレッタセコハンのメンバー3人がそれを車の中で聴いたらしいんです。てっきり東京のバンドかと思ったら福岡のバンドだと知って、わざわざ僕達のライヴ・スケジュールを調べて観に来てくれたんですよね。で、「自分達もバンドをやってるんですけど、やる場所がなくて…」みたいな話をしてくれたのが最初でした。そこから彼らには『CHELSEA-Q』の中期から後期にかけて関わってもらったんですよ。
──憲太郎さんがNUMBER GIRLと掛け持ちしていたstink bombも『CHELSEA-Q』の常連だったんですか?
中尾:いや、出たことはないですね。
吉田:でも、『CHELSEA-Q』に出たからあのコンピ(『Headache Sounds SAMPLER CD volume two』)にも入ってるんじゃない? 1回くらいは出てるはずだよ。
──そう、'90年代後半の福岡シーンを語る上で『Headache Sounds SAMPLER CD』は当時の熱気を伝える重要な音源ですね。
吉田:『〜volume one』のほうは、NUMBER GIRLだけ向井君が録音していて、あとは全部僕が録音しているんですよ。『CHELSEA-Q』にレギュラー出演していた精鋭バンドの音源を集めたコンピレーションなんですけど、今思うと福岡っぽい匂いがどのバンドにも通底している気がしますね。あの頃は当事者として渦中にいたからそんなことは気にも留めませんでしたけど、上京して高円寺の20000Vや秋葉原のGOODMANで働いていた時に観た福岡出身のバンドにはやはりどことなく“らしさ”を感じましたよね。武骨さが際立っていて、熱い。もう暑苦しいくらいに(笑)。どこか過剰なところがあって、とにかく濃いんですよ。
中尾:それが福岡っぽさと言われても、当時は他の地域と比較して客観視できる情報もなかったですからね。未だに客観視はできないですけど(笑)。『〜SAMPLER CD』に収録されたバンドも、仲のいいバンドももちろんいましたけど、全部が全部仲が良かったかと言えばそんなこともなくて。今みたいにCD-Rで簡単に音源を作れなかったから、束になってみんなでオムニバスを作ったっていう側面があったと思いますよ。



盟友・向井秀徳との確執
──『CHELSEA-Q』に携わった顔触れの中で、東京へ出て勝負をしたいという意識が最も強かったのは…。
吉田:やっぱり、向井君でしょうね。
中尾:でもそれは、イヴェントができるようになって、NUMBER GIRLをちゃんと続けることができるようになってからじゃないですかね。
吉田:東京のレコード会社から「ソロで契約しないか?」っていう話を貰ったけど、自分はあくまでもロック・バンドをやりたいから態度を保留にした、なんて話を当時聞きましたけどね。
三栖:どこのメーカーの人かは知らないけど、連絡を取り合って助言を貰ってたみたいですね。その話は途中で立ち消えになったらしいですけど。向井は東京云々の前に、カセットではなくアルバムをちゃんとCDでリリースしたいっていう意識のほうが強かったんじゃないかと僕は思いますけどね。インディーズで『SCHOOL GIRL BYE BYE』を出してから、すぐに東芝EMIの??人が目を付けてくれたから割と早かったけど。
──吉田さんもNUMBER GIRLと時を同じくして'98年9月には上京して、活動拠点を東京に移すわけですが。
吉田:『E.F.Y.L.』のオリジナルのデザインがうまく行かなかったというさっきの一明君の話に繋がるんですけど、赤裸々な話をしますと…これ、ホントは話すのやめようと思ってたんですけどね。
中尾:もういいんじゃないの?(笑)
吉田:最初は“イヴェントを盛り上げよう、先代のめんたいロックに恥じない動きを活発化させて勢い良く突破していこう”と一丸となっていたんですけど、後期になるに従って「自分達はメジャーと契約してデビューしたい」とか「ウチはバンドをやめる」とか、バンドの置かれた状況や『CHELSEA-Q』に対する意識が食い違ってきたんです。PANICSMILEはずっとマニアックなことをやってきたので、メジャーとの契約はできないだろうし、長くバンドを続けていくためにもインディペンデントなレーベルの仕組みやディストリビューションの流れを自分達でも勉強していかなくちゃいけないと考えた時期だったんですね。それと、同じ時期に向井君と僕の間に確執があったんですよ。
──それは『CHELSEA-Q』に対しての見解の違いですか?
吉田:と言うよりも、バンド観の違いですかね。NUMBER GIRLがEMIとうまい感じに行き始めて、ある時酔っ払った向井君が僕にこう言ったんですよ。「吉田君、俺はもういち抜けますわ。地方で盛り上がるだけの場所に自分はいつまでもいたくないです」と。僕は「ずっと一緒にやってきた同志だろ? 何を言ってるんだよ!?」と説得したんですけど、「俺は次を見てますから」と言われて。これには僕も愕然として、それ以来、向井君とは一切口を聞かなくなっちゃったんです。その後も向井君はビブレホールにフラフラやって来ては酔っ払ってワーッと盛り上がっていたんですけど(笑)、いい奴だなとは思いつつも、妙な意地の張り合いで突っぱねちゃったんですね。
──東京進出を決めた向井さんに対する嫉妬心もありましたか?
吉田:ええ。正直に申し上げると、やっかみがあったんですよ。当時僕は28歳になっていて、30代を目前にして“自分で選んだ道をちゃんとやらないかん!”という焦りもあったし、もの凄く混沌としていたんですよね。そんな状況だったから、一明君も「このデザイン、どうしていいか判らんよ」っていうことだったんだと思います。『E.F.Y.L.』を作っている時は『SCHOOL GIRL BYE BYE』のデザインも同時進行でやっていて、“『SCHOOL GIRL〜』のほうはあれだけデザインに力を入れているのに、こっちは何だよ!?”っていう気持ちが正直あったんですよ(苦笑)。でも、一明君は限られた時間の中で精一杯やってくれたわけだから、そういう考え方はいけないなと思って。
──その後、向井さんとの仲は改善されたんですか?
吉田:向井君は何度も何度も歩み寄ってくれたんですよ。「俺達も東京で動員が増えてきたんで、一緒にイヴェント出て東京で頑張りましょうよ」と言ってくれたんですけど、「君の話は聞きたくない」と突き放してしまって。
中尾:だから、その当時は三栖君も僕も本気で板挟みだったんですよ(笑)。
吉田:(苦笑)その後上京して落ち着いた頃に自分が大人げなかったのを認めて、向井君に「ごめんなさい」と頭を下げましたけどね。僕のほうが向井君よりも年上なのに、本当に大人げなかったと思いますよ。