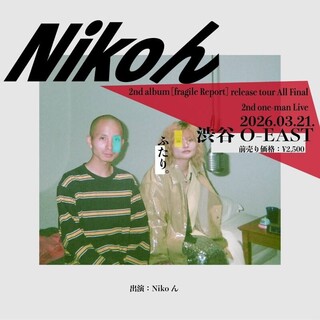高い殺傷能力だけを求めていた
──今回再発されたPANICSMILEのファーストは、憲太郎さんと三栖さんにはやはり衝撃の一枚でしたか?
中尾:僕はこれ、ファーストだと思ってませんから。その前にいっぱいカセット音源があったので。今回CDに追加された『SCALE KIT 1/72 100%PLASTI??C』の前にも、全く世に出ていない音源がいろいろあるんですよ。
三栖:『E.F.Y.L.』って'98年8月のリリースでしょう? 僕達にとっては“ファースト”じゃ全然ないんですよ。
中尾:僕にとっては“後期”なんですよね(笑)。
吉田:そうだろうね。'93年くらいからデモ・テープはかなり作ってましたからね。
三栖:自分にとってのPANICSMILEは、やっぱり「分解」に尽きますね。やっさんのあのギターのリフはへんちくりんで凄く恰好良かった。あの曲は僕にとって2回目のブレイク・ポイントやったみたい。ライヴで踊り狂ったもん(笑)。この『E.F.Y.L.』の中では断然「MECKI 16」が好きですね。
吉田:「MECKI 16」も、言ってみれば「分解」の延長線上にあるパワー・リフの曲だからね。
──憲太郎さんと三栖さんが最初に観たPANICSMILEのライヴって覚えていますか?
中尾:確かビブレホールの何かのイヴェント枠で、GILLCOVERのツアーだったような気がしますね。直球のグランジで、リアルでしたよ。PANICSMILEみたいなバンドはそれまで観たことがなかったから、とにかく衝撃的で。今聴いてみると無闇なノイズってわけでもないですけど、当時としては凄かった。
三栖:記憶に残ってるのは、ビブレホールで映画のイヴェントとくっついたライヴですね。そこでPANICSMILEがゴダイゴの「銀河鉄道999」のカヴァーをやって、“オォ!”と思いましたね。それが最初です。そう考えると、『E.F.Y.L.』はやっぱり僕にとってはPANICSMILEの後期なんですよ。鳥井さんと大石さんのいた第1期の後期。
中尾:そうだね。最初に観たライヴがいきなり『E.F.Y.L.』の時期だったら、多分受け容れなかったですね(笑)。
──吉田さん自身がこの『E.F.Y.L.+1/72』を改めて聴いて思うところは?
吉田:当時自分が求めていたのは高い殺傷能力だけだったんですよ(笑)。如何に耳を虐げられるかみたいなところで。現状に対する焦燥感だったり、未来が見えない中で音楽をやっていく自分に対する責任感だったりを突き詰めたら、あんなノイズになったんです。今回、マスタリング・スタジオで久し振りにオリジナルを聴いて、自分でも酷いなと思いましたよ(笑)。マイナス・パワーがこれでもかとばかりに噴出していて。だからエンジニアさんに「当時自分が思っていたよりもネガティヴな音になっているので、もっと明るい音にして下さい」とお願いしたんですよ。
──今回のリマスター盤は、オリジナルのジャケットを手掛けた三栖さんがデザインも“リマスタリング”して一新されていますね。
三栖:そうですね。当初は単なる焼き直しで行くかっていう話だったんですけど、吉田さんが「ジャケットのイメージを変えたい」っていうことで。これ、余りいい話じゃないかもしれないけど、オリジナルのデザインをした頃はよく判らなくなってた時期なんですよ。
──デザイナーとして、ですか?
三栖:いや、PANICSMILEに対してもそうだし…。
中尾:三栖君が板挟みに遭った頃っていうこと?(笑)
三栖:いや、そんなことない。僕は板挟みになったことはないし、あくまでいつも中立の立場だったから。『CHELSEA-Q』もその当時4年目で、イヴェントがスタートした時の新鮮さと面??白さの勢いがフラットになってきて、それぞれのバンドの活動形態も変わってきていたんです。僕はNUMBER GIRLのほうもいろいろと手伝ってたし、彼らが東京に行く準備をしていた頃で、それぞれがそれぞれの次の方向に向かっていった時期だったんですよね。『CHELSEA-Q』を今後どうしていくか、それぞれの思惑があったみたいで。昔みたいに“何も言わないけど共感している”っていう塊ではなくなっていたタイミングだったんです。そういう、僕自身も何を面白がっていいのかよく判らなくなっていた時期に、この『E.F.Y.L.』のジャケットを手掛けたんですよ。
──ちょっとほろ苦い時期だったわけですね。
三栖:そうですね。余りいい時期ではなかった。『CHELSEA-Q』のフライヤーを僕は月一でずっと作ってたんですけど、最後の1年は作らなくなってましたから。


表現の基本であるハンドメイドな感覚
──NUMBER GIRLのファンには、向井さんが目を閉じて煙草をくわえた写真をあしらった『CHELSEA-Q』vol.5のフライヤーがお馴染みですけど、三栖さんの手掛けるフライヤーはいつまでも手許に残しておきたい秀逸なデザインばかりですよね。
吉田:うん、本当に素晴らしいと思いますよ。
三栖:『CHELSEA-Q』の1回目から手掛けてますからね、バカボンのママを使ったやつ。
吉田:いや、1回目のは一明君のデザインが間に合わなくて、僕が手書きしたやつだったんだよ。
三栖:あれ、そうなんだ? てっきり間に合ったのかと思ってた。向井はそんなこと言ってなかったよ(笑)。
中尾:僕が見た最初の『CHELSEA-Q』のチラシは、“Q”ってでっかくトリミングされてるやつだったよ。
三栖:あ、そうなの? 僕、確か『CHELSEA-Q』の1回目には行けなかったんですよ。2回目から「お前がやってくれ」って向井から直接トスが来て、そこからレギュラーになったということか。
──いろいろと意見が食い違ってますが(笑)。でも、当時はデザインも完全に手作業ですよね?
中尾:カラーコピーを使ったりしてたよね。切り張りでフライヤーの原紙を作って、コンビニのコピー機で黒インクのコピーをした後にそれを給紙に再度入れて、更に赤インクのコピーをして重ね刷りしたり。
三栖:僕はデザインの学校に行ってたから、レタリングの本をコピーしてアルファベット順に切り抜いて、糊で貼り付けて、バンド名とかタイトルを作ってたんですよ。
中尾:基本ですよ、そういうのはやっぱり。
──マックには絶対出せない、何とも言えぬ温かみがやっぱりありますよね。
三栖:あると思いますね、間違いなく。後年はマックを導入しましたけどね。『CHELSEA-Q』も、PANICSMILEも、NUMBER GIRLも、外に向かうエネルギーがどれも凄く強かったんですよ。ただ自分達だけで好きなことだけをやるような内輪ノリは一切なかった。彼らの凄く前向きで外に向かう部分に僕は凄く共感していたし、自分がヴィジュアルを作る立場で参加する上で、デザインで如何に外に向かって伝えるかっていうのを常に意識してましたね。適当に殴り書きしただけのフライヤーはパンキッシュで??、視覚的に恰好いいのかもしれないけど、それじゃ外に向けて伝わるものも伝わらないと僕は思う。そういうところで、外に向かう作業を手伝えたことが当時の僕には凄く重要だったと思いますね。
──前から伺いたかったんですけど、三栖さんにはバンドをやろうという発想はなかったんですか?
三栖:なかったですね。ギターを練習しようとかしたけど、家にあるアコースティック・ギターは遊びに来た向井が気持ち良い顔をして弾いてただけです(笑)。僕がそこで向井よりも弾けたら、向井は多分気持ち良くなかったはずです(笑)。 吉田・
中尾:はははははははははは。
三栖:僕はフライヤーを作る時に、“あ、このイヴェントに行ってみよう”と思わせたい一心で作ってましたよ。ライヴハウスやレコード屋にそのフライヤーが置いてあるとしたら、それを必ず持って帰らせたい。とにかくそういう意識でしたね。
──そういう意識は、今日に至るまで三栖さんの手掛けるフライヤーに一貫していると思うし、憲太郎さんが手掛けるSLOTH LOVE CHUNKSのフライヤーにも同じことが言えますよね。
中尾:そうですね。ハンドメイドな感覚っていうのは、何事においても基本でしょう?