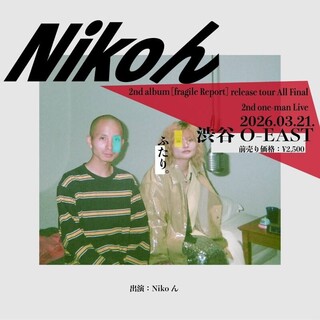'98年8月に発表され、長らく廃盤の憂き目に遭っていたPANICSMILEのファースト・アルバム『E.F.Y.L.』がこのたび目出度く復刻された。しかも、'95年に発表された14曲入りのカセット音源『scale kit 1/72 100% PLASTIC』を追加収録し、丁寧なデジタル・リマスタリングが施された上にジャケットまで新装されたパニスマ・ファン必携のアイテムである。凄まじく殺傷能力の高いノイズと不安定ながら革新的なビートが今なお鮮度を失っていないこの不世出の名盤の再発を記念して、PANICSMILEの吉田 肇、SLOTH LOVE CHUNKS/SPIRAL CHORDの中尾憲太郎、NUMBER GIRLやZAZEN BOYSのアートワークで知られるデザイナーの三栖一明を迎え、'90年代当時のPANICSMILEとそれを取り巻く福岡シーンの状況を今改めて検証してみたい。(interview:椎名宗之)
イヴェントをやるためのレーベル発足
──まず、『E.F.Y.L.』を再リリースした経緯を吉田さんから訊かせて下さい。
吉田:最初に福岡で自主制作した時に、流通する手段というものを全く持っていなかったんですよ。体当たりでお店にアプローチして、委託販売をお願いする形ばかりで。福岡以外だけじゃなく他の地域でも売りたいと思って1,000枚プレスしたんですけど、そのダンボールの山を自分の部屋でずっと眺めながら辛い思いをしていました(苦笑)。
──ライヴの物販でも相当売れたんじゃないかと思いますけど。
吉田:そうですね。ツアーはかなり精力的にやっていたので、ツアーの合間に委託で扱ってもらえるレコード店を回ったりして、何とか1,000枚は捌けたんです。有り難いことに「音源を聴きたい」という声を今までも頂いていたんですけど、店頭在庫のみの状況が続いていて。そこで、今は『Headache Sounds』のレーベルA&Rとしての活動を本格化しているので、ちゃんとした形でCDを全国に流通してみようと思ったんです。
中尾:よーく探してみると、今もディスクユニオンとかで500円で売ってることもありますけどね(笑)。
──そんな憲太郎さんは、向井秀徳(ZAZEN BOYS)、豊嶋義之(ex.ロレッタセコハン)の両氏と共に「90年代当時の証言記録」として特別寄稿されていますね。情緒があって、僕は非常に好きなんですが。
中尾:はい、頑張りました。赤裸々な感じで(笑)。
──当時ビブレホールで働いていた吉田さんの紹介で憲太郎さんがビブレホールで働くことになり、吉田さんの家に居候までしていたのはよく知られた話ですね。
中尾:吉田さんの前にまず保田(憲一)さんと知り合ったんですよね、大学の時に。その頃まだ保田さんはPANICSMILEのメンバーじゃなくて、キューティーリップスパイっていうフレンチ・ポップのバンドをやっていて。その保田さんに連れて行かれたライヴがPANICSMILEだったんですよ。
──憲太郎さんは吉田さんの第一印象を覚えていますか?
中尾:最初にライヴを観に行った時は、確か挨拶くらいしかしなくて。ビブレホールのベンチで当時のドラマーだった大石(進)さんに「パンクが来た! パンクが来た!」って言い方をされて、2人でずっとBUZZCOCKSを唄って、ゲラゲラ笑ってた…そのイメージがありますね。
──それがいつ頃の話ですか?
中尾:僕、年代の割り出し方がよく判らないんですよ(笑)。
吉田:'93年頃ですかね。PANICSMILEの結成が'92年の11月で、ビブレホールに出るようになったのが'93年の春からくらいからなんですよ。
──三栖さんは、吉田さんや向井さん、安積一仁さんと『Headache Sounds』を立ち上げた一人として有名ですね。
三栖:僕は福岡の文脈と出会う前に、向井との仲がまずあって。先に向井がやっさん(保田)や??安積君、吉田さんと仲良くなって、それからですね。向井に連れられてやっさんや安積君の家に遊びに行ったり、PANICSMILEのライヴを観に行くようになったりする感じでしたね。
──'93年に立ち上がったレーベル『Headache Sounds』は、どんな形で始まったんですか?
吉田:最初の最初は、まずイヴェントをやろうってことになって、団体を作るんだったら何か名前を付けようぜ、って話になって。イヴェントをやるなら、その主宰名義がいいだろう、ってことで。
三栖:僕はその“イヴェントやろう”っていうスタートの時にはまだいなかったんです。向井から「『CHELSEA-Q』っていうイヴェントをやるから、お前フライヤーを作ってみてみぃ」って言われたのが関わりの最初だから。



閉塞感を打ち破った“博多NO WAVE”
──ちなみに、『Headache Sounds』という名前の由来はどこから?
三栖:フランク・ブラック(ex.PIXIES)の曲に「Headache」っていうのがあるから、そこから採ったのかなと僕は思ったんですけど。
中尾:うーん、その頃フランク・ブラックはまだソロを出してなかったんじゃないかな。
吉田:そうそう。ただ僕が覚えてるのは、『CHELSEA-Q』で向井君がフランク・ブラックの「Headache」をDJで思いきり掛けたことがあって、彼にはフェイヴァリットな1曲なんだなと思ったことはあったけど。安積君がEARACHEとか好きだったから、それをもじったのかもしれない。
──それは向井さんがまだNUMBER 5の頃ですか?
吉田:憲太郎が入る前のNUMBER GIRLかもしれないですね。リズム隊が全然違う、トリオ編成の時代があったんですよ。
──じゃあ、『Headache Sounds』は当初、『CHELSEA-Q』という自主企画を始めるためのものだったんですね。
吉田:それと、向井君が自分で作ったカセット・テープのラベルに付けるマークとして(笑)。
中尾:スタイルですよ、スタイル。スタイル・イズ・エヴリシング(笑)。
──向井さんのライナーによると、当時の福岡シーンはライヴハウスのブッキングで演奏するのが主流で、自主企画でライヴハウスを借りて『CHELSEA-Q』のようなオールナイト・イヴェントをやることは皆無に等しかったそうですね。
吉田:そうですね。僕は19歳くらいからビブレホールで働いてたんですけど、当時“イカ天”(『平成名物TV・三宅裕司のいかすバンド天国』)はまだやっていたものの、そのからくりが透けて見えて何となく白けるところが既にあって、つまりはバンド・ブームの終焉時期だったわけです。“イカ天”にも出演したことのあるたけのうちカルテットっていうプログレ・バンドとか、あとはモッズの亜流みたいなバンドばかりだったんですよ。ヴォーカルはリーゼントで、サウンドは8ビート一辺倒っていうような。僕はルースターズやARBといったいわゆる“めんたいロック”と呼ばれる音楽も純粋に大好きだったので、余計にこれでいいのかと思ったんですよね。福岡で新しいものはもう生まれないのだろうか? という閉塞感があったんです。
──当時隆盛を極めていた、グランジや??オルタナティヴに感化されたバンドが出てくる土壌がなかったわけですね。
吉田:ジャンル的な括りに関係なく、全く新しいことを志向していた人達はいたんですよ。蝉やFREEMAN、人間、グラインドサアフといったバンドですね。そういったバンドには、個人的に凄く感銘を受けました。それまでの、サンハウスから始まったロックの文脈ではないところのサウンドが福岡にもあるんだという認識が持てたので。それで、彼らのようなバンドを軸としたイヴェントをビブレホールでも打ち出していきたい、と思うようになったんです。
中尾:それが『博多NO WAVE』に繋がるわけですね。
吉田:そうそう。僕はPAもやっていたので、バンドの承諾を得てライヴ音源をまとめた『博多NO WAVE』というカセットも出したことがあるんですよ。
中尾:ビブレホールの他にDRUM Be-1っていうライヴハウスがあって、系列店のLOGOSはヴィジュアル系やヘヴィ・メタル系のバンドが動員力を誇っていて、Be-1で演奏できないニュー・ウェイヴ/パンク系のバンドがビブレホールに流れてきたんです。要するにその手のジャンルは余りにアンダーグラウンドなので、人が入らないんですよ。
吉田:目立った活動はないにせよ、スワンキーズを筆頭としてパンクの流れはずっと生きていたんです。その流れとは関係なく、クラブから派生したハードコア、スケーター・パンク系のバンドも活動してましたし。Be-1に出てたバンドも僕は結構好きで、ちゅうぶらんことかライカスパイダーといった濃いバンドは、セックス、ドラッグ&ロックンロールを地で行くような人達でしたね。
──話を伺っていると、吉田さんは当時の福岡シーンにおける新しい動きの首謀者的存在だったように思えますが。
中尾:うーん、そういう感じでもないんですよね。それまでの流れにない新しいバンドがライヴをできる場を提供していった、というのはありますけど。
三栖:強いリーダーシップを持って、声を張り上げて「こうやれ、ああやれ」って言ったわけじゃないしね。
吉田:僕が躍起にならなくても、憲太郎とか下の世代が自然と育ってきてましたからね。「動員が少ない」っていうだけでBe-1から締め出しを喰らった自分より年上のバンドにビブレホールでやってもらったり、目当てのバンドの演奏が終わったらお客さんが帰ってしまうようなイヴェントではない、粒の揃ったバンドのブッキングに腐心したりはしましたけどね。
──そうした吉田さんの果敢なブッキングによって、ビブレホールはオルタナティヴの匂いが色濃いライヴハウスとして認知されていった、と。
吉田:ビブレホールはデパートの中にあって、当時はテナント契約のシステム上、余り売上げを出しちゃいけないっていう変わったハコだったんです。だから集客のないバンドでもブッキングしやすい状況にあったというのがその一因としてあるんですよ。