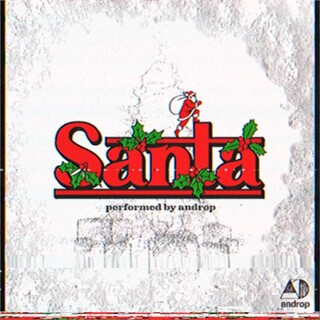雷に撃たれたような衝撃を覚えた「静かなるアフガン」
なんの因果か(笑)、長渕 剛の「静かなるアフガン」を聴いてぶっ飛んだ。どんよりと重くたれ下がった雲と6月のコンクリート・ジャングル......新宿の街角の雑踏の中で、ほんの小さなレコード屋からそのメロディと歌詞はビルを吹き抜ける風に乗って流れてきた。70年代のメッセージ・フォークを彷彿させる独特な低音のうなりに似た長渕節が流れ、駅に向かう急ぎ足の群衆の流れに抗するように私一人の足がふと止まった。群衆(alone-together)の中で私の琴線〈きんせん〉に鋭く触れた。えっ、なんだって?......「海の向こうじゃ 戦争がおっ始まった/人が人を殺し合ってる/アメリカが育てたテロリスト......戦争に正義もくそもありゃしねぇ」と切れ切れに聴こえてくるメッセージに、雷に撃たれたような衝撃が私の全身を貫いた。こんな気になったのはジョン・レノンの「イマジン」以来か? これって唄っているのは長渕じゃないか?(text:平野 悠)
平野:長渕さんの今回のシングル「静かなるアフガン」、これは僕にとって“何だこれはッ!?”っていう衝撃的なものだったんですよ。僕も音楽業界のことは少しは知ってるんで、例えばNHKとか大手の放送局では“絶対にこの曲をかけられないだろうな”と思ったんですよ。それが一番初めの僕の感想だったんです。大手の媒体やらお役人やらは「これはヤバイ!」って勝手に自主規制しちゃいますからね。じゃあ、“孤立無援なこの曲に対して僕は何ができるだろう?”と。で、長渕さんご本人とは関係なく、僕は僕なりにこの曲を支えてみたいと思ったんです。
長渕:はい(笑)。
平野:それで、ウチのロフトという店に出入りしてる音楽評論家の吉留(大貴)に「オイ、長渕に会わせろ!」と。そしたら色々と根回しをしてくれて、フォーライフの横田(利夫)さん[プロモーション本部]を紹介してもらって。それだけの話なんですよ、実は(笑)。こんな歌を作った奴に会ってみたいと…。長渕さんは全共闘世代っていうか、団塊の世代の一番最後の頃…つまり、何をやっても敗北感を味わう時代が青春だったと思うんです。僕は長渕さんより12歳年上なんで、ああいう政治的な季節に青春を送っていて、どっかで“勝ち組”なんですよね。デモをやれば1万人くらいすぐに集まったり、ロック、映画、演劇、ストリート、あらゆる場所で雑多な文化が花開いていた時代。日本のルネッサンス(夜明け)だった。高校でもストライキが確立したりね。そんな時代の洗礼を受けながら、プレッシャーはあったけれど、いつも新しい未来、新しい社会を想像し、夢見ることができた。でも、長渕さんの世代は何をやっても「そんなことは上の世代がもうやったよ。内ゲバ、リンチ殺人、最悪…それで社会は変わったの?」などと言われてしまう…。
長渕:そうですね。僕らの兄貴分の世代…仰るように団塊の世代の人たちが「時代を変えるんだ!」とか、社会の理不尽なものに対して反骨精神があったわけですよね。その中の一環として“歌”というものがあって、そこに魅了されたのは明らかな事実であり、僕が音楽をやり始めたきっかけです。僕らは世代的には“三無主義”(=無関心、無感動、無気力)の世代に入るんですけれども、僕がデビューしたての頃は《遅れてきたフォーク少年》っていうキャッチフレーズがやっぱりたくさん付きましたよ。だから今仰ったように、兄貴たちが敷いてきたレールがすでにあったものだから、「自分はそのレールの上に乗っかっていくだけか!?」っていう部分での敗北感というのかな。今振り返れば、デビューして10年くらいはその中で苦しんでたと思います。
平野:その話は僕も聞いたことあります。最初は随分と売れなくて、凄く苦しんでいたという…。
長渕:最初は僕も<照和>という福岡のライヴハウスで3年間やってましてね。その中で半分東京に足を突っ込んだり、また福岡に舞い戻ったりという生活をして。本格的にプロとしてデビューしてからは、僕の場合は他人から見れば意外と順風満帆にここまで来たように見受けられますけども、当の本人はそうでもないところがあってね。どうしても一等賞になれない、っていうのかな。何をやっても先人がやってしまっている。やれ誰それに似てるだの。また、客も一流でしたね。気にくわなきゃ「帰れ!」って野次を飛ばすんだから。確かにレールを敷いてくれたのは団塊の世代だ。僕の精神性というのは、そういう団塊の世代の兄貴分たちと一緒に闘いたかったわけです。それが次第に「なぜ闘わないの!?」って気持ちに変わってくるんですよね、ある時期から。しかも、彼らと近づけば近づく程。
平野:要するに昔はハッパを吸って「ピース、ピース!」って言ってたような奴らが、今は一生懸命ジョギングしたりして健康管理に勤しんでるわけでしょう?(笑) 「自分の身さえ守れれば全てOK!」って。昔は反体制運動を盛んにやってた連中が、今の日本の権力機構の中枢にいるんですよね。そういう世代に対して「お前ら一体今まで何をやってきたんだ!? 少しは自分の青春を思い返せよ!」という苛立ちがあったんでしょうかね?
長渕:本当に、彼らに近づけば近づく程失望していくことのほうが多いなぁ。“なんで一緒に怒らないんだろう!?”と。で、そこから飛び出して独立という道を選んだ。随分と遠回りした。そして今、フォーライフ ミュージックエンタテイメントの後藤由多加[代表取締役]とまた連帯を持って一緒にやろうということになった。果 たしてそれでどこまでやれるのかは判らない。しかし、その昔アンチ芸能だったオピニオン・リーダーの後藤由多加と、男をかけて、共に闘いたいんですよ。こういうことを言うと「生意気だ!」と怒られるかもしれないけど、バブルの崩壊をきっかけに、やれ人員削減だ何だでレコード業界の団塊の世代も、だいぶ勉強したんじゃないかと思うんです。
平野:うまく生きるっていう勉強を?
長渕:いや。バブルが崩壊してからの、“音楽ってものは何だったんだろう?”っていう自分たちの原点をもう一度確認できたということです。“我々が根ざしていたものは手売りでチケットをまいたり、自分の手を使って電信柱にポスターを貼ったりしたことではなかったのか?”というようなことです。
平野:そうだ! うん、その通り! ロックなんて歌謡曲に対するカウンター・カルチャー(対抗文化)なわけで、日本のロックの黎明期には、ロック好きは情報がなくって自分の足で探すしかなかったし、若い連中が好きなバンドのフライヤーを勝手に作って、ライヴハウスの前に列作ってチラシをまく。「私はこのバンドを支持します!」って…素晴らしい時代だった。そうやって日本のロックは大きくなっていったんだ。それまでは、ロックってただ“一部不良の音楽”って言われていたんだよね。それがいつの間にか巨大ビジネスになってメイン・カルチャーになってしまった。
長渕:歌って本来、何だったのか? 自分の言葉で、自分のメロディで、世にケンカをふっかけてきたんじゃなかったのか! 不良が文化を創ってきたという自負心をもう一度奮い立たせる時なんです。古き良き時代を振り返るいいチャンスなんです。凄くいい勉強を今は強いられているのではないかと思うんです。
平野:長渕さんみたいに東京ドームを何日も満杯にできる人が、そんなことを思うんですね。面 白いな。
長渕:東京ドームが満杯になるからこそ、思うんです。
平野:うん、長渕さんはまさにアウフヘーベン(止揚:過去の歴史の良いところはちゃんと残して新しい時代の1ページを作る)しているね。