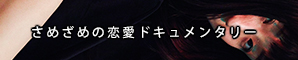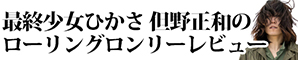今まで25年以上続けてきたこのコラム。最近のロフトグループの躍進とか、香港の問題だとか、書きたいことはたくさんあるのに、また全編を小説にしてしまった。さて、どうなんだろう。テーマは「生と死」なのだが、このか細い男女の成り行きは…続けられるのかどうか不安になってきた。
小説ー6「誰にもやってくる死という常識」
前号までのあらすじ:難病に侵され希望を失った男と、病魔に侵され命の終わりを決めかねていた女は公園で出会い、一夜を共にした。二人は朝まで自分たちの人生を互いに語らっていた。

明け方、オレンジ色の太陽が半島の山々の向こうから上がってきた。私たちは無言で、日が昇ってゆくのを、そして今日という世界の始まりを感じていた。
「ああ、なんていう美しさ。この美しさは生きている。海も地球も素晴らしく美しいわ」と、開けた海の彼方に目をやって彼女はつぶやいた。
「人は生きることが海です。薄っぺらな生命礼賛は私たちに必要がない。昨夜に言ったかもしれないけど、私はこの江ノ島の海で自分の人生に区切りをつけて終わるつもりだったのです。死の恐怖に打ち勝てるほど、海はとてつもなく幻想的で好きです」遠くの海を見ながら意味もなく、だが力強く言う。
私たちは黙想し、そして語り始める。私はただ海を眺めていた。
「治る見込みのない血液の病気を持った自分の体は、近い将来壊れる。そして、自分は死ぬ。いずれ皆、死に至るんだということを私たちは知っている。でも多くの人はそれに気がつかないふりをして生きている。ジタバタしようが死ぬときは死ぬ」
「そうね、ただ、ずっとくよくよしていたらもったいないなって。だったら、状況が良くなる方を選びたい。死ぬまでは生き方を選ぶことができると思うの」
「人生はおもちゃだ、と大自然の海は言う。なぜ人は死を恐れるのか、死は観念の中にしかない。余命を告げられたら暗い気持ちにはなるし、落ち込む。起きたら全部夢だったってことにならないかなぁって思ったり。目の前にある『死』の問題は答えが出ない。答えが出ないものをあれこれ考えても意味がないはずだ」
「余命を医者から宣告された時、一瞬絶望してのたうち回ったわ。そして傷つくだけ傷ついたわ。みんなから優しくされればされるほど」
「私は思うのです。どこまで考えても死なんてものはない。たとえ肉体が滅びても、それを誰が死と言えるのだろうか。それは言葉だけだと知るだけだ。もう私には死の恐怖はない。自分が死ぬ、生まれてから死ぬまで生きているという、まるで理由のない行為を、日々僕たち人間は強いられてきたわけだ。望んで生まれてきたわけでもないに、ひたすら死へと追いやられる。苦しみを背負って……生命は有限であるからこそ価値がある。生命が無限になると、その価値はなくなってしまう。生命に執着することは、生命が有限である限り不幸にするということだと思う」
こんな重い話を真剣に語り合うのは初めてだった。どこか私は興奮していた。
「きっと私たちは運が悪かったのよね。なぜ私なのって。医者から肺がんと半年の余命を宣告された時、一番最初に思ったことがこれだったの」
「私は自らの死を垣間見てから、果てしない孤独と戦ってきた。45歳でこの病気になって20年、この苦しみは一生続くのかと思ったらなかなか生きる希望は出てこない」
「あなたの言うことが少しわかってきたわ。生命に執着することは、生命が有限である限り人を不幸にする……ということね」
「すごく正解なことを言いましたね。私たちがこの世に生まれた時も、やはり信じられないほど何十億分の一の確率で幸運だったと思うと、その死の悲しみは救われている。同時に今生きていることが幸運だったと気づいていても、生きている方が必ず幸せだったということにはならない」
「私たちは、『生きている方が良いとは言えなくなっている時』を迎えているわけね」
「運命はそう決めたんです。何か身体を超越するものがあると思っても、私たち人間には肉体は滅びても魂がある。その魂の存在を前提にすれば、私たちには永遠に生き続ける可能性があると思う」
こんな風に、朝まで私たちの「生と死」についての哲学論争が続いた。
久しぶりに浴びた7月の朝の太陽は眩しかった。私たちは新しい日差しの中にゆっくり移動してゆく。朝方、彼女は青木夏子と自己紹介をした。江ノ島のシティホテルに食堂はなく、私たちは朝早く新宿に向かってロマンスカーを使った。列車は町田を過ぎるとノートPCを開くサラリーマンばかりになった。
彼女は新宿の高級ホテルの上階に住んでいた。1日いくらするかもわからないが、それなりに部屋は素晴らしかった。彼女がどのくらいの資産を持っているかは聞く気にならなかった。その資産を自分が死ぬまでに全部使い切りたいと彼女は言う。ビルを売ったお金か……一体、何億持っているんだろうと想像したが、そんなことを詮索しても仕方がないのですぐにやめた。
私だって死ぬまでに自分だけで使い切りたいお金を多少は蓄えていると思った。多分、私の方が自分の命を粗末にしない限り、夏子さんより長く生きながらえるはずだ。だからこの孤独でひとりぼっちの彼女の余命が尽きるまで、この人をとことん支え、付き合ってみようと覚悟した。
ホテルの上階から高層ビルが見え、新宿中央公園の緑が映える。美しい夫人たちが薄いスカートをひらひらさせながら通り過ぎてゆくのを眼下に見て、私たちは遅い朝食をした。もちろん彼女の希望通り、カリカリのベーコンエッグと色とりどりのパンだ。洗練された都会のホテルの明るい陽が差し込む食堂で、アメリカンなモーニングとコーヒーは私たちの心を豊かにした。
なぜかこの朝食の瞬間、私はこの女性に恋をしたようだ。夏子さんの命が尽きるまで、あと半年。私は彼女とどう付き合えるか、とことん付き合えるのか、夢想した。
「私たちにはこれから一緒にやらねばならないことが出来たものね。私たちには時間がないの。無理に長く生きたくはないけど、成り行きに従って生きて死んでゆくのは幸せだと思う」
彼女は、どこか吹っ切れたように淡々とした感じがあった。
「あなたにいろいろなしがらみがなければ、ここに住んでもいいのよ。私がね、ここに住んでいるって誰も知らないの」
突然、彼女は無造作に言った。