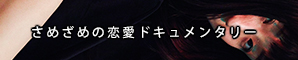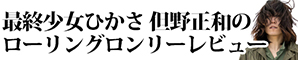いやはや、コロナ騒動のおかげで、ロフトの公演中止が相次いでいる。ロフト経理部にはこのままでは半年ぐらいしか会社は持ちません……と言われるなか、私は会社で陣頭指揮を執ることもせず、政府の言う通りに自宅に籠って音楽を聴いたり、本を読んだり、原稿を書いたり、酒を飲んだりしている。
来年は私がロフトの看板を掲げて半世紀(50年)だ。その時には正式にロフトからは「引退」したと思っている自分がいる。もう50年もやったからいいだろうと……。
連載小説『命』PART13 コリアンタウンのレストランで
喧騒に包まれたコリアンタウンの韓国家庭料理の店の窓外では、いつの間にか粉雪が空に舞っていた。私は緊張していたが、Hさんと話しているのが心地好かった。こちらの話していることがよく通じ、Hさんの30年も前の思い出話も私には新しい発見がたくさんあり、とても貴重で楽しい時間だった。
韓国レストランの奥には不似合いなサキソホンが飾ってあった。店内は焼肉の煙とニンニクの匂いでいっぱいだ。テレビ画面にはイケメンのK─POPの軽妙な音楽が流れていた。
Hさんはマッコリを片手に淡々と語り始めた。私たちは一番奥の木の椅子に座っていて、喧騒のなか柔らかい時間の流れを感じていた。
「そうだな、夏子さんに関して一番思い出深いのは、彼女の最後の新宿ロフトでのライブの日だったな。あれは今日みたいに寒く北風が吹きすさび、乾燥した淡い陽が差す1日だった。『そうか、夏子さんは今夜が新宿ロフト最後のライブなのか?』と思った。これで私は夏子さんの最初のステージと10年後の最後のステージに立ち会えるわけだと思ったが、私にとってはそれほどの感激はなかったんだな。夕刻、ロフトで行なわれていたリハーサルに顔を出してみた。当時、夏子さんはマネージャーのMさんと結婚していたのかどうかわからないが、なんだかMさんは私と夏子さんがリハーサルの合間にお茶することを嫌っていた。だからこの数年、彼女と会話することもほとんどなくなっていた。私が店に入ると夏子さんはリハーサルの最中だったがバンド演奏を突然止めて、みんなの注目のなかマイクスタンドをど〜んと倒して『Hさ〜ん!』と叫んでステージを降りて、私のほうへ走り寄ってきたんだ。あれにはびっくりしたね。
『Hさん、私ね……』と夏子さんは私に何か言いかけたが、その言葉はしまわれた。
『そうか、ワラシ(私たちが呼んでいた彼女の愛称)元気だったか。無理して話さなくてもいいよ。今までよく頑張ってきたよね。もう気が済んだんだね』と私は優しく声をかけた。
『はい、私は今日で歌手をやめることにしたんです。この10年、いろいろとお世話になりました。本当にありがとうございます。Hさんには感謝しています』と言ってステージに戻っていったんだ」
「最後のライブは成功したんでしょうか。どんな感じだったのでしょうか」
「最後の頃の夏子さんは圧倒的なお客さんの動員はなかったな。すなわちブレイクはしなかったんだと思う。150人ぐらいだったか。相変わらずお客さんは貧相なメンヘラみたいな、どこか社会を斜めで見ているような、長い髪とボロボロのジーパンと小脇に単行本を抱える青年が多かったな。みんなほとんど一人でやって来る。だからインターバルの時間も会場内はお葬式のようにシーンとしていたな。そこにあのテレビドラマ『高校教師』の脚本家だった野島伸司さんがお客として来ていたというのは後から聞いた話だ。
演奏が終わって彼女のアルバムのサイン会が開かれるんだけど、ほとんどの客はアルバムを買って、彼女が丁寧に一人一人にメッセージとサインをしていくのが2時間以上かかるんだ。そのセレモニーが終わるのを待つのがしんどくなって、私は挨拶もせずに現場を去った。あれから30余年。私は夏子さんの消息を全く知らないでいたんだ。いや、探してはいけないと思っていたのかもしれない。夏子さんは悲しいことを唄っている。もっと複雑な気持ちを汲み取ってあげなきゃいけないと思った。だけど結局、私は彼女には何も聞けずに終わったと言うのかな。……そう、言おうとして言えなかった」
Hさんの長い語りの言葉が突然フェイドアウトし、無造作にしまわれた。

「そうですか、今日は本当にありがとうございます。多分Hさんしか知らないとても貴重な話を聞かせてもらいました。私も夏子さんを口説きますから、ぜひ彼女と会ってほしいのです。それで彼女の最後のライブをロフトでできたら感動ものですから」
「なんとも長いこと話し込んでしまったな。だが私の興味本位の意識で夏子さんに会いに行って良いのだろうか?」
「夏子さんの最後のライブに力を貸してください」
「そんなに上手くいくとは思えないな。多分無茶な話だろう。でも彼女が最後に望んでいるライブだったら協力は惜しまないよ。私は今でも夏子さんに聞いてみたいことがたくさんある。一番の興味は夏子さんが愛し、彼女が唄い出すきっかけとなったであろう、50年前に自殺したという中核派の国大生だったOさんとの関係だ。夏子さんの歌の原点はそこから始まっているような気がする」
「えっ、Hさんは夏子さんの高校生の頃の恋人を知っておられるんですか?」
「私と党派は違うけど、Oさんは私と同世代の全共闘だった。彼の自殺は衝撃だった。後にOさんの遺族が日記を公開しているのを読んで、彼が夏子さんの恋人だったとはあまり自信がないけど、夏子さんと同じA高校に出身だし、まさに時期は同じだと思う……」
「いろいろありがとうございました。私はこれからまた夏子さんのホテルに行きます。今日のことを彼女に全部話しますが、ひょっとしたらHさんとは会いたくないと言う可能性もあります。その時は許してください」と私は言い、次の言葉が見つからないでいた。
「それは問題ないよ。夏子さんとあなた。私はあなたのほうをどこか心配している。あなたからはまだこれからそれなりに長く生きていく覚悟が見えないんだ。そういった生きるオーラがあなたから見えないんだ。それが痛いほどわかるんだ。これからも生きるという意味を見出してほしい……」
「私は今、生きる希望を持ちつつあるんです。大丈夫ですよ」
「それは、夏子さんが生き続けている時間の流れの中にあるだけで、夏子さんがいなくなったらおそらく君も消えようと考えているんだろう。そういった気持ちもよくわかるが……これから死んでゆく者にとって音楽も文学も思想も哲学ももはや無意味だ。何を慌てている……」
そう言いながらHさんは伝票を持って立ち上がった。「大きなお世話か……」 Hさんはそんな消え入るような独り言を言った。
まさか私の命の問題をHさんから指摘されるとは思ってもいなかった。
だが、私の今日のこの行動が良かったのか、「彼女の命はあと4カ月……彼女は今、消えかかっている命の炎と戦っているのだ」と思ったら一刻も早く彼女のそばに行きたかった。
店を出ると粉雪はもうおさまっていた。もうすぐ冬は終わる。けっこう遅くなった。時間は午後9時を回っている。私は見知らぬ街を歩いている気分になった。夏子さんのホテルが歌舞伎町からも見えた。私は急ぐ。早足で。彼女のもとへ。