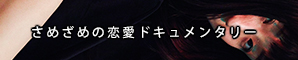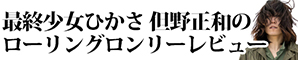インド洋上のピースボート、サンセット
新しい年が始まった。年老いた私は、今年こそは長年育んできた「ロフト」を引退して会社は若手に任せて、悠々自適な隠遁生活に入るためにいろいろ考えてきた。
そもそも自分が27歳の時、つまり45年前に打ち立てた会社だ。もう会社存立から40数年も経って「老舗」として存続しているというのも不思議だ。今ではそれなりの中小企業となっている。
オーナー会長には定年がない
苦労して会社の経営を安定させ事業を拡大してきたオーナー会長に、必ず訪れる大きな課題がある。それは自身の会社の辞め時だ。確かに経営者は、働こうと思えばいつまでも働くことはできる。しかし「自分自身をクビにはできない」という悩みがある。
昨年も一昨年も会社の第一線で活動しただろうかと思い返すと、ほとんど何もしていない自分がいる。会社の広告塔だといっても、出勤をしてもあまりすることがない。では、また新しい事業をおっぱじめるかと思っても、もうそんな気力はほとんどない。ただただ会社で偉そうな顔をしているだけの自分を見てしまう。
昨年、第一線の仕事からはずれた私は有り余る時間があった。だから存分にデモ(社会運動)も旅もできたし、ジムのエクササイズをし、本も映画も芝居もたくさん見て、毎週末、東京の郊外の武蔵野をたくさん歩いた。会社では若い世代がすくすくと育ってきている。もう私は会社で必要がない存在なのだと思うことしきりなのだ。勿論、自分がまさかの時もじっくり考えていきたいと思っている。すなわち歳をとるというのは、そういうことなのだ。
習い事をたくさんする〜新年考えたこと
さて、会社も退職状態なので、有り余る時間をどう過ごそうかと考えてみた。そこで導き出した結論は、今までやり損ねた中途半端な物事をなんとか納得できるまで高めてみたいと思った。今年は週5回の習い事をしようと思っている。
週2日のジム通いは健康のために必要だ。語学も囲碁も社交ダンスも油絵も、ほとんど中途半端に終わってしまっているのがどこか悔しいのだ。かつては、英語とスペイン語の勉強にはやたら時間を使った。(頭の悪い私は語学の勉強に相当な時間を割いた)特にスペイン語は、5年も住んでいたカリブ海の島
で事業を立ち上げるために、毎日家庭教師を雇って勉強をしていた。それから日本に戻ってきて30年、もう英語もスペイン語もメレンゲのダンスもほとんど忘れてしまっているのが悔しい。あの忙しい最中に使った膨大な勉強時間を無駄にしたくないと思っている。確かに今さら英語やスペイン語を勉強しても、日本にいてはほとんど使う時がないが、やはり人生でやり残したことのひとつなのだ。この歳になると単語のひとつも覚えられないのが悔しい。
歳をとると男には楽しいことは何もない
私も70歳になった。仕事も引退して悠々自適の生活に入り……そんな時、好きな人がいなければ人生は生きるに値しないということに気がついた。
「妻と子供を愛しているならそれで充分じゃないか」
誰だって自分を支えてくれる愛情が必要だ。それを配偶者が支えてくれるのだろうか?
不倫は罪悪なのか?
私は浮気性だ〜平和な感じがすると刺激が欲しくなる
結婚したら死ぬまで相手に尽くし、他の異性には目もくれず、最後は家族に見守られて死ぬのが理想か……しかしだ、永遠の愛というものはなかなか手に入らない。
我々が常識と思っている愛の形はもしかして例外なのかもしれない。さらには愛情もないのに離婚ができず、辛い思いをしながら一生を生きる。
愛情がなくなったら別れる、好きになったらその人と付き合いたい。これは自然だ。
もともと人間は生きている限り人を愛するようにできているわけで、一人を選んだら死ぬまで他の相手を拒絶しなければならないという方が不自然なのだ。
ピースボート世界一周での一コマ
6月のインド洋の船上デッキにて。
海の色に溶け込んだブルーのワンピースは、6月の淡い陽を浴びて、身震いするほど綺麗だった。
「何でもないのに涙が出るほど綺麗です。」
インド洋に沈んでゆく真っ赤な夕焼けに照らされている彼女に、私は独り言のようにそう言って、小さく笑った。しばらくして彼女は満面の笑みを浮かべありがとうと言った。
「私だって誰かと口をききたなります」と、彼女は少し驚くように私の顔を見た。
「親だったり亭主だったり家族の世話だったり、少しは自分の時間が欲しいの。このぶんだといずれボケがくる」としょんぼり海に目をやる。
「あがいているんですね。みんなじたばたしている。甘いことなんかないって、もうこれから歳をとっていくしかないって、じたばたしている。趣味なんて持ってもどうにもならない。生きていればいろんなことがあるのだが……」私は唐突に今の自分の気持ちを言った。
しばらく私たちは黙ったまま、それぞれの飲み物を飲んだ。
「甘さとか異性の優しさに飢えている。これから先は人生の検討も大方ついている。まだ若さがなくなってしまった訳ではない。ただ、男と女の色めいたこともそろそろ限界なのかもしれない。だからあがいている。」私の力のない言葉が、切なく海の彼方に飛んでゆく。
もうコーヒーは冷めていたが、冷たい苦さが心地良かった。
「あの時、突然胸がキューンとなってどうしていいかわからなくなった。人を好きになるなんてそんなことじゃないですか? 私も、もう若くはない。急にその気になった。」
「急じゃない。心の隅でず〜っとこうしたかったの。」と、彼女は遠くの雨雲を見ながら呟いた。私は彼女に恋をしているのだと強く感じた。