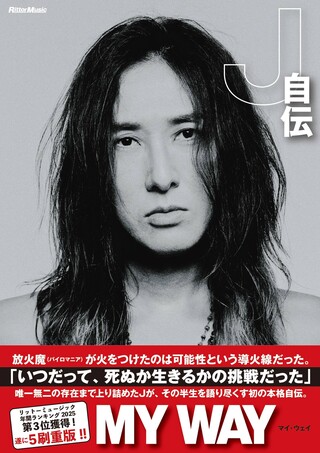PANTAの頭の中を想像しながらアルバムを聴いてほしい
──慶一さんが完成させたこのアルバムをPANTAさんが聴いたら、何と言うと思いますか。
鈴木:「なんだよ、俺の歌が5曲しか入ってないじゃないか」と怒られるかもしれないな(笑)。あるいは「この歌詞は迷っていたところだから入れなくても良かったんじゃない?」とかさ。でもそれはしょうがないよね。私はPANTAが書いたものを全部入れたかったんだから。
田原:「慶一はとにかくいっぱい詰め込もうとするんだよ」とPANTAは話していましたね。レコーディングの帰りの車で「いろんなものを入れちゃってさ」と言っていましたけど、それがまるで子どもみたいな話しぶりだったので本人は凄く嬉しかったと思うんです。自分のジャッジだとどんどん削る一方だから、慶一さんに委ねられることが楽しかったんじゃないですかね。
鈴木:前半はふたりで相談しながら歌入れを進めていたけど、後半はそれができないのが辛かった。あと、一度だけPANTAが怒ったことがあったな。録音の作業を私がとんとん進めていたら、「いま何をやっているのか教えてくれよ!」と言われたことがあった(笑)。「あ、ごめんごめん。ベースを弾いてよ」ととりなしたけど。
田原:慶一さんとのやり取りは打てば響くので、PANTAは嬉しくて仕方なかったんです。慶一さんはPANTAの博識にもちゃんとついていけるし、今回の慶一さんとのスタジオワークはお互いの宝箱や隠し箱を出し合えて、それが嬉しくてしょうがないみたいな感じでしたね。そんなやり取りをスタジオでできて、PANTAは幸せだったと思います。
鈴木:「エルザ」でふたりで同時にギターを弾いたんだよ。それがテイク1かテイク2でOK。それ自体、生まれて初めてのことで異例だったけど、ふたりでソファーに座りながら弾くのも異例だった。あれは楽しかったね。まさにこのアルバムのジャケットみたいな感じ。PANTAが左利きだから隣同士で座れるわけだ。それもライン録音だから「それいいぞ!」とか無邪気に話しながら弾いてさ。
田原:その録音の帰りに「慶一と一緒にポール(・マッカートニー)とジョン(・レノン)をやっちゃったな」と凄く嬉しそうに話していましたからね。
──ああ、互いのギターが左右対称になる感じで。とにかくどの楽曲も素晴らしいので、ぜひ今後のライブでも披露してほしいところですが。
鈴木:それはね、録音しているときに1日に1回は必ずPANTAが言っていた。「これをライブでどうやろうか?」って。コンピュータを駆使して密室で作った音楽だからどうするんだ? とライブのことをずっと気にしていたし、PANTAとしては私と一緒にライブでやるものだと当たり前のように考えていた。それができないのはとても残念だね。このアルバムの曲を一緒にステージでやれたら本当に楽しかっただろうなと思うよ。
──こんな形で盟友の思いを継いで作品を完成させるケースは、慶一さんのキャリアにおいて二度とないかもしれませんね。
鈴木:そうだろうね。こんなプレッシャーの中で音楽を作り上げることはもうないと思う。ただそのプレッシャーは落ち込むような類のものではないんだ。PANTAが残した歌詞をどう当てはめていくかということも含めてどうにか完成させなくちゃいけないという、とても励みになるプレッシャーだったから。出来の良し悪しは自分でもまだよくわからないけど、プロデューサー的立場でありながらお互い五分と五分のユニットでもあるという貴重な経験をさせてもらった意味でPANTAにはとても感謝している。最後にPANTAと話したのは、亡くなる1週間前くらいだったかな。電話がかかってきて、「あのさ、小坂忠さんと渋谷の街をクルージングして、カラオケに行ったことがあったよね? あのとき忠さんは何を唄ったっけ?」と訊いてきた(笑)。ジュディ・ガーランドの「オーバー・ザ・レインボー」だよと答えたけど。
──本作にも「虹のかなたに」という物憂げで深い余韻を残す同名のオリジナル曲があるし、できすぎた話ですね。
鈴木:そうなんだよ。しかも虹の色は今日、LGBTの尊厳と社会運動のシンボルとしてフラッグにも使われている。そういう未来を見据えた視点や謎解きがこのアルバムにはいっぱいあるんだ。その謎解きは晩年のPANTAの頭の中を覗き見ることでもあるし、歌詞という虚構の世界にこそ何らかの真実が込められているのかもしれない。そういう作品を何とか作り終えることができて今は安堵しているし、本当に良かったと思っている。私がPANTAの頭の中を想像しながらこのアルバムを完成させたように、聴いてくださる皆さんもPANTAの思いを想像しながら聴いてもらえると嬉しいね。