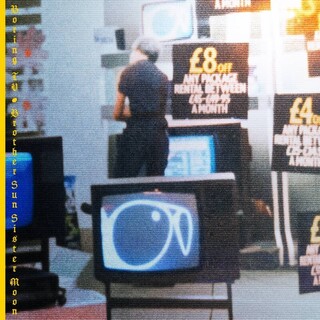今年、結成55周年を迎える頭脳警察が、通算12作目の最新作にして最後のオリジナル・アルバム『東京オオカミ』をPANTAの誕生日である2月5日にリリースした。メンバーもスタッフも、おそらくはPANTA自身もこれが遺作となる覚悟で制作に臨んだであろう本作は、前作『乱破』の発表以降に生まれた「絶景かな」を始めとする新曲、バンドに新たな息吹をもたらした若手メンバーが手がけた楽曲、キノコホテルのマリアンヌ東雲によるモノローグが映える水族館劇場・桃山邑の作詞曲、PANTAのキャリア史上最も物議を醸したソロ作品『KISS』から42年を経て完成した橋本治へのラブソングなど、精選された全12曲を収録。すでに4年ものあいだ活動を共にしてきたメンバーの一体感、アンサンブルの妙味、至高のグルーヴに支えられ、PANTAの歌声は病魔に冒されていたとはとても思えぬほど実に溌剌として瑞々しく、これぞ日本屈指のロック屋の面目躍如と言わんばかりに硬軟織り交ぜた楽曲群を変幻自在に歌唱している。2021年8月に肺癌のステージ4と余命1年を宣告されたPANTAが懸命な治療の甲斐もあり1年を乗り越え、小康を得た時期に集中してレコーディング作業と対峙、紆余曲折を経て完成に漕ぎ着けたという『東京オオカミ』。その制作過程でPANTAは何を思い、どんな構想を抱いて渾身のスワンソングを紡いでいったのか。唯一のオリジナル・メンバーであるTOSHIこと石塚俊明、50周年メンバーの澤竜次と宮田岳、本作のレコーディング・プロデューサーを務めたアキマツネオ、そしてPANTAの最期を見送る覚悟を決めて奔走し続けたマネージャーの田原章雄に、今だからこそ明かされるエピソードの数々を語り合ってもらった。(interview:椎名宗之)
頭脳警察の活動継続を決心した意図
──先日、TOSHIさんが夕刊フジの取材に応えて「頭脳警察は続きます」とバンドの継続への思いを告げられました。昨年9月1日に行なわれたPANTAさんのお別れ会・ライブ葬のときは頭脳警察の看板はいったん降ろすと話していましたが、どんな心境の変化があったのでしょうか。
TOSHI:マネジメントの田原氏と話していて、PANTAの一周忌もスケジュールとして入っていることだし、やっぱり続けていこうかなと。具体的にどんな形で継続するかのイメージは今のところ全然ないんだけど、今のメンバーとはこの先もずっと付き合っていきたいという思いが個人的にもあるので。その辺りの話は、田原氏やメンバーとの対話の中で今後具体的になっていくのかなと思ってる。
──PANTAさんが旅立たれて半年が過ぎましたが、今はどんなお気持ちですか。
澤:長いこと会ってないなという感覚ですね。頭脳警察のレコーディングで1カ月会う機会があった後はPANTAさんの治療期間が何カ月かあって久しぶりに会うという感じだったので、いまだにその感覚が抜けないと言うか。毎月頻繁に会うのではなく、会うときは集中して会うみたいな。それと、今の世界情勢や社会のニュースを見るたびにPANTAさんと話してみたいなと思うことが多々あります。だけどもうそんな話もできないんだな、一緒にスタジオへ入れないんだなと、いろんなニュースを見るたびに実感しますね。
宮田:僕も似たような感じです。洗濯物を干しているときにふと思い出したりとか。もういないんだなと言うよりは、今ごろどうしているんだろう? と思ったり。
アキマ:つい最近まで『東京オオカミ』の作業をしてずっと聴いていて、PANTAはそのアルバムの中で生き生きとした姿で実在しているわけですよね。だから亡くなってしまったことを頭では理解しているけど、実感があまり湧かない。PANTAが夢に出てきたことはありますけどね。しょっちゅう会ってる体で「よう!」って来るんだけど、夢だから会話が噛み合わないんです。PANTAが凄く真剣な表情で何かを喋っているんだけど全然聞き取れないし、「何を食べてるの?」と聞いても駄洒落みたいな受け答えだし。人に伝わらないような駄洒落をよく話していたじゃないですか、自分だけ大喜びするような(笑)。
──TOSHIさんは、PANTAさんが夢に現れたりすることは…?
TOSHI:何度か見たよ。凄く元気だった。
──このたびリリースされた『東京オオカミ』ですが、アルバムを残しておきたいというPANTAさんの意向が制作の発端だったんですか。
TOSHI:その経緯については、田原さんに……。
田原:最後にみんなでアルバムを作ろうと、自然発生的に動いた感じでした。結成50周年を記念して発表した『乱破』で終わりではないという認識が共通してあったし、新曲もできていましたし。2021年8月にPANTAさんが余命1年と宣告され、そこから未来を見据える上でも新たなアルバムを作ることがミュージシャンとして自然なモチベーションであったと思います。新曲を作る、ライブをやり続けることが未来へ繋げる行為でしたし、実際、2024年2月4日までライブハウスのスケジュールを押さえていました。PANTAさんが存命なら、そこまできっちりライブをやる予定でいましたから。
──制作期間はいつ頃だったのでしょう?
田原:PANTAさんが退院した2022年の9月から11月頃までに全部を録りきりました。余命1年を乗りきり、そのときの治療が上手くいって元気になったので、取れる限りのスケジュールを取ってレコーディングに集中したんです。最初に「東京オオカミ」のテーマが生まれて、そこから一気に録っていきました。
歴史に復讐する象徴的存在としてのオオカミ
──「東京オオカミ」の作詞は、PANTAさんと田原さんの共作という珍しいケースですね。
田原:2人で随分と話し込んで資料を集めたり、一緒に東京中の神社を探し歩いてオオカミの像を見つけたりしました。僕が生まれたとき、家の門に赤い犬と白い犬が住み着いて、1カ月くらいいたんです。自分が生まれたときに突然いなくなったんですけど。その話をPANTAさんにしたら、「田原、それは犬じゃなくてオオカミだよ」と。ニホンオオカミは明治時代に絶滅しているし、そもそもオオカミが東京にいるわけがないのに、PANTAさんは「いや、オオカミに違いない!」と譲らない(笑)。それが「東京オオカミ」のテーマが生まれたそもそものきっかけなんです。東京にオオカミがいるんじゃないかという妄想から始まり、最初の寛解の後にTOSHIさんの個展とライブ(『とし+とめ展』)に行きたいとPANTAさんが言い出して。それでTOSHIさんが個展を開催していた高崎のギャラリーまで同行したんですが、その道中で食事をしたお蕎麦屋さんが、日本にオオカミはまだ生存しているんじゃないか? と考える猟師さんたちの集い場みたいな店だったんです。その店の壁一面にオオカミの写真や絵が貼られてあって、オオカミの資料も豊富に置いてあったんですね。そこでPANTAさんの中で一つの物語が出来上がり、「東京オオカミ」の創作へと繋がっていったんです。
──PANTAさんとしては、絶滅したオオカミの姿に自身を投影した部分があったのでしょうか。
田原:オオカミは歴史上抹殺された生きものだけれども、実は生きている。その有り様を時代への復讐、歴史への復讐と捉えていたんだと思います。「タンゴ・グラチア」もそうですね。明智光秀の娘である細川ガラシャをテーマにしたのは、石田三成の人質になることを拒み、壮絶な最期を遂げたとされるガラシャへの鎮魂歌でありながら、もしかしたら彼女は生き延びていたのではないか? というテーマもあるんです。それもまた歴史への復讐であると。『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』も死んだはずなのに生きていたというのがテーマとしてありましたが、ああいう作風からの影響もあるでしょうね。史実とは異なる仮説から新たな物語が生まれるというような。
──「東京オオカミ」のエンディングは「銃をとれ!」を彷彿とさせるし、「そう伝説を飛び出せ」という歌詞は「歴史から飛びだせ」を連想します。他にも「絶景かな」のイントロは「世界革命戦争宣言」を意識したようにも感じるし、本作は頭脳警察のセルフオマージュ的要素が随所に盛り込まれていますよね。
田原:「絶景かな」のイントロはおおくぼ(けい)さんのアイディアでしたが、セルフオマージュを散りばめるのはPANTAさんやメンバーの間で固まっていたんでしょうね。
──「タンゴ・グラチア」のような曲が生まれたのは、PANTAさんがマーティン・スコセッシ監督の『沈黙 ─サイレンス─』で隠れキリシタンの集落であるトモギ村の村民役を演じたことが大きかったんでしょうか。
田原:『沈黙 ─サイレンス─』の村長が処刑されるシーンで、PANTAさんの顔がアップになりますよね。そこで呟くように唱えているのが「ぐるりよざ」という、隠れキリシタンの人々が口伝してきたグレゴリオ聖歌なんです。“グロリオサ”(Gloriosa)が訛って“ぐるりよざ”として広まったと言われています。その話をPANTAさんが調べていて、「ぐるりよざ」という曲の存在を竹内(理恵)さんとおおくぼさんが知っていたんです。竹内さんに至ってはその場で吹いて聴かせて、それを「タンゴ・グラチア」のイントロに使っているんです。
──ガラシャが隠棲したのが京丹後市ということでタンゴの曲調にしたというのが面白いですね。
田原:ガラシャの悲劇はヨーロッパにも伝わり、1698年にウィーンのハプスブルク家で『気丈な貴婦人-グラーチア 丹後王国の女王』というイエズス会のオペラが上演されています。それをマリー・アントワネットが子どもの頃に観劇していたんですよね。その戯曲の楽譜が見つかったという話も「タンゴ・グラチア」が生まれた経緯の一つみたいです。PANTAさんに言わせると、「タンゴの語源は丹後に違いない!」と(笑)。そんな妄想からタンゴの曲調になったようですね。