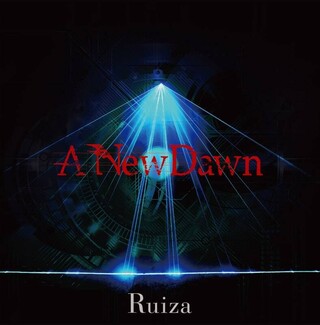何か残さないといけない
――改めて内海賢二さんのお声は意識して聞きましたが、やっぱりいい声なんで楽器みたいなんです。ご出演されているレジェンドのみなさんの声も素晴らしいので、その声をいい音響で聞きたいというのはファン心理としてはあります。
榊原:分かります。音・発声の面でプロはやっぱり違いますね。
内海:僕も予告編を見たときにみんなの音圧から流石プロだなと感じました。楽器とおっしゃられましたが本当にその通りで、それだけ入ってくる声なんだなと感じました。その素晴らしい声を映画館で聞きいてもらいたいですね。
――演じられる役柄によって全然印象が違うので、そこも曲ごとに違ったイメージを感じる楽器のように感じたのだと思います。柴田秀勝さんが「台詞は歌うように。」とおっしゃられていることに繋がっているなと感じました。
榊原:確かにそうですね。
――奥様である野村道子さんをはじめレジェンドのみなさんも元気な姿を映像で観れたのも嬉しいです。
内海:分かります。業界的にもこういったみなさんのインタビューを集めた記録がないんです。TVではあったかもしれないですけど。
――バラエティー的な番組で少しお話しされているくらいですよね。
内海:アニメも歴史を重ねてきている中で黎明期から日本のアニメを支えてくださってきた方々が亡くなられてきている。そんな中で何か残さないといけないということは業界全体としても話していたんです。
榊原:この映画を作る意味についても話し合いました。「記録として残すだけでも凄く価値があるからやりましょう。」と話したのを覚えていますね。
――訃報を聞くまでは、僕より長生きするんじゃないかと思う方ばかりですよね。
榊原:キャラクターは年取らないですからね。羽佐間道夫さんも年齢を感じなかったです。
――声を聞くと作品の画が浮かぶんです。作中でも語られていますが昔のアニメはCGもないしアナログな部分も多く今よりも絵に制限があり、絵も今ほど動かせない中で役者さんの力に支えられている部分がより強くかった。その声・演技の力強さがあるので、人知を超えたキャラクターと役者のみなさんがシンクロするんですよね。
内海:生涯現役でやられるというのは人並みの苦労ではないと思います。やらなければそれだけ衰えてしまいますし、70歳・80歳までとなると健康管理も含めて声帯の訓練もより大切で、父も毎日発声をやっていましたからたゆまぬ努力の賜物です。
――賢プロの分裂など、苦労話を盛り込まれたのは何故ですか。
榊原:賢太郎さんからは「固有名詞さえ出さなければNGはない。」といただいていたんです。内海賢二さんは日本の声優がどのように今に至っているかの時代を生きてきた方なので、本当に深く描くためにはそういった部分もしっかりと描けないと思いました。
内海:独立騒動がなければ僕は賢プロを継いでいなかったですし、僕も母も方々で包み隠さず話しているので、さらけ出すことに抵抗はなかったです。
――声優業界の事件ということではストライキも盛り込んでいますが。
榊原:あの世代の人たちは何故あんなに個性があるのだろうオーラがあるんだろうとなったときに、三間雅文さんもおっしゃられていましたが、賃金が上がったことで淘汰され個性がある人しか生き残れなかったということもあると思うんです。そういう部分も含めて今の業界をつくっているレジェンドがいかに凄いのかということの理解にも繋がると考えて描きました。
――三間さんも「製作費で考えると大変だけど、この人に頼まないと作品としての命を吹き込めない」とおっしゃられていて、まさに通りだなと思いました。今も昔もアニメは絵であることは変わらない、生身の人間ではない分、表情を付ける・周りの風景のリアリティ表現はどうしても限界があります。そこに声優のみなさんが命を吹き込んでくれるので人間味が出て作品に深みがでる、描かれている以上の情報を感じてリアリティが生まれるんだと思います。私も小学生低学年のこときに観ていた『北斗の拳』は現実に起こるんだと思いました。
内海:『北斗の拳』は描写の過激さから再放送が出来なかった作品ですけど、そのころに観ていたんですか(笑)。
――そうなんです。私は小さい頃は、特撮で怪人が出てきたら怖がって隠れていたらしいんです。でも、『北斗の拳』は観れていたんですよ。小さい頃はアニメも実写もどちらも現実のように受け止めていて、境界がないじゃないですか。それでも観れていたということは、ラオウの声を通して内海賢二さんの人間味を感じていたんでしょうね。
内海:そう感じていただけたのであれば、父も喜びます。
――演じている声でもそう感じたくらいで、後輩の面倒見も良い方だと聞いていた内海賢二さんが父親としての接し方に戸惑いがあったというのが意外でした。
内海:劇中で柴田さんがおっしゃられていますが「内海賢二を演じていた。」ということなんでしょうね。あの言葉は凄く刺さりました。社長として、役者として、父親として、使い分けていたということはないんですけど、こうでないといけないという理想があってそれを意識していたのかもしれないです。父は小さい頃に両親を亡くしていて、気を使って生きてきたのが染みついているように思います。僕から見ても気を使っているなと思うところがあって、「そんなに気を使わなくてもよくない。」と言ったこともあるんです。「いや、いいんだよ。」って、「感謝の気持ちを持ち続けないといけない、人に良くしなさい。」とは言われ続けて、それが僕の中にも残っています。だからこそ、沢山の人に愛され、ご出演いただいた皆さんにもご出演を快諾いただけたんだと思います。
――お話しされている皆さんの目がキラキラしていたのが印象的でした。
内海:カメラの前でもそれ以外でもお話しされていることが変わらなくて、自然にお話しいただけました。
――あえて、よく言おうとしていないのがいいですよね。私なんかは後輩を育てることがライバルをつくることになるんじゃないかと思ってしまうこともあるので、内海賢二さんは若くして賢プロを立ち上げて後進を育てられていますから凄い器が大きいなと。
内海:立ち上げたときは個人事務所なので自分のための事務所なんです。なので、母がマネジメントも兼ねて入ってきて、野沢那智さんのマネジメントをしていたりとか、人が増えてきてスタッフがそちらに回ったときは「俺のための事務所じゃないのかよ」とは言っていましたよ。
――それは意外です。
内海:先輩後輩の付き合いと会社の代表とマネジメントするというのは違いますから。賢プロを立ち上げたときはここまで人が増えることを想像もしていなかったです。内海賢二の人徳もあって人が集まってきたこともあって、自分が前に立って人の育成をしなければいけないと意識が変わっていったんだと思います。
――演技指導はどのようことをされていたのですか。
内海:芝居のことで細かいダメ出しをして、演技論を語るということはなかった気がします。それよりは、基礎や人として大事なことを伝えていた印象ですね。
――役者によって演じ方・アプローチの仕方は変わりますからね。求められることも違うとなると、得意なことを伸ばすということの方がいいということなんでしょうね。
内海:そうですね。