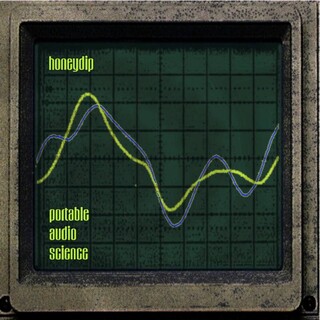良し悪しのジャッジは世代の違う父娘でも同じ
──いわゆる曲先で、KOZZYさんが持ち寄った曲に対してAKIRAさんが詞を書き上げていった感じですか。
AKIRA:それもあったし、曲作りの段階で「こういうテーマで歌詞を書いてみたらどう?」と提案されるケースもありました。
KOZZY:たとえば「“卒業”とかどう?」みたいに僕からお題を出したりね。「アメリカへ行くことになったときに感じたことはどう?」とか。そうするとああだこうだとLINEで返事がくる。
AKIRA:家の中でもLINEなんですよ(笑)。
KOZZY:今の時代ですから(笑)。逆に「ちょっとモータウンっぽい曲調はどう?」と提案すると「それなら“出発”みたいなテーマが合うじゃないかな?」と返ってくることもあった。そんなやり取りの中で一番最初にできたのが「Tokyo Girl」だったのかな。
AKIRA:そうですね。まさにちょっとモータウンっぽい感じで。
KOZZY:AKIRAから出してくるテーマや「こういうタイトルはどう?」みたいなアイディアが幅広かったので、プロデューサーとしてはそこを上手く汲み取ってあげたかった。僕自身はいまルーツ・ミュージックやロックンロールといった古い音楽を主体にやってるけど、こう見えていろんな音楽を知らないわけじゃないし、AKIRAの好きなコンテンポラリーな音楽にアイディアを寄せてみること自体はすごく楽しかった。「ちょっとここはラップっぽく歌を入れてみようか?」とか、今風のリズムトラックを作ったりとかね。
──おっしゃる通り「Remember Me to Myself」や「The Night in the Valley」には打ち込みのリズムが部分的に使われているし、ロックスヴィル・スタジオ・ワンでのレコーディングとしては珍しいケースですよね。
KOZZY:ここ最近は使ってないけど、打ち込みに関してはわりといち早くやってたんだよ。今だと全然普通だけど、Macを使ってリズムのシーケンサーを走らせたりとか。あれはコルツを始めようとしていた1990年くらいなのかな。それで言えばAKIRAが生まれたのは1995年、物心がつくのは2000年以降になるわけで、その時代の音楽が彼女のベーシックにあるんだよね。そういうAKIRAの資質と僕の持ち味を合わせてみたらどうなるんだろう? という興味もあったし、いざやってみたら面白い曲がどんどんできてきたのでこれはいい感じの作品になりそうだと思った。だから無理に古い音楽のほうへ引っ張るんじゃなく、かと言って世の中的に新しい音楽に合わせるのでもなく、それぞれのいい部分を自然に出せたと思う。
──たとえば「The Night in the Valley」はビートルズっぽいニュアンスをメロディから感じますが、音の装飾は今日的だと思うんです。だからロックスヴィル・スタジオ・ワンとしてはだいぶ新たな試みが為されたのではないかと思って。
KOZZY:まあ、新しいと言っても最先端の音楽制作に携わる人が聴いてどう感じるかは分からないけど、僕らの中ではかなり新しいアプローチかもしれないね。でもそれもAKIRAにとっては自然なアプローチなんだと思う。そういうAKIRAのナチュラルな持ち味を今回は活かしたかった。たとえば「The Night in the Valley」で言うと、僕が曲調に合うマイナーな進行を弾いていたらAKIRAが勝手にメロディを付けて唄ってきたんだよ。じゃあそれに合うような歌詞を書いてくれと言えばいい感じのものが出てくるし、それで自ずと進むべき方向性が決まる。そういうやり取りが多かったね。
──このロックスヴィル・スタジオ・ワンへ入ってくるとき、出入口に年季の入ったタイプライターが置いてありましたが、あれは「Remember Me to Myself」の冒頭で使われたものですか。
KOZZY:そう、あのタイピング音を入れた。「このタイプライターで昔の自分に手紙を書くとしたらどんなことを書く?」ってお題をAKIRAに出してね。
AKIRA:今はあまり使われない表現で、「Remember Me to ×××」で「×××によろしく」って意味があるんですよ。だから「Remember Me to Myself」は“今の私から過去の自分へどうぞよろしく伝えてほしい”という歌なんです。昔の自分にメッセージを送るなら? というお題で書いた歌詞で、今の私の視点で当時の自分を思い出しながらメッセージを贈った感じです。
──歌詞を推敲する作業は順調でしたか?
AKIRA:サラッと書けたものもあるし、けっこう悩んだものもあるし、もともとあったものを活かしたのもあれば新しく書いたのもあります。英語もそうですけど、日本語の言葉選びは特に悩むことが多くて。「The Night in the Valley」の頭に“喚(わめ)くサイレン”という歌詞がありますけど、最初は“喚く”じゃなくて、そこに入る3文字くらいのいい日本語がないか探していたんです。そういうところでKOZZYさんからすごくアドバイスをもらいましたね。
KOZZY:英語だと“鳴る”=“sound”くらいの表現しかないんだろうけど、日本語なら“鳴る”の代わりに“響く”とか“轟く”とかいろいろあるでしょ? 僕が「英語だとここは何て言うの?」と訊くこともあるし、森山さんからAKIRAに「これは英語だと何て言うの?」ってLINEで来るときもあるんだけど、それと同じようにAKIRAから「日本語でこれは何て言うの?」と訊かれることも多くてね。経験上、彼女は多感な時期をアメリカで過ごしたから日本語のいろんな種類の言い方が分からないのは仕方ないし、それが逆に面白いところでもある。英語にも何種類も言い表せる言葉はあるし、そうじゃないのもあるけどね。そんな言葉のキャッチボールを経てメロディに合う言葉を見つけ出して、実際に唄ってもらって良い着地点にたどり着くようにするわけだけど、その良し悪しの判断がAKIRAも僕も結果的に同じなんだよね。そこに世代の違いも音楽的嗜好の古いも新しいもない。「あ、今の良かった。上手くハマったね」っていう感覚は全く同じで、共通項がちゃんとあるんだなと実感した。そこで僕が影響を受けたオーセンティックなロックに寄せるわけでもなく、ジャッジはあくまでAKIRA次第というか。「Remember Me to Myself」で「過去の自分にタイプライターを打つならどんな感じ?」というお題を出して、尚且つ最初はポツポツと語るような唄い方にしてほしいと難しいリクエストをしたんだけど、AKIRAはAKIRAなりの表現でしっかり応えていたと思う。それが今回のアルバムの象徴でもあるよね。古いタイプライターを使って新しい世代の女の子が昔の自分にメッセージを伝える、そんなテーマの歌をヴィンテージの機材でレコーディングするっていうのは“古いもの=僕”と“新しいもの=AKIRA”が融合するわけだから。それが2人の表現できる最たるものというか。まあ、いろいろ試行錯誤はしたけどね。唄い回しとか細い部分は任せたけど、そういう感じならキーをもう少し下げようとか何度か変えたりもしたし。「Remember Me to Myself」はそういうトライ&エラーの果てにああいうルースな感じになった。