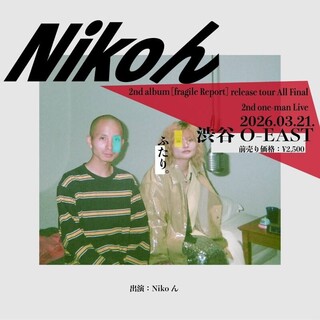ギタリストに中川暁生が加入し、ドラムスに大地大介が戻った編成で、傑作アルバム『ヘイセイムク』を完成させたのが2012年のこと。あれから9年の歳月を経て、ついにBEYONDSが新作『Serpentine』をリリースした。コロナ禍の影響もあり、フィジカルは2曲入りの7インチ+ダウンロード・コードで全4曲を収録という形になったが、BEYONDSでしかありえない強固な個性は微塵も揺らぐことなく、聴き応え充分な内容だ。
以下のインタビューを読めばわかる通り、9年の間にはバンドとしての波もあったようで、それでもメンバー4人の顔ぶれは変わらないまま、しっかりじっくりと新たな音を模索してきたことも確認できる。
日本のパンク・シーンにおいて特異な存在感を発揮し続ける稀有なバンドの近況を、ボーカルの谷口健から語ってもらった。(interview:鈴木喜之 / photo:菊池茂夫)
活動が失速していたように思われた理由
──前回インタビューさせてもらったのが『ヘイセイムク』のリリース時(2012年3月)ですから、9年ぶりになります。この間には、しばらくBEYONDSの活動が停滞していた時期もあったように感じていて。どうしてそう思ったかというと、2018年12月の江ノ島オッパーラでのライブに、「ひさびさのBEYONDSだ! 嬉しい!」っていう空気がすごくあったからなんです。確か、大地さんも「ドラムを叩くのが久しぶりでしんどい」みたいなことを言ってましたよね(笑)。
谷口:ああ、確かに、そのオッパーラは久しぶりでしたね。あれはそもそも、オッパーラのオーナーが「BEYONDSの、93年に最初のアルバムを出したときに作ったTシャツのシルクスクリーン、まだ手元にありますよ」ってSNSで報告してくれて、そこで「ぜひまた作りたいです」と伝えたら、「わあ嬉しいです、ところでライブもやりませんか?」って提案してもらったことがきっかけだったんですよ。
──で、その後わりとすぐに、ファースト『UNLUCKY』がアナログ盤でリイシューされました。
谷口:それは、オッパーラでのライブとは無関係で、たまたま、そのアルバムを出した当時から僕らのことを担当していた与田太郎さんが、「新しく始めたKilikilivillaというレーベルから、今度はアナログ盤で出さないか?」と言ってくれて実現しました。
──続いて『The World, Changed Into Sunday Afternoon』もリイシューされたので、その時期のBEYONDSには、なんだか復活感というか、リバイバル感みたいな雰囲気が生じたんでしょうかね。
谷口:まあ、そういうことも、自分たちの活動を勇気づけるきっかけを作ってくれたかもしれない。オッパーラ以降、また見に来てくれるようになった人もいて、わりとコンスタントにライブをやるようになったり。だから僕は、すごくオッパーラに感謝してます、本当に。
──ただ、同窓会的なパーティの雰囲気が強かったのはオッパーラだけで、その後のライブでは、ちゃんと「今のBEYONDS」も伝わってきたんですよ。リイシューにあやかって、昔のナンバーを再現して懐かしんでるだけではなくて、ちゃんと『ヘイセイムク』からの延長にあるバンドが現在進行形の形で伝わってきたので、これは新譜も早く聴きたいぞ! と思ったんです。というわけで、今回の『Serpentine』はまさに待望の新作でした。クレジットを見ると、2020年の12月に川崎でレコーディングしたんですね?
谷口:はい。とっても良い個人スタジオをお借りして録りました。『ヘイセイムク』からあまりにも時間が経っているので、溜まっている曲を形にしようっていう機運は、けっこう前からあったんですけど、コロナの影響もあり、メンバーみんな、いっそう仕事や家庭を重視しなければいけない状況になってしまって……。でも、多分そこで「まだ、いいか」なんて言ってたら、この7インチすら出来ていないことになっていたと思うんです。もう、このままズルズルいったらどうにもならないと思ったので、去年の夏くらいから、なんとか7インチ1枚でも絶対に世に出そうよって。それで、4曲だけレコーディングしました。
──そうしてリリースされた『Serpentine』を大喜びで聴いて、興奮するのと同時に「なんだか聴き覚えがある」という感覚を持ったんですね。で、取材のためにBEYONDSの過去の音源を整理してたら、なぜか2012年11月のシェルターでのライブが出てきて。それを確認してみると、すでに「Serpentine」と「Accomplice」が演奏されていたんです。
谷口:そう、やってましたね。つまり、その時期からあった曲なんですよ。もう『ヘイセイムク』は出来上がったんで、どんどん新しい曲をやっていきましょう、っていうアケオくんの気持ちもあったんでしょう。
──中川さんは『ヘイセイムク』レコーディングの直前に入って、収録曲のうち3曲くらいでソングライティングに関わっている、という感じでしたね。ただ、「Serpentine」に関しては、まだこのタイトルになってる言葉を歌う、コーラスのリフレインがついていない状態でした。
谷口:そう! それは、さっきの活動が失速していった理由ともちょっと関係してくるんですけど、そのときに演奏していた、まだ「Serpentine」ではなかったこの曲に、僕自身は「どうなのかな?」と感じていたんです。ある種の行き詰まりというか、そういう気分を象徴するような曲だったんですよ。だから「1回ちょっとバンドを離れて、メンバーそれぞれ1人1人の時間を設けたい」って考えたんですね。そういうのがあったから、止まっていたように思われたのかもしれない。
──ライブで聴いた初期バージョンも、充分にカッコよかったですけどね。
谷口:ホントですか? だけど当時の自分としては全然……まあ、fOULのときにもそういうことはありましたし、ずーっと活動を続けていれば、誰かはノリノリでも、他の誰かはそうでもない、みたいなことは必ず起きてくる話ですけどね。
──「Serpentine」というタイトルがついたのは、いつ頃のタイミングだったんですか?
谷口:1年くらい前ですかね。
──では、その段階で、タイトルを繰り返すボーカル・パートとか、後半の朗読といった要素が加わっていったんですね。
谷口:そうです。やっぱり「あれを形にして出さないと」という話になって、去年の頭くらいから構成とか符割とかを決めていく中で出てきました。ただ、語り自体は、それ以前のライブの段階から、なんとかインドの宗教みたいなフィーリングをのせたいなと思っていて。語りを自分のメロディの符割で乗せていくっていうのは、もう何百回も練習してたので、それでやりました。
── 一方で、スネアの手数の多い感じ、厳密には違うのかもしれませんが、フィーリングとしてはサンバみたいなノリとかは、最初からありましたね。
谷口:それは、曲を書いたアケオくんから「こういうのを叩いてみてもらえますか?」という要望があって、それを大地が自分で消化したという感じだったと思います。