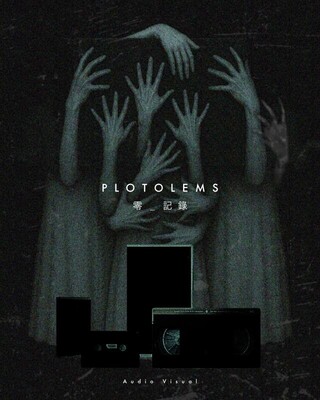ライブの記録の断片、初期衝動として聴いてほしい
──〈Disc-1〉では初期衝動の赴くがままにパンクの精神性だけで疾走するゼルダが、〈Disc-2〉では徐々にパンクから脱却してさまざまな音楽的要素を呑み込みながら身体性を帯びていくのが窺えます。メジャー・デビューするまでにすでに何段階かの変遷を経ていたことがわかりますね。
サヨコ:少しずつニューウェイヴ色が強くなっていきましたね。ピアノやクラリネットを入れてみたりして。ファースト・アルバムを出した頃は周囲から女性バンドとして奇異な目で見られることが多くて、パンク・ロックやニューウェイヴ・シーンに対して理解のある人がレコード会社でも少なかったんです。ジャケット写真も私たちではなくレコード会社のスタッフが選んだり、モモヨさんにプロデュースしてもらってアルバムの構成を決められたりして、自分たちに主導権がなかった。もっと言えばデビュー曲の「ミラージュ・ラヴァー」はモモヨさんの書き下ろしで、私たちの演奏が下手だったら他のミュージシャンに代わりにやってもらったり打ち込みをするといった提案をされたりしました。そういうメジャーの洗礼に当時はかなりの葛藤がありました。私は自分で書いた歌詞を自分で唄うことがやりたくてゼルダに入ったし、そういうレコード会社主導の在り方にびっくりしたんですよ。
──難解すぎるという理由で歌詞の書き直しを要求されたり?
サヨコ:過激な言葉を整理されたりはしました。今となればそうやって言葉を整理してレコードという記録に残すことも理解できますけど、当時はちょっと受け入れられなかったですね。
──なぜニューウェイヴなテイストのままでファースト・アルバムを作れなかったんだろう? とは思いますよね。この『はじまりのゼルダ』があまりに素晴らしい内容なので余計に。
サヨコ:メジャーでは無理だったんじゃないですかね。少なくとも私たちのタイミングでは無理だったと思うし、当時のレコード会社は新しい感性を持った女性バンドをデビューさせることに重きを置いていましたし。それに、結果的にメンバーも変わってしまったので(註:1983年にギターが鈴木から石原富紀江に、ドラムが野沢から小澤亜子に交替)。それが一番大きかったですね。私自身は、他の人が書いた歌詞や曲を唄うことがかなり辛かったです。
──僕も長年、モモヨさんの作詞・作曲による「ミラージュ・ラヴァー」がなぜシングル・カットされたのかが謎だったんです。
サヨコ:でしょ? 私も泣きながら唄っていました(笑)。でもそれもレコード会社からの要請で、モモヨさんが私たちとレコード会社の間に入っていろいろと調整してくれたんだと今なら思えますけどね。
 ──1981年から82年にかけてのゼルダの進化と深化は目覚しいもので、さちほさんは1981年1月11日の屋根裏のライブ音源が「初期ゼルダのピークかも」とライナーノーツに書いていましたね。
──1981年から82年にかけてのゼルダの進化と深化は目覚しいもので、さちほさんは1981年1月11日の屋根裏のライブ音源が「初期ゼルダのピークかも」とライナーノーツに書いていましたね。
サヨコ:これが他人事なら素直に格好いいと思えるんですけど、今も歌を唄い続けている身としては音程のことが気になったり、ここでこんな過剰に叫ばなくてもいいんじゃないか? とか思うわけですよ(笑)。でもここに収録されたライブ音源は音楽と言うよりもライブの記録の断片、初期衝動として聴いてもらえるといいかなと。
──とは言え〈Disc-2〉の後半、1981年の暮れ頃になると初期衝動という言葉では語りきれない音楽的成長を如実に感じますが。
サヨコ:当時、チホさんは音楽評論もやっていていろんな音楽を貪欲に聴いていたので、ものすごくアイディアが豊かだったんです。チホさんが持ってきたベースのフレーズにギターのヨーコさんが反応して、マルちゃんがドラムをつけて、その上に私が書き溜めていた詩のノートから即興で言葉を選んでのせていくのが初期ゼルダのスタイルで、はじまりはチホさんのベースなんです。だからいま聴いてもベースが印象的なんですね。お互いの初期衝動を出発点として、みんなで反応し合いながらセッションで曲づくりをしていたのが当時のゼルダで、〈Disc-2〉にはのちの『CARNAVAL』、『空色帽子の日』、『C-ROCK WORK』で陽の目を見る曲も入っていますね。
純粋で赤裸々な衝動が生きる力になれば嬉しい
──『C-ROCK WORK』と言えば、「Question-1」が1981年にはすでに「問1」として完成していたのを今回初めて知りました。
サヨコ:「問1」という実に高校生らしいタイトルをただ英語にしただけですよね(笑)。『CARNAVAL』や『空色帽子の日』に入るような曲調じゃなかったし、ロック色が戻ってきた『C-ROCK WORK』で昔の曲を引っ張り出すことにしたんだと思います。
──「マリアンヌ」はのちに招き猫カゲキ団の「砂漠のマリアンヌ」となったり、「ハベラス」はのちに『空色帽子の日』に収録されたりと、ここでも楽曲の変遷が楽しめますが、「ハベラス」は正式に発表されたバージョンとはちょっと違う感じですね。
サヨコ:違いますね。それだけ時間が経つと歌詞もちょっと変わってくるし、レコーディングという記録を残す行為はライブとは意識が変わってくるんです。ライブは初期衝動でありパフォーマンスも伴いますが、レコーディングはスタジオで音楽に集中して練ったりしますからね。
──パーカッシヴで躍動感溢れる「うめたて」も実にライブらしく生々しいテイクですね。
サヨコ:あのドライブ感は好きだったスリッツの影響もあるでしょうね。アリ・アップも私と同じ15歳くらいから唄い始めていたし、ネナ・チェリーも一時期スリッツにいたじゃないですか。私はネナ・チェリーもすごく好きだったんです。スリッツを聴いてからレゲエも好きになったし、そこからエイドリアン・シャーウッドのOn-Uサウンドを知ってダブを好きになったりして。レゲエはもともとレベル・ミュージックだし、音だけではなくそういう部分にも共鳴していました。
──ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「WHITE LIGHT / WHITE HEAT」をカバーしたのはさちほさんのセンスだったんですか。
サヨコ:私が入る前からやっていたんじゃないですかね。私の前にケイさんという初代ボーカルがいて、その名残だったと思います。私は当時、英語で唄うことに全く関心がなくて、あくまでも日本語で唄うことにこだわっていたんです。書き溜めていた詩をメロディにのせることにしか関心がなかったし、「WHITE LIGHT / WHITE HEAT」がヘロインの歌だということも全く知らずに自分の発想だけで歌詞を書いたんです。
──ゼルダではストゥージズのカバーもやっていましたよね。
サヨコ:「I Wanna Be Your Dog」を唄っていましたね。あれはアクシデンツやルースターズのメンバーと知り合うようになって、いわゆるめんたいロックのルーツと呼ばれる音楽を教えてもらって、よりロック的になってから唄うようになったんだと思います。それに比べて初期ゼルダの私の歌は、ロックがどうこうと言うよりも純粋な叫びですよね。
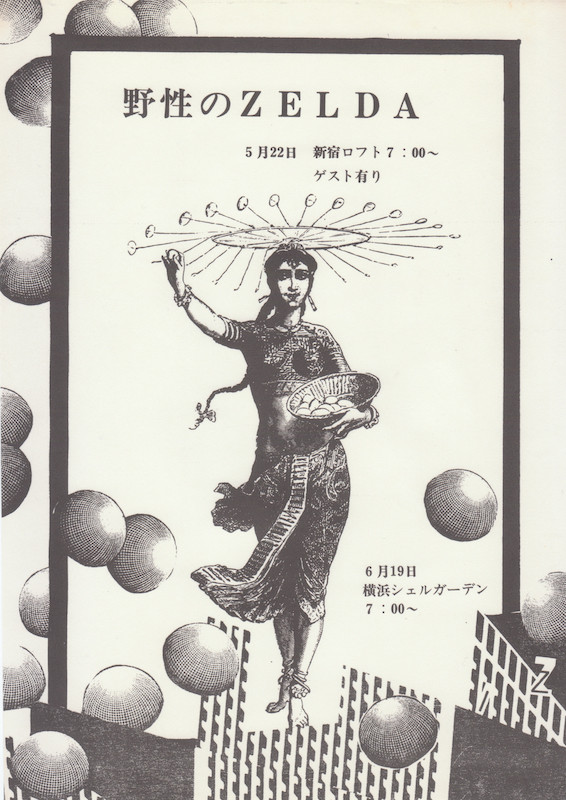 ──この最初期音源集で聴けるサヨコさんの歌声は思春期にしか出せない純粋無垢で瑞々しいもので、混沌として鬼気迫るアンサンブルとの対比がまた良いんですよね。
──この最初期音源集で聴けるサヨコさんの歌声は思春期にしか出せない純粋無垢で瑞々しいもので、混沌として鬼気迫るアンサンブルとの対比がまた良いんですよね。
サヨコ:自分としてはちょっと恥ずかしいですけどね。こんなにも叫んでいて、こんなにもイライラとしていて(笑)。それに当時の歌詞も、今の自分なら絶対に書かない猟奇的な内容があったりして。今の時代、実の子どもを虐待するとか、猟奇的な事件がよく起こるじゃないですか。十代の頃はそういうものに対してリアリティがなかったし、死というものもどこか架空の物語のように思えたんです。私はストラングラーズのジャン=ジャック・バーネルが好きで、彼の影響で三島由紀夫の作品を読んだりして死の美学みたいなものにリアリティなく憧れていたので、当時はそういう負のイメージの言葉を歌詞にしたりしたんです。でもこの歳になると、目を覆いたくなるような事件や現実がこの世界に溢れていることに心が痛むんです。だから「とらわれ」みたいな曲は今そのままの形では唄えません。事実、「とらわれ」はファースト・アルバムに入れるにあたって一番変化した曲ですよね。レコード会社としてはまず歌詞がNGということで。
──今回、「とらわれ」のように挑発的で過激な曲を選曲から外すことも考えたんですか。
サヨコ:他のメンバーとも相談したんですが、結局はそのままの形で出したほうがいいという結論に至りました。今の自分には唄えませんけどね。それは大人になって分別がついたということではなく、こうして現実の世界を知ってしまうと、いくら架空の産物とは言え言霊として発することは地球に影響を与えてしまうという意識があるので。もちろん人それぞれの意見があるでしょうし、私自身はそう感じるというだけです。私としては、今回のCDを聴いてくれた人たちが当時一緒にライブに行っていた人や一緒にバンドをやっていた人、付き合っていた人のことなんかを思い出したり、当時はこんな服を着ていたとかこういう音楽が好きだったとか、あの頃の空気感や状況を思い出したという話を聞いて、音ってそういう記憶を喚起させる力があるんだなと改めて実感したんです。今の私がこのCDを出して何ができるのかと言えば、これは自分も含めてなんですけど、当時のゼルダの音を聴いてこれだけ純粋で赤裸々な衝動があったことを思い出して、それが生きる力になればいいなということなんです。そんなふうに受け取ってもらえたらいいなと思ったんですね。