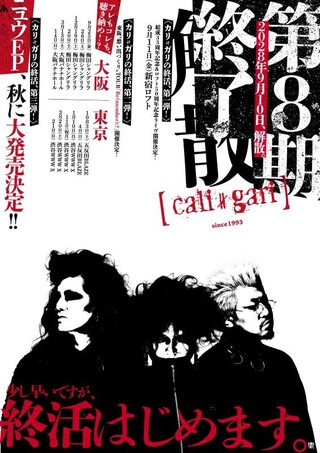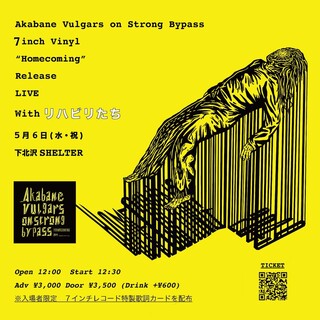熊篠にスポットを当てるべく東奔西走
この2002年は、ブッシュ大統領が悪の枢軸発言を行ない、イラク、イラン、北朝鮮は大量破壊兵器を保有するテロ支援国家であると名指しで非難した年でもあった。人々の記憶には、9.11アメリカ同時多発テロの爪痕も生々しく残り、国内でも反戦ムードの機運が徐々に高まりつつある年でもあった。
そんな中、従来のデモ行進的な要素を排除し、社会的な主張をさまざまな表現によってアピールする、ピースパレードと呼ばれる新しいデモが日本の各地で開催されるようになり、年末に向かうに従って参加者は増え続けていった。
これらのムーブメントをいち早く察知したのが、ロフトプロジェクトのプロデューサーである加藤だった。
ロフト関係者に声をかけたのが始まりとなって、その後はボランティアスタッフや音響機材の提供、文化人やアーティストへの呼びかけに発展、それらの交渉も加藤が積極的に行なうようになっていった。
そんな中での私の仕事は、関東各地で行なわれる反戦デモの記録映像を撮影することだった。
この時期、平野や加藤とさまざまなデモの開催地域を訪れては、撮影機材を片手に目一杯走り回り、デモの最前列から最後尾に至るまでのパフォーマンスを克明に記録して、店のスクリーンで映像を公開するといった作業を繰り返していた。
そんな中、それらの映像を食い入るように見ていた熊篠から、「増田さん、僕もデモに連れてってよ」と、唐突に告げられた。
もちろん、その場では諭すような口調で諦めさせたのだが、このような発言が後々波紋を呼ぶことになろうとは、まだ誰も気づいていなかった。
風光明媚な海岸線を順調に走っていたワゴン車が徐々にスピードを緩めて左折すると、殺風景な空き地に停車した。
ドライバーに感謝の気持ちを伝えて降車し、小走りで先乗りした制作部のスタッフに挨拶しながら確認すると、この場所がシーン48のロケ地なのだと教えてくれた。
ワゴン車を遠目に見ると、熊篠が降車の準備をしている様子が窺えた。周囲に視線を走らせながらほんの少し歩いただけなのに、海岸線の殺伐とした空き地に冷たい海風が吹き抜けて、予想をしのぐ寒さだった。
そうしているあいだにも次々と撮影用の車両がロケ地へと到着する。その中の一台は、まるで消防のはしご車のような形状だったが、どうやらそれは、海岸線を走る劇用車をロングショットで収めるクレーン付きの撮影車両のようだった。そんな光景を熊篠と小一時間ほど見て回り、ワゴン車へと戻った。
その後、ありがたいことに制作部のスタッフからロケ弁とお茶が支給された。撮影前のピリピリした空気を実感した私は食事を済ませた後も車内に留り、このルポの構成案をまとめてみようと考えていた。ところが食事を早々に切り上げた熊篠は、タバコが吸いたいと言い出して再び乗降リフトで地面に降り、寒空の中を一人で出ていった。
2002年4月に出会って以来、熊篠とのあいだには15年もの月日が流れていった。出会った当時はともに30代であり、お互いに偏屈なところがありながらも何かとウマが合い、店で会えば遅くまで語ったりする仲になっていった。
時折、私がプロデュースするトークライブや映像作品に、熊篠がシビアな意見をぶつけてくることがあった。予算や現場の状況を無視した高みの見物的な物言いに何度も呆れかえってしまったが、当時はぐっと胸にしまい込んでいたものだった。
しかし、よくよく考えてみると理にかなった大人の意見を真摯に伝えようとしてくれていたことも、今となっては理解できる。だが、その当時は無性に腹が立ってしかたがなく、何度か衝突したこともあった。そんな下世話な思い出話で良ければ、いくらだって書けるのだが、今回は熊篠という人物を知らない未知の読者に対して、何をどのように伝えれば良いのかがいちばんの課題となっている。
熊篠には多少ヤンチャなところがあり、それら数多くのエピソードに多少の脚色をして列記すれば、実話誌の読み切り記事的な面白さはそれなりに伝わるとは思う。
思いつく限りでも、かつての仕事仲間と『愛・地球博』へのバスツアー旅行を企画したところ、チャーターした観光バスが東名高速を走行中、スピードを上げた熊篠の乗用車に追い越されてしまい、現地合流すると同時に電動車椅子を走らせて撮影したパビリオン映像を帰京直後に有料上映して一儲けしてしまった話であったり、私が制作した商業映画の地方公開が決まり、公開初日に街宣パレードを企画したところ、真っ先に現れた熊篠が主演女優を電動車椅子のステップに乗せて先陣を切って颯爽と走り回り、大人数で商店街を行進したところまでは良かったのだが、悪ふざけが過ぎて地元の不良と所轄警察を刺激してしまい、逃げ遅れた私が双方から追いかけ回されてしまったという危ないエピソードまで、いくらでもあったと思う。
過去にはそういった部分を前面に押し出して、実話系のマスコミに取り上げてもらおうと熊篠と二人で躍起になっていた。
また、当時は自叙伝的な単著を出版し、アダルトビデオにも出演したりと、明らかに文筆家の乙武洋匡や、お笑い芸人のホーキング青山を意識して、強烈にライバル視しているのが傍目からも容易に想像ができた。
それならばと、私が監督した商業映画やロフトプラスワンのオープニングPVの撮影現場に来てもらっては、主要なキャラクターを配役して、劇場公開時のパブリシティ記事や、舞台挨拶やトークショーで常に熊篠にもスポットが当たるような工夫を凝らしていたのだが、そういったアプローチはもう、この数年間でやり尽くしてしまったような気がしてならなかった。
撮影に立ち会う熊篠の介助をサポート
そんな過去の出来事や、このルポの構成案のいくつかを車中でぼんやりと思い巡らせていたところ、ワゴン車の後方から数名の話し声が伝わってきた。
不意に車内の扉を開けて冷たい外気を一気に吸い込むと、ワゴン車の後方で台本を持って談笑する松本監督と目が合った。そして、防寒用のコートを羽織った熊代嘉浩役のリリー・フランキーと、竹田恵理役の小池栄子が熊篠とにこやかに談笑する姿が視界に飛び込んできた。
邪魔をしないように監督と俳優部にさりげなく挨拶して車中へと戻ったのだが、熊篠からこぼれ落ちるその笑顔は幸福感に満ちあふれていた。
その後、クレーン車をフル活用した海岸線でのロングショット撮影や、撮影部の長野泰隆が走行する劇用車から半身を乗り出しながらも、的確にカットを繋いでいく緊張感漂う撮影を見学させていただいた。
千倉白間津でのロケ撮影は順調に進み、熊代の恋人・塩満涼子を演ずる清野菜名を中心に据えた、海のロッジ撮影へと主要スタッフは移動していった。
次のシーンの撮影では、スタジオでのセット撮影とは違い、パームビレッジという実在の宿泊施設をロケセットとして使用して、さまざまなアングルから俳優の演技を収めていく撮影技法を多用する。そのため、私たちはカメラアングルから外れ、見学が可能な場所を探して確保する必要があった。
かすかに輝く夕陽が海岸線へ消えゆくのと同時に、松本監督が涼子役の清野菜名と恵理役の小池栄子に大まかな動きをつけるリハーサルを開始した。
その様子を、熊篠はパームビレッジの駐車場にある吹き抜けのバーベキュー小屋から真剣に見学していた。しばらくすると食事休憩に入り、ありがたいことに制作部のスタッフがロケ弁と一緒に野外撮影用の熱風式ストーブを届けてくれた。熊篠はストーブの前に車椅子を移動させ、底冷えのする寒さから少しばかり解放されはしたものの、少しでもストーブから離れると身も凍るような海風にさらされた。この撮影に参加するすべての人間が、日没と同時に真冬の厳しさを実感せざるを得ない状況となっていった。
──こっちは冬の野外撮影に慣れてるから我慢できるけど、寒さで変調をきたすようならワゴンに戻ろう。
「いや大丈夫、それだけはしたくない。何とかこの小屋の中から撮影を見ていたいんで。ちょっと、車椅子の後ろから小便袋を取ってもらえるかな」
──えっ、今すぐ出るの? とりあえずキャップを外しておくから隅っこのほうでやっちゃえば。
「うーん、昼のお弁当のお茶も我慢したのにね。でもこの後、キャストとスタッフの集合写真撮影があるんで、この小屋で待機するしかないよね。なにせ今日は、見学と取材と記念撮影がすべて重なっちゃったからね」
そうは言ったものの、足元から深々と冷えてくる真冬の現実は変わらない。バーベキューの煙がくすぶらないように方々の壁が取っ払われ、海風が吹き抜けるように設計されたであろう柱だけの小屋で、一灯の裸電球を頼りに私たちはロケ弁を食べることにした。
フタを外したロケ弁を熊篠の手元近くに置いて、割り箸を慎重に割いてゆっくりと手渡した。熊篠はいつものように感謝の言葉を述べる。
飲み物がテーブルに置かれた際には、包装から取り出したストローを缶やグラスに差しつつ口元へと向ける。
不意な挨拶や名刺交換の際には、電動車椅子にぶら下げてあるポーチから名刺入れを取り出して、人差し指と中指のあいだに、『NPO法人ノアール理事長 熊篠慶彦』と印刷された本人名刺を挟んであげる。そして、挨拶を交わした相手の名刺を再び指のあいだから抜き取り、名刺入れに保管してポーチを元の位置に戻す。
急な尿意を訴えた場合には、小便容器の入った筒形の袋を車椅子の後方から取り外し、容器を抜いてキャップを外した状態で膝の上に置き、用を足した容器を素早く袋に入れるといった行為を、私は不器用ながらもそれなりに会得していった。
そのような信頼関係から、クランクイン直前のオールスタッフ会議に始まり、主要キャストが揃うロフトプラスワンでのロケセット撮影、熊篠が観客役でエキストラ出演したいと言い出した主人公・熊代嘉浩の講演会撮影、武井哲プロデューサーの家族が経営するイタリアンレストラン・パドマでの大がかりなロケセット撮影まで、事前に松本から付き添いを頼まれ、同時に熊篠からも確認の電話が入るといった状況が何日か続いていた。
映像関連の仕事を続けてきた私にとって、主人公の熊代嘉浩役に熱心に取り組むリリー・フランキーの仕事ぶりや、松本の演出を現場でつぶさに見学できる、またとないチャンスでもあった。そのような理由から、至らない点は多々あれど、熊篠の介助を精一杯するつもりだと松本に伝えた。
「ごめん、用を足したんで容器を袋に入れて車椅子に戻しといてもらえるかな」
──ああ。もうすぐ撮影再開するみたいなんで、集合写真はこの後になりそうだな。
「このロケに参加しなかったらさ、集合写真に入れなかったんで、今日は付き添ってもらって助かったよ。やっぱり、リリーさんたちと一緒に集合写真を撮りたかったんで」
──武井さんも監督も、集合写真は主要キャストが揃った撮影日じゃないと撮れないんで、いろいろと調整に苦労した感じだったな。
「寒い中、じっと待ってて本当に良かったよ。僕もスタッフの一人だからさ」
不意に熊篠が本音をつぶやいた。決定稿と印刷された分厚い脚本の6ページ目には、「原案 熊篠慶彦」と正式に表記されている。
当初、監督の松本から熊篠本人に、今作はスタジオでのテレビドラマ収録などとは異なり、さまざまな地域や建造物でのロケーション撮影がメインになるといった細やかな事情説明がなされていた。その時点で私にはピンとくるものがあったが、熊篠は一貫してロケ地近辺のホテルに滞在し、リリー・フランキーの出演シーンには早朝から立ち会い、細かい動作の流れを演者本人にアドバイスしたいと申し出ていた。
原案者としては、公私ともに付き合いのあるリリー・フランキーと監督ならば当然、発言の真意が伝わるものと安易に考えていたはずであった。
ところが私の経験上、商業施設や住宅をあらかじめ取り決めた条件でロケセットを使用する場合、限られた時間内に撮影が進行するよう、さまざまな制約がスタッフに課せられる。
衣装替えやヘアメイクはロケセット内とは別の場所で行なうか、待機場所であるロケバス内ですべて済ませてしまうことが多く、そのどちらにも熊篠が俳優部とコミュニケーションを取るような場所やゆとりがない。ましてや、電動車椅子での移動となれば、スタッフの誰かが事前に段差の有無を確認しておかなければならず、松本にとっても頭の痛い決意表明であったことは確かだった。
結局、クランクイン直前の多忙な松本から相談があり、熊篠への説得を任された。そこでまず、金銭的にも負担のかかるホテル滞在は断念させ、通勤ラッシュを避けた時間帯に公共交通で自宅から現場へと向かい、同行する私やヘルパーと常に行動を共にして、現場では必ずスタッフの判断に従う、といったルール設定を熊篠と一つ一つ取り決めていった。
熊篠の心中を察するに、原案者としての一途な思い入れと相反する、電動車椅子での現場参加への足枷は非常に重く、また過去のさまざまなトラウマを呼び覚ませてしまうであろう説得の過程に、得も言われぬ矛盾を抱え込みつつも、この問題は数日後に解決した。
だが、これら一連の説得で、ある出来事の記憶が鮮烈に甦ってくるとは思いもよらなかった。改めて当時の記憶を頼りに文章を起こしてみようと考えた。