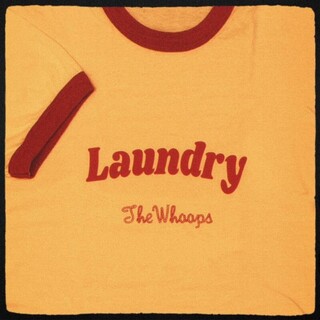『パーフェクト・レボリューション』企画協力/東海林二郎役 増田俊樹
気の利いた一言がいえない性分
映画『パーフェクト・レボリューション』のモデルである熊篠慶彦が撮影現場を見学したいと制作側に打診したことにより、その道中に本人取材が実現した。
普段であれば、熊篠は川崎市内の自宅から都内へと移動する際、自ら運転する特別仕様の専用ワゴン車を使用するのだが、早朝に川崎市内を出発して東京湾アクアラインを走り抜けての長距離運転となると、さすがに躊躇した様子だった。
かくして、私たちは制作部が手配したドライバーの運転する、電動車椅子が乗降可能なリフト搭載のワゴン車に同乗させてもらい、熊篠と目的地を目指すことになった。
後部座席が取り外された車内に電動車椅子ごと乗車した熊篠は、どこか落ち着きのない様子で車窓に映る風景を眺めている。私は熊篠の右隣の固定シートに座ってとりとめのない雑談を交わしつつ、鞄の中からICレコーダーを取り出して取材を開始した。
──適当に質問を始めてもいいかな? まず、ずっと通い続けているロフトプラスワンなんだけど、熊篠の中ではどんな存在なの?
「ここで、せっかくロフトブックスさんから本を出版してもらえるのだから何か言えばいいんだろうけど、それにしてはおべんちゃらが出てこないんですよね」
──だんだんとわかってきたよ。熊篠って、相手をヨイショしたりするのが得意じゃないよね。おべんちゃらを言ったほうがいい時に限って必ず黙る。
「うーん、言えない。言えたらもっと上手く世の中を渡れた。おべんちゃらって言うとちょっとあれだけど、気の利いた一言がいえない」
2015年の年末、映画『パーフェクト・レボリューション』のクランクイン直前、仕事仲間である松本准平からある相談を受けた。
熊篠は2001年から今日まで、世界初のトークライブハウスと呼ばれる新宿のロフトプラスワンで、いくたびもトークライブに出演している。また、常連客の一人として店に通い続け、バリアフリーを基調とする店内を電動車椅子で移動しては、さまざまな人々との交流を育んできた。
そんな中で、そのユニークな個性が話題となり、フットワークの軽い行動力も評判を呼んで、メディアが主催する講演やトークイベント、また雑誌のインタビュー記事にもたびたび登場する機会が増えていった。
『パーフェクト・レボリューション』の監督と脚本を担当する松本は、そんな事情を鑑みたのだろう。新宿ロフトやロフトプラスワンを運営するロフトプロジェクトの名物オーナーであり、ロフト系列でのトークライブに熊篠を登場させ続けてきた平野悠に、映画監督としての使命感から、映画化の経緯説明ならびに制作協力への相談を事前に済ませてから撮影に臨みたいと考えていた。
そこで、かつてロフトプロジェクトの映像部門に所属し、平野の側近として活動していた私に相談を持ちかけたのだった。
2016年の年明け早々、松本の要望をロフトプロジェクト側に伝えるべく思案をしていた矢先、私と同じくロフトから独立し、高円寺にトークライブハウスを開店させた後輩の奥野徹男から電話があり、店の新年会への参加を呼びかけられた。
その際に、「今晩は平野さんも参加するみたいですよ」と伝えられ、とりあえず店に顔を出した平野と酒を酌み交わし、ざっくばらんに松本からの要望を伝えようと考えた。1995年のオープン当初から筆舌に尽くし難いほどの強烈なシンパシーを感じ、その後ろ姿を追ってきたあこがれの平野との再会に正月早々胸が躍った。
ところがである、酒の席というのは何かと間違いが起こりやすい。
最初は上機嫌で熊篠の近況や映画化の経緯を聞いていた平野だったが、酔いも手伝ってか製作委員会方式というフレーズに反応し、さらに業界大手の制作会社が現場制作を担当すると告げた途端、血相が変わった。
「おいおい、なんだって? 俺はロフトの平野だよ。今さらなんで大手の制作会社と組んだりしなきゃならんのだ。熊篠が困ってるんなら制作費だってなんだって面倒見てもいいぐらいに思ってたよ、だけど大手とは絶対に組めないな。はい、その話はもうおしまい」
この発言を放置しておくべきではないと考えた私は、ただちにロフトプラスワンを訪れた。
そこで、オープン以来の生え抜きプロデューサーであり、ロフトプラスワン界隈の面倒事に直面しては体を張り、何かと矢面に立たされてきたロフトプロジェクト社長代行(現ロフトプロジェクト社長)の加藤梅造に事の成り行きを伝え、苦笑いを交えつつ善後策を協議した。
ロフトプロジェクト内では、政治色の強い活動やサブカルチャー部門を長らく牽引し、平野が最も信頼する右腕と呼ばれた加藤だが、彼もまたロフト系列のライブハウスから発信されるさまざまなメッセージに影響を受け、スタッフとなっていった一人だった。
安定した大手企業のサラリーマン生活にピリオドを打ち、ドロップアウトしてロフトプラスワンの三代目店長になったという経歴の持ち主だけあって、同志とも呼べる頼れる男だった。そんな加藤の賢明なアドバイスはありがたかった。
「熊篠とロフトプラスワンの関係は長いよね。10年ぐらい前までは、僕や増田ちゃんも熊篠のトークライブを担当していたからね。もしもここで熊篠がブレイクするんなら、ロフトプラスワンでの撮影や、関連書籍の出版という流れの援護射撃は当然させてもらうよ。でも、平野さんの主張は翻らないと思うんで、初号試写を観せてもらった後に監督から事後報告すれば大丈夫でしょう」
熊篠にとってのロフトプラスワンとは
東京湾アクアラインを疾走するワゴンの車中で、たった数カ月ほど前のそんな出来事が鮮明に脳裏を過ぎていった。そこであえて私は熊篠に苦言を呈した。
──あの時、平野さんに電話したほうがいいと助言したにも関わらず、絶対にしなかったよね。強制されると「するもんか!」ってなる。松本だって電話さえしてくれれば、妙な誤解もすぐに解けたはずだって思ってたから。ならばもう、絶対に電話なんかするなって言うしかない。
「だからさ、何度も繰り返すようだけど、そういった時に限って気の利いた一言がいえないんだよ」
なんともバツの悪い空気が車内に流れたまま、東京湾アクアラインの海中トンネルから漏れるカクテル灯が、フラッシュのように熊篠の横顔に当たっては消えていった。
海中トンネルを高速で走り抜けたワゴン車は一旦、東京湾に浮かぶパーキングエリアとして知られる、海ほたるに停車。2014年1月、松本准平監督作品『最後の命』に配役され、柳楽優弥と共演した木更津ロケの際にも立ち寄ったことを、ふと思い出した。
若干、曇ってはいたものの、空を見上げることのできる風光明媚なスポットでもあり、一息つくにはちょうど良い場所だった。少し気がかりなのは、川崎を出発する際に8度だった気温が急降下したような気がしてならなかったこと。勢いよく車を降りると頬を切る海風が吹き去り、冷え冷えとした寒さを実感させた。急いでホットミルクティーのペットボトルを買って、車中で待つ熊篠へと手渡した。
「さっきの質問なんだけど、車椅子の客に対してスタッフがさ、わざわざ遠いところ当店にご来店いただきまして…なんてことは誰一人言わなかったよね。そこかな、良かったところは」
ロフトプラスワンが自身にとってどういった存在だったのかを思い出した挙句、出てきた答えがそれだった。
──平野さんなんか、電動車椅子が通行の邪魔だとかって文句を言いながらも、熊篠を見つけると嬉しそうに話しかけてきたよね。
「いやいや、他のお客さんは丸椅子だってのに、一人だけ背もたれのついた偉そうな椅子でおまえはいいよなって、増田さんも言ってたよ」
──平野さんや周囲のスタッフは、とにかく面白い奴が来店すると必ず客前でいじるからね。当時はそうすることによって、その人に興味が集まればしめたものだと考えていたから。
「ロフトプラスワンの存在っていうのを改めて考えてみると、最近では当たり前になってきたんだろうけど、当初から相当マニアックなテーマのトークライブばかり企画してましたよ。たとえば、スナック菓子『うまい棒』に関するトークなんかをやってた。あの頃のことで言うと、ステージの一日店長の人もさ、ゲストやお客さんもすっごいマニアが多いじゃん。本当のマニアって感じの人がそこにいてしゃべってるわけじゃん。たとえばさぁ、僕がいくらプロレスや格闘技が好きだっていっても単純に見るのが好きなのであって、マニアの人は身長とか体重とか、ミドル級だヘビー級だと全部頭の中に入っていて、何月何日の何とかの大会のどっちが勝った、どっちが負けたとか全部頭の中に入ってるじゃん。そういういろんな分野の人たちがそこそこな人数いるっていうのがさ。もうね、通ってるうちに僕なんかは足元にも及びませんって感じになっちゃったんですよ」
──実を言うと、みんなそんなふうに思っていたんだけどね。
「そこでさ、いや、まだ僕のほうが知識あるぞ、この分野ならいけるぞとなったら、これはメジャーを狙おうかってことになったんだろうけど、もう諦めちゃいましたよね。世の中は広いし、この人たちには到底敵いませんってなっちゃって、僕はただのファンでいいですって。そういうことを僕に教えてくれたのがロフトプラスワンなんです」
──店側からすると、客席のマニアックな人が発言すればさらに盛り上がるんじゃないかと思って、ワイヤレスマイク片手に客席を徘徊するんだけどね。そんな中で、勢いあまって客席からステージに登壇した途端にお客さんの心を掴んでレギュラー企画を持っちゃうような人もいれば、客席でワイヤレスマイクを向けようが何しようが一切しゃべらない、私だけは勘弁してくれというような無口な人ってのもけっこういるんだよね。で、最初の頃はどっちだった?
「僕はしゃべれないから、勘弁してくれっていうほうだったよね」