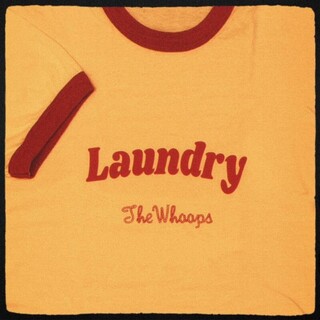ビッグ・ジェイの隣りで吹いて知り得た発見
──2015年のビッグ・ジェイ再来日時、ライブは渋谷クラブクアトロのみでしが、これはやはりレコーディングを優先した形だったんですか。
甲田:そうですね。レコーディングありきだったので。山中湖のスタジオでレコーディングを終えた後にクアトロでライブをやる強行スケジュールだったんです。
──アルバムの内容は事前に決めてあったんですか。
甲田:お互いのセルフカバーをやろうとか、やり取りはしてましたね。お互いのやりたい曲をピックアップして、何度かディスカッションしたりして。ビッグ・ジェイは新曲も3曲書いてきたし、結果的にかなりの曲数になったんですけど、それを吟味していきました。レコーディングでは15、6曲くらい録って、そこから10曲に絞った感じですね。
──山中湖のスタジオには何泊したんですか。
甲田:3日ですね。レコーディング最終日に機材を片づけて東京へ帰って、その翌日がクアトロでのライブだったんです。ビッグ・ジェイの飛行機のチケットも手配していたし、レコーディングの日程を伸ばせなかったんですね。最初はそのスケジュールもゆとりを持って組んで、1日空けたりしてたんです。そしたらビッグ・ジェイに「この空いてる日は何だ?」って言われて、そうだ、ビッグ・ジェイは休まない人なんだって思い出したんですよ(笑)。「空いてる日は必要ない。お前ら、疲れちゃうか?」って逆に言われて、休みなしのスケジュールになったんです。
──レコーディングは1日中みっちりやるんでしょうから、相当な集中力が必要となりますよね。
甲田:1日中みっちりだったんですけど、ビッグ・ジェイがスタジオへ来るのは夕方以降だったんですよ。それまでに僕らが曲の構成とアレンジを固めておいて、ビッグ・ジェイが来たらすぐに録れるようにして。仕事的にここまでやらなくちゃいけないっていうのは深夜の1時、2時くらいまでだったんですけど、ビッグ・ジェイはその後が長いんですよ。なかなか帰ろうとしないので(笑)。「今日はここまでです、お疲れ様でした!」ってなると、「終わったか? よし、じゃあ、こんなのはどうだ?」ってまた吹きだすんです。それをしばらく無視してると、「早く来いよ、お前ら! こっち、こっち!」って感じで目で訴えかけてくるんですよ。そこでドラムのキミノリが根負けして乗っかると、「うわー、やっちゃった!」とか思うんですけど(笑)、それから15分くらいセッションになったりするんです。
 ──「Hot Special」のPVを見ると、皆さんスーツを着込んだ正装でプレイしているじゃないですか。あの格好もなかなか気が休まらなかったと思うのですが。
──「Hot Special」のPVを見ると、皆さんスーツを着込んだ正装でプレイしているじゃないですか。あの格好もなかなか気が休まらなかったと思うのですが。
甲田:スタッフがPVを撮りたいってことだったので。ライブでもスーツだし、全然大丈夫でしたよ。それに今回はビッグ・ジェイとの真剣勝負だったし、身なりのことまで気にしてられなかったですね。
──憧れの伝説的ホンカーの隣りで演奏するのは、大きな喜びととてつもないプレッシャーがない混ぜになった感じでしたか。
甲田:演奏が始まると緊張感もなくなったし、むしろいろんなことを学べましたね。ビッグ・ジェイが吹いてるのを横目で見て、「そんなことをやっていたのか!?」って長年の謎が解けたりもしたので。主に指使いに関してですけど。あとはブラック・フィーリングにつながる間の取り方も間近で感じることができたし、これは凄いものを見てしまったぞと思いました。ただ、そういうのに気を取られていると、ビッグ・ジェイはとにかく音がバカでかいので、後でプレイバックを聴くと僕の録れ音が圧倒的に小さかったりしてしんどい思いもしましたね。一本のマイクで録ってるから、後で調整ができないんですよ。
──ビッグ・ジェイから「吹けよ」とアイコンタクトされて甲田さんが吹くパターンが多かったそうですが、そういったコール&レスポンスの妙でとりわけ印象深いのはどの曲ですか。
甲田:ビッグ・ジェイが書いてきたバラード「I Want To Be With You」は、当然ビッグ・ジェイが全部吹くと思ってたんですけど、録音が始まってビッグ・ジェイが一節吹いたら「吹け!」って合図が来たんです。あれは前もってコピーしておいて良かったなと思いました(笑)。
──「I Want To Be With You」はアルバムの最後に持ってきてもいいくらいの名バラードですよね。酸いも甘いも知り尽くした円熟した魅力が全体から感じられて。
甲田:男と女の曲らしいんですけど、ビッグ・ジェイが何歳くらいでどんな風景を思い浮かべて作ったのかなと興味を持ちましたね。ちょっとおとぎ話っぽくも感じたりして。
「Deacon's Hop」と「Blow Big Jay」は絶対に外せなかった
──今から68年前に全米チャート1位を獲得した「Deacon's Hop」の改訂版と言うべき「Big Jay Meets The Deacon」やベッシー・スミスを始め数々のアーティストにカバーされてきた「Nobody Knows You When You're Down And Out」といった有名曲と、ブラサキとビッグ・ジェイが持ち寄ったオリジナル楽曲がとてもよく馴染んでいて、時空を超えた選曲の妙が素晴らしいですね。
甲田:自分としては「Deacon's Hop」と「Blow Big Jay」がマストで、絶対にやりたかった曲なんです。特に「Blow Big Jay」は僕が初めて聴いたビッグ・ジェイの曲で、絶対に外せないと思っていて。最初にこっちがやりたいと思ったビッグ・ジェイの曲の中にはビッグ・ジェイ的にNGなのもあったんですけど、ブラサキのオリジナル曲も含めていいところに落ち着いた気がしますね。
──「Deacon's Hop」はなぜ改名して収録されたんでしょう?
甲田:多分、「俺と一緒にやろうぜ!」っていうビッグ・ジェイの気持ちの表れだと思うんですよ。だから嬉しかったですね。あと、「East Meets West」も西海岸のビッグ・ジェイと極東のブラサキが出会うって意味なんです。曲の中で「ヤングコーン!」「ビッグ・ジェイ!」って掛け声があるんですけど、最初は「ヤングコーン!」じゃなくて「ミスター・コウダ!」だったんですよ。ビッグ・ジェイが「ミスター・コウダ」がいいってことで。でもウチのメンバーに「シンタロウ」か「ヤングコーン」がいいんじゃない? って言われて「ヤングコーン」にしたんです。別に僕はどっちでも良かったんですけど(笑)。ビッグ・ジェイは「『コウダ』が言いやすいんだよな」って言ってましたけどね。
──「East Meets West」はなかなか演奏が終わらなかったのでフェイドアウトにしたとか(笑)。
甲田:ビッグ・ジェイが演奏を止めないので、ホントに長かったんですよ。だけど演奏中のビッグ・ジェイはもの凄く楽しんでいたんです。「East Meets West」は3テイクくらい録ったんですけど、ビッグ・ジェイはどのテイクでも「こんなこともやっちゃうぜ」みたいなプレイを繰り出してくるんです。それにこっちが応えると大喜びして、間とかも無視して喜んでから吹いたりするんですよ。そうやって音で会話するのが凄く楽しかったし、ビッグ・ジェイも単独で吹く時より相手と会話するように吹く時のほうが俄然ノリがいいんです。それは身体に染みついたものなんだろうし、彼らにとって音楽とはそういうものなんでしょうね。
 ──テナー・サックスだけではなく、ビッグ・ジェイは歌でも堂々とその存在感を見せつけていますね。「Insect Ball」でも「Nobody Knows You〜」でも年輪を感じさせるしわがれ声がとても味わい深くて。
──テナー・サックスだけではなく、ビッグ・ジェイは歌でも堂々とその存在感を見せつけていますね。「Insect Ball」でも「Nobody Knows You〜」でも年輪を感じさせるしわがれ声がとても味わい深くて。
甲田:1957年にニューヨークのバードランドでやったライブが音源化されているんですけど、そこでは正式なボーカリストを迎えつつ、ビッグ・ジェイが会話をするように合いの手で唄ってるんです。「Insect Ball」もそこで唄ってるんですけどね。
──あれだけ雄弁にテナー・サックスで唄っている人だから、直接唄わなくてもいいんじゃないかという気もするのですが(笑)。
甲田:自分一人で乗り込んで地元のバンドマンと一緒にライブをやることが多いビッグ・ジェイにとって、自分一人でエンターテイメントを成立させるために歌が必要な場面があったのかもしれませんね。それは僕の憶測ですけど。
──クリス・パウエルのカバー「I Come From Jamaica」はバンドの一体感を実感できる高揚感溢れるナンバーで、スタジオ内の緊張感を飛び越えて、録音に携わった全員の純粋に音を鳴らす喜びみたいなものが窺えますね。
甲田:緊張感があったほうが演奏は楽しいんですよね。今回のレコーディングは準備万全だったのでいいものが絶対に録れる自信があったんですけど、その上で何がどうなるか分からない緊張感、ビッグ・ジェイとブラサキが一瞬一瞬で作り上げていく緊張感が絶えずあったし、あって良かったと思います。緊張感と言うか、真剣勝負と言ったほうが近いかもしれませんけど。