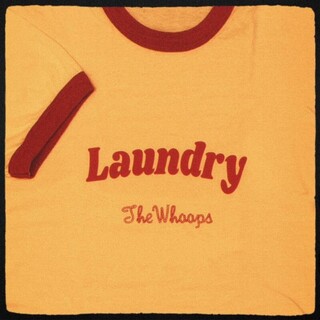ビッグ・ジェイの底知れぬバイタリティの根源にあるもの
──今回はピアノとキーボードに伊東ミキオさん、パーカッションに山崎哲也さんという盟友も参加して、真剣勝負をするには申し分のない面子でビッグ・ジェイと闘えたのでは?
甲田:そうですね。ミキオさんは2012年のツアーの全公演に参加してくれたし、僕らのやりたいことを分かってもらえると思って入ってもらったんです。山崎の哲っちゃんは、たとえば「Blow Big Jay」の冒頭がパーカッションから入るし、「I Come From Jamaica」みたいにパーカッシブな曲も録る予定だったし、不可欠なパートなので参加してもらいました。
──どれも1曲につき2、3テイク録ることが多かったんですか。
甲田:だいたい3テイクくらいは録りましたね。そこからOKテイクを選ぶのは、「いいよ、お前らが選べよ」みたいな感じでビッグ・ジェイが僕らに委ねてくれました。考えてみれば、それも凄い自信ですよね。「俺はどこを切り取られても大丈夫だ」ってことですから。よく言われる1テイク目の良さっていうのもありましたけど、コール&レスポンスや掛け合い的に良かったテイクを優先しましたね。それもあって3テイクは録るようにしたんです。
──ヴィンテージ・サウンドを知り尽くしたシュガー・スペクターさんがエンジニアを務めたことでモノラルっぽい音の塊がとても生々しくて、目の前でライブ演奏を聴いているような音作りですよね。
甲田:機材の選び方からメンテナンス、その場のマイクのセッティングまですべてを含めてシュガー・スペクターの知恵と技術が集約されていると思いますね。
──マイク一本の置き方一つ違っても、だいぶ音の感じが変わるものなんですか。
甲田:全然違いますよ。1センチ単位でかなり変わってきますね。今回はビッグ・ジェイが座って吹いていたので僕も座りましたけど、これが立って吹くだけでセッティングをし直さなくちゃいけなくなるんです。それくらい微妙な違いが出てくるんですよ。しかも僕一人だけじゃなく、バンド全体の音のバランスを考えなくちゃいけないですし。ただそれも、2日目、3日目にもなるとそういう位置のバランスがみんな感覚的に分かるようになるんです。立とうが座ろうが目測で何となく分かるようになってくるんですよ。シュガー・スペクターも僕らがそんなふうに分かってくるのを分かった上で録音作業に挑んできたので、良い相乗効果だったと思います。
──そういう録音環境とか、サポートを含めたブラサキの演奏が心地好かったからこそビッグ・ジェイは終始ノリノリで、なかなか帰ろうとしなかったんじゃないですかね。
甲田:でしょうね。きっとそう感じてくれていたと思いますよ。
 ──ビッグ・ジェイの底知れぬバイタリティの根源にあるのは何だと思いますか。
──ビッグ・ジェイの底知れぬバイタリティの根源にあるのは何だと思いますか。
甲田:心の底から音を奏でることが好きなんだと思います。ビッグ・ジェイは酒もタバコもやらないし、あの頃のミュージシャンには珍しくドラッグも一切やらなかったし、完全にクリーンなんです。きっと楽器を演奏してケースにしまったところで1日が完結できてるんじゃないですかね。レコーディングでもライブでも自分の好きなことを際限までやりきってアドレナリンを出しきって、楽器をしまったら1日が終わる。そういうリズムができてるんだと思います。
──とても純真で、音楽に対するピュアな愛情が尽きないんでしょうね。
甲田:だと思いますよ。愛情があるから楽器も凄く上手いですしね。一見ハチャメチャにやってるように見えますけど、それも全部分かった上でやってますから。
──そんな百戦錬磨の巧者にブラサキは決して怯むことなく、がっぷり四つに組んで闘いを挑んでいるのが音の端々からも窺えますね。
甲田:少なくとも大御所だから負けていいとは全く思ってなかったので。むしろ勝ちたいし、手加減はできませんよね。だけどお客さんを無視した勝ち方をしてもしょうがないし、常にお客さんのことを意識するビッグ・ジェイと同じ目線で勝負ができたんじゃないかと思います。
その曲に演奏する側の魂が入っているかどうか
──ビッグ・ジェイとのレコーディングを通じて、純粋に音を奏でることの楽しさを改めて教えられた部分はありますか。
甲田:ありますね。コール&レスポンスも純粋に楽しいことですから。「エッ、お前、そんなことを思ってるの?」「そうだよ! 知らなかったの!?」みたいなやり取りをその場の音で形にするわけですから、凄い刺激になりますよね。今までもずっとコール&レスポンスをやってはいましたけど、ビッグ・ジェイとのやり取りほど刺激的な経験はなかったんです。あと、モチベーションもあまり大きすぎると自己満足になったり、お客さんを置いていったりすることになるし、適度なモチベーションを維持することの大切さもビッグ・ジェイから学べたことですね。
──今回のビッグ・ジェイとの共作盤を聴くと、音楽に国境はあるけど壁はないことを実感しますね。祖父と孫ほど歳の離れた両者が世代も時空も超えてリズム&ブルースの最良の部分を体現できているわけですから。
甲田:そう言ってもらえると嬉しいですね。ジャンルの区分けとか時代感って、意外とやる側が頑なになってる部分じゃないかと思うし、それよりも大切なのは、その曲にやる側の魂が入っているかどうかだと思うんです。究極はそれだけなのかもしれない。かのレイ・チャールズも「そこにソウルがあるかどうか。ただそれだけだ」って言ってますしね。だからルーツ・ミュージックや古い音楽であろうと、どこの国の曲であろうと関係ないと思うんですよ。
──せっかくこれだけ良質なアルバムができたことだし、海外でのリリースやライブの回数を増やしていきたいですね。
甲田:もちろんそういったことも視野に入れて活動していきたいと思ってます。今回のレコーディングの最終日に香港でライブをやる話をもらって、今は年に2回、香港でライブをやってるんですよ。そこでも学べたことがけっこうあるんです。最初はMCも英語を覚えて暗記してたんですけど、全然受けなかったんですよ。それで開き直ってMCを日本語で通すことにしたんですけど、そのほうが圧倒的に伝わるんですよね。ライブの最後に紙に英語で書いたMCを棒読みして、英語ができないキャラとして笑わせるんですけど(笑)。僕らの曲のタイトルはだいたい英語だし、それさえ言えば後は日本語でもいいと思うんですよね。無理に共通言語でコミュニケーションするのではなく、熱量や思いを伝えようとしたほうが効果的なんです。
──僕らが洋楽アーティストのライブを見る時、MCで何を言っているのかは分からなくても、音楽で伝わるものは充分伝わるのと同じですよね。
甲田:そうなんです。自分たちの言いたいことを一語一句伝えるのではなく、多少大雑把でもいいから大きな流れで楽しませたほうがいい。僕らは音楽をやってるんだから、言葉よりもフィーリングや伝え方のほうが大事なんですよ。そういう意識の変化は2012年にビッグ・ジェイを招聘した時から始まってるし、いま思えばあれが物語の第1章だったんです。それから『Rhythm And Blues』という単独のアルバムが出て、ジュウェル・ブラウンとのレコーディングとライブがあり、今回のビッグ・ジェイとのアルバムがあり、香港公演がある。全部つながってるんですよ。香港公演は一見関係がなさそうだけど、ビッグ・ジェイとのレコーディング中にもらった話だし、全部地続きなんです。すべてはビッグ・ジェイ・マクニーリーとの出会いから続いてるんですよね。
──物語の第3章はどんな筋書きになりそうですか。
甲田:どうですかねぇ。近々面白そうなニュースも発表できると思うので、楽しみにしていただきたいですね。ビッグ・ジェイやジュウェル・ブラウンと育んだ縁はいまも続いてるし、ここまでやってきたことを応援してくれた人たちの期待にも一つひとつ丁寧に応えていきたいんです。ブラッデスト・サキソフォンはインスト・バンドなので不利な部分があると思うんですけど、逆にそこを武器にして、日本だけに留まらずにいろんな場所で活動の幅を広げていきたいですね。そこで焦ることなく、一つひとつ丁寧に広めていきたいんですよ。辛くても一個一個丁寧に塗り潰していく感じって言うか。
──急がば回れという言葉もあるし、それが一番の近道ですよね。
甲田:そう思いますね。今ちょっとのろくて進まないって時は、これは近々何かあるぞ、って思うんですよ。今ここを丁寧にきっちりとやっておけば後で面白いことが必ず起こる、って。そんなふうに進んでいけば、いつでも豪勢に分厚いステーキを食べられる生活が送れるかな? って(笑)。
BLOODEST SAXOPHONE feat. BIG JAY McNEELY ”BLOW BLOW ALL NIGHT LONG" TRAILER
BLOODEST SAXOPHONE feat. BIG JAY McNEELY / BIG JAY MEETS THE DEACON
BLOODEST SAXOPHONE feat. BIG JAY McNEELY / HOT SPECIAL