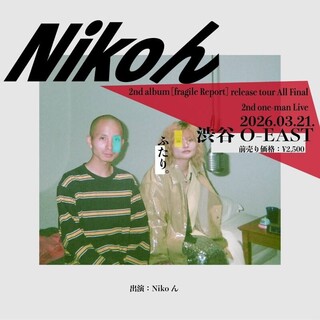歌舞伎町へ移転して以降の新宿ロフト15年間の歴史のなかでも、a flood of circle(以下、AFOC)との出会いはとりわけ鮮烈なものだった。ロフトに出演し始めた頃の彼らは弱冠19歳で、メンバー各自が精通する古今東西のロックを下地にしたその音楽性はまだ節くれ立ったところがあったものの、才気煥発の片鱗とバンドに懸ける気概が見て取れた。あれから8年。こよなく愛するブルースを分母に置いて常に最新鋭のロックンロールをアップデートし続けるAFOCの目覚ましい躍進ぶりはご承知の通りだ。バンドの出自であり、節目節目で重要なライブを行なっている新宿ロフトとは彼らにとってどんな存在なのか。フロントマンの佐々木亮介(vo, g)に話を聞いた。(interview:椎名宗之/photo:新保勇樹)
全レパートリーを再現するライブを敢行した意図
──東京キネマ倶楽部で3日間にわたって開催した「a flood of circle 8th Anniversary Oneman Live“レトロスペクティヴ”」はこれまでリリースしてきた作品を全曲演奏する試みでしたが、これはどんな意図があったんですか。
佐々木:自分のバンドマン人生のなかで作ってきた曲を全部やるということは、ここまでの歩みも試されるし、これを乗り越えられるかどうかというこの先のバンドマン人生も試されるわけで、純粋に面白いなと思ったんです。ちょうどレコーディングと並行してこのライブの準備をしていたので、過去の作品を回顧しながらこのバンドはこの先どこへ向かっていくのかを確かめられたのが良かったです。
──単なる回顧ではなく、未来を視野に入れた試みだったわけですね。
佐々木:バンドも歴史を積み上げていくと、どうしても昔の曲をやらなくなるじゃないですか。俺たちもそうなりかけていたし、せっかく大事に作った曲を使い捨てみたいにするのもイヤだったんですよ。俺たちがやらなくなった曲があるということは、その時期が好きだったのに見に来なくなった人たちもいるわけですよね。実際、今回の企画だからこそ久々にAFOCを見に行こうとした人たちがけっこういたみたいで、姐さん(HISAYO/b)がやってるツイッターにもメッセージが来たそうなんですよ。「姐さんが入ってからの4年間は一度もライブを見てなかったんですけど、今日見たAFOCが凄く格好良かったので、これからはまた通い続けようと思いました」って。それを聞いて、やって良かったなと思いましたね。
──過去の作品を冷静に分析できる良い機会でもありましたよね。
佐々木:たとえば岡庭(匡志)が失踪した後の『PARADOX PARADE』は混沌とした状況のまま勢いで作った曲が多いから、今やると凄く難しいんですよ。細かいことをやろうとしていて、再現するのが大変で。でもいざやってみたらお客さんが凄く盛り上がってくれて、あんなにリアクションが大きいとは思いませんでしたね。

 ──サポート・ギターの曽根(巧)さんやHISAYOさんのツイッターを拝見する限り、とりわけ準備が大変だったようですね。
──サポート・ギターの曽根(巧)さんやHISAYOさんのツイッターを拝見する限り、とりわけ準備が大変だったようですね。
佐々木:俺とナベちゃん(渡邊一丘/ds)はともかく、2人は全部で80曲を覚えなくちゃいけないわけですからね。曽根さんは3枚目のアルバム(『ZOOMANITY』)から、姐さんは4枚目のアルバム(『LOVE IS LIKE A ROCK 'N' ROLL』)からAFOCに関わったので、倍くらいは知らない曲があるんですよ。だからホントに苦労をかけましたよね。
──そんなAFOCですが、「ロックンロールバンド」の歌詞にも出てくる新宿ロフトというライブハウスに対してどんなイメージがありますか。全都道府県のライブハウスを駆け抜けてきたからこそ見えたロフトの特性もあるんじゃないかと思うんですが。
佐々木:ロフトはもともと憧れのライブハウスでしたね。大好きだったスピッツがロフトのインディーズ・レーベルからアルバムを出したこともあったし。だから最初は「どうすれば出られるんですか?」って普通にロフトに電話をしたんですよ。そしたらデモテープを持ってきてと言われて、現店長の大塚(智昭)さんのところへ持っていったんです。その後、大塚さんから「新人のイベントがあるんだけど、出る?」と連絡が来たのが凄く嬉しくて。それで2006年の夏に初めてロフトに出たんですよ(2006年8月29日、『歌舞伎町市松物語 其の十四』)。47都道府県を回って思ったのは、ロフトってけっこう変わったハコなんだなって(笑)。550人っていう独特のキャパシティだし、雰囲気も独特ですよね。あと、どの街へ行っても「ロフトの所属バンドです」って挨拶をすると、良くも悪くも身構えた反応をされるんです(笑)。そのたびにロフトってやっぱり凄いハコなんだなと思うし、今回の“LOFT FES.”の面子を見てもロフトならではで凄いと思うし。
「まだ砂利道を歩いてねぇな」と言われたことへのリベンジ
──SAのTAISEIさんは「決してやりやすいハコじゃないけど、お客の圧がやっぱり凄い」と話していましたが、その辺はどうですか。
佐々木:俺はロフトでやるライブが凄く好きですね。見せ方をいろいろと考えられるし、横にあるスピーカーに「乗るな」って紙が珍しく貼ってないのもロックのハコっぽいし(笑)。あと、バーステージも多目的なスペースでいいですよね。
──僕はAFOCのデモテープを当時のシェルターの店長からもらったり、『What's Going On』という自主企画もやっていたから、初期のAFOCと言えばシェルターのイメージが強いんですけど、ロフトにはかなり早い段階から出演していたんですね。
佐々木:ロフトの所属になってからはよく出させてもらうようになりましたね。イベント終演後のバーステージで、告知もせず見ず知らずの数人のお客さんの前でライブしたり(笑)。(過去のライブ・スケジュールを見ながら)…あれ? LUNKHEADの企画(2007年5月2日、『SRD×LUNKHEAD presents CIRCUS』)にはマスザワ(ヒロユキ)さんも個人で出てたんですね。この人が今や俺たちのレーベルのディレクターですから(笑)。これは深夜のアフター・パーティーみたいなライブで、石井(康崇)がインフルエンザになったので3人編成でやったんですよ。…そうそう、ONE OK ROCKともロフトでやったんだった(2007年7月12日、『ロフトノススメ 〜シンプルトリプル〜』)。懐かしいな。ROCK'N'ROLL GYPSIESとThe DUST'N' BONEZのオープニング・アクト(2007年9月3日、『LOFT presents ROCK'N ROLL ALWAYS』)もよく覚えてますよ。池畑(潤二)さんの貫禄が凄くて、思わず萎縮しましたからね。まぁ、それは今も変わりませんけど(笑)。
──とりわけ印象深いロフトのライブは?
佐々木:初めてのワンマン(2009年1月30日)ですね。メジャー・デビュー直前の頃で、凄くよく覚えています。景気づけにここで一発やっておこうって感じのライブで。この後の『BUFFALO SOUL』のツアーの最中に岡庭が失踪してしまったので、結果的にはオリジナル・メンバーの4人でやった最初で最後のワンマンだったんですよ。こうして見ると、対バンの面子も含めて感慨深いものがありますね。この間の“レトロスペクティヴ”に石井が見に来てくれたりもしたし、いろいろと思い出すタイミングなのかな。AFOCを8年間がむしゃらに続けてきて、過去を振り返る余裕なんてありませんでしたからね。
──ロフトで言えば、HISAYOさんと初めて一緒にステージに立ったクリスマス・イブのライブ(2010年)も忘れ難いですね。何とも言えない張り詰めた空気があって。
佐々木:あれは確かに凄かったですね。RUDE GALLERYのイベントで、石井が抜けたフィーバーのイベントからわずか10日後に新編成でやるっていう。お客さんも姐さんがどんな人なんだろう? という見方だったと思うし、俺たちも新しいAFOCをどう見せるかという緊張感が半端じゃなかったんです。内容よりも気合いとか気持ちの部分で忘れられないライブだったと言うか。そう考えると、ロフトでは節目節目で大事なライブをやっていますよね。
──AFOCは“LOFT FES.”が開催されるクラブチッタのイメージはあまりないですよね。
佐々木:今度のチッタはリベンジの場でもあるんですよ。と言うのも、シェルターのイベント(2007年10月19日、『SOUND ON SOUND 〜SHELTER TOURS 2007〜』)でチッタに出た時、俺たちのライブを見たある共演者から「まだ砂利道を歩いてねぇな」って言われたんです。それが凄く悔しかったし、あれから自分なりの砂利道を7年間歩いてきたつもりなので、“LOFT FES.”では是非リベンジしたい気持ちでいっぱいなんですよ。歌舞伎町へ移転して15周年を迎えたロフトをお祝いする気持ちももちろんあるんですけど、実はそういう裏テーマが個人的にはあるんです。