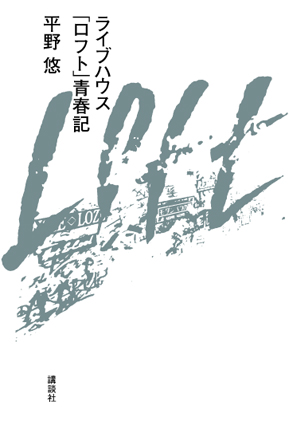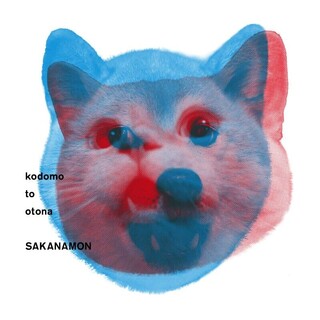「ロフトは常にトップを走っているんだ!」という自負
──そんな下北沢ロフトの成功にも飽きたらず、翌年には新宿ロフトをオープンさせるという快進撃ぶりで。
平野:ターミナル文化に対する自分なりの落とし前ですね。渋谷か新宿に進出したい気持ちがずっとありましたから。
──その新宿ロフトが後に「アマチュア・バンドの登竜門」「ロックの聖地」と呼ばれるようになると考えていましたか。
平野:聖地なのかはよく分からないけれど、天下を獲るつもりで店作りをしましたからね。新宿でキャパシティ300人のライブハウスなんて当時はなかったし、スピーカーもJBLの4550をアメリカから直輸入して音響設備は最高だった。ライブハウスでは天下ですよ。ロフトは常に日本のロック・シーンのトップを走り続けたい、その中心であり続けたいという思いが僕の中にはずっとあったんです。他のライブハウスに先を越されるのが凄く悔しくてね。
──もともとジャズが好きだった平野さんがそこまでロックに入れ上げたのはなぜなんでしょう?
平野:負けたら悔しいから(笑)。ロフトはいつだってトップを走っているんだという自負ですよ。日本のロックをロフトが牽引していた自負もあります。西荻窪では浅川マキや山下洋輔、友部正人といった面々に演奏の場を提供して、荻窪では細野晴臣やシュガー・ベイブ(山下達郎、大貫妙子が在籍)といったティン・パン・アレー系のシーンを確立して、下北沢では上田正樹や憂歌団といった関西のブルース系ミュージシャンの拠点になった。新宿はそれらの集大成になるような店にしたかったんですよ。
──下北沢ロフトと言えば、サザンオールスターズの毛ガニこと野沢秀行さんと大森隆志さん(2001年に脱退)がアルバイトをしていたことも有名ですね。閉店後に練習場所として店を使うことをサザンに許可していたと伺いましたが。
平野:まさかあれほどの国民的バンドになるとは思いませんでしたね。サザンの下北沢ロフトでのライブは本当にお客さんが入らなかったし。ロフトがサザンを育てたなんていう驕りは一切ありませんけど、ウチのハコがなければ今頃どうなっていたのかな? とは思いますね。サザンのメンバーは下北沢ロフトで毛ガニと知り合っているわけですから。そういうバンドは多いんですよ。BOφWYは(高橋)まことが彼らの初ライブを新宿ロフトで見たことが縁で加入オーディションを受けているし、パーソンズも新宿ロフトで知り合ったメンバーが意気投合して結成したんです。
──山下達郎さんが「ロフトの平野氏は、ミュージシャンのチャージ(料金)をピンハネせず、採算はあくまで飲食営業でまかなうという、画期的な発想の持ち主だった」というコメントを寄せていますが、ロフトのような営業を続けていたライブハウスは他になかったんですよね?
平野:あるわけないですよ。昼間は12時から5時までが音楽喫茶、5時から10時まではライブハウス、その後は午前4時までロック居酒屋、という3本柱で営業していたんですけど、それがどれだけ大変なことか。よほど根性の入った経営者じゃなければ、そんなことはまずやりません。でも、背に腹は代えられない。西荻窪や荻窪の頃はライブの動員なんて10人、20人がいいところだったし、それじゃ店の経営は成り立たない。当時はライブを週に3、4日くらいしかやらなかったし、ライブ・チャージは全額ミュージシャンに渡して、ウチはあくまで飲食営業を中心にするしかなかった。でも、実はそれがロフトが長続きした理由でもあるんです。今のライブハウスみたいに「お客さんが入らなかったらお金をもらいますよ」なんてシステムでやっていたら、誰も出てくれないでしょう。彼らはお金がないわけだし。まぁ、当時は僕もちゃっかりしていましたけどね。ライブが終わると、ミュージシャンが呑んでいるところに平気でお客さんを入れちゃったりして。「おーい、おいでよ!」ってね(笑)。だって、みんな好きなミュージシャンのそばに来たくて仕方ないんだから。
──本書の大半を占める新宿ロフトの章は、東京ロッカーズの出現やパンク、ハードコアの台頭、今なおロフト御三家と呼ばれるARB、アナーキー、ルースターズの活躍、そして新宿ロフトでライブ・デビューを飾ったBOφWYのことなど、興味深いエピソードが満載ですね。
平野:新宿ロフトと言えばパンクのイメージが大きい世代もいますけど、ロフトがパンクに舵を切ったのはやむを得ない事情もあるんです。つまり、ティン・パン・アレー系のミュージシャンが大御所になってロフトには一切出てくれなくなって、集客力のあるバンドがいなくなってしまった。日本初のパンクの祭典『Drive to 80's』だって、集客が見込めない夏休みの時期だから「好きなようにやりなよ」って地引雄一と清水寛に任せたのがきっかけなんです。まさかあんなにお客さんが入るとは思わなかったですよ。しかも、そのパンクが後に新宿ロフトのパブリック・イメージになるんだから面白い。
まだ誰もやっていないことをやるのが好き
──80年代に入って平野さんのロックへの興味とライブハウス経営への熱が奪われていったのは、やはりBOφWYのマネージメントの挫折が大きな要因だったんですか。
平野:サザン、竹内まりや、BOφWYは僕にとって苦い思い出なんです。あれだけ近い距離にいて、自分たちが手掛けていたにも関わらず、彼らの才能を見抜くことができなかった。BOφWYは見抜けていたはずなんだけど、当時のロフトにはお金がなくて、あれ以上の投資ができなかったんです。しかも、ビーイングがBOφWYから手を引いてしまった。その後も僕はBOφWYのために「レコードを出してくれませんか」と必死になってレコード会社を回ったんだけど、力及ばずだった。その辺のことはメンバーも知らないんじゃないかな。BOφWYだけは本当に悔しかったですね。そのBOφWYの失敗で、僕は日本のロックの在り方に対して絶望的になったんですよ。店は6軒あってそれなりに順調だったんだけど、なんだかもう疲れ切ってしまった。
──それで新宿ロフトだけを残して他の店舗は譲渡または閉店、平野さんは無期限の世界放浪の旅に出ると。
平野:皮肉なことに、僕が日本にいない間に空前のバンド・ブームが到来するんですよね。新宿ロフトは「ロックの聖地」という確たる地位を築くことになって。
──もしバンド・ブームの頃まで平野さんが日本にいたら、どんなことを仕掛けていたでしょうね。
平野:分からない。僕がいないで店を任せたほうが正解だったような気もするし。まぁ、それはまさに歴史の皮肉ですよ。僕は27歳から36歳になるまでに6店舗もの店を作り、レコードやフリーペーパーまで出していた。生き馬の目を抜く東京でそんなことを成し遂げた自信がとにかく大きかったんですね。だから、音楽の仕事に情けなく擦り寄る気がさらさらなくなってしまった。「全世界が俺を呼んでいる!」くらいの気持ちがその頃はあったし、これだけのことをやってきた人間なんだから、世界中のどこへ行ってもやっていけるはずだという揺るぎない自信があった。ロシアだろうがチェコスロバキアだろうが、そこで働いて生活をして骨を埋めちゃうのも面白いだろうと思ったんです。ロックのライブハウスを日本でやるよりも、そのほうが断然スリルがあるぞと思ったしね。僕はやっぱり、どうしてもスリルを求めてしまう性格なんですよ。安定とか発展とかにはまるっきり興味がなくて、今さえ面白ければそれでいい、みたいなところがある。100ヵ国を回ろうと世界中を旅していた時は、ロフトがどうなろうとまるで興味がなかったわけです。なぜなら、自分はこの先どうやったって食っていけると思ったから。新宿ロフト以外の店舗を売ったお金が4、5千万ありましたしね。その後、ドミニカ共和国で日本レストランと貿易会社を興して何千万も使い果たしたけど、別にどうってことはなかった。またどうとでも生きていける自信があったので。
──なぜドミニカ共和国で店を開こうと思ったんですか。
平野:日本食のレストランが建ち並ぶニューヨークやロスに店を出すなんて、格好悪いじゃないですか。日本から職人を招いて、ロスで寿司屋をやったって面白くも何ともない。上手く行けば儲かるかもしれないけど、ドミニカで商売をやるほうが断然面白く思えた。だからこそドミニカを選んだ。なぜならば、日本から遠いし、日本人も少ないから。つまり前例がない。ロフトだってそうですよ。前例がないライブハウス、それがロフトだった。ロフトプラスワンという世界初のトークライブハウスをオープンさせたのも同じことです。まだ誰もやっていないことをやるのが好きなんですよ。それが僕の美学なんですね。
──こうしてご自身の半生を1冊の本として書き上げて、率直なところどう感じていますか。
平野:何やかんや言って、自分の人生はロフトと共にあったということでしょうね。10年近いブランクはあったにせよ、こうして41年間ロフトと過ごしてきたわけだから。この本の中で書いたことはロフトにとってまさに青春だったし、日本のロックにとっても青春に当たる時代だった。だから『ライブハウス「ロフト」青春記』というタイトルにしたんです。それと、僕の人生においてお客さんとのコミュニケーションが凄く大事だったんだなと改めて思いました。僕はずっとお客さんに育てられてきたし、お客さんこそが先生だったわけです。出演者やお客さんとの信頼関係を築きながらライブハウスという心地好い空間を作り上げて、自分の人生を切り開いていった。その紆余曲折の様をこの本の中で余すところなく書き綴ったつもりです。
──今後の目標は?
平野:「ロフトプラスワン物語」に着手したいですね。資料も豊富にあるし、書きたいことがたくさんあるんですよ。今回みたいに記憶を辿るのに精一杯ということもないだろうし(笑)。
──平野さんの41年間にわたるロフト人生は一貫して空間作りにあったわけですが、また新たに店作りをしたいとは思いませんか。
平野:いい物件が見つかれば考えますけど、僕はもうすぐ68歳にならんとしているし、全面的に指揮を執って店作りをする体力もありませんからね(笑)。空間作りは確かに好きだけど、とにかく大変だし、もの凄く辛いんですよ。でも、そんな苦労が報われるだけの大きな歓びが確かにある。接客はやっぱり楽しいしね。僕は結局、お客さんと一緒になってワイワイ騒ぐのが好きなんだろうな(笑)。