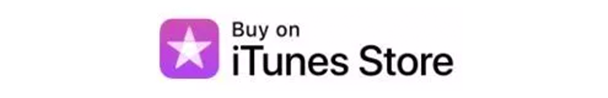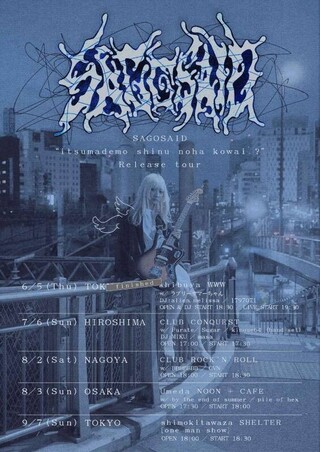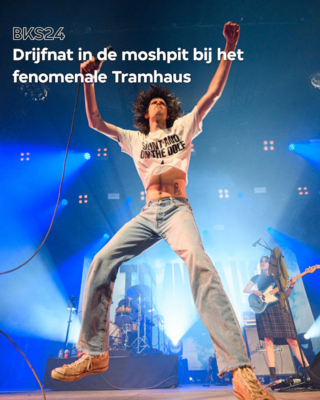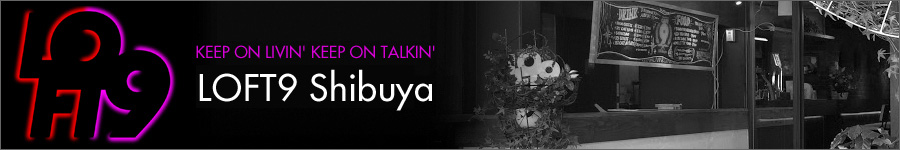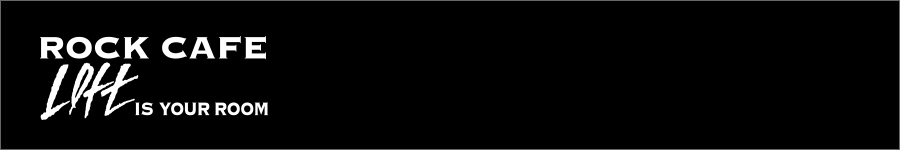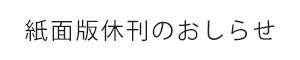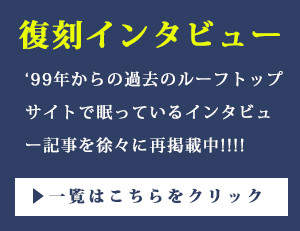いわゆるポスト・ロックの流れを汲む音楽性をその出自としながら、日本的な情緒を加味しつつも肉感を帯びた爆音を轟かせるインストゥルメンタル・バンド、te'〈テ〉がまさかのメジャー進出を果たした。パートナーシップを育むことになった徳間ジャパンコミュニケーションズから発表される通算4作目のオリジナル・アルバム「敢えて、理解を望み縺れ尽く音声や文字の枠外での『約束』を。」は、これまでになく微に入り細に入り緻密な音作りを志向しながらも、内なるパトスのままに奔流する激情のアンサンブルは不変。今や9mm Parabellum BulletやPeople In The Box、mudy on the 昨晩といった名だたる気鋭バンドが所属する残響レコードの初号バンドである彼らが新境地に達したことを鮮烈に印象付ける傑作だ。ポスト・ロック特有の難解なイメージや暗示的なアルバム・タイトルに惑わされてはいけない。この作品で打ち鳴らされている音楽は、ロックが本来持ち得たダイナミズムとスリリングな躍動感、徹頭徹尾エモーショナルなリズムとビートなのである。日本のロック史に残るであろうこの新たなマスターピースの発表を祝して、本誌ではメンバー4人のソロ・インタビューを奪取した。本稿がte'の音楽性を読み解くサブテキストの役目を果たせたら嬉しい。(interview:椎名宗之)

kono
part of guitar
te'の旗頭、残響レコード代表としての透徹した視座
"敢えて"メジャーと手を組んでリリースをする意義
──今回、敢えてメジャーと手を組んでリリースをするのはどんな意図があったんですか。
k:今まで3枚のアルバムを残響から出して、前作が内容的にも自分たち的にも集大成みたいに感じたんですよ。サードを作り終えた時に「ちょうどここで一区切りだね」という話にもなったし。それで次に何をやるかを考えた時に、もう一ランク上の作品を作っていきたい気持ちがメンバーの中ではあって、それにはまず従来やってきたような音楽的なアプローチは捨てようと。これまで目指してきたのはライヴ感のある音作りで、ライヴそのものをパッケージすることに意識を向けてきたんです。でも、今回はもうちょっと作品寄りと言うか、アーティスティックな側面を見せたアルバムを作ったほうが伝わりやすいんじゃないかなと。ライヴ感は残しつつも、ギターやドラムのダビングをやってみたり、今までやってこなかったことに取り組んでみたんですよ。今まではシンプルに一発録りで、アナログ・テープを回していく感じだったんですけど、今回はパーツの一個一個を細かく話し合いながら作り込んでいったんです。一度出来たアレンジを全部崩し直したりもしたし。あと、タイミングも良かったんですよね。動きとしても何か新しい展開ができないかなと思ってた頃に徳間ジャパンから「ウチと手を組みませんか?」と話を頂いて。残響だけで出すのでも全然良かったんですけど、残響のスタッフでやれることは動きも含めてサードでやり切った感じがあったんです。だから、ここでメジャーと組むのはいい機会だなと。今までもそういう話は頂いてきたんですけど、敢えて突っぱねてきたんですよ。でも、今回はちょうど新しいことをやりたい時期に話を頂いたので、チャレンジしてみようと思って。
──新たなアプローチを試みると言いつつも、長文のタイトルとジャケットの体裁だけは変わらずですね(笑)。
k:僕らの音楽に対するスタンスは変えないぞという意思表示ですよね。勝負するフィールドがちょっと広がったというだけで。
──アルバム全体でも然り、1曲の中でも然り、静と動の対比が緻密に作り込まれた作品になりましたね。
k:結構練り上げましたね。今の音楽を好きな若いリスナーが好きそうなアレンジやサウンド、展開も意識して作ったんです。尚かつ、これまでの自分たちにはなかった新しい引き出しも開けてみました。
──たとえば、最後に収録されている曲『参弐零参〜』の緩急が付いた構成たるや凄まじいアイディアの坩堝じゃないですか。そんな楽曲が12曲も揃っているのだから、これほど情報量が過密なアルバムもそうはないですよね。
k:僕が聴いてる音楽の引き出しから「こういうアプローチはどう?」と提案して、みんなの思うところをまとめていく感じですね。設計図が何となくあって、みんなでセッションして作っていくうちに全体像が見えてくると言うか。作曲は感覚的な感じで進行していくんですけど、僕自身は楽曲サンプルを提示して具体的な伝え方をします。
歌がないぶんだけ好きなことができる
──迸るパッションを音塊としてぶつけつつも、静寂にも似た甘美で穏やかなメロディが交錯する『天涯万里、〜』がte'の音楽性を最も端的に表していると思うのですが、音の質感も含めて楽曲のクオリティは過去随一じゃないですか?
k:4枚目ともなると、お互いのキャラクターや役割を充分理解しているからやり取りもスムーズなんですよね。ギターで言えば、hiroに「メロはお前に任せる!」と半ば強引に言ってみたり(笑)。僕の中ではhiroのギターがヴォーカルの立ち位置なんですよ。僕がバッキングに徹することで彼がフレーズを弾きやすくして、そのぶん暴れ回るパフォーマンスをする。そういう役割を4人ごとに忠実に決めて作ったのが『天涯万里、〜』なんです。だからte'のレパートリーにしては判りやすい曲になったと思うし、弾いてる人間の顔が見えやすい曲じゃないですかね。
──他にも、konoさんとhiroさんのギターだけで奏でられる『瞼の裏に〜』や女性のハミングが入った『自由と孤立と己とに〜』など、新機軸の楽曲も多いですよね。
k:インスト・バンドっていろんな先入観を持たれるんですけど、僕らが今回のアルバムで言いたかったのは「凄く自由なバンドなんだぜ」ってことなんです。歌がないぶんだけ好きなことが存分にできるんだよ、っていう。
──『秤を伴わない剣〜』なんかを聴くと鉄壁のリズム隊の手腕に改めて舌を巻いてしまいますが、彼らの存在があってこそ上物はより好きなことが存分にできるのでは?
k:僕ら2人に限らず、基本的にみんな自由ですよ。リズム隊も自分たちをリズム隊と思ってないと言うか、むしろフロントマンだという意識が強いですからね。masaはもともと自己主張の少ない男だったんですけど、さっきも言ったように今までやらなかったことをやろうということで、その一環としてベースがもっと主張していこうというのがあったんです。それもあって、今回はリズム隊がガンガン前へ出てきてるんですよ。
──konoさんが強引な振りをしても、それに応えるスキルとセンスが各自にないと形にはならないじゃないですか。本作を聴くと、尋常ならざる演奏力にとにかく圧倒されますね。
k:いや、上手く聴こえるだけだと思いますよ。確かに息はぴったり合ってますけどね。バンドって、要所要所で演奏が合えば凄く上手く聴こえるんです。僕らの演奏を細かく聴けば結構ズレてると思うんですけど、キメや頭がバスッと合う瞬間が多ければそれなりに聴こえるんですよ。
──でも、『闇に残る〜』のようにスロー・テンポでじっくり聴かせる曲はごまかしが利きませんよね。
k:難しいですね。今まではワン・テイクかツー・テイクしかやらないのがルールだったんですけど、今回はいいテイクが録れるまでひたすら弾いたんですよ。レコーディングの期間を多めに取ったわけでもないんですけど、今回は録り方を研究したのが大きいですね。たとえば、Protoolsの特性を活かしてアホなことをやってみたりとか。
──それはどの収録曲に活かされたんですか。
k:1曲目の『決断は無限の扉を〜』ですね。曲作りの時点からProtoolsを使って音の素材を組み合わせたんです。それを変拍子にして、違う録り方をして、全部が完成した上でドラムを別録りしたんですよ。"Protoolsってそういうふうに使うもんじゃないよね?"ってことにチャレンジしてみたと言うか(笑)。この曲を同じようにレコーディングして再現してみようとすると、エンジニアは相当悩むと思いますよ。
──なるほど。てっきり剥き出しの生演奏だと思っていました。
k:だと思いますけど、僕らからすればデジタルそのものでしかないんです。デジタルを如何に上手く使ってレコーディングするかがひとつのテーマでしたからね。
音に滲み出たプレイヤーの生き様
──デジタルの無機質さと人力の熱量が極めて理想的なバランスで配合されているわけですね。
k:人間らしさは絶対に残したいんですよ。ライヴ感を出したいのはそういうことだし、CDって人が弾いてる感じがしないことが多いじゃないですか。僕らは人がちゃんと演奏してる感じを大事にしてきたし、今回はそれにデジタルの要素を加えてみたんです。3曲目の『秤を伴わない剣〜』のイントロは、hiroの携帯電話の着信音なんですよ。それをギターのピックアップに当てて拾ってるんです。そういうのがちょっと今時かな? と思って(笑)。やっぱりインスト・バンドでしかやれないことをやりたいし、歌があるとどうしても歌を立てなきゃいけないパートが出てくるんですよね。僕らはそういう縛りがないし、一辺倒にならないように面白く作りたいんです。
──決して技巧だけに走ることなく、演者の肉体性とロックのダイナミズムが音の端々に脈打っているのがte'の大きな特徴のひとつだし、そこが凡百のインスト・バンドと違う部分だと思うんですよね。
k:音楽には血が通った感じが絶対にあるべきだと思ってるんですよ。プレイヤーの生き様が音に滲み出てるのが好きなんですね。
──インスト・バンドをやろうという発想はバンド人生の初期の頃からあったんですか。
k:いや、全然なかったです。ただ、2000年くらいからUSインディーのマニアックなインスト・バンドに衝撃を受けて、楽器だけでできる表現というのも面白いんじゃないかとte'をやる前のバンドの頃から思ってたんですよね。前のバンドが終わってまず思ったのは、デス・キャブ・フォー・キューティーみたいな歌の映えるバンドがやりたいなと。でも、いいヴォーカリストがなかなか見つからなくて、インストだけでやってみたら意外と反応が良かったので、そのまま今日に至る感じなんですよ。
──上手く唄えないようであれば、シューゲイザー系のバンドのように浮遊感のある唄い方にする選択肢はなかったんですか。
k:te'の前にやってたのがシューゲイザー系のバンドで、その辺はやり尽くした感があったんですよね。今度は楽器だけでどこまでやれるか挑戦してみたかったんです。まぁ、最初は困りましたけどね。ヴォーカルがいれば歌の最中は休めるけれど、インストの場合は全員休む暇がないんですよ。だから、力を出すところと抜くところのメリハリが全然判らなかったんです。でも、そのうちインストの面白さに惹かれて、この表現方法を使えば何でもできるんじゃないかと思って。
──曲作りは難産ではないほうですか。
k:曲に困ることは少ないですね。te'の場合、曲作りの前にレコーディングの日程を決めるのがまず最初なんです。「来月の5日までに3曲録るから」ってことになれば、きっちり3曲を仕上げるんですよ。te'の曲作りは無限大だなと思うんですよね。仮に「ラジカセをイメージした曲を作って下さい」と言われても、すぐにできますよ。ラジオのザーッとしたノイズを組み込んでみようとか、いろいろとイメージが湧きますからね。自分の中で湧き起こるイメージを楽器でどれだけ表現するかがテーマで、僕の場合はそれがたまたまギターだったということですね。メンバー各自がそんな感じなんです。
──ライヴでの破天荒なパフォーマンスもte'の大きな魅力ですけど、それぞれ自由な立ち居振る舞いなのに不思議と統一感があるのが面白いですよね。
k:前の3人はホントに自由ですね(笑)。基本的に放任主義なんですよ。みんなやりたいことをやればいいし、それで上手く回ってる時はそれでいい。もちろん、良くない方向へ行きそうな時はしっかり反省会をしますけど。他の3人は暴れすぎて訳が判らなくなることがあって、そんな時に僕の音を聴いて戻ってくるんです。だから僕は後ろで地味に弾いて、ガイド役に徹しているんですよ。僕までちゃんと弾かなくなったらオシマイなので、努めて冷静を保ってますね。僕もテンションが上がって前のほうへ出て行ったことがあるんですけど、あまり評判が良くなかったんですよ(笑)。まぁ、各々に役割があるってことですね。