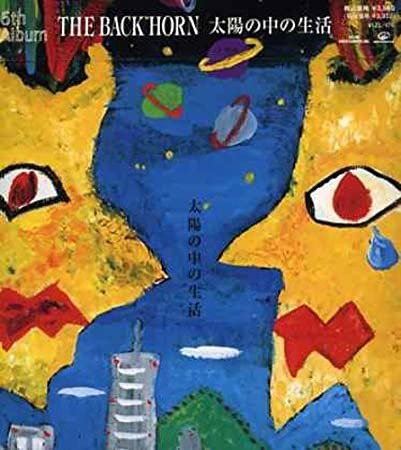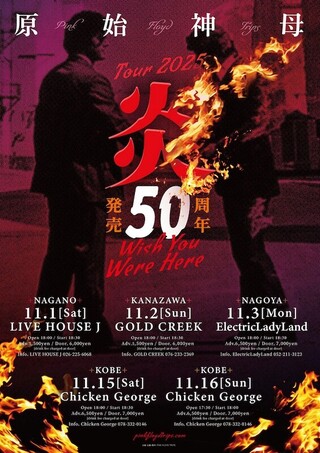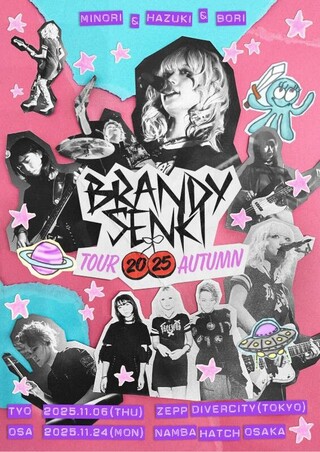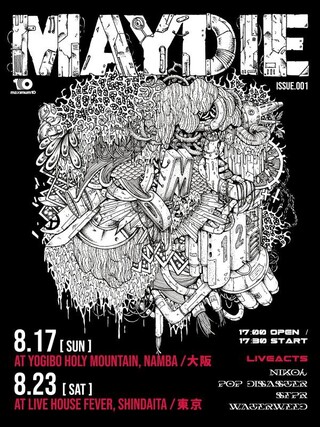奏でる瞬間こそが音楽なんだ

──割とゆるい感じで(笑)。で、どうでした? 初のニューヨーク・レコーディングは。
菅波:確実に違うのは、言葉ですよね。
松田:曖昧さが伝わらないんですよ。
菅波:音楽って曖昧なことばかりなのに、そこを言葉で説明できないっていうのは大変ですよね。でも、そこで浮き彫りになってくるものもあったりして。
──と、言うと?
菅波:簡単に言うと、“俺らの音は果たして、音として強いのか?”ってこと。“歌詞を読めば判るだろう”とか“あとで言葉で説明すればいい”っていうのが通用しないから、全部音に込めなくちゃいけない。そういう意識は日本に帰ってきてからも残ってますね。奏でる瞬間こそが音楽だっていう…。そういう努力はすべきだと思います。
岡峰:あっちでレコーディングした後、スペインと台湾でライヴをやったんですよ。日本語も判んないし、バックホーンがどんなバンドかってことも判らないところでライヴをやるっていう体験も、かなり大きいですね。言葉が判らなくても、ちゃんとリアクションは返ってくるんですよ。ハンパなことをやってるとお喋りが始まっちゃうし(笑)、いい演奏をすればウワーッて盛り上がるし。
山田:言葉が伝わらないのは判ってるけど、でも、何かを伝えたいし、エネルギーの交換をしたいから。(ニューヨークで録った)「ブラックホールバースデイ」をライヴで最初にやったのがスペインだったんですけど、明らかに反応が良かったですね。
松田:向こうでレコーディングしたことによって、日本の良さっていうのも明確になりましたね。曖昧なことに価値を見出す、っていうか、“YESかNOか”だけじゃない良さっていうのもあるじゃないですか? それは日本の美しさでもあるんだなって。それって外国の人にはなかなか判らないんですよね。
菅波:まぁ、感じるヤツは感じるだろうけどな。俺が感じたのは、向こうの人ってビートに対して敏感で、肉体的に音楽を理解してるってことですね。それって、俺らは忘れがちだと思うんですよ。バンドをやってる人は判ると思うけど、普通に暮らしてる中で、音楽の“ノリ”っていうことを理解するのって難しいじゃないですか? それは凄く勉強になりましたね。
──メンバー全員が歌詞を書いてる、っていうのも初めてですよね?
松田:うん、そうですね。
菅波:これからずっと、そういうふうにしたいですけどね。バンドだし。4人でひとつのバンドだから。
山田:共通認識があるんだったら、誰が書いてもいいかなって。全員が書くことによって、(歌詞の)幅も広がるだろうし。
──「浮世の波」は岡峰さんの歌詞。どうでした、作詞は?
菅波:大変だった?
岡峰:どうですか? って訊かれたら……難しいですよね、やっぱり。一生懸命、考えながら書きました。
菅波:でも、「浮世の波」っていう言葉は、フトした瞬間に出てきたらしいですよ。光舟の部屋のベランダには椅子が置けるようなスペースがあるんだけど、そこに居る時に思いついたらしくて。
岡峰:夜風に当たろうと思ってベランダに出たら、たくさん明かりが見えたんですよ。世間の浮き沈みとか、自分のバイオリズムとかいろいろあるけど、そんなことに関係なく、風は吹いてて…。そんなことを考えたら、“浮世の波”っていう言葉が自然と出てきて。
──「ゆりかご」は山田さんの歌詞ですが、どんなシチュエーションで書いてたんですか?
山田:メロディと一緒に出てきた感じですね。やっぱり難しいですけどね、歌詞は。なんていうか、ポロっと出てきた言葉は信用できないってところがあるんですよ。そこまで自分を信じてないっていうか、ちゃんと考えてない時に書いた言葉を歌詞にしていいの? っていう気持ちがあるので。まぁ、これからもっともっといっぱい書いて、いろいろと身につけていければいいなって思いますけどね。
──「ゆりかご」は、凄くアルバム全体のテーマに沿ってますよね。なんだかんだ言って、自分の人生を生きるしかないんだよな、っていう。
山田:そうですね。もちろん、自分に自信が持てない時もありますけど…。さっき“鉄柵みたいなバンド”って話が出てたけど、自分自身にも言えることだと思うんですよ、それって。自分を守ろうとしてガチガチのプロテクターをつけていても何も始まらないし、自分もでかくなれないし。それを捨てて、やっと何かが始まっていくんだろうなって思いますね。
菅波:そう、自分で自分の中を探しても、意外と何も見つからないんだよね。それよりも、周りにいる人のほうが自分の良さを判ってることもあるし。プロテクターを外すのは、自分のためにもいいことだと思うよ。