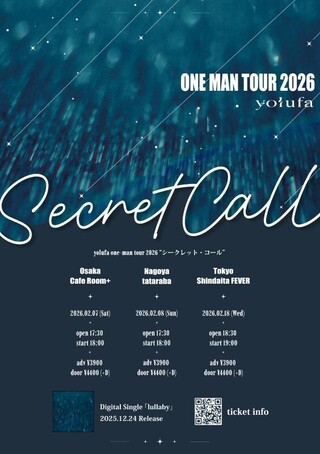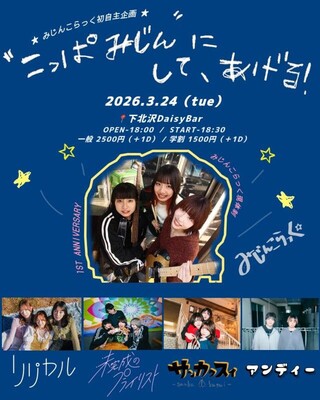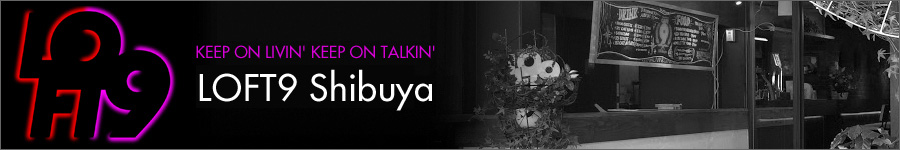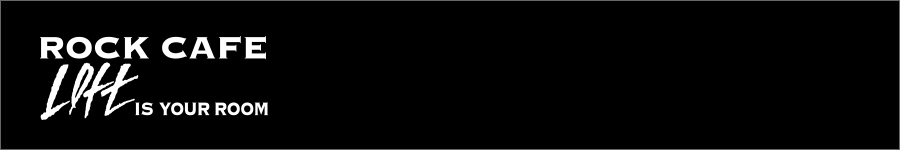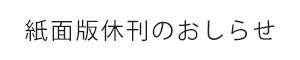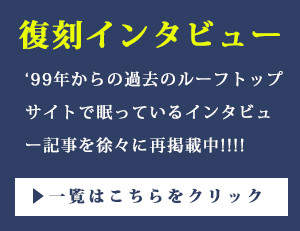絶対に諦めるわけにはいかなかった
――コロナ禍に動き出すのは難しくありませんでしたか。
山本:映画制作の話しをするとみな「コロナが終わってからにしませんか」という消極的な答えばかりでした。それだといつできるんだと思っていたなか、「山本さんが宮城で映画創るらしいよ。」と俳優たちが集まってきてくれたんです。
――それが「UNCHAIN10+1(アンチェインイレブン)」になるんですね。
山本:最終的に「UNCHAIN10+1」は22人になり、それ以上増えてもということでストップをかけました。
――多くの賛同者がいらっしゃったんですね。
山本:彼らの本業は俳優ですが「僕が届けたいということがあるのであれば、手伝いたい。」と言ってくれ、お金集め、みんなとロケ場所探し、オーディションの仕込みと本作を支えてくれました。
――本作について話し合われたことはあったのですか。
山本:22人のチームとは毎日のように集まって、話しをしていきました。制作母体も何もなかったので、そうしないと前に進めなかったんです。
――そういう環境の中で進むということに怖さはありませんでしたか。
山本:僕は道なき道を突っ走るタイプなので怖さはなかったです、絶対に何とかなると信じていました。本作には宮城の子供たちも参加してくれていますが、出演が決まった子たちが泣いて抱き合って喜んでいる姿を見ていたので、この子たちのためにも集まってくれたみんなのためにも絶対に諦めるわけにはいかなかったんです。
――制作開始を振り返って如何ですか。
山本:制作開始から3年になりますが、僕がスタートライン立った時よりも事態が悪化している感覚があります。日本人の自殺率も急上昇しているという報道もあります。
――日本は自殺率も上がっていると言われていますね。
山本:それでも減少傾向にあったのが、コロナを機に上がっているんです。ほかにも不登校児の数も過去最多の数が出ていて、子供たちが未来に対して希望を持ちにくい状況になっています。だからこそ、この映画をやらなければいけないとより強く思いました。
――何もできない状況になり、よくも悪くも自分と向き合う時間が出来すぎてしまいましたね。そういった中で誰にも相談できないことで負の感情に引っ張られてしまう人が増えているということですね。
山本:だからこそカルチャーの力が必要だと感じています。みんなが下を向いたままじゃダメなんだと言いたいです。表現者たちが亡くなることが、どれだけ世の中を暗くしているかに気付かないといけない、この映画はカルチャーの力を信じて立ち上がるぞという企画なんです。
この輪をさらに広げていきたい
山本:「災害を生きる」という言葉がありますが、災害と災害の間をどう生きるかというのが大事なことなんです。このコロナ禍も災害の一種だと思っています。コロナによって子供たちは学校に通えない時期もありました、体育館を使用禁止にされることもあったそうです。友達とおしゃべりも出来ない、マスクで顔も分からない中で何をしに学校に行くんだと思いました。
――学校は勉強するだけではない、人間関係を経験する場でもありますからね。
山本:こんな青春時代を過ごさなければいけない子たちが社会に出たときに何が起きるのかが心配でしょうありません。いま宮城県は不登校率が高いんです。子供たちが生まれたばかりのころに震災が起き、親が亡くなったり家が無くなったという人たちがたくさんいて、愛情が不足しているからだと思います。生きる力が足りなくなっているんです。
――災害にはそういったメンタル面での影響もあるんですね。
山本:アフターコロナとなったときに、みんながもう一度有り触れたコミュニケーションをとることが出来るのかを問いたいんです。この考えに多くの方から賛同をいただけ、この輪を広げたいと世界中からこの映画に対してのご支援をいただきました。公開をキッカケとしてこの輪をさらに広げていきたいと考えています。
――その想いが「前進あるのみ」というセリフにも繋がっているんですね。
山本:いろんな考え方がありますが「前進あるのみ」という言葉だけでは、人によっては苦しいだけになってしまいます。なので、群像劇として描いて、いろんな言葉をいろんな角度で話しています。
――私が作品から感じた以上のエネルギーが集まっているんだなとビックリしましています。
山本:表現者としてはお客さんにどう届くかがゴールです。この映画を観て泣いて、拍手をもらい、彼らと作ってよかったなということを感じていきたいと思っています。本作を観てくれるみんなに「ありがとうございました。」と言いたいです。東京での舞台挨拶もなるべくみんなで行って、肌感でお客さんに届いていることを感じさせることで彼らが俳優としてこの先生きていく大きな糧になると信じています。
©UNCHAIN10+1