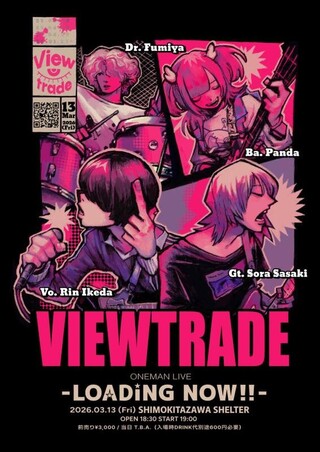ここ数年世界的にブームとなったシティ・ポップ。今や単なる昭和ノスタルジーではなく、ひとつの新しい音楽カテゴリーとしてマニアックな音楽ファンのみならず多くのユーザーを巻き込むムーブメントとなった感があるが、個人的にはそんな良質なシティ・ポップのエッセンスを目一杯詰め込んだアルバム『swing in the dark』を2022年1月にリリースしたGOOD BYE APRILの進化ぶりには正直驚かされた。もともと楽曲志向の歌ものバンド的なスタンスが強い印象はあったものの、自らのルーツでもあるニューミュージックやシティ・ポップのエッセンスと対峙しながら独自の世界観を軽やかに構築し、いつのまにやら貫通力のある楽曲を作り上げるバンドに成長していたのだ。コロナ禍を経て、この年末の12月26日には新宿ロフトとの共催となる年末大感謝祭2022をオーガナイズする彼らに気になるサブタイトル、「beyond the city pop」に込めた思いも含めてイベントへの意気込みと来年への展望を語ってもらった。(interview:鈴木ダイスケ)
ライブハウスシーンでずっと浮き続けてきた
──まず今年はニューアルバムが発売されたことがバンドにとってはけっこう大きな出来事だったかなと思うんですが。
倉品:そうですね。今年の1月に発売されたんですけど、今のシティ・ポップムーブメントの波に上手く乗れたのが良かったかなと思ってて。
延本:ほんとそうですよね。バンドの出来事的にはそれが一番大事なところだったんで。
倉品:既存のシーンにうまく属せたことが大きかったかなと。ライブハウスシーンで僕ら、今までずーっと浮き続けてきたんで、初めてなんじゃないですかね? そういう時代の流れと自分たちがやりたかったことがリンクしたのは。
延本:はい。ほんとにそうで。バンドとしてもマーケットと、ようやくクロスした感じじゃないですかね。
倉品:もともとはシティ・ポップやニューミュージックって呼ばれる音楽は親の影響で好きだったんですよ。だから自分の中ではちゃんと整合性も取れているので今の状況はウェルカムなんですよ。
延本:ですよねえ。結成当時は四つ打ち全盛期だったじゃないですか。
──2010年代初頭ですね。当時のバンドシーンは非常によく覚えてますよ!
延本:私たち、当時の音楽シーンではなかなかハマれなかったんですよねえ。そもそもすでにメジャーデビューしてるって思われがちな傾向もありまして。長くやってるからですかね?(笑)
倉品:全然違うんですけどね。そういうチャンスがなかったわけじゃないんですけど、シーンから浮き続けてようやく現在地にいるってのが実情なので。あはは(笑)。
延本:もうほんとに(笑)。「いくぞー!」みたいな煽りがほんと苦手だったんで。
──わかりますよ。当時、GOOD BYE APRILってバンドは知ってましたけど、見事に浮いてたもんね(笑)。いい曲やってんのになあって思いながらライブ観た記憶があります。
延本:そうなんですよ! それこそブレイク前の髭男とか、歌ものバンドとはよく共演してたんですけどね。でもああいう王道のJ-POP志向の方々とやっても浮いてたんですよ。私たちの曲っていい意味でエヴァーグリーン、ただ聴くひとによってはニューミュージックとか歌謡っぽい雰囲気が強くて最先端のJ-POP志向の方々と並べるとどっか違う空気感になってしまって。
──うーん。そうだよね。
延本:なのでライブハウスシーンからも浮いてしまい(笑)。
──それ、非常にわかりやすい展開ですよ!
延本:だから自分たちの音楽を好きなお客さんを探しに一時期はショッピングモールとか行ってたんですよ。アコーステックセットで営業的なノリでライブをやったりするのが主戦力になってたり。そこで出会えた人たちもたくさんいるのでよかった部分もありますが、シーンに属せないことでいろいろデメリットもあったという。難しいことが多かったんですよね。
──あのね、個人的にはGOOD BYE APRILを知ったのは2011年とか2012年でして。知ってはいたんです。
倉品:そうなんですね。最初の全国流通盤がちょうど2012年とかでした。
──知ってはいたんですけど、その頃の音楽性と年頭に発売されたアルバムとの内容の差にとても驚きまして(笑)。いつの間にこんなことになったんだと(笑)
倉品:あはははは(笑)。ですよね。その頃(2010年代)は普通にギターロックバンド然としてたというか。
──そうだよね。だけど染まりきってはなかったですよね。ボクにはそこが妙に印象深くて。
倉品:それはたしかに。
延本:私たち、押しが足りなかったんですよ。お客さんを引っ張っていくカリスマ性ってあるじゃないですか? あれができなかったんですよねえ。「みんなついてこいよ!」的な煽りというか。
──できなかったっていうか、嫌だったんでしょ?
延本:まあ、はい(笑)。
倉品:キャラじゃないんですよ。
延本:そう。DNAに入ってないんです(笑)。
──無理するとろくなことにならないからいいと思いますよ!
倉品:や、ほんとそうなんですよ。10代の頃は世代的にもロックバンドを聴いて育ってるんで憧れはあったんです。
延本:でもなりきれないねって。どうやってもできなかった(笑)。
──それでだんだん今の音楽性に寄せてきた感じだよね?
倉品:だんだんライブハウス対応の音楽スタイルにも合わせづらくなってきて。2016年に出した『ニューフォークロア』ってアルバムがあるんですけど、そこで方向転換というか。ほんとに自分たちが小さい頃聴いてきたニューミュージック的なことをやろうと。で、歌に特化して作品を作り出したのがそのへんからなんで。そこで一旦変化はしたものの。