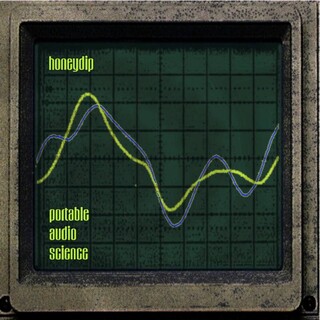自分たちなりのスタンダード・ミュージックを作っていくための答え
──ロフトとしても大事にしているイベントですもんね。コロナ禍の中で止まることなくライブを続けてこれたっていうお客さんやバンドに対しての感謝もあるでしょうし。
倉品:そこに抜擢されたのは僕らとしてもほんとに嬉しいですね。僕らもコロナで世の中が止まっていた頃は手作りで配信ライブをやって凌いでたんですけども。ちょうど去年の11月にwwwでワンマンをやって、そのあたりからライブ再開ってムードになってきて。で、今年はとにかく最初からライブをたくさんやろうって決めてた年だったんですよ。
──あ、そうだったんだ。
倉品:はい。僕らもライブに自信が持てるようになってて。「今、僕らのライブはいい感じで観てもらえるかも」ってバンド内でのテンションもいい具合だったし。アルバムも出たし、今年はあちこちでライブやっていこうって話をしてたときにロフトの樋口さんから連絡もらったので。で、今ってシティ・ポップ的なアプローチをしているバンドって増えてるじゃないですか。
──そうだよね。世界的なブームにも押されてるんだろうけど。
倉品:ロフトのブッキングでご一緒することで知り合いになったバンドも多いんですけど、シティ・ポップなカテゴリーの中でもちょっとづつルーツ・ミュージックも違ってたりするからそこも面白くて。そういう刺激も受けつつ、イベントのサブタイトルに「beyond the city pop」ってモロな言葉を書かせていただきましたけど(笑)、やっぱり一過性のブームにしたくない思いもありますしね。そのためにはシティ・ポップの向こう側に僕らも行かなきゃいけないなって思ってるし。それが自分たちなりのスタンダード・ミュージックを作っていくための答えな気がするんですよ。僕らもたまたまサウンドのアプローチを変えていく中でシティ・ポップというジャンルに片足を突っ込んだって形になっているだけで、僕らの軸のすべてがシティ・ポップって思ってるわけじゃないんですよ。自分たちにしか作れない音楽を追求していった過程の中で、たまたま「シティ・ポップ」ってフレイヴァーを味わえますよってスタンスなので。
延本:ちょっとふりかけがかかってますよって(笑)。
──GOOD BYE APRILはいわゆるダンス・ミュージックを基盤とするシティ・ポップじゃないもんね。
倉品:そうなんですよ。僕らは繰り返すようだけどいいメロディがあって歌詞があってっていう。こだわっていきたい本質的な部分ってまずそこなんですよ。それがあって林哲司さんやチューリップの財津和夫さんに多大な影響を受けた結果、今のような音楽性に辿り着いただけなんですよ。
──チューリップだとやっぱり財津和夫さんなんですか? 宮城伸一郎ではなく。
倉品:財津さんですね。でも宮城さんの曲も好きですよ(笑)。
延本:「エジプトの風」とかね。ライブで聴いたら嬉しい名曲。
──1984年にリリースされた『I dream』の1曲目だね。ちなみにチューリップだと時期的にはどのへんが好きですか?
倉品:あー(笑)、個人的には2期ですかね。
延本:2期ってどのへんなのかな?
倉品:ドラマーの上田(雅利)さんが抜けた時期じゃないかな。
──ドラマーが伊藤薫さんに変わった時期ですね。それこそ宮城伸一郎さんがベーシストとして加入した時期。80年代頭じゃないですか。
倉品:ソングライターとしての財津さんの濃いところってそれこそ70年代のチューリップに集約されてると思うんですけど、メンバーが変わってサウンドも時代的な流れもあって変わっていったじゃないですか。僕はそのバランス感に惹かれてるところもあるんですよね。その後3期を経て解散しちゃいましたけど、90年代に入って再結成されて。97年の武道館ライブは小さな頃からVHSでずーっと見てましたから。
延本:松田聖子さんとかアルバム聴いてて「いい曲だな」って思ったら財津さんの曲だったってことが多いですね。あと私は宇崎竜童さんと阿木燿子さんのコンビ曲はすごいなあって。作詞家で一番憧れてるのは阿木さんかもしれない。
──めっちゃ昭和じゃないですか(笑)。
延本:ノスタルジックな意味とは違うんですけど、楽曲の力がめちゃくちゃ強いじゃないですか。
倉品:そう。リスナーへの届き方がすごいと思うんですよね。言葉の選び方もそうだし、メロディもそうだし。
──GOOD BYE APRILにとってのポップスってそういうことなのかもね。踊れるとかそういうことが前提っていうよりは記憶に残る音楽というか。いつまでも聴き継がれていくスタイル。
倉品:僕らがシティ・ポップっていうジャンルに憧れを持ってるとしたら、そういうことかもしれないですね。だって30年、下手したら40年近く前の音楽がYouTubeをきっかけに世代を超えてリスナーに届いてくって楽曲冥利に尽きると思うんですよ。だから年末のイベントをまずはステップに、来年以降少しでも自分たちの理想とする音楽を届けていければいいなって思ってます。