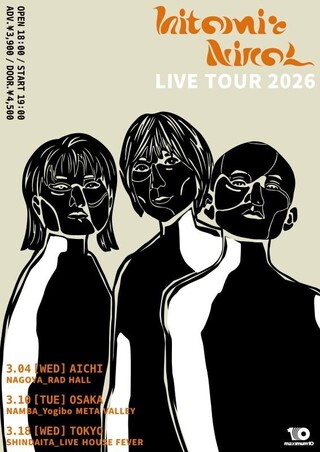行くとこまで行こうという責任感がでてきました
──『ヤマト』にお仕事として初めて関わられたときの印象に残っている当時のエピソードがあれば伺えますか。
宮川:最初に仕事としては関わったのはパイプオルガンを弾いた時ですけど、作曲家としては関わったのは19歳の浪人生のころでした。『ヤマトよ永遠に(以下、永遠に)』の時に父から「彬良、書いてみるか」と声を掛けられて参加しました。本当に大変だったので猫の手も借りたかったんだと思います。絵コンテを見せてもらって、「メロディーはこれね」とモチーフをもらって、「さすがお父さん、いいメロディーだね」と思いながらやりました。
──録音にも参加されたのですか。
宮川:どんな音になるかは一番興味があるところだったんですが、同時にもう心臓が壊れそうに緊張しちゃって、とてもじゃないけど行けませんでした。行けないと聞いた父は「あ、そうか。」くらいの反応でしたね。僕の気持に気づいてくれてたのかもしれません。録音が終わった後にド緊張しながら「どうだった」って素知らぬふりして聞くと、「いやぁ、西﨑さんが椅子から転げ落ちてたぞ。」と言われました(笑)。全然、音が違ったんだそうです。「泰先生の気がおかしくなったのかと思った」と西﨑さんがおっしゃっていたと聞きました。録音したカセットテープをくれたので聞いてみると、僕が思い描いていたものと若干違った感じでした。「この部分はいいな」とか「ここ音間違ってた」と、ド緊張しながら聞きました。父はやんわりとしたコミュニケーションが上手い人だったので、「ココの音なんかは自分じゃ全然書けないよ」と上手に褒めてくれましたね。その曲は予定した所では使われなかったんですけどまた違う本編で使われていたんです。没になって使われないと思っていたので、使われたと知ったときは「言ってくれよ。直したいよ」って思いました(笑)。笑い話半分・武勇伝半分で、まるで昨日のことのようです。
──それを経て『2199』『2202』のシリーズに携わるとなった時にはどんな気持ちだったのですか。
宮川:実は『2199』シリーズより前に『ヤマト』へのお誘いがあったんです。西﨑さんが『宇宙戦艦ヤマト復活篇(以下、復活)』をやるということで、大友(直人)さんから一緒にやらないかと連絡をいただいていたんです。ですけど、僕はその時お断りをしたんです。僕は本当に最初の『ヤマト』が好き過ぎて、だから『復活』は受けられなかったんです。それで出渕さんからお話をいただいた時も「悪いけど、また断りに行かなきゃいけないんだ」と思ったんです。
──最初は断るつもりだったんですね。
宮川:はい。なので、まず僕の最初の『ヤマト』に対する思いを伝えたんです。「原点である最初の『ヤマト』が好きなので、続編はやりたくありません」と伝えると、出渕さんが「彬良さん、僕がやりたいのはまさにそれです。最初の26話をリメイクしたいんです。」とおっしゃったので、「じゃぁ、やります。」って快諾しました(笑)。本当に漫画みたいでしたよ。
──お二人の『ヤマト』に対する思いは一致したんですね。現場での出渕さんはどのような方でしたか。
宮川:本当にオーダーが上手い方でした。「訓練学校の校歌やりましょう」とか、「ガミラス国歌やりましょう」とか、横道から攻めてくれて僕をリラックスさせてくれたんです。
──最初は固辞していた作品へ参加されていかがでしたか。
宮川:参加するとなればあとは行くとこまで行こうという責任感がでてきました。「僕がやらなかったら、それはイメージ違うよな」という事を自分でも思えるようになりましたし、「そこはお前が守ってくれよ」と父が横で囁いてくれているような感じがあります。そこは上手くいったからこそ、考え方が変わってきた部分じゃないかと思います。
音楽で物語を書いている
──お父様の作品を引継がれて分かった音楽家としての凄さはありましたか。
宮川:凄さは嫌というほど感じました。特にメロディーというものに対する信心の強さが違うんです。彼がもし今の音楽を聞いて天から告げるとしたら「メロディーを失って君たちはいいのか、メロディーを忘れていいのか」と怒ると思います。それは時代のこともあると思いますが、ちょっと考え方が違うんです。メロディーというのは音楽の本質そのもので、一番中心にあるという思いに確固たるものがあって、彼はその思いを死ぬまで信じていました。それは『ヤマト』の一連の曲を聞けばわかります。全部メロディーがある、これはひれ伏すしかありませんでした。
──それだけパワーがあるからこそ、世代を超えて聞き継がれているんですね。
宮川:そう、パワーがあるんです父のメロディーには。しかも父のメロディーはAメロに戻る時のタメというのか、じらしというのが必ずあって、そこでめちゃくちゃ気持ちが入るんです。「宇宙戦艦ヤマト」だとサビから戻るところ「笑顔で応え」に入るところの「誰かがこれをやらねばならぬ」のあたり、昔のアニソンに良くある手法で「タララッタララッタララタララ」と入る。あの瞬間が昭和なんですよ。
──確かに今の楽曲と違いますね。
宮川:そこがエモいんです。エモーショナルというのは感覚でもあるけど、実は理論でも証明できるんです。その1つがドミナントという和音で、主人公の和音に戻ってくるその前の瞬間が気持ちいいんです。
──「待ってました」という感覚になって、ガッと気持ちをつかまれます。
宮川:そうなんです。
──それは、日本的な感覚なんでしょうか。歌舞伎の見得にも通じているなとも思いますが。
宮川:音楽では日本的であるっていうより、昭和的であるっていう方が正しいと思いますね。実は、ベートーヴェンやバッハの中にもそれは沢山入っているんです。
──確かに。「運命」などもそうですね。
宮川:音楽で物語を書いているという事なんです。それは自然の摂理に則ったことでもあって、その自然の法則を音に置き換えたのが音楽理論になるんです。これから先また違うスタイルのドミナントが発明されると思いますが、やっぱり人間はそれを避けられないんだと思います。
──そうですね。最後は王道に戻ってきますから。
宮川:だから“エモい”という言葉が流行ってくれて本当に嬉しかったです。「みんなそこを忘れてなかったんだ」と思いました。
この曲には次の世代に残していくべきものがある
──今回の交響組曲には元になる物語がありますが、物語を元にしての音楽を作曲する面白さはとは何ですか。
宮川:面白さというより、僕にとってはそれが当たり前の事なんです。僕は文字があると反射的に音が聞こえてくるんです。絵があると音が浮かんでくる人とか、逆に音があると絵が浮かぶ人がいるじゃないですか。
──いますね。
宮川:僕の場合は、活字を見ると音が浮かぶんです。
──それは絵とともに音も浮かぶという感じなんですか。
宮川:言葉が織りなす空気が必要としているものが全部解るという感じで、音が聞こえてきちゃうんです。なので、メニューとか説明文みたいなものからも音がしていて、音が鳴らない瞬間というものがないんです。
──天性の感覚ですね。だからこそ『ヤマト』の音楽・物語を引き継ぐことができたということにも繋がっているんですね。
宮川:そうかもしれませんね。もしかしたら、父にもそういう所があったかもしれないです。僕は『ヤマト』に限らず、オペラやバレエなど物語がある作品の音楽を作ることは天職だと思っています。
──天職とされている方に作っていただけてありがたいです。今回の交響組曲を聞かせていただいたのですが、本当にヤマトの物語が映像で観えてきました。
宮川:ありがとうございます。僕にとって今回の交響組曲は、ほぼ自分で台本を書いたオペラを作っているような感覚でした。単なる音楽作品ではなく、音楽の中に物語が封じ込められているということを感じながら書いていました。本当に一世一代の作曲なので、この曲には次の世代に残していくべきものがあると思っています。今ファンじゃない人にも是非どこかにインプットされてほしいと思っています。
──その思いも伝わってきました。これからも引き継がれていく交響組曲になると思います。
宮川:ありがとうございます。そうなってくれると本当に嬉しいですね。