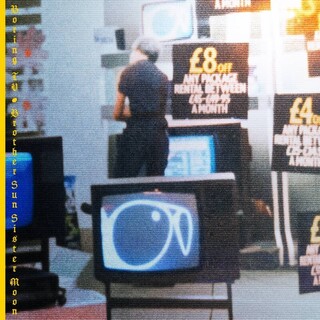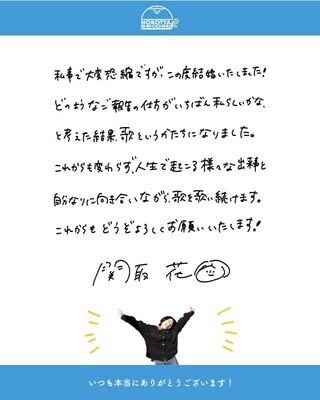昨年、日本の法律で初めてアイヌ民族を〈先住民族〉と明記した《アイヌ新法》が成立し、今年は北海道白老町に《ウポポイ》というアイヌの文化施設が開業するなど、近年またアイヌが注目を集めているなか、現代を生きるアイヌに焦点を当てた劇映画『アイヌモシㇼ』が10月17日(土)より渋谷ユーロスペースほか全国の劇場で順次公開される。
阿寒湖畔のアイヌコタンを舞台に、アイヌの血を引く14歳の少年カントが自身のアイデンティティや父親を亡くした喪失感と向き合いながら成長していく物語。彼が反発していたアイヌの精神と文化をアイヌコタンの中心人物であるデボから教え込まれ、それをどう受容するのかが一つの見所だ。また、イオマンテという伝統儀式に対する認識と価値観にはアイヌの中でも個々人や世代間で相違があり、現代のアイヌが抱える葛藤と苦悩を浮き彫りにもしている。あくまでフィクションという体でありながらも、演技経験のない現地のアイヌがアイヌ役を演じることでドキュメンタリー映画のように生々しいタッチの作品となっているのが実にユニークで、前作『リベリアの白い血』(2017年)でもキャスト起用で同様の手法を用いた福永壮志監督の面目躍如といえるだろう。
アイヌという非常に繊細な題材をあえて選び、近くて遠い存在であるアイヌの現況を掘り下げつつもしっかりと娯楽作品として完成させた福永監督に本作の制作意図、作品に込めた思い、多様性と寛容の重要性について語ってもらった。(interview:椎名宗之)
アイヌの役を実際のアイヌに演じてもらうのが前提
──監督がアイヌに関心を持ったのは20歳で渡米した後、ネイティブアメリカンに興味を抱いた頃だったそうですね。
福永:生まれが北海道で高校卒業まで住んでいたんですけど、アイヌについてちゃんと学ぶ機会がなかったんです。アイヌの同級生もいたけどそのことについて聞いちゃいけないような気がして、知りたいけど知れない悶々とした思春期を過ごしました。その後、アメリカに留学してミネソタ州に2年いた後に、映画を学ぶためにニューヨークへ移り住んだのですが、ミネソタ州ではネイティブアメリカンの存在感が強かった。地域によって差はあれど、もともとネイティブアメリカンがいた土地を奪って今の自分たちがいるという認識がアメリカ人には総じてあるし、ネイティブアメリカンに関することに対して意識が高いんです。アメリカの先住民族がどういう考え方を持っていたのかとか、そういうことを少しずつ知るうちに彼らの文化に惹かれていきました。そこでふと思ったんです。自分が生まれ育った北海道にもアイヌという先住民族がいるじゃないかと。それなのにずっと何も知らないままでいたことを恥ずかしく感じたんですね。今でこそ『ゴールデンカムイ』のようなコミックがあったり、メディアがアイヌを取り上げる機会も増えてきましたけど、当時は海外はもちろん日本でもアイヌに対する理解と認識がとても低かったので、自分ももっと学びたいと思ったし、アイヌを題材に映画を作ることには意味があるんじゃないかと思い始めたんです。それから具体的に企画を立ち上げるまで時間がかかりましたけど、ようやく形にすることができました。
──二風谷、白老、屈斜路、阿寒とアイヌの代表的なゆかりの地がある中で、阿寒町を舞台に選んだのはなぜですか。
福永:阿寒にはしっかりとコミュニティがあると感じたのが大きいです。阿寒以外の町にも訪れてアイヌの方々にいろいろと話を聞いたんですけど、白老は博物館を中心として各地のアイヌが集っているイメージで、二風谷はアイヌの人口密度は高いけど、自分たちの生活をそれぞれ営んでいるような印象を受けました。それに対して阿寒は観光の仕事を通してコミュニティの結束も強いし、生活の中にアイヌ文化が息づいている。その一方で、観光で見せる姿と実生活の差もあったりします。映画の舞台としてコミュニティはすごく大事だったし、現代のアイヌを映画で描く上で、物語になる要素が阿寒にはたくさんあったんです。
──ということは、阿寒を選んだのはキャストに起用した下倉親子が暮らしていたことが大きかった?
福永:それも一つの理由ですね。最初は主人公を青年にした脚本を書いていたんですが、カント君(下倉幹人)と出会ったこともあって少年の成長の話にすることにしたんです。阿寒にはデボさん(秋辺デボ)やエミさん(下倉絵美)といった役者が揃っていました。映画の中のアイヌの役を実際のアイヌの方に演じてもらうのが前提だったので、舞台のリサーチはキャスティングを兼ねていました。各地で話を聞きながら出演者を探していて、実際の本人役ではあるんだけど、演じるというよりも自分の違うバージョンを映画の中で出してもらう。またそれが自然でいられる環境作りやアプローチが大事だったし、その人物や設定、そこで起きる出来事をそのまま映画に持ってくる手法を考えたときに、阿寒に住む人たちを阿寒で撮るのが一番スムーズだったんですよね。
予定調和じゃないサプライズが生まれるのが面白い
──劇映画だけどすごくリアリティがありますよね。まるでドキュメンタリーを観ているような錯覚に陥るところもあるし、主人公であるカント君の佇まいがとにかく素晴らしい。普段は寡黙だけど目力が雄弁で、何度も引き込まれそうになります。
福永:彼は映画に出ている通りに口数は少ないけど感受性の豊かな子で、何事も自分なりに考えたり感じたりする下地がしっかりあるし、あの目がとても印象に残るのはそういうことの表れだと思います。
──主人公に起用したのもそういったことが理由だったんですか。
福永:最初はエミさんを介して阿寒へ行くようになって、その都度カント君とも会っていたんですけど、会うたびにちょっと特別な子だなと感じていました。とても印象的な目をしていたし、彼もまたアイヌをルーツに持つ少年だし、エミさんとは実際の親子だからそのままの設定でいけるし、いろんなことが必然性を持ってつながっていたんですよね。
──前作の長編デビュー作『リベリアの白い血』でも演技経験のない方を役者として起用していましたが、それは劇映画の中にドキュメンタリーの要素を入れておきたいからですか。
福永:ドキュメンタリー的要素でいえば前作より本作のほうが結果的に大きくなりましたが、理由はいくつかあります。まず大きいのは、自分のように外から来た人間がこういう繊細な題材を扱うときに自分が持つイメージに押しこむようなやり方をしてはいけないと考えているから。そのためにすでにあるもの、実在する人物に作品を近づけるというプロセスを踏まなければいけない。そうなると、アイヌの役は実際のアイヌの方に演じてもらうのがベストなんです。それと、自分の頭の中で思い描いていたものがそのまま形になってもあまり面白くないんですよ。想像をそのまま具現化するのではなく、それにもっとリアリティを持たせながら想像を超えるものを作品に落とし込ませたいという自分の姿勢もありますね。
──想定外の化学変化が生まれたほうが面白いと。
福永:そうです。パーフェクトじゃなくてもいいから「これを観るだけでも価値がある」というものを何かしら撮れたら作品としては成功なんじゃないかと思うので、細部にわたって緻密に画コンテを作り込んで演者やスタッフを駒のように動かすよりも、予定調和じゃないサプライズが生まれる環境に身を置いたほうが今は面白いと感じます。
──本作におけるキャストの皆さんの芝居があまりに自然なんですが、脚本は一応あるんですよね?
福永:あります。出演者の皆さんと事前にいろいろ話をしてその人となりを知った上で、できるだけ本人に近づけた脚本を書きました。セリフももちろんあるし、内容を分かってもらうためにあらかじめ読んでもらいましたけど、セリフを暗記することはお願いしませんでした。現場で緻密なリハーサルをやることもなく、だいたいの内容を伝えて「ここからここまで話を進めます」と説明して、あとはテイクごとに微調整をしていきました。セリフはできるだけ自分の言葉で話してもらうようにお願いしました。脚本上、ポイントとして必ず言わなくちゃいけない言葉がいくつかありましたけど、それも別にこういう言い方じゃなければいけないという決まりはありませんでした。そういう余白を持たせた進め方だったし、顔馴染みの人たちとの共演なので、ポンと出るアドリブのほうがよっぽど生きた言葉だったり、自分では絶対に書けない言葉だったんですよ。そうやってみなさんが自然体で演じられる環境作りを意識しましたし、その中で出た生きた言葉を映画にたくさん入れてあります。
──監督の意図するところが功を奏したわけですね。本作のキーパーソンであるデボさんがセリフをちゃんと覚えてくるようには思えませんし(笑)。
福永:覚えてくださいとお願いしても無理でしょうね(笑)。
──デボさんが新聞記者役のリリー・フランキーさんに「シャモ(和人のこと)ならそう言うべな」と言い放つのもアドリブですか?
福永:あれはセリフにありました。「シャモ」はちょっと蔑視的なニュアンスがありますが、興味本位に詮索する新聞記者に対してデボさんが敵対心を持つシーンなので、あえて使いました。映画の中でその言葉の意味は説明していませんが、歴史上で和人がアイヌにしてきた過ちを知るきっかけになればいいと思います。