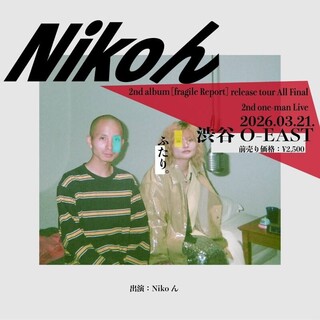ヒップホップじゃ格好のつけ方がわからない
──水戸さんはヒップホップを聴くことがあるんですか。
水戸:なくはないね。俺はメロディよりも言葉に重きを置いた人間だから以前から関心はあって、日本語ラップの黎明期にけっこう聴いてみたりはした。自分もこういうことがやれるなら面白いなと思ってはいたけど、いざやってみても俺にはできなかった。今回の「Happy 31」みたいに、朗読や怒鳴りならできるんだけど、ラップではない。なぜそうなのかを考えると、単純に十代の頃にヒップホップを聴いていなかったからだと思う。
──ああ、なるほど。
水戸:俺は十代でロック、特にパンクこそ一番格好いいと刷り込まれてるのね。そこから俺なりに格好をつけるというルールでずっとやってきてるわけだけども。たとえばアンジー時代にポコチンロックとか言っておちゃらけてたけど、いわゆる格好悪いことを実はそれが格好いいと思ってやってんだよ。逆にいわゆる格好いいとされるものを格好悪いと感じるようなひねくれた価値観があった。それはパンクの価値観の刷り込みだろうね。
──わかります。「種まき姉ちゃん」もあれはあれで格好つけているわけですよね。
水戸:そう、実はね。独特のルールで格好をつけて「お乳ふりふり」と唄っている(笑)。根本にあるのはいつも格好をつけたいってことで、ヒップホップじゃ格好のつけ方がわからないんだよ。
──それと、ヒップホップをやることに対する照れくささもありますよね。
水戸:うん、まさにそれだと思う。ラップとは言えメロディだから、それ特有の唄い回しをやろうと思えばできなくもないんだけど、格好つけるものとして自分の身体に入ってないんだよね。どうしても拭えない照れがあるから、仮に俺がヒップホップをやっても聴く人には無理をしていることがわかっちゃう。ギャグとしてやるならできるけどね。それだったら俺なりの格好のつけ方だから。
──そもそも身の丈に合わないことをやるのは恥ずかしいですしね。
水戸:自信がないことも含めてなんだろうけどね。それを格好いいと感じる確信がないってことは自信がないってことだから、それが照れとして出ちゃう。素人が唄っているのを見て俺が一番気になるのも照れだしね。ステージに上がったらバーン!と勢いよくやればいいじゃんと思うよ。俺はステージに上がっても照れがないから歌手として成立しているし、上手い下手は二の次だと思う。
──「青のバラード」というアンジーのレア曲でアルバムの最後を飾ろうと考えたのはどんな理由からですか。
水戸:ゴスペルにハマりそうだったからというのも理由のひとつなんだけど、「青のバラード」って実はアンジーの最後のシングル候補だったんだよ。そろそろ大きめのバラードでシングルを切りたいと思って何曲か作っていた中の1曲で、デモ録りなのにフルオーケストラまで入れる凝りようでね。サンプリングではなくわざわざ生オーケストラを呼んで音を入れるくらいの力の入れようだった。でもその直後くらいにバンドを休止する話が出て、そのまま休止に向かっていったのでレコーディングが宙に浮いてしまった。アンジーの『RARE TRACKS』に入っているのは、その宙に浮いた未発表テイクなんだよ。そういう経緯もあって、いつかちゃんとした形で発表したいと考えていて、今回がいい機会だと思って入れることにしたわけ。オリジナルのフルオーケストラをそのままコーラスに置き換えたら成立すると思ったからね。
──『ウタノコリ』然り、『不死鳥Rec.』や『独翔 ver.』然り、ここ数年の作品ではそんなふうに過去の埋もれた楽曲に敗者復活の機会を与えることが多いですよね。それは水戸さんがミュージシャンではなく唄い手だからなんでしょうか。
水戸:それは大きいだろうね。もう一度脚光を浴びせたいのもあるし、歌を唄う自分が成長しているのであれば、歌のほうだって放っておいても成長しているはずだしね。その辺の意識は生粋のミュージシャンや生粋のアーティストとはちょっと違うかもね。多くのミュージシャンは一度完成した曲をセルフカバーすることに抵抗があるみたいだけど、俺は全然そんなふうに思わなくてね。なぜひとつの曲を一度しかレコーディングしちゃいけないんだろう? なぜそんなルールをみんな勝手に守っているんだろう? と思うしさ。どのタイミングでレコーディングしようが、「たまたま今はこうです」ということだとしか俺は思ってない。もちろんその時点で全力を尽くして百点満点を出しているつもりだけど、時間が経てばもっと点数を出せるはずだから。
真剣な遊びとしてロックをやり続けたい
──水戸さんらしい発想で納得です。「青のバラード」は「昨日より若くなる/ひとつづつ若くなる/永遠に若くなる」という歌詞が印象的ですが、20代の終わり頃に書いた歌詞と考えると当時の水戸さんはだいぶ老成していたようにも思えますね。まだ充分若い時分に「永遠に若くなる」という歌詞を書くわけですから。
水戸:当時の俺に言ってやりたいよね、「お前はまだ何もわかってない」って(笑)。「永遠に若くなる」というフレーズは今の自分のほうが願いとして、より正しく唄えるよ。当時、なぜそのフレーズを使ったのかよく覚えていないけど、あの頃の若い自分が唄ってもあんまり説得力がないよね。ただ単に「永遠に若くなる」と言ってみたかっただけじゃん、って。「人生は永遠じゃない」とか自分が50歳を過ぎた頃にようやくリアリティを感じたことだよ。「あれ? あっという間にこれだけ生きちゃってるぞ。ということはこの先の人生って思ってたほど長くないぞ」というのを今は実感してるから。だからこそ「永遠に若くなる」ことを切実に願えるんだよね。
──なるほど。VOJA-tensionとのライブは今回のアルバム同様、歌とボーカルを際立たせた迫力のある内容になりそうですね。
水戸:トクちゃんにマックからのトラック出しをしてもらうんだけど、それに加えてピアノは必ず生で弾いてもらう。それで唄いやすさが違うから。Zun-Doco Machineでもゲストでワジー(和嶋慎治)のギターが入った時に唄いやすさが全然違ったという経験からそう決めた。唄いやすさが違うということは聴こえ方も違って、つまりライブ感がすごく違ってくるんだと思う。
──デビュー31年目にして今までやったことのないライブをやるとはかなりのチャレンジですよね。
水戸:一本目のumeda TRADまではドキドキだろうね。トラックに合わせて唄うのはZun-Doco Machineで慣れているのでできなくはないと思うんだけど、どう意識してもライブの時は歌が粗くなるものなんだよ。本来バンドで唄ってる時にはバンドの音に抗うわけだし、元がパンクだからさ。それに対してVOJA-tensionは正統的に上手いグループで、その上手いはロックにおける上手いとはまた違うんだよね。ロックにおける上手いは癖つけてなんぼだから。そうではない、誰が聴いても上手いよねと感じる人たちのコーラスと、聴く人によっては下手にも聴こえる俺の歌がライブで混ざらなきゃいけない時に、どこまで俺が寄れるのかがポイントかな。逆に彼らにもこっちに寄ってもらうように要求するし、互いに歩み寄ることになるんだろうけどね。その辺のバランスがどうなるかが不確定要素で面白い。
──水戸さんほどのキャリアを積むと、およそのことは経験済みで想定内だと思いますが、今回ばかりはどうなるかわからないと。
水戸:どんなライブでも自分の予想を超えてくるから面白いんだけど、今回に限ってはそもそも予想が完全にはできないからね。このキャリアでそういうライブをやれるのは嬉しいことだよね。
──水戸さんは澄田さんや内田さん、和嶋さんといった全幅の信頼を置くお馴染みの面子と一緒に作品づくりやライブをやり続ける反面、今回のプロジェクトのようにこれまでやったことのないことを突如始めたりしますよね。それは水戸さんなりのバランス感覚なのでしょうか。
水戸:ひとつのことをずっとやってると、どこかでそれが遊びじゃなくなる気がしてね。俺の場合は遊びだからこそ出せる集中力と真剣味だから。それは昔から自分の傾向としてあるね。
──今回のゴスペル・グループとのコラボレーションのように、意外性のあるプロジェクトは今後も続けていく予定ですか。
水戸:Zun-Doco Machineがすでに相当思いきったユニットだからね(笑)。元ナゴムでもともとYMOが好きだったウッチーはともかく、俺が今さらテクノをやるなんて意味不明でしょ?(笑) でもいざやってみるとなんか成立してる。その自由度は自分が歌手だからというのが大きいかもね。3-10 chainというバンドをやっても、『ウタノコリ』というアコースティック・ライブをやっても、最終的には自分が唄ったところで完結するわけだから。観念的なことじゃなくて、歌というのは楽器という道具を使わないから、自分自身と身体的に同一なんだよね。自分が唄いさえすれば完結するということに裏打ちされた自由なんだと思う。だからいろんなことをやってるようで、実はずっとひとつのことしかしてない気もするしね。その自由を常に保ちたいし、俺は一生遊んで暮らしたいんだよ。遊びじゃなくなったらもうやめ時だと思ってるから、これからもずっと真剣に遊び続けていたいよね。